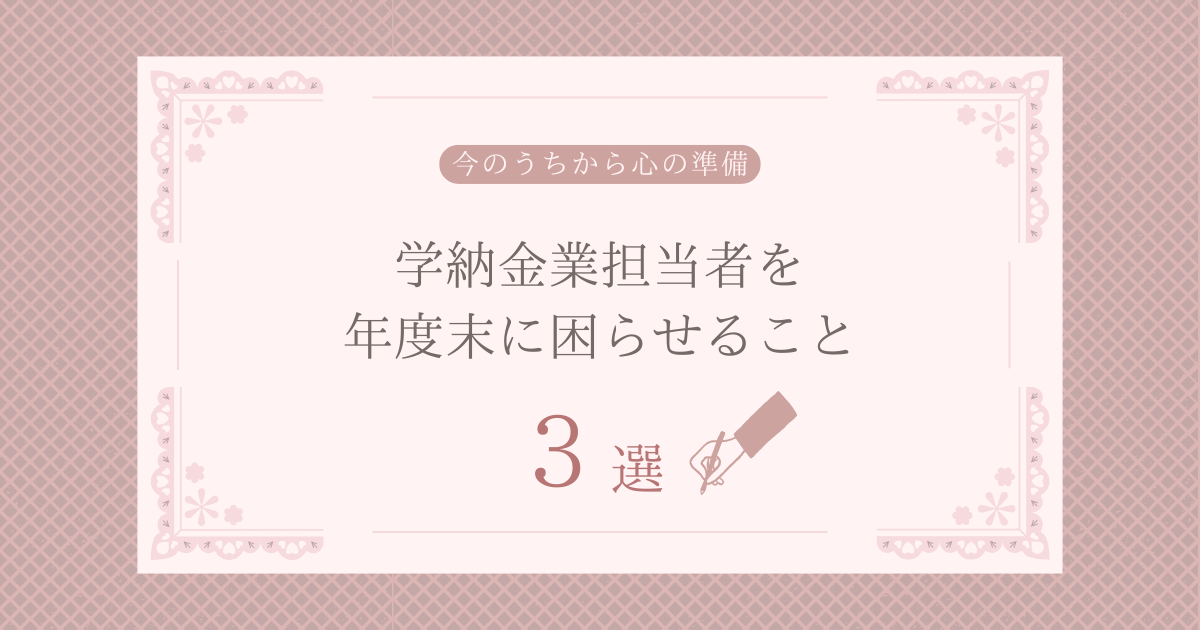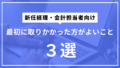この記事の内容は以下のとおりです。
・年度末に起こることが多い「学納金業務担当者の頭を悩ませる出来事」を紹介
私立学校事務員の方、特に新たに経理・会計担当や高校事務室に配属される事務員は、学納金業務の担当に就く傾向があります。
実際私もそうでしたし、他の学校の様子を伺ってみても同様の状況でした。
そこで今回は、その学納金業務のうち年度末に発生することが多い「お困りごと」について、私自身や別の事務員の体験をもとに3つ紹介させていただきます。
4月から私立学校事務員として働く人や学納金業務を担当することになった人への予備知識として、参考にしていただければと思います。
もちろん、それ以外の事務員の方も「そうそう」と共感していただければ幸いです。
【結論】学納金業務担当者を困らせるのはこの3つ
先に結論として「3つのお困りごと」を紹介させていただきます。
以上の3つです。
詳しい内容は後述しますが、どれも自分一人では対処が難しいものばかりです。
しかし「年度末にはこんなことが発生するかもしれない」と心の準備ができていれば、慌てることなく落ち着いて現状に向き合うことができると思います。

「起こるかも」と思っていれば、実際に発生した際も「やっぱり起こった」と心へのダメージを軽減できます。
この記事を読んで、備えておきましょう。
それでは、1つずつ紹介していきます。
【お困りごと①】学納金未納者への対応
未納者への対応は年度末に限らず1年中、学納金業務担当者を悩ます問題ですが、その中でも特に、年度末をむかえようとしているときの未納者の存在は要注意です。
基本的にどの学校も、学則において学納金未納者への取り扱いを定めていると思います。

例えば「未納期間が〇カ月を超えると除籍」などです。
ただ、私の今までの勤め先の状況や他の学校の事務員の話などからすると、その学則で定める期間を超えた場合でも、年度途中であれば何かしらの手続きを経て、さらに猶予期間を設けている傾向があります。
それでも、「年度を超えて」猶予を与えている学校は、私の知る限りでは「ない」という認識です。
それは学校の会計年度や卒業、進級判定などの関係だと考えられます。
そうした関係で、年度末には何としてでも未納の状態を解消させる必要がありますので、事務員以外に担任など教員も巻き込んで、とにかく年度末までに納付することを促します。
しかし、こればかりは相手が納付してくれなければどうしようもありません。
ここが、学納金業務担当者を最も悩ますポイントです。
これといった有効な解決法はないというのが正直なところで、とにかく粘り強く納付をお願いし続けるだけです。

私は3月31日に現金で納付を受けたことがあります。最後までひやひやしました。
解決法ではありませんが、一人で悩むことなく、上席者や担任などに逐一状況を報告し、情報を共有して「大変な状況になっていますよ」ということを周りに知らせるようにしておきましょう。

余談ですが、今までの話は高校を想定しています。大学は高校に比べるとあっさり年度途中でも未納者を処分しているように思います。
「高校の時は猶予してくれたのに」という恨み節を、何度か聞いたことがあります。
以上が1つ目のお困りごとです。
【お困りごと②】新年度徴収者数の変動
年度末ということは、年度初めの準備の時期でもあります。
高校であれば1学期、大学であれば前期など、4月は学納金の納付月に設定されていることが多いです。
生徒の保護者など実際に学納金を支払う方からの話によれば、納付期日の1か月前には請求金額の通知が欲しいそうです。
つまり、高校のケースでいうと、4月の上旬が1学期の学納金の納付期日であれば、3月上旬には請求書が欲しいということになります。
そのタイミングに合わせるために、学納金業務担当者は請求の準備を進めるわけですが、年度末は生徒の異動が発生しやすい傾向にあります。

異動とは休学や転学、退学などのことを言います。
担任等から「あの生徒が転学を考えている」などの情報が入るわけです。
その情報を聞いて、当該生徒への請求書の発送を止めておきますが、その後の連絡がないことが多いです。
担任に「あの生徒の件、どうなりましたか」と尋ねてようやく「ちょっと連絡してみます」と動き出すような状況です。
- 教員目線:「向こうが連絡してこないから待つしかない」
- 事務員目線:「こちらから連絡をとって、早く教えてほしい」
といった感覚の違いでしょうか。
さらに、請求書を発送してから異動の情報が入るときもあります。

保護者等から「担任に転学するとお伝えしてますけど」という旨の電話がかかってきたときには、気が重くなります。
こうした生徒の異動が、学納金業務担当者の頭を悩ませます。
これも抜本的な解決策はありませんが、年度末が近づいてきたときには、ことあるごとに「異動の情報があれば、未確定でも事務室まで一報をください」と呼び掛けておきましょう。

あと異動には「復学」という学校を休んでいた状態から戻ってくるパターンもあります。請求を忘れないようにしましょう。
これが2つ目のお困りごとです。
【お困りごと③】新年度徴収金額の未確定
②で学納金の請求の話をしましたが、請求には人数だけでなくもう1つ「金額」という大事な要素があります。
この「金額の確定」も年度末に学納金業務担当者を悩ませます。
授業料などは学則に定められていますので、突然変わることはありませんが、それ以外のもので変動するものがあります。
例えば「学年費」のようなものです。
学年費の具体例を以下に挙げます。
- 行事にかかる費用
- 選択する授業によって異なる教材の購入費
- 模擬試験を受験する費用
その年度によって「どこへ行くか」や「何をするか」が変わるため、金額が変動します。
また同じ年度であっても、学年によってやることが異なるため、金額に違いが生じます。
こうした情報をとりまとめたうえで請求金額を確定し、保護者等に通知する必要がありますが、これがなかなか決まらないわけです。
これも②の状況と同様で、以下のような教員と事務員との意識の違いによる部分が大きいです。
- 教員目線:「3月の段階でそんなにきっちり決められない」
- 事務員目線:「正確な金額をお知らせする必要があるから決めてほしい」
学校によっては、大まかに「年間〇万円」とあらかじめ決めておいて、毎年同じ金額を徴収し、その金額内で賄うようにしているところもあるようです。
しかし、この方法もうまくいかず、年度途中に不足が生じ、追加で徴収するパターンが多いという話を聞きます。
その際には、保護者等から「どんな管理をしているのか」というようなお叱りの声を頂戴するようです。

ただ、そのお𠮟りを受けるのは事務員で、教員には届かないという実態があります。これが上述のような教員と事務員の意識の違いを生んでいるように思います。
いずれの徴収方法もそれぞれのメリット・デメリットがありますので、理解しておきましょう。
細かく内訳を決める方法を選んだ場合は、前述のとおり徴収金額が決まらないという問題が生じやすいです。
この問題については「〇月△日には学納金の請求書を発送しますので、それまでに学年費の金額を確定してください」と繰り返し教員に伝えるという方法以外に対処法はないように思います。
根気よく呼びかけるように努めてください。
以上が3つ目のお困りごとです。
まとめ
学納金業務担当者が年度末に困ることを3つ、私自身の経験や他の事務員の経験をもとに紹介しました。
これら3つのお困りごとのポイントは「情報共有」です。
どのお困りごとも、保護者等や教員といった他人に行動を促すことが重要になります。
「こういう理由で困るんです」という情報を保護者等や教員に共有し、共感・協力してもらうことがなによりも重要です。
特に新任事務員は、頑張って一人で対処しようとする傾向が強いように思いますが、私の経験上、積極的に情報を発信した方が良い結果につながるケースの方が多いので、意識して発信しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。