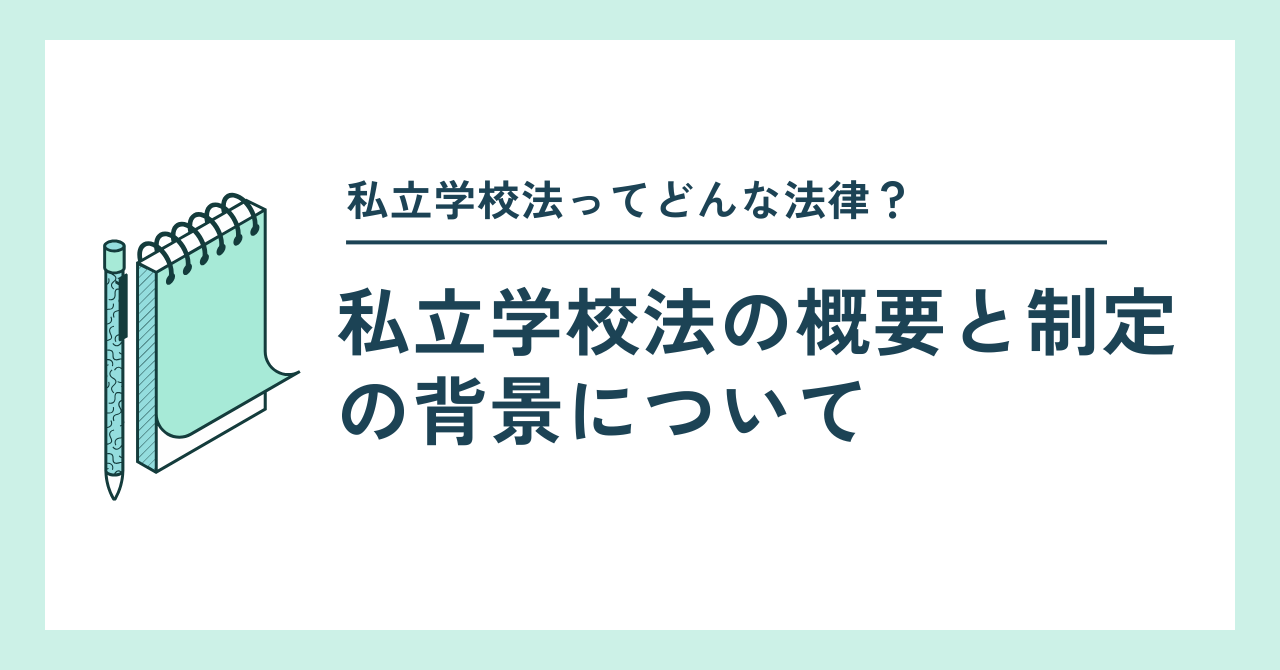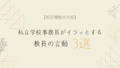この記事は以下のような人を対象としています。
・私立学校法が改正されたと聞いたが、そもそもどんな法律なのか知りたい
令和7年4月1日から改正私立学校法が施行されました。
学校法人の運営に大きな影響を与える改正があったわけですが、新任の私立学校事務員の方などにとっては、「そもそもこの法律がどんなものなのか」を学ぶ機会があまりないように思います。
そんな人たちのためにこの記事では、今回の改正の影響がない「私立学校法の基礎」にあたる部分を解説しています。
私立学校事務員として20年以上働く私の経験から、おさえておくべきポイントを以下の2つに絞って解説します。
- 私立学校法制定の背景
- 私立学校法の概要
読むのが面倒な条文の引用は、最低限に留めるようにしています。
皆さまの知識の習得の一助になれば幸いです。
【時間がない人はここだけ】私立学校法制定の背景
・私立学校法は、何故制定されたのか。
→私立学校の健全な発達を図るため
私立学校法
e-gov 法令検索より引用
第一条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
まずは、私立学校法制定の背景を理解しておきましょう。
背景を大まかに整理すると、以下のとおりです。
- 国は、日本の教育振興のために私立学校に発展してほしい。
- その発達のためには、国から私立学校への助成が必要である。
- 「国のお金=公的なお金」であり、その「公的なお金」を使って助成するためには、助成の対象が「公的な存在」でなければならない。
- 私立学校法を制定して、私立学校を「公的な存在」として法的に位置付ける。
このように、国が私立学校の健全な発達を支えるための根拠として私立学校法は制定されました。

私立学校は、国が1つの法律を制定してまで発展を支えたいという存在であるということを理解しておきましょう。
そのような重要な存在の一員として、私立学校事務員は働いているわけです。
【細かい条文は理解不要】私立学校法の概要
・私立学校法では、どのような内容が定められているのか。
→私立学校法の定める内容を理解するためのポイントは以下の2つ
・「自主性の尊重」
・「公共性の向上」
それでは、この「健全な発達」を支えるために私立学校法はどのようなことを定めているのでしょうか。
それを理解するために意識してほしいポイントが上述の2点です。
以下、1つずつ見ていきましょう。
自主性の尊重
私立学校の運営にあたり、国や都道府県など外部から必要以上に干渉を受けてしまうと「健全な発達」は望めません。

私たちも周りからあれこれ口出しされると、嫌になることがありますよね。
このような外部からの干渉を最小限におさえるために、一定のルールを定めているわけです。
これが1つ目のポイントです。
「公共性の向上」
前述の制定の背景でも触れましたが、私立学校は「公的な存在」として位置づけられています。
それにより、公的助成が受けられるわけです。
この公的助成がなければ、私立学校は教育・研究活動に必要な施設設備等を全て自己資金で調達しなければならなくなり、私立学校の経営状態の悪化を招く恐れが生じます。
このように、私立学校の健全な経営をするうえで「公共性」は重要なものであるため、「公共性」を高めるために私立学校が最低限備えておくべきことを私立学校法で定めています。

国民から「私立学校は公的助成を受けるに値する存在である」と認めてもらえる組織でなければならないというわけです。
これが2つ目のポイントです。
私立学校法の構成
以上の2つのポイントを意識しながら、私立学校法の構成を見てみましょう。
2つのポイントのうち、「自主性の尊重」は私立学校を取り巻く外部に対する規律、「公共性の向上」は私立学校内部に対する規律というように読み替えて整理すると理解しやすいです。

ここでは前者を「外部規律」、後者を「内部規律」と表現します。
令和7年4月1日施行「前」の私立学校法は、全5章で構成されていました。
この5つの章を「外部規律」と「内部規律」という枠組みで整理すると、以下のようになります。
| 外部規律 | 内部規律 |
|---|---|
| 第二章 私立学校に関する教育行政 | 第三章 学校法人 第一節~第四節 |
| 第三章 学校法人 第五節 | 第五章 罰則 |
第一章は、私立学校法の目的や言葉の定義等を規定しています。
「私立学校法の定めを理解するための前提知識をまとめたもの」と理解しておけば問題ありません。
第四章は「雑則」であり、他と比べて重要性がそれほど高くないと思いますので、ここでは解説を省略します。
以下、それぞれの内容を見ていきましょう。
【外部規律①】第二章 私立学校に関する教育行政
この章で規定している内容を一言で表すと以下のようになります。
「私立学校の所轄庁である文部科学大臣や都道府県知事でも、勝手に私立学校の設置・廃止等できない」

もう少し中身に触れると、法律で定められた機関の意見を聴かなければならないとされています。
つまり、文部科学大臣など外部に対する規律ということができます。
【外部規律②】第三章 学校法人 第五節
この部分では「助成及び監督」という内容が規定されています。
これも一言で表すと以下のようになります。
「私立学校の所轄庁である文部科学大臣や都道府県知事でも、干渉は限られた場面でしか認められない」

要するに「口出しの制限」ということです。
これもやはり、外部に対する規律と読み取れます。
【内部規律①】第三章 学校法人 第一節~第四節
ここでは、私立学校を設置する学校法人に求められる事項を定めています。
厳密には別ものですが一旦「私立学校=学校法人」と置き換えて考えましょう。
その学校法人に対し、以下のような事項を義務付けています。
- 役員や理事会、評議員会の設置
- 予算や事業計画の作成
- 解散の制限
「代表となる人物の選定」や「予算や事業計画作成の義務」など、前述のとおり、私立学校の「公共性」を高めるために必要な事項を定めているとも言えます。

代表となる人もおらず、計画性もない。さらに自由に解散できるという状況で「この私立学校には公共性がある」と言っても国民は納得しませんよね。
民間企業などとは異なる「特別な法人」として、私立学校法による規制を設けているわけです。
「公的助成を受ける立場として、最低限これだけは守ってほしい」という、「内部=学校法人」に対する規律であると、ひとまず理解しておきましょう。
【内部規律②】第五章 罰則
折角、内部規律①のような事項を定めても、守られなければ意味がありません。
定められた内容を徹底して遵守させるために、この章では罰則を設けているわけです。
罰則という内部に対する規律を設けることで、学校法人を牽制しています。
まとめ
【私立学校法制定の背景】
- 日本の教育において私立学校は重要な存在であるため、国としては私立学校が健全に発達してほしい
- その健全な発達のためには、私立学校に「自主性」と「公共性」が必要である
- その「自主性」と「公共性」の法定根拠として私立学校法が制定された
【私立学校法の概要】
- 私立学校法の内容は「外部規律」と「内部規律」に区分できる。
- 外部規律は「自主性」に関わるルールであり、私立学校を取り巻く外部団体等を適用対象としている。
- 内部規律は「公共性」に関わるルールであり、私立学校やその母体である学校法人を適用対象としている。
私立学校法について、私が私立学校事務員としてこれまで働いてきた経験に基づき、最低限理解しておくべきことを紹介しました。
私のような高校事務員からすると、私立学校法が日々の業務に直接的な影響を与えるケースはほとんどありません。
だからといって、全く関係がないわけではありません。
私立学校法に関する知識を身につけることで、自分たちの仕事が私立学校の健全な発達を支え、さらに日本の教育の発展につながっているということが意識できるようになります。
そしてそれが、自身の仕事に対するやりがいにも結び付くと考えています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。