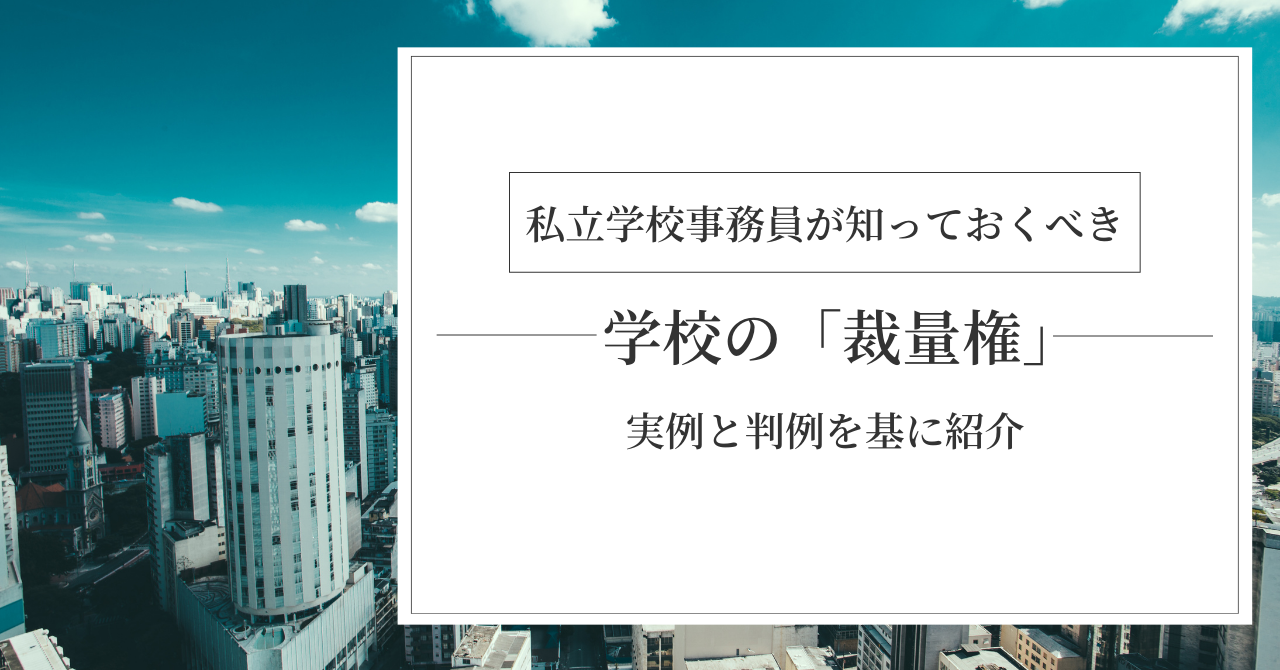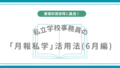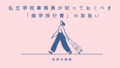この記事は以下のような人を対象としています。
・「学校って、本当に生徒を退学させることができるほどの権限を持っているの?」と思ったことがある人
先日、こんな記事をニュースで見ました。
「飲酒を理由にした退学勧告は違法」
東京の私立高校に通っていた女子生徒が、飲酒を理由に高校から退学勧告を受け、その後自主退学したというのが、大まかな事の経緯のようです。
このニュースを見た私の第一印象は「意外だな」でした。
今回の記事は、私がなぜ意外に感じたかを実例や判例に基づき、紹介したいと思います。
記事の概要は以下のとおりです。
- 私が見た実例その1:喫煙
- 私が見た実例その2:万引き
- 私が見た実例その3:傷害
- 番外編:裁判例
私立学校事務員として働くうえでは、同じような事例に必ずと言っていいほど遭遇すると思いますので、参考にしていただければと思います。
私が見た実例その1:喫煙
これは、以前に勤めていた高校でのケースです。
1年生の女子生徒が学外で喫煙をし、その様子がSNSにアップされていました。
そのSNSを見た人が「この制服、あの学校じゃないか」と気づき、学校へ一報が入ったわけです。
当時、まだ5月でその生徒は入学したばかり。
ただ、素行があまりよくないという話は学年の教員にも伝わっていたようで、一報を聞いた担任はそれほど驚かなかったとのことでした。

喫煙の事実よりもむしろ「もう問題起こしたのか」という驚きの方が大きかったと言っていました。
当然、何らかの処分を下す必要があるわけですが、どうやら調べれば調べるほど色々と問題行動が出てきたそうです。
そして、下された結論が今回のニュースと同じく「退学勧告」。
ちなみにですが、「退学処分」と「退学勧告」は別物です。
「退学処分」は会社で言うところの「クビ」「解雇」みたいなものです。
一方、「退学勧告」は大まかに言うと、校長などから「自主的に退学しなさい」と言われるもので、退学するかどうかは生徒側が決めます。
生徒本人としては「行いを反省して、学校に残る」という選択肢が残されているということになります。
結局、その生徒は「退学勧告」を受け入れ、入学して早々に学校を去っていきました。
私が見た実例その2:万引き
これも、以前に勤めていた高校で起こったケースです。
その日は定期試験の期間中で、午前中に試験が終わり、生徒はすでに帰宅。
それに合わせて教員も、入試広報活動のため中学校や塾へ訪問に行き、学校の中はほとんど誰もいない状況でした。
そんな時に、事務室に外線がかかってきました。
事務員の一人が電話をとり、対応していると、その事務員の声の調子がどんどん固くなっていきます。
少し離れた席にいた私でも直感的に「何かよくない内容だろう」と感じ取りました。
電話が終わり、周りにいた人に告げられたのは「生徒による集団万引き」という内容でした。
学校から少し離れた書店で、生徒がグループになり、万引き行為を行っていたとのこと。
しかも、その日が初犯ではなく、以前から常習的に犯行に及んでいたため、警察がマークしていたそうです。

「よりによって、こんな手薄のときに」というのが、一報を聞いた時に最初に心に浮かんだ言葉でした。
「とにかく、管理職または生徒指導の教員が対応する必要がある」という事務長の判断のもと、すでに学校を出ている教員の携帯電話に片っ端から連絡を入れていきます。
生徒指導部長という役職の教員と連絡がとれたため、事情を話し、警察が待つ現場へ行くように伝え、何とかその日のうちに対応することができました。
その後、学校関係者で処分を検討した結果、今回も「退学勧告」ということになりました。
「退学勧告」であるため、勧告を受け入れる場合は「自主退学」というかたちをとるわけですが、それには手続上「退学届」を生徒側が学校側に提出する必要があります。

前述のとおり「退学処分」は会社でいう「解雇」なので、一方的な面が強いですが、「退学勧告」からの「自主退学」は「解雇」ではなく「退職」に近いため、このような形式になるわけです。
ところが生徒側はこの処分に不満があったようで、通常の退学届には理由欄に「一身上の都合」と書くケースがほとんどですが、このときは「学校に退学するように言われたため」とはっきり書いてこられました。
生徒側と学校側でどういうやりとりがあったのかは不明ですが、個人的には後味の悪い結末になったと感じたのを覚えています。
私が見た実例その3:傷害
最後も、以前の勤め先での出来事です。

10何年も勤めていると、こんなことの2つや3つどこでもあると思ってください。 決して、以前の勤め先が荒れていたというわけではありません。
前の2つの実例よりも大きな問題となった案件であるため、学校が特定されないように、詳細は割愛させていただきます。
ここではひとまず、「傷害事件を起こした」とだけご理解いただければと思います。
この事件、メディアにも報道されてしまい、社会的な影響もありました。
そのような事情も勘案し、学校側が下したのは「退学処分」。
前述のとおり「退学処分」は企業で言う「クビ・解雇」で、「退学勧告」よりもさらに重いものです。
この処分について、私よりもベテランの事務員に尋ねてみると「退学処分が下された例は、今まで見た記憶がない」という旨のことをおっしゃっていました。
私としても驚いた処分でしたが、やはりそれほどレアなケースだったようです。
番外編:裁判例
ここまで、私の勤め先で実際に起こった出来事について紹介してきました。
これらの実例に基づき、私が独自に作った判断基準は以下のとおりです。
- 法律に反する行為(未成年者の喫煙や万引き)をした者には「退学勧告」
- メディアで報道されるなど、社会を不安に陥れるような行為の場合は「退学処分」
このような考えに至った根本的な部分に「学校の裁量権」というものがあります。
この「学校の裁量権」が関わる最高裁判所の判例を2つ紹介します。

一応、私は行政書士試験に合格していますが、法律の専門家と言えるほどではないと考えておりますので、ここでは判例の紹介にのみ留めさせていただきます。
最高裁判所判例その1(裁判所ウェブサイトへのリンク)
最高裁判所判例その2(裁判所ウェブサイトへのリンク)
2つの判例の中で「社会観念上」または「社会通念上」という言葉が使われているところがポイントだと考えています。
つまり「社会通念」や「社会観念」という視点から見て、当該処分が「学校の裁量権」の範囲内かどうかを判断しているわけです。
この判例と、これまで紹介してきた勤め先での実例を組み合わせた私の考えは以下のとおりです。
「法に反する行為に対して、退学勧告という処分をすることは、社会通念上妥当であり、学校の裁量権の範囲内である」
ところが、今回ニュースになった件はこれとは反対の結果になっているように感じました。
これが私が「意外だな」と思った理由です。

もちろん、何度も言いますが私は法律の専門家ではありませんので、上述の考えはあくまで「私個人のものさし」でしかないという点はご了承いただければと思います。
まとめ
私立学校の事務員として働くうえで理解しておくべき「学校の裁量権」について、私の勤め先の実例や判例に基づき述べてきました。
「退学」などの学校が下す処分は、学生生徒等の今後の人生に大きな影響を与える可能性があるものです。
その点からも「学校の裁量権」は濫用されることがないようにしなければなりません。
しかし一方で、私立学校には「建学の精神に基づく自主性」も認められています。
この「自主性」に基づき、教育活動に取り組み、発展し続けることも求められており、そのためには「学校の裁量権」も必要となってきます。
そのバランスを考える際に重要なのが「社会通念上」という視点です。
皆さまも、自身の勤め先等の事例を探してみてください。
そのうえで、自分の中での「社会通念」と照らし合わせて妥当な判断だったかを考えてみてはいかがでしょうか。
今回のニュースの件は、今後の状況が気になるところですので、新たな展開があればまた紹介したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。