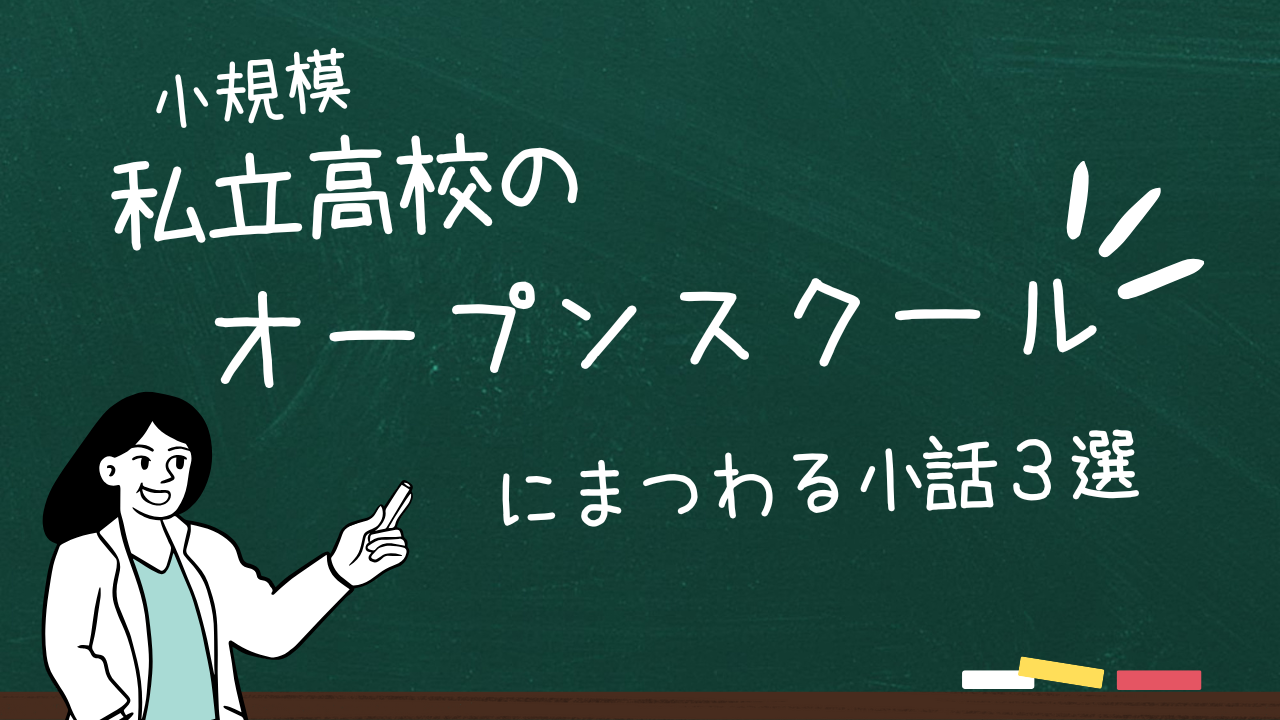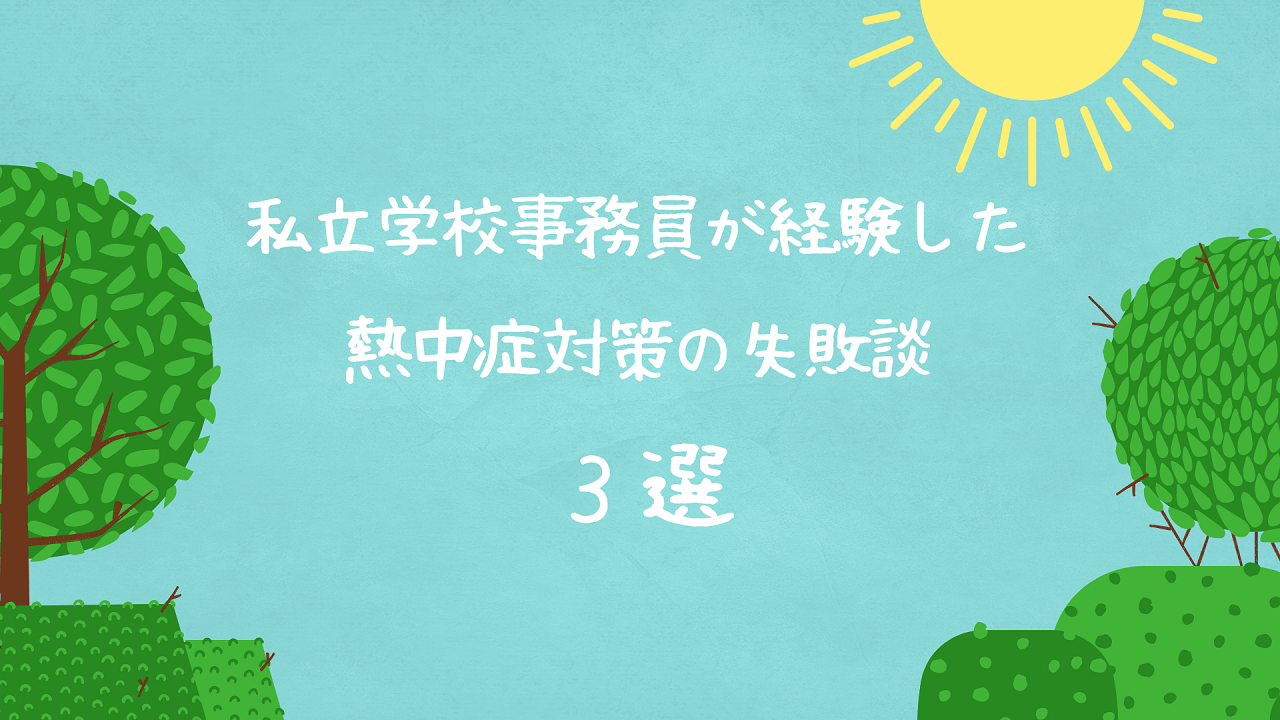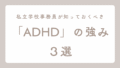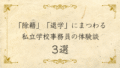この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・高校のオープンスクールにまつわる話が聞いてみたいと思っている人。
中学3年生は夏休みに向けて進路を固めて、勉強に励んでいる時期と思います。
それにあわせるかたちで、多くの高校でもこの時期にオープンスクールを開催しているという印象です。
もちろん、私の勤め先も実施しています。
中学生にとっては、実際の学校の様子を知ることができるいい機会。
高校側も自校の魅力をアピールするチャンスであるため、特に力を入れているイベントではないでしょうか。
そこでこの記事では、そんな大切なイベントであるオープンスクールにまつわるちょっとしたエピソードを3つ紹介したいと思います。
その3つは以下のとおりです。
- 在校生との交流
- 来場者用ノベルティグッズ
- 事務員の役割
私が実際にオープンスクールに携わってみて、感じたことや体験したことなどをまとめてみました。
何かの参考になれば幸いです。
【一番の盛り上がり】在校生との交流
多くの学校では、以下のようなオープンスクールの構成になっていると思います。
- 全体会:学校長や入試部長等のお話
- 体験授業:教科やコースごとの模擬授業など
- 個別相談:進路先や学校生活等について直接相談
実際のところメインは「体験授業」で、教員の皆さんも特に注力して準備をしています。
参加する中学生もそれを楽しみにしている様子です。

個人的な感想では、体験授業の中でも「理科」系が一番好評な印象です。
今の勤め先とは別の学校で見たのですが、液体窒素の実験でカチカチになったゴムボールを投げて割るとかロボットを動かしてみるといった内容は、教室の外まで楽しい声が聞こえてきましたね。
ただ、私の中で最もおすすめなのが「在校生との交流会」
参加した中学生が最も関心を示す催しという印象があります。
今の勤め先で実施しているのですが、時間無制限ということもあり、いつも話が盛り上がってなかなか参加者が帰ろうとしません。
準備するものはお菓子と飲み物、話をするためのちょっとしたスペース。
あとは、在校生がうまく話をしてくれます。
もちろん、実際に応対する在校生のコミュニケーション力がカギとなりますが、生徒会に所属する生徒にお願いしておけば、問題ないと思います。

実際、生徒会メンバーは毎年変わりますが、「今年の対応はちょっと・・・」みたいなことはありませんでした。
生徒会に立候補するくらいなので、皆それぞれが「学校のために」という思いを持って取り組んでくれているように感じています。
また、その在校生と中学生とのやりとりを横で聞いていると「そんな風に学校のことを見ていたのか」という新しい気づきも得ることができます。
年齢の近い者同士が話をすることでお互いリラックスすることができ、その状態の生の声を聞くことができる。
それが今後の学校づくりのヒントになるかもしれません。
「体験授業」は自分が体験できるとはいえ、進行の主体となるのは教員であり、個別相談は保護者がメインとなりがち。
そうした中で、中学生自身が積極的に関われる「在校生との交流会」は意義が大きいというのが私の感想ですので、おすすめします。
【そこはそんなに】来場者用ノベルティグッズ
オープンスクールにつきものなのが「ノベルティグッズ」です。
各学校が様々なグッズを準備し、またそうしたグッズを取り扱う会社からは連日のように「こんなのありますよ」といった連絡が学校に寄せられます。
もちろん、もらう側からすれば変なものをもらうよりも「実用的なもの」や「持っていて気分が上がるようなもの」をもらって方が嬉しいわけですが、ここに注力し過ぎるのはどうかというのが私の思いです。
特に今の勤め先の担当教員は、ノベルティグッズへの入れ込み具合が強いように感じています。
ちなみに、以前に紹介した「スペルが間違ったうちわ」を準備したのもこの教員です。

やたらと「これどう思いますか?」と尋ねてくるのですが、それよりも当日のイベントの構成や実施要項の整備に時間をかけた方がいいのではと思ってしまいます。
中でもこだわっているのが「食べ物」です。
以前の勤め先では実施していなかったのですが、今の勤め先では参加者に食べ物をプレゼントしています。
- パン
- アイスクリーム
- プチケーキ
などがありました。
確かにもらった側は喜んでいるのですが、なんとなく本来のオープンスクールの趣旨からは外れている印象を持ってしまいます。

一応、どの食べ物についても学校と何かしらの関係があります。
例えば、学校行事があった際に校内で販売されることがあるといったところです。
しかし、ただ単に「このパン、学校で販売することもあるんですよ」と伝えるだけでは「へぇー」と言われておしまいだと思うわけです。
そこに例えば、「このパンは、生徒とお店が共同で企画したパンです。こうした取組みを授業の一環として行っています」という学校の教育活動に結びつくエピソードがあるのであれば、学校のアピールになるように思います。
そのことを担当者に伝えるわけですが、なかなか理解していただけず、「とりあえず来場者が喜ぶから」ということで続けられています。
評判はいい取組みなので、もうあと一歩学校の魅力につながるように工夫できないかと思っている次第です。
【保護者に安心を】事務員の役割
今まで紹介してきた中で、事務員が登場することはありませんでしたが、オープンスクール当日は何もしていないのかというとそういうわけではありません。
学校によって違いはあると思いますが、私が担当した業務には以下のようなものがありました。
- 受付、校内巡回
- 駐車場誘導、道案内
- 個別相談対応

以前の勤め先では「受付」のみでしたが、今の勤め先では「駐車場誘導」や「個別相談対応」も担当しています。
この中でも私が一番重要だと考えているのが「個別相談対応」です。
オープンスクールを開催する目的は「学校のことを知っていただき、入学につなげる」だと思います。
そのために、学校が提供する「サービス」の中でメインとなる「教育」を実際に体験していただくわけですが、それだけでは不十分です。
例えば、とても魅力的な教育だったとしても、学費が高額だったりすると保護者としては負担が大きく、安心して通わせることができるか不安になります。
そこまで極端でなくても、保護者は学費に対する不安を多かれ少なかれ持っているというのが私の印象です。
そうした不安を払しょくするために、学費の支払い方や利用できる学費補助の制度などを説明する必要があり、そこを普段から業務を担当している事務員が担うわけです。
単純に、支払方法や奨学金をはじめとする学費補助制度を紹介するだけであれば、パンフレット等を見せればよいわけですが、それでは不安はぬぐい切れません。
実際にあったケースなどをあわせてお伝えし、自分と似たような状況の人でも学費の支払いができたということを知っていただくことで、安心していただくことができます。

だから、事務員として普段から「相談で使えるケースの収集」という意識で業務にあたるようにしましょう。
そう考えれば、多少面倒な対応でも「新しいケースが見つかった」と前向きにとらえることができます。
学校選びと言えば「教育」やその結果である「進学実績」などが重視され、事務員が関わることができる部分が少ないのは事実です。
しかし、「保護者の安心」という面から見れば、事務員としての知識や経験が役に立つケースもありますので、積極的に機会を見つけて参加することが大切だと思っています。
まとめ
冒頭にも述べましたが、オープンスクールは高校の生徒募集にとって重要な役割を担っています。
これから私立学校事務員を目指す人にとっては、そのような大事なイベントの裏側をこの記事から少しでも知っていただければと思います。
今現在事務員として働いている人は、この記事の内容に「そうそう」と共感いただければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。