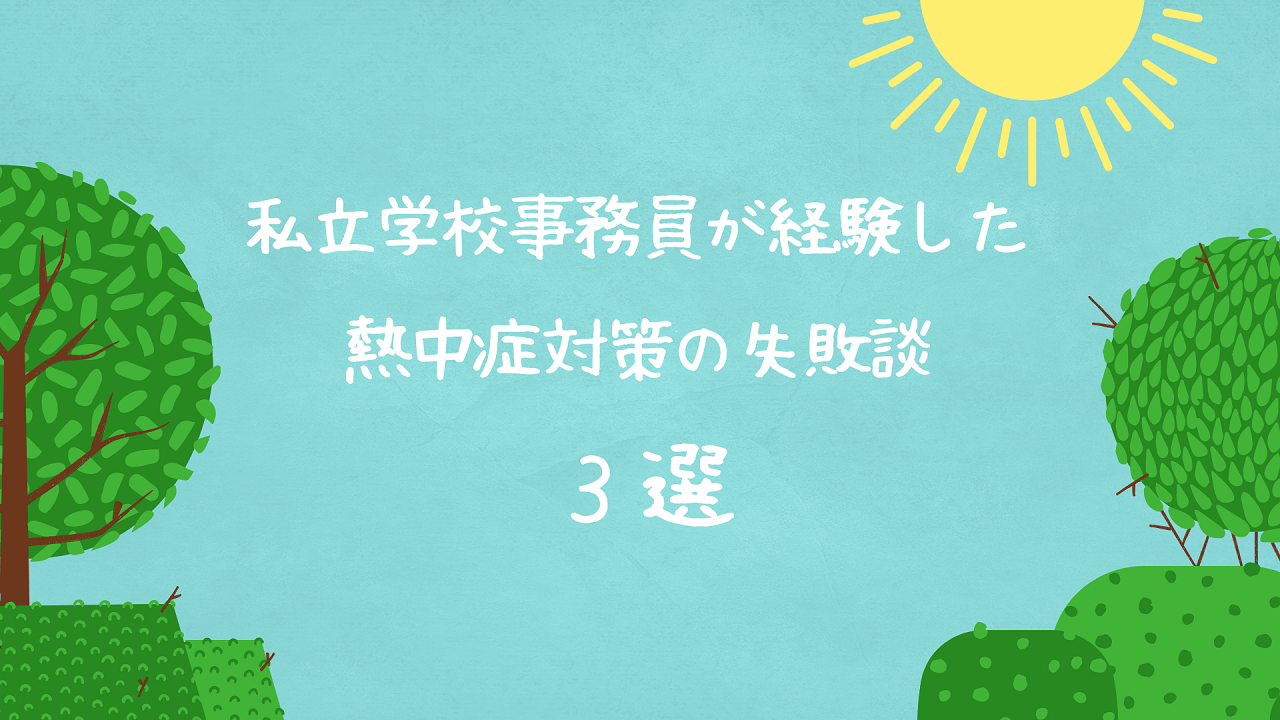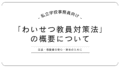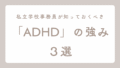この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・生徒等の熱中症対策で、どんな取組みをしていて、どんな失敗があったかを知りたいと思っている人。
暑い季節がやってきました。
気温が連日のように上昇し、通勤・通学することに気が重たくなっている人もおられるのではないでしょうか。
また、ニュースでも「〇〇市の学校で生徒が熱中症」といった報道をよく耳にします。
私立学校事務員として働いていると、こうしたニュースが他人ごとではないように感じてしまいます。
そんな熱中症対策として、当然学校は何らかの手を打つわけですが、時には思いがけない失敗をしてしまうこともあるわけです。
そこでこの記事では、私が体験した熱中症対策にまつわる失敗談を3つ紹介したいと思います。
その3つは以下のとおりです。
- 4つのスポットクーラー
- 電気のデマンド契約
- オープンスクール用うちわ
どの失敗も直接、熱中症被害につながったことはなく、情けない笑い話的な要素が強いものになりますので、息抜きがてらに読んでいただき、参考にしていただければと思います。
【①事前確認が大切】4つのスポットクーラー
皆さん、スポットクーラーってご存じですか。

私は駅の改札スペース付近などでよく見かける印象で、電車を待っている際によくそのクーラーが出す風にあたりに行きます。
同じことを考えている人が先に風を独り占めしていることが多いですが。
それなりに大きく重量もありますが、運べないことはなく、電源さえ確保できれば屋外でも使用できるため、利便性の高い冷房機器と思っています。
あるときこれを4台購入したのです。
もちろん熱中症対策のためにです。
校舎内の各教室等にはすでにエアコンが設置されているので、この4台は主に体育館で使用することを想定していました。
体育館の四隅にスポットクーラーを設置して風を送れば、それなりに空気が循環し、暑さが和らぐと考えたわけです。
そして、いよいよ暑いシーズンが到来し、スポットクーラーの出番がやってきました。
早速体育館の四隅に配置し、一機ずつスイッチをオン。
スポットクーラーは勢いよく運転し始めました。
ところが最後の4台目を起動したときに、トラブルが発生しました。
ブレーカーが落ちたのです。
まさか、体育館の電気のキャパを超えるほどの電気使用量になるとは思っていなかったので、「なぜ?」という思いでした。
結局、4台のうち1台は、ドラム式の延長コードを使って体育館から一番近い校舎の電源につないで使うことに。

事情を知らない人からすれば、体育館から外に向かって無駄にコードが伸びているように見えていると思います。
皆さまは、このようなことがないように事前によく調べてから購入しましょう。
もう一点、追加でお伝えしたいのは、暑さが本格的に厳しくなったときはスポットクーラー4台では追いつかないということです。
体育館の窓や扉を開け、スポットクーラーをフル稼働しても、暑さの方が上回ります。
やはり高額でも、建物自体にエアコンを導入する方向で検討した方がよいというのが、実体験に基づく感想です。
文部科学省も、
- 公立の小中学校等の体育館にエアコンを整備する事業に対して補助金を交付
- 私立学校の「持続可能な教育環境の実現」として、熱中症による事故を防⽌するため空調設 備の整備を推進
といったかたちで動いている様子ですので、私たちもこの流れに乗って、安心安全な学校づくりを進めていきましょう。
参考:「学校体育館への空調整備の早期実施に向けて」(文部科学省ホームページへのリンク)(https://www.mext.go.jp/content/20250306-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf)
参考:「文部科学省 令和7年度予算のポイント」(文部科学省ホームページへのリンク)(https://www.mext.go.jp/content/20250305-ope_dev03-000037774-1.pdf)
【②うっかりは禁物】電気のデマンド契約
これは以前の私の勤め先での話です。
熱中症対策の代表例といえば、やはりエアコンではないでしょうか。
ただ、ガンガンにエアコンをかけてしまうと、それはそれで学校の経営には大きな負担になります。
学校で働く者として、生徒等にとって安心安全な環境を確保しつつ、学校経営の面も考慮するといったバランス感覚が求められていると考えています。
そんな学校経営の観点から、以前の勤め先では電力会社と電気の供給等に関する契約をする際に、「デマンド料金制」で契約電力を決定していました。

詳しい話は本題から逸れてしまいますので省略しますが、ざっくり言うと「使う電気は最大でこれくらいです」ということをあらかじめ決めておいて、契約をしていると理解していただければと思います。
こうすることで電気料金の面でメリットがあるわけですが、このあらかじめ決めた最大使用量を超えてしまうと、逆に電気代に大きな悪影響をもたらします。
そのため、現在の使用量をモニターで確認することができたり、電気の使用量が最大値に近づいてくると設置している警報機からアラームが鳴り、知らせてくれたりする仕組みになっています。
そうした仕組みを理解したうえで、日々電気の使用量を監視しているわけですが、ある夏の暑い日にそれは起こりました。
電気の使用量がどんどん最大値に近づいていくので、早めに手を打とうと各自が行動を始めました。
一人は屋上に行って水を撒き、別の人は校舎の各所を回って使用していない教室等でエアコンがついていないかを確認するといった感じで、各自で電気の使用量を下げようとしました。
電気の使用量がそこまで上がるのが久しぶりだったので、そこにいた人全員が我を忘れてしまい、「なんとかしなくては」という思いで対応に走ってしまったわけです。
ところが、皆が対応に回ったことで肝心のアラームそのものの様子を監視する人が誰もいなくなってしまいました。
その結果、アラームが鳴り出したことに気づかず、最大値を超えてしまったのです。

おそらくは、あまりの暑さで冷房の設定温度を通常よりも低くした教室がいくつもあったのでしょう。
対応に出た人たちは、仕事をやり終えて皆満足げに戻ってきます。
そこで、ようやくアラームが鳴っていることに気づき、皆大慌て。
しかし、その時点で使用量が最大値を超えているので、なす術がありません。
モニターを見ていれば、使用量がだんだん増えていくことに気づき、設定温度そのものを上げるという対応もとれたのでしょうが、もう時すでに遅し。
使用量が見える化できたり、アラームでお知らせしてくれたりと便利な機能はいろいろ備えているわけですが、それを扱う「人」がいなければ意味がないわけです。
熱中症対策とそれにかける手間暇も含めたコストとのバランス。
その大切さと難しさを学んだ事例でした。
【③時間に余裕を】オープンスクール用うちわ
熱中症対策は、普段の授業だけに限った話ではありません。
オープンスクールなど、外部の人を招いて行うイベントの際にも実施する必要があります。

特にオープンスクールは、夏場に開催することが多いので、熱中症対策は必須です。
あるときのオープンスクールで熱中症対策として行ったのが、
- うちわを配布する
- 最寄駅から学校までの途中で冷たい飲み物を渡す
の2つでした。
後者の方は、通学路の途中に急な登り坂があるので、その登りきったところで飲み物を渡すというもの。
これは、のちのアンケートで大変好評をいただいた様子でした。
一方、前者の方ですが、こちらは学校の名前を入れた仕様になっており、学校の宣伝という目的も兼ねていました。
しかし、このうちわには重大な問題が。
なんと、アルファベット表記の学校名のつづりが間違っていたのです。
うちわが納品されたのが、イベント前日。
資料は事前に袋詰めをして準備しますが、うちわは配るだけなので、担当者は箱を開封せずにそのまま箱ごと配布場所に置いていました。
当日になって箱を開けて、担当者が私にうちわを見せます。
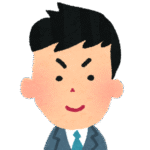
どうです?いいでしょ?

そうですね。(?何か違和感が)

あれ?それつづり間違ってません?
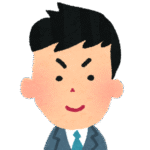
え?
こうして、イベント開始直前に問題が発覚したのです。
ただでさえ、あまりお勉強が得意ではない生徒が受験する学校。
それに輪をかけて、こんなスペルミスが発見されてしまうと「あぁ、あの学校やっぱり・・・」となってしまいます。
結局、担当者が校長と相談して、うちわはそのまま配布することになったのですが、正直SNSとかで画像が出回らないか心配でした。

幸い、そういったことが起こらなかったのでほっとしています。
後から確認したところ、こちらのミスではなく制作会社のミスだったので、代金不要となったのですが、お金の問題ではなく学校のイメージに悪影響を及ぼしかねない事態だったのでとても苦い思い出になりました。
- 納品日には余裕をもたせる
- 納品されたら即確認
熱中症対策から、これらの思わぬ教訓を学ぶことができました。
まとめ
熱中症対策にまつわる私の体験を3つご紹介したわけですが、これらのエピソードの共通点は「直接熱中症とは関係のないところにも問題は潜んでいる」ということだと思います。
「熱中症になる人がいないように」ということに意識を集中しすぎて、その他のところに気が回らなくなってしまう。
そんなことにならないように、今回の記事が参考になれば幸いです。
これから、もっと気温が上がり暑くなることが予想されます。
皆さまも、どうぞご自愛ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。