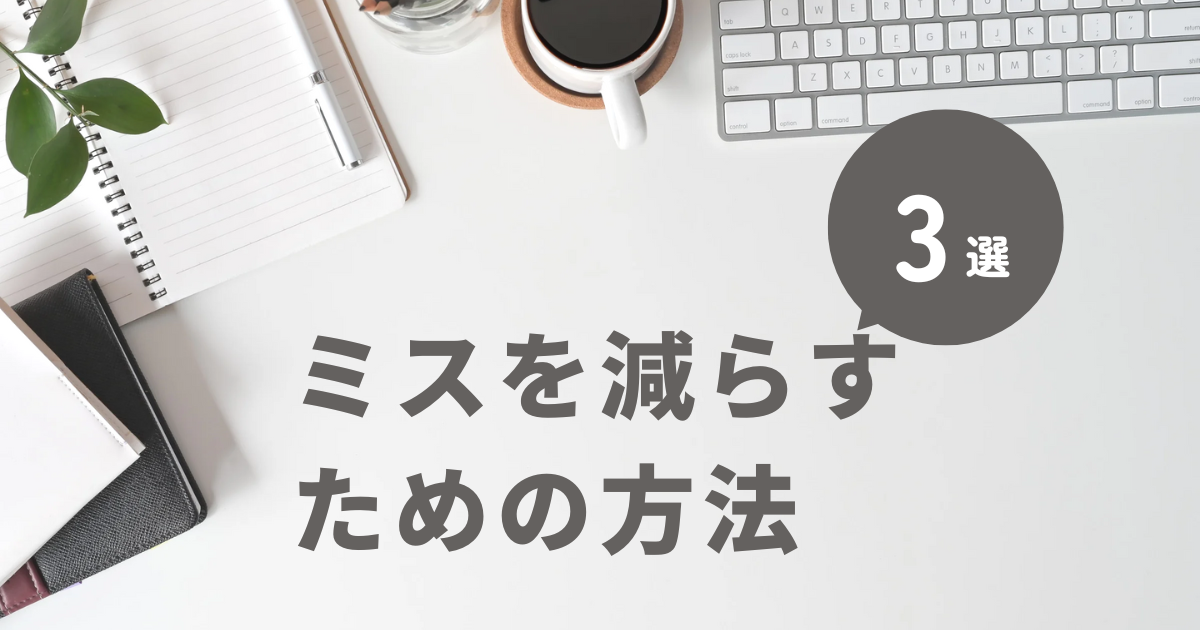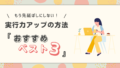この記事は以下のような人を対象としています。
・つい、うっかり小さなミスを繰り返してしまう。簡単にミスを減らすための方法が知りたい。
私立学校事務員の仕事、中でも経理・会計業務は正確さが強く求められます。
一つのミスが「補助金の不正受給」などのように報道され、学校に大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。
このように、お金を扱う仕事は「1つのミスも許されない」と言っても過言ではないものです。
その経理・会計業務に長年携わってきた私も、正直に言うといくつものミスを犯してきました。
そこで、そんなミスから私が学んできた「ミスを減らす方法」の中でも特に効果があったと実感している方法を3つご紹介いたします。
その3つとは以下のとおりです。
- 「目」と「耳」を使って確認する
- 行動を具体的に言語化する
- 「1秒の間」を取る
経理・会計業務担当だけに限らず、公共性の求められる「学校法人」という組織の一員として働く私立学校事務員は、ミスをなくし、周りからの信頼を得ることが大切です。
この記事の内容が、皆さんのミスを1つでも減らすことのお役に立てればと思います。
【ミスを減らす方法①】「目」と「耳」を使って確認する
書類やデータのチェック業務、皆さんも毎日1回は行っているのではないでしょうか。
私のような経理・会計担当の事務員の場合、全ての業務のうち、かなりの部分をこのチェック業務が占めています。
そして、扱う件数が多くなればなるほど、ミスが発生する可能性も高くなるという傾向があります。

恥ずかしながら、私もチェックミスを何度も犯しています。
例えば、振込先の間違い。
私も、本来振り込むべき取引先とは別の誤った取引先の金融機関口座へ振り込んでしまったことがあります。
お金の振り込まれた取引先から「これは何の支払いですか」という問い合わせの連絡を受けて初めて発覚し、「やってしまった」という気持ちでいっぱいになったのを今でも覚えています。

この時の金額は数万円でしたが、私の先輩は数億円の振込先間違いをしたことがあります。
ある証券会社へ金融商品を購入するための資金を振り込む手はずでしたが、別の証券会社にそのお金を振り込んでいました。 近くでそのやり取りを聞いていて、他人事ながらゾッとしました。
そして「もう二度と同じミスはしない」と決心し、様々な書籍を読んでその内容を試した結果、たどり着いたのがこの「目と耳を使って確認する」という方法です。
皆さん「目」で書類のチェックをすることは普段から行っていると思いますが、そこにさらに内容を読み上げ、「耳」で聞いて確認するというステップを加えます。
振込データの確認などの場合は、請求書に記載されている振込先金融機関と金額を読み上げながら、作成したデータや書類の内容をチェックするわけです。
この方法を取り入れてから一件もミスを犯していませんので、その効果を実感しています。
さらに、仕事上の文書作成でもこの方法を使っています。
作成した文書を一度読み上げてみると、誤字脱字を発見しやすくなるという効果があることに気がついたからです。

周りに人がいると、声を出すことに抵抗を感じるかもしれませんが、声の大小は効果に影響がありません。
実行する際の周り様子に応じたボリュームでやってみてください。
また、人数的に可能であれば二人一組で読み上げチェックをすることもおすすめします。
私は現金を扱う場合は同僚に声をかけて、一人が金種や枚数を読み上げ、もう一人が現物を確認するようにしています。
これも、このやり方をしていて一度もミスは起こっていないので、おすすめです。
【ミスを減らす方法②】行動を具体的に言語化する
これはいわゆる「チェックリスト」の作成です。
「チェックリストの作成なんか当たり前」と感じた方もおられると思います。
ただし、作成に際し注意が必要な点があります。
皆さんもよく、以下のようなことを書いたチェックリストを見かけませんか。
- 〇〇を徹底する。
- △△の内容をよく確認する。
「徹底」や「よく確認」は、個人によって程度の違いがあります。
ある人にとっての「徹底」「よく確認」が、別の人にとっては不十分だったりするわけです。

生徒会が作成する学校スローガンならいいかもしれませんが、事務員のマニュアルとしては避けたい表現ですね。
ですので、具体的な行動を書き出すようにしましょう。
ちなみに、私が会計ソフトにデータを入力する際に使用しているチェックリストで書いてある内容を、一部ですが以下に紹介します。
おそらく、私以外の別の事務員がこのチェックリストを見て入力作業をしても、私と同じ行動をとると思います。
この「誰が見ても同じ行動をとる」ということが、チェックリストにとって重要なポイントになります。
チェックリストを作成する際には、このことを意識しましょう。
可能であれば、作ったものを使って自分以外の人に実際にやってもらうのが一番です。
また、チェックリストの項目は、自分や他人のミスから「どんな行動をとればよかったか」を振り返りながら考えることをおすすめします。

ミスすると「なぜ、あんなことをしたんだろう」と考えがちですが、そこを「どうすればよかったのか」という問いに変換しましょう。
ミスを前向きにとらえることも、ミスを減らすための大切な要素です。
【ミスを減らす方法③】「1秒の間」を取る
自分がミスをした際に、あらためて状況を思い返してみると、はっきりと思い出せないということに気づきました。
そしてこれはおそらく、ルーティン業務を機械的にこなしていることが原因だと思いました。
慣れた作業なので、無意識に近い状態で書類のチェックやデータ入力を行っている場面があるということです。
そこで、作業する前に「1秒の間」を取るというルールを設定しました。

例えば振込データを入力する際、1件ごとに少し間を置いて「振込先は〇〇、金額は△△」と確認してから入力するようにわけです。
確認時には声を出すようにして、前述の「目と耳を使った確認」もここで実行します。
前述のチェックリストの項目例で挙げた「入力する内容を1回声に出して読み上げる」とは、このことを指します。
すると、「チェック+意識を入力作業に集中」という2つの効果を得ることができました。
データ入力作業は、入力件数が多いうえに一件あたりを見ても金額や振込先、勘定科目などたくさんの内容を入力する必要があるため、ついスピードを重視してしまいがちです。
そうなると思い込みや経験を優先し、内容の把握が不十分となります。
あえて「一秒の間」を取ることで、意識を「今」に集中させることができ、ミス防止にもつながることを実感しています。
まとめ
・「声だし」「チェックリスト」「一呼吸」こうした地味な行動が最もミス防止に効果的
私の経験やこれまでの職場の様子を思い起こすと、新入職員の方や異動してきた方など、新たな職場で働くことになった方々は、慎重に仕事に取り組む傾向が高いので、ミスは犯しにくいように思います。
逆に慣れてきた時ほどミスが発生しやすいように感じます。
「最近、機械的に仕事をこなしている」「ミスが増えてきた気がする」など思い当たる人は、今こそ基本を思い出し、この記事の内容を参考にしていただき、地味な行動を愚直に繰り返しやり通すことに立ち返りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。