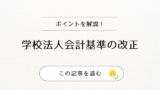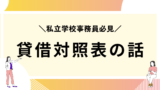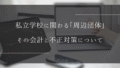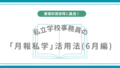この記事は以下のような人を対象としています。
・「会計」という言葉を聞くと「数字は苦手」と思い、敬遠してしまう人
これまでの記事でも、学校法人会計基準のことなど「会計」に関して、私立学校事務員として知っておくべき基礎知識について解説してきました。
私が経理・会計業務に長く携わってきたということももちろん関係していますが、社会人として働くうえで「会計」についての知識は必須だと考えています。
ただ「会計は大事」とわかっていても、「数字が絡むともう無理」など数字アレルギーを持っている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、数字の話は一旦脇に置いて、「会計の役割」について学ぶことができる書籍を紹介したいと思います。
学校法人会計基準に限定せず「会計」という大きな枠組みの中で、経理・会計担当の事務員でなくても理解しておくべき点を書籍の中から3つピックアップしました。
その3つとは以下のとおりです。
「稼ぐ力は会計で決まる」より引用
- 帳簿から始まる一連の流れ全体「会計」と呼びたいと思います。それは、「帳簿」→「監査」→「報告」→「責任」という流れです P30
- 開示によって(1)つなぐ、(2)浄化する、(3)鍛える、(4)計る、という4つの力が生まれる P46
- 企業理念をB/Sで表現する P74
2025年(令和7年)4月から施行された改正私立学校法や改正学校法人会計基準にもつながる部分がありますので、参考にしていただければ幸いです。
書籍の紹介
書籍名:稼ぐ力は会計で決まる
著者名:山下 明宏
出版社:幻冬舎
発売日:2025年3月
【役割その1】記録→チェック→公表→前進のサイクルを回して信頼獲得&組織の発展
書籍の言葉を再掲します。
「稼ぐ力は会計で決まる」より引用
- 帳簿から始まる一連の流れ全体「会計」と呼びたいと思います。それは、「帳簿」→「監査」→「報告」→「責任」という流れです P30
「帳簿」については、以前の記事で解説しました。
一言で言えば「組織の活動を記録したもの」が帳簿です。
「会計」と聞くとこの帳簿を作成する作業を思い浮かべる人が多いと思います。
そしてその帳簿にはたくさんの数字が記載されており、それが数字アレルギーの方を会計から遠ざけている要因になっているというのが私の印象です。
しかし、上述のように「会計」は帳簿作成に止まるものではありません。
書籍にそれを解説した箇所がありますので、以下に引用します。
「稼ぐ力は会計で決まる」より引用
- 帳簿をつけたら、それを税理士や会計士などの資格を持つ第三者がチェック(監査)して、最終的にはそれを決算書という形で報告する。その報告内容を踏まえて会社の業務を次に進めていくのが、社長の責任です。 P30

「会社」は「学校法人」、「社長」は「理事長」に置き換えていただければ問題ないと思います。
こうした一連のサイクルを「会計」と呼ぶ、という考え方をこの書籍では紹介しています。
ここが重要ポイント。
なぜかというと、このたびの私立学校法や学校法人会計基準の改正に関係しているからです。
以下の2点に注目してみましょう。
- 私立学校法改正:「会計監査人による会計監査を制度化」
- 学校法人会計基準改正:「ステークホルダーへの情報開示を主な目的として位置づけ」
それぞれの改正については、以下の記事も参考にしていただければと思います。
つまり、私立学校法改正の方が「監査」、学校法人会計基準改正の方が「報告」の部分にあたると考えられます。
そして、この「監査」と「報告」の部分を改正した目的は「社会の信頼を得て、一層発展していくため」です。
これらの点をまとめると、広い意味での「会計」に関する部分を改正することで、社会からの信頼獲得や学校法人の一層の発展を図ろうとしたと言えると思います。

特に「監査」の方は、書籍でも「最も重要」と紹介されています。
監査を経ることで、帳簿が信頼性のあるものとして意味を持つことになるからです。
まとめると以下のとおりです。
- 会計は「帳簿」→「監査」→「報告」→「責任」のサイクルのこと
- このサイクルを回すことで、社会の信頼を得て、発展することが会計の役割の1つである
さらに、書籍では「責任」の部分が社長に限定されていますが、「報告」を受けて事務員も「自分が社会からの信頼獲得、学校の発展のために何ができるか」を意識するようになれば、「会計」を自分事と考えられるようになるのではないでしょうか。
【役割その2】「外」と「内」をつないで、信頼獲得&組織の発展
書籍の言葉を再掲します。
「稼ぐ力は会計で決まる」より引用
- 開示によって(1)つなぐ、(2)浄化する、(3)鍛える、(4)計る、という4つの力が生まれる P46
役割その1でも少し触れました「監査」と「報告」に関わる部分です。
せっかく「監査」しても「報告」しなければ意味がありません。
特に、結果を外部に「開示」することが信頼獲得には必要不可欠です。
まず学校法人という「内部」と取引先などの「外部」をつなぐ力が会計にはあります。
「開示」した内容を外部の方が信頼してくださることで、継続的な取引等が行われるようになり、学校法人は活動に必要な役務の提供を受けることができます。
また保護者や国、地方公共団体とつながり、信頼を得ることで学納金や補助金といった収入を確保することができるわけです。
開示によって、収入の確保や役務の提供など、学校法人の永続的な活動に必要なものを外部から得るための「つなぐ」力。
これが4つの力のうちの1つ目です。
そして、開示するということは外部の目に触れるわけですから、当然「きれいな状態」を見せたいと思うようになります。

書籍でも触れていますが、自分の部屋でも外部の人に見せようと思うと、きれいな状態にしておこうという気持ちが起こりますよね。
こうした「きれいな状態を作る努力」を生み出すことが、2つ目の力である「浄化する」にあたります。
もちろん「きれいな状態」であればよいのですが、年度によっては収支状況がよくない「きれいではない状態」の時もあります。
そうした時でも、隠すことなく公開することが大切であることは言うまでもありません。
さらに、「もっときれいな財務状態を目指す」という気持ちが沸き起こることで、教育力の強化や業務効率のアップといった自らを「鍛える」取り組みにつながります。
これが3つ目の「鍛える」力ということです。
最終的には、これら「つなぐ」「浄化する」「鍛える」の成果が出ているかを決算書などから把握する力が必要となるわけですが、それが4つ目の「計る」力のことを指します。
これら4つの力は全て「信頼獲得」や「組織の発展」につながります。
まとめると以下のとおりです。
- つなぐ力:学校法人の永続的な活動に必要なものの確保
- 浄化する力:正確性、透明性の向上
- 鍛える力:経営力の向上
- 計る力:現状の把握
この4つの力を学校法人に身につけさせ、社会からの信頼獲得や組織の永続的な発展につなげることが会計の役割の1つとなります。
【役割その3】理念を「見える化」して信頼獲得&組織の発展
書籍の言葉を再掲します。
「稼ぐ力は会計で決まる」より引用
- 企業理念をB/Sで表現する P74
1つ目や2つ目とは異なり、具体的な決算書であるB/S(貸借対照表)が出てきます。
B/Sについてはこちらの記事もご参照ください。
B/Sには、学校法人設立から今までの積み重ねが記載されます。
ということは、「今までどういった理念で法人を運営してきたか」ということの結果が表れているとも言い換えることができるわけです。
つまりB/Sを見て、財務状況が悪いようであれば、その運営が社会から評価されていないということになります。
「理念が社会に受け入れられているか」を映し出す「鏡」の役割。
これが、会計の3つ目の役割になります。
B/Sの見方については、前述の関連記事の方をご参照いただければと思いますが、それに加えてもう一つの見方を紹介したいと思います。
これも以前の記事で紹介しましたが、「決算書を金額と面積が比例するような図(縮尺比例図)」に変換してみる方法を応用します。
まず、自分の勤め先の直近の決算におけるB/Sを縮尺比例図にしてみます。
そして、その図を「型」として覚えてしまいます。

細かな数字や比率は覚える必要はありません。
各ブロックのなんとなくの大きさを覚えれば十分です。
それを過年度のB/Sの縮尺比例図と見比べてみるわけです。
「型」が変化していれば、理念の社会からの評価も変化していると言えます。
また、学校法人が理念の実現のために何かしらの施策を講じていれば、それも「型」に反映されます。
これも「鏡」の役割の1つです。
「理念の実現」という内部の様子と「理念に対する社会の評価」という外部の様子をB/Sの「型」という「鏡」から感じることができると思います。

会計の知識は全く必要ありません。
裏紙にでも手書きで図を描けば、誰でもできるのでやってみてはいかがでしょうか。
ちなみにこの決算書を「型」として意識するということも、この書籍で紹介されている内容になります。
まとめると以下のとおりです
- 「理念に対する社会の評価」=「信頼獲得」
- 「理念の実現」=「組織の発展」
会計はこれらを映す「鏡」としての役割があるということになります
まとめ
3つの役割の共通点は「信頼獲得や組織の発展のため」でした。
皆さまが会計を学ぶということは、帳簿や決算書の見方などを学ぶだけではなく、「信頼獲得」や「組織の発展」のために必要な知識を身につけるということになります。
そう考えれば、経理・会計担当以外の事務員の方々も会計を学ぶ必要があると理解していただけるのではないでしょうか。
私立学校事務員として、会計の役割を意識して日々の業務に取り組みましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
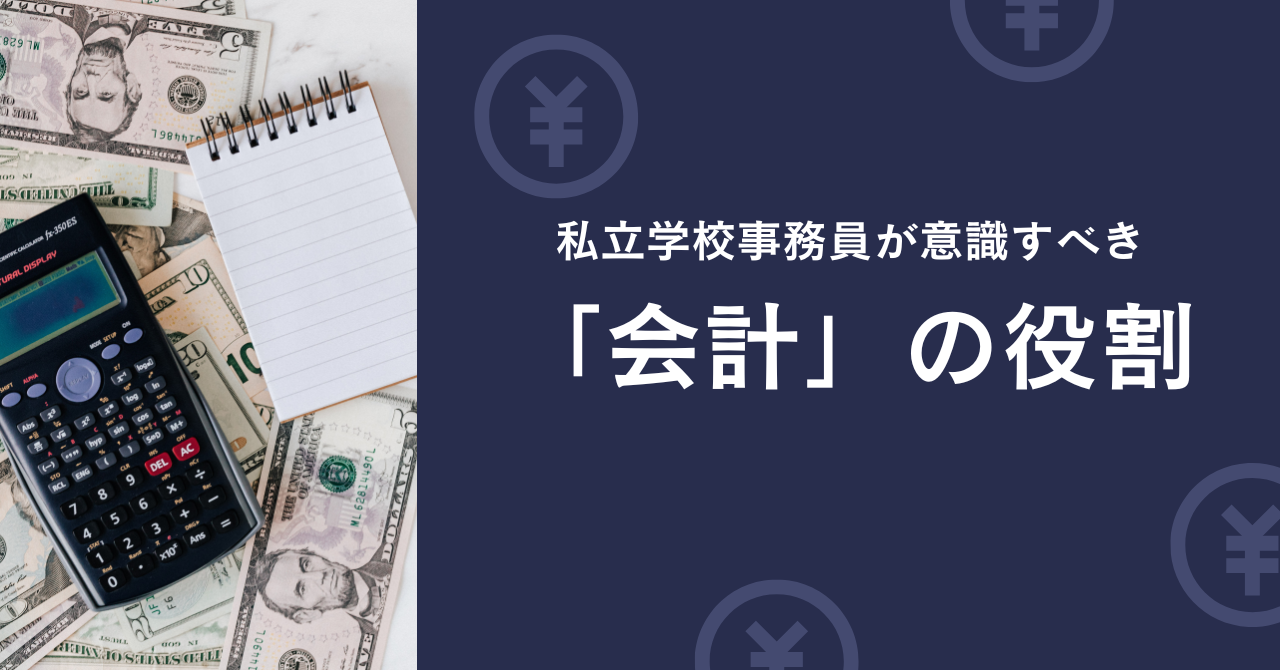
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=21551686&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7647%2F9784344987647_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)