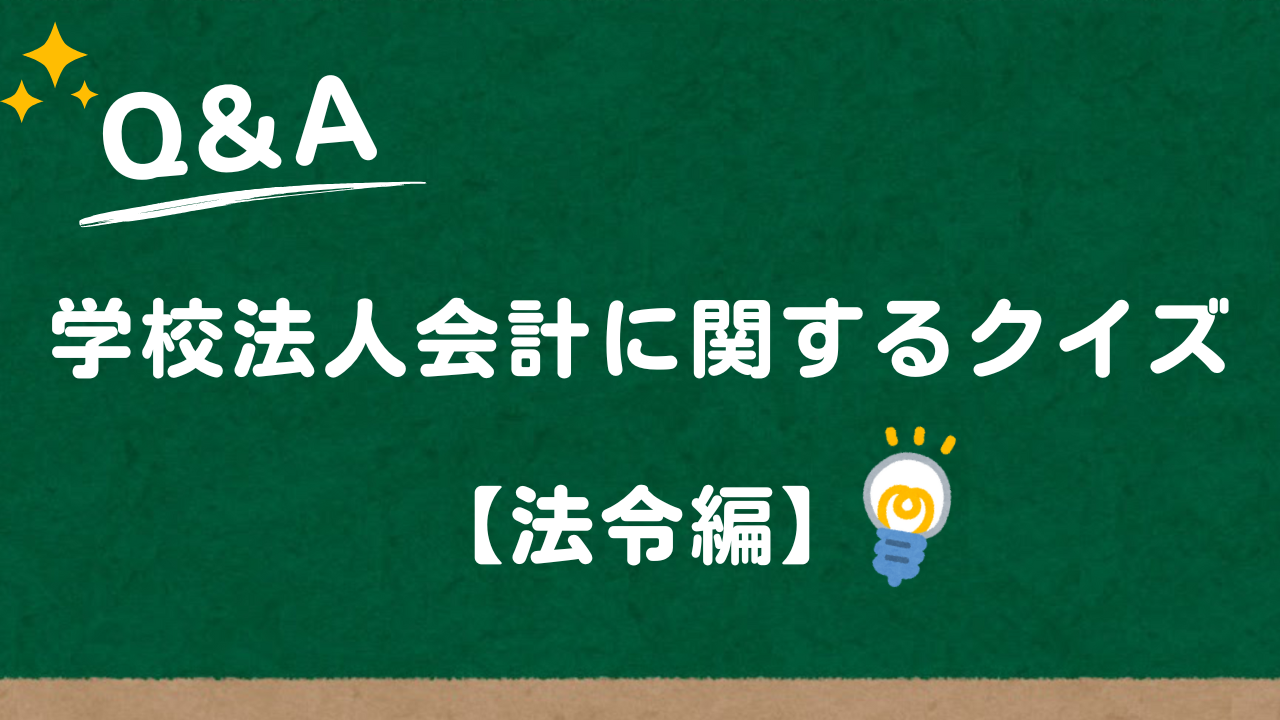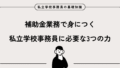この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・学校法人会計に関する知識を身につけたいと考えている人。
「学校法人会計」と聞くと、
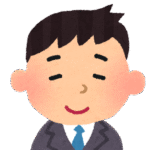
会計でしょ?私には関係ないし。
と思ってしまう私立学校事務員の方が多いというのが私の印象です。
確かに学校法人会計「基準」の知識を使って、計算書類の作成など直接的に業務に携わる機会があるのは、経理・会計担当部署の事務員に限られると思います。
しかし、それはあくまで学校法人会計「基準」の話。
「基準」の中の細かなルールは別として、「学校法人会計」自体は私立学校法など、私立学校に勤める上で理解しておくべき法律等とつながりがあるものです。
そうしたつながりと学校法人会計基準が定める原理原則の部分をおさえておくことは、私立学校事務員として必要だと私は考えています。
そこで今回は、学校法人会計にまつわる法令についてのクイズを作成してみました。
形式はビジネス会計検定3級を参考にしています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとに今回の出題に関連した情報を紹介しています。
私立学校事務員として社会的責任を果たせるよう、知識を身につけておきましょう。
なお、この記事は掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
【第1問】計算書類全般①
私立学校法は学校法人に対し、毎会計年度終了後三月以内に計算書類等を(ア)することを義務付けている。一方、私立学校振興助成法では助成対象学校法人に対し、毎会計年度終了後三月以内に計算書類等を(イ)することを義務付けている。
(ア)と(イ)に入る言葉の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
正解:B
私立学校法と私立学校振興助成法の目的はともに「私立学校の健全な発達」です。
その健全な発達のために、私立学校法は全ての学校法人に対して、計算書類等の作成を義務付けている一方で、私立学校振興助成法では助成対象学校法人に対し、計算書類等を所轄庁に提出することを義務付けています。

助成を受けたかったら、作成だけでなく所轄庁に提出もしないとだめですよ、ということですね。
私立学校法の方で全ての学校法人に計算書類等の作成を義務付けているから、私立学校振興助成法ではわざわざ作成を義務付ける必要はないということです。
どちらの法律に何が定められているか、混乱しがちなので覚えておきましょう。
参照:私立学校法第103条第2項、私立学校振興助成法第14条第4項
【第2問】計算書類全般②
次のうち、私立学校法の定めに基づき、学校法人が作成しなければならないと学校法人会計基準上で定められている計算書類に含まれないものはどれか。
正解:C
学校法人会計基準では以下のとおり定められています。
第十六条 法第百三条第二項の規定により学校法人が作成しなければならない各会計年度に係る計算書類は、次に掲げるものとする。
一 貸借対照表
e-GOV法令検索より引用
二 次に掲げる収支計算書
イ 事業活動収支計算書
ロ 資金収支計算書及び資金収支計算書に基づき作成する活動区分資金収支計算書
以上のとおり財産目録は計算書類の中には含まれていません。
なお、財産目録は計算書類には含まれていませんが、私立学校法上、学校法人に作成が義務付けられている書類には該当します。
【第3問】計算書類全般③
次のうち、私立学校法の定めに基づき、学校法人が作成しなければならないと学校法人会計基準上で定められている計算書類の附属明細書に含まれないものはどれか。
正解:B
これも学校法人会計基準では以下のとおり定められています。
第四十一条 法第百三条第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、次に掲げるものとする。
一 固定資産明細書
e-GOV法令検索より引用
二 借入金明細書
三 基本金明細書
以上のとおり現預金明細書は計算書類の附属明細書に含まれていません。
現預金明細書は、各学校法人が独自の決算資料として作成している場合があります。
【第4問】収支予算書
次のうち、予算又は予算書の作成を義務付けていないものはどれか。
正解:C
私立学校法では予算及び事業計画の作成を義務付けています。
(予算及び事業計画)
e-GOV法令検索より引用
第九十九条 学校法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。
一方、私立学校振興助成法では収支予算書の作成を義務付けています。
第十四条 第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人(以下この条において「助成対象学校法人」という。)は、収支予算書を作成しなければならない。
e-GOV法令検索より引用

設問1と同様で、予算の作成義務は私立学校法で定めており、さらにそれを「収支予算書」というかたちでまとめることを私立学校振興助成法で義務付けていると理解しておけばよいと思います。
なお、学校法人会計基準では各種計算書類の作成にあたって、予算と対比して記載することを義務付けています。
【第5問】計算書類等の閲覧
次のうち、計算書類等の関係者等への閲覧について定めているものはどれか。
正解:A
私立学校法では「計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等」について定めています。
特に閲覧については、計算書類等が書面で作成されているか電磁的記録で作成されているかといったケースごとの定めがあります。
債権者等から閲覧の請求があった場合に適切に対応できるようにおさえておきましょう。
参照:私立学校法第106条第1項から第4項
【理解度アップ】法的根拠の確認習慣
学校法人会計の中でも、お金とは関係のない法的な部分を中心に問題を作成しました。
というのは、私たち私立学校事務員の仕事は法令を根拠にしているものが多いと思っているからです。
しかし、この法的根拠を確認する習慣がない事務員を見かけることがあります。
例えば最後の設問にある計算書類等の備置きについて、以前の勤め先で高校事務室に勤務していたときのエピソードを紹介します。
私立学校法の定めにあるとおり、計算書類等は事務所に備え置かなければならないことになっています。
ところが、このことを知らない事務員が過年度分の計算書類等を処分しようとしたのです。
処分を止めさせて事情を尋ねると、
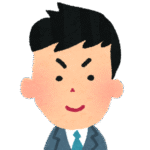
事務員
本部にあるから処分してもいいと思った。
とのこと。
私立学校法には、計算書類等の備置きの期間まで定めているので、その期間を超えたものを処分するのであれば問題ないわけですが、様子から勘案するとそのような理解があったうえでの行動ではないようです。
私は経理・会計担当部署に配属されていた際に、上司から私立学校法に基づいて計算書類等を各設置校の事務室に送る旨を教えられていましたが、この事務員はそういったことを教わったことがありませんでした。
その一件をきっかけに、私は異動先の部署で後輩や新人職員に計算書類等の備置きについて説明するように心がけています。
これはあくまで一例でしたが、このように、
- なぜこの書類を作らなければならないのか
- なぜこのスケジュールなのか
といったことの法的根拠を確認する習慣を私立学校事務員は身につけておくべきだと私は思っています。
それらの定めは、
- 学校法人の関係者に正しい情報を公表するため
- 税金を財源とする補助金を適切に交付するため
といったことを目的としているからです。
これらの目的は最終的に「私立学校の健全な発展」につながるものです。
私たちが取り組む一つひとつの業務が、この「私立学校の健全な発展」に関わるものであることを自覚するためにも、法的根拠を確認する習慣を身につけることをおすすめします。
まとめ
何かを覚える際、インプットよりもアウトプットの比重を多くした方がよいという話を書籍で読んだことがあります。
ここで言うアウトプットは「人に説明する」や「問題を解く」といったものです。
私自身、資格試験の際に意識的にアウトプットの機会を増やすようにして良い結果を得ることができたと実感しています。
この記事でアウトプットした経験が、皆さまの知識の習得につながれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。