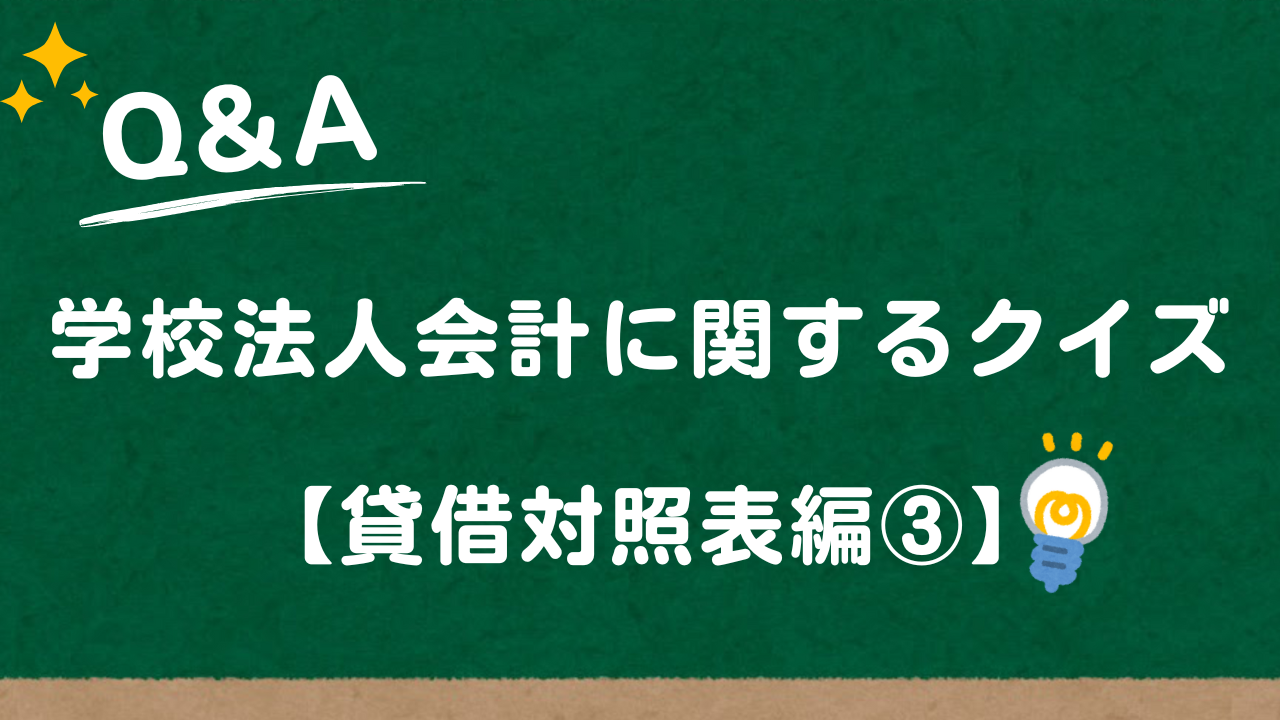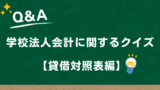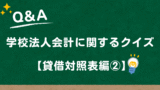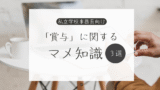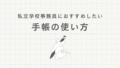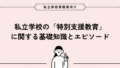この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・学校法人会計に関する知識を身につけたいと考えている人。
以前の記事で学校法人の貸借対照表についてのクイズを出題しました。
以前の記事でも述べましたが、貸借対照表には学校法人の財政状況を表す重要な情報がたくさん掲載されています。
そのため、1回だけでなく複数回にテーマを分けて出題したいと考えています。
そこで今回は、貸借対照表の「負債」をテーマにクイズを作成してみました。
形式はこれまでと同様にビジネス会計検定3級を参考にしています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとに今回の出題に関連した情報を紹介しています。
学校法人が負っている「負債」の内容が適切に理解できるよう知識を身につけ、私立学校事務員として社会的責任を果たせるように準備しておきましょう。
なお、この記事は掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
【第1問】負債の評価
次の文章の( )に当てはまる語句として適切なものはどれか。
負債については、基本的に会計帳簿に( )を付すものとされている。
正解:C
学校法人会計基準の条文を引用します。
第十一条 負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付すものとする。
e-GOV法令検索より引用
資産の時は、原則「取得価額」で評価することとなっており、その取得価額とは、本体価格に取付費用など「付随費用」を加えたものとされています。
この付随費用に含まれないものの一つに「家電リサイクル費用」がありますので、これを例に資産と負債の計上の違いを見ておきましょう。
例えば以下のようなエアコンの取替費用が発生したとします。
- 新たなエアコンの取得価額(設置費用含む):100
- 古いエアコン処分に係る家電リサイクル費用:10
こちらについて年度内に支払いまで完了して、エアコンが学校の資産となった場合、貸借対照表の「資産の部」には、100が記載されることとなります。
一方、年度末までに支払いが完了せず、未払金となった場合、貸借対照表の「負債の部」には、110が記載されます。

取替工事をした会社からの請求書に記載された金額の総額を、そのまま負債の額として載せるというイメージですね。
この「エアコンの更新」の事例のように、同じ内容でも資産と負債とでは記載する金額に違いが生じる場合があるということを覚えておきましょう。
【第2問】引当金の評価
次の文章の( )に当てはまる語句として適切なものはどれか。
引当金については会計年度の末日において、将来の事業活動支出の発生に備えて、その合理的な見積額のうち( )の負担に属する金額を事業活動支出として繰り入れることにより計上した額を付すものと定められている。
正解:B
学校法人会計基準の条文を引用します。
第十一条
e-GOV法令検索より引用
2 退職給与引当金のほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の事業活動支出の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を事業活動支出として繰り入れることにより計上した額を付すものとする。
前設問も含め、この負債に関する条文は令和7(2025)年4月1日施行の改正学校法人会計基準から追加されたものです。
この条文の追加により、引当金の計上要件が明確になりました。
具体的には以下の4点が要件となります。
① 将来の特定の事業活動支出・・・次年度以降に事業活動支出が見込まれる
文部科学省ホームページより引用
(例:次年度に賞与支出が見込まれる)
② その発生が当該会計年度以前の事象に起因している・・・支出の原因が当年度以前である
(例:当年度の12月~3月の勤務実績に応じて次の賞与支給金額が決まる)
③ 発生の可能性が高い
(例:賞与の支給がほぼ確実に見込まれる)
④ 金額を合理的に見積もり可能
(例:賞与の計算方法が給与規程に明記されており、年度末時点で計算可能)
【解説資料】学校法人会計基準の改正等について
(文部科学省ホームページへのリンク)

引当金は、実際にはまだ支出が発生していないけど、発生したものとみなして準備しておく「みなし貯金」みたいなイメージですね。
引用した部分の(例)に関係していますが、この改正により、多くの学校法人において「賞与引当金」というものを計上する必要性が生じました。
賞与引当金については、後ほど触れたいと思います。
【第3問】負債の概念
次のなかから、負債に該当する項目の合計額を計算した場合、正しいものはどれか。
貸付金30 借地権50 減価償却引当特定資産70 借入金50 施設利用権60 前受金20
正解:A
問題文で挙げたものを分類すると以下のようになります。
資産:貸付金、借地権、減価償却引当特定資産、施設利用権
負債:借入金、前受金
よって負債に該当するものを合計した結果は70となります。

「引当金」と「引当特定資産」は名称が似ていますが、全く別物です。どちらが資産でどちらが負債なのかを整理しておきましょう。
経理・会計担当以外の人でも「負債」の内容は覚えておくべきです。
【第4問】固定負債の項目
次のなかから、固定負債に該当する項目の合計額を計算した場合、正しいものはどれか。
退職給与引当金150 徴収不能引当金50 長期未払金100 短期借入金50 預り金50
正解:C
問題文で挙げたものを分類すると以下のようになります。
固定負債:退職給与引当金、長期未払金
流動負債:短期借入金、預り金
注記事項:徴収不能引当金
よって固定負債に該当するものを合計した結果は250となります。

徴収不能引当金は「引当金」という名称がついていますが、負債の部には記載されません。
貸借対照表の「注記」という部分に記載されるルールになっています。
【第5問】流動負債の項目
次のなかから、流動負債に該当する項目の合計額を計算した場合、正しいものはどれか。
基本金200 徴収不能額100 未払金150 前受金50 水道光熱費50 1年以内償還予定学校債100
正解:A
問題文で挙げたものを分類すると以下のようになります。
流動負債:未払金、前受金、1年以内償還予定学校債
純資産:基本金
支出:徴収不能額、水道光熱費
よって流動負債に該当するものを合計した結果は300となります。

未払金も「長期」未払金という名称になった場合は、流動負債ではなく固定負債に属することになります。文言に注意してみましょう。
学校債は多くの学校法人にとってなじみの薄いものだと思いますので、ここでは名称と負債に属するということだけ覚えておけば問題ないと思います。
【理解度アップ】賞与引当金
賞与引当金については以前の記事で少しだけ紹介しました。
設問2で紹介しましたとおり、学校法人会計基準の改正により、引当金の要件が明確化されたことでこの賞与引当金というものを引き当てることになったわけです。

決算業務を担当する者からすれば、ただでさえ慌ただしい決算でやることが一つ増えて正直面倒くさいという思いです。
引き当てる目的としては退職給与引当金と同様に「正しい財務状況をステークホルダーに公表する」だと推察されます。
確かに教職員側からすると、
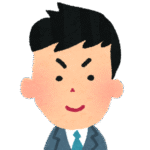
自分たちの賞与について学校法人が払う義務を認識して準備してくれている。
という見方もできると思われます。
具体的な計上方法については、各学校法人で異なると思われますが、参考までに私の今の勤め先のケースを少し紹介したいと思います。
まず、賞与基準日は毎年6月1日よ12月1日と給与規程に定められています。
加えて、基準日以前6ヶ月以内の期間における在職期間に応じて、支給の割合が調整される仕組みにもなっています。

4月1日入職だと、3ヶ月未満なので30%支給みたいな感じですね。
こうした規定により、6月分の賞与については、前年度(12月2日から3月31日)の勤務実態が反映されるため、前述の②の要件を満たすことになります。
①と③の要件も今のところ満たしていますので、④の見積もりを行うことになります。
見積もりの対象となるのは、
- 賞与支給額
- 所定福利費(共済掛金)
の2点です。
これらを計算して、前年度分と今年度分とに期間案分し、賞与引当金を計上します。
令和7年度のケースでは、令和8年6月1日支給の賞与が引当金対象となるので、
- 令和7年12月2日から令和8年3月31日:120日(0.66)
- 令和8年4月1日から令和8年6月1日:62日(0.34)
の期間で案分することになるわけです。
こんな感じで決算に向けた準備を進めています。
まとめ
企業や学校法人など、組織は負債が支払えなくなったときに倒産します。
言い換えれば、負債を賄うだけの資産がなくなったときに倒産するとも言えそうです。
そう考えると、資産の金額、特に現金預金の金額が重要となるわけですが、同時に負債の中身も重要となってきます。
そのためには、すぐに支払わなければならない負債はどのくらいあるのか、といったことを貸借対照表から読み解くことができるようになる必要があります。
今回の記事で皆さまが、そんな負債についての知識を少しでも身につけられたのであれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。