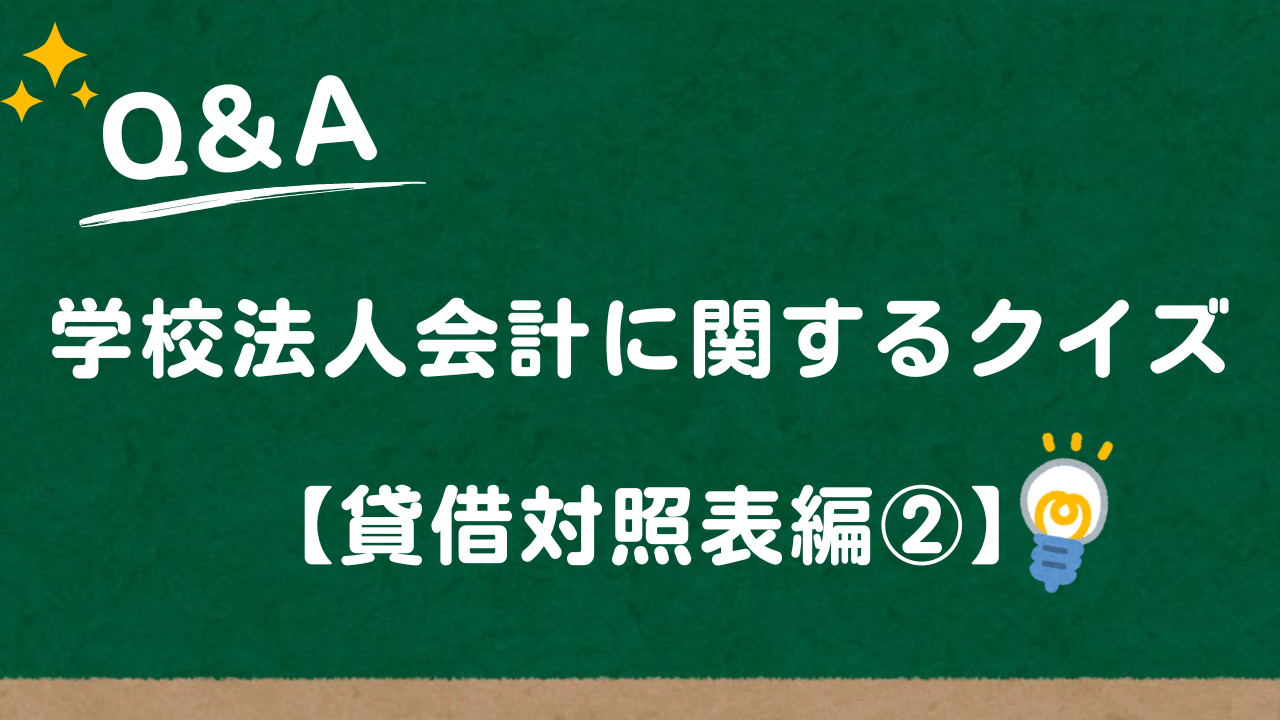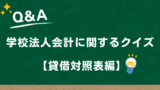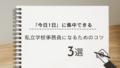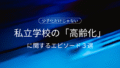この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・学校法人会計に関する知識を身につけたいと考えている人。
以前の記事で学校法人の貸借対照表についてのクイズを出題しました。
前回も述べましたが、貸借対照表には学校法人の財政状況を表す重要な情報がたくさん掲載されています。
そのため、1回だけでなく複数回にテーマを分けて出題したいと考えています。
そこで今回は、貸借対照表の「資産」をテーマにクイズを作成してみました。
形式はこれまでと同様にビジネス会計検定3級を参考にしています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとに今回の出題に関連した情報を紹介しています。
学校法人が保有している「資産」の内容が適切に理解できるよう知識を身につけ、私立学校事務員として社会的責任を果たせるように準備しておきましょう。
なお、この記事は掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
【第1問】資産の評価①
次の文章の(ア)および(イ)に当てはまる語句の組み合わせとして適切なものはどれか。
資産を購入した場合、(ア)に(イ)を加えた金額を取得価額といい、学校法人の場合、資産の評価は、取得価額をもってするものと定められている。
正解:A
学校法人会計基準の条文を引用します。
七条 資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。
e-GOV法令検索より引用
この「取得価額」は購入価額に付随費用を加えたものになります。
購入価額は本体価格とほぼ同じものとここでは理解していただければ結構です。
一方、付随費用には以下のようなものが挙げられます。
- 取付費用
- 引取運賃
- 仲介手数料
例えば100万円の装置を購入して、その取付費用として1万円が生じた場合、取得価額は101万円になるといったイメージです。
この場合、貸借対照表には101万円の有形固定資産として掲載されるということになります。
【第2問】資産の評価②
学校法人会計基準第7条に基づき、金融資産も原則として取得価額で評価されますが、評価した価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価するものと定められている。
少なくとも時価が帳簿価額の何%相当額を下回った時にこの「著しく低くなった場合」に該当するとされているか。
正解:B
学校法人会計基準の条文を引用します。
第九条 有価証券については、第七条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。
e-GOV法令検索より引用
学校法人会計基準では、この「著しく低くなった場合」について具体的に明示されていませんが、学校法人委員会実務指針第45号で、50%以上の下落があった場合は「著しく低くなった場合」に該当するとの見解が示されています。

私のこれまでの勤め先などを見ていても、多くはこの判断基準を用いている様子でした。
なお同指針では、下落率が30%以上50%未満の場合については、
「各学校法人が合理的な基準を設けて判断する」
という見解を示している点もおさえておきましょう。
加えて、同基準第9条では「有価証券については」と定めているため、土地などはこの評価方法の対象外とされていることも理解が必要です。

土地の価格が50%以上下落していても、取得した時の金額のまま貸借対照表には載っているということですね。
【第3問】資産の概念
次のなかから、資産に該当する項目の合計額を計算した場合、正しいものはどれか。
特定資産100 預り金20 未収入金30 借入金50 現金預金80 前受金10
正解:B
問題文で挙げたものを分類すると以下のようになります。
資産:特定資産、未収入金、現金預金
負債:預り金、借入金、前受金
よって資産に該当するものを合計した結果は210となります。

特定資産とは、「退職金用」とか「施設設備用」といった感じで、多額の資金が必要となるものについて、あらかじめ用途を決めて貯めておいた資産とここでは理解していただければ結構です。
経理・会計担当以外の人でも何が「資産」になるのかは覚えておきましょう。
【第4問】その他の固定資産の項目
次のなかから、その他の固定資産に該当する項目の合計額を計算した場合、正しいものはどれか。
特定資産200 ソフトウェア100 建設仮勘定150 電話加入権50 構築物100 退職給与引当金200
正解:B
問題文で挙げたものを分類すると以下のようになります。
有形固定資産:構築物、建設仮勘定
その他の固定資産:ソフトウェア、電話加入権
特定資産:特定資産
負債:退職給与引当金
よってその他の固定資産に該当するものを合計した結果は150となります。

固定資産は「有形固定資産」「特定資産」「その他の固定資産」の3つのブロックに分かれていることを覚えておきましょう。
【第5問】流動資産の項目
次のなかから、流動資産に該当する項目の合計額を計算した場合、正しいものはどれか。
現金預金200 貯蔵品50 図書150 未払金50 土地200 短期貸付金50
正解:B
問題文で挙げたものを分類すると以下のようになります。
有形固定資産:土地、図書
流動資産:現金預金、貯蔵品、短期貸付金
負債:未払金
よって流動資産に該当するものを合計した結果は300となります。

以前の記事で解説しましたが「長期」と「短期」の区分基準、覚えていますか?
学生生徒等に奨学金として貸し出したお金のうち、1年以内に返済される予定のものが「短期貸付金」として扱われ、流動資産として記載されます。
【理解度アップ】運用資産に注目
以前の記事では、貸借対照表における「固定」と「流動」のバランスと、流動資産の中でもキャッシュが重要という話を紹介しました。
今回はそのキャッシュに関わるものとして「運用資産」について取り上げたいと思います。
一般的な企業における貸借対照表の固定資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」「繰延資産」の4つのブロックに分かれています。
一方、学校法人の場合は設問4の解説で述べたとおり、3つのブロックに分かれており、そのうちの1つとして「特定資産」が設けられています。
学校法人が永続的に活動を行うためには、施設設備の計画的な取替更新が必要です。
また、内部的な視点では、そこで働く教職員等の将来の退職金支払に備えた資金を確保しておくことも重要となります。
そうした中・長期的な目的に対する資産は、流動資産に含まれるような現金預金とは分けて保有しておく必要があるわけです。

現金預金と混ぜてしまうと、短期的な給与の支払いや日々の取引先への支払いなどにお金が流れてしまい、いざ目的のために使おうとした際にお金が足りないといったことが起こる恐れがあるからです。
その現金預金とは切り離して管理された資産が特定資産になります。
従って、
- 現金預金は短期的なキャッシュ
- 特定資産は中・長期的なキャッシュ
といった理解をしておけば問題ないと思います。
そして私学事業団は、学校法人の経営を持続的かつ安定的に継続するために必要となる資産を「運用資産」と呼び、以下の計算式で求められるものとしています。
運用資産=特定資産+有価証券(短期および長期)+現金預金
この運用資産を用いて、学校法人が将来必要となる資産をどれだけ保有しているかを見るための指標がありますが、それについてはまた別の機会で紹介できればと考えています。
ひとまずここでは、貸借対照表を見る際にこの「運用資産」にも注目しておくということだけ覚えておきましょう。
まとめ
貸借対照表を含め、決算書を読み解くためにはある程度暗記が必要となります。
特に勘定科目は覚えるしかありません。
中学の英語のように、「have=動詞」のように「現金預金=流動資産」といった感じで、単語とグループをセットで覚えるようにしましょう。
そのためには、とにかく決算書を読む回数を増やすことが大切だと私は考えています。
さらに、そこで覚えたことをこの記事のようにクイズでアウトプットするとより身につきやすいと思います。
今回の記事が貸借対照表を理解するための第一歩となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。