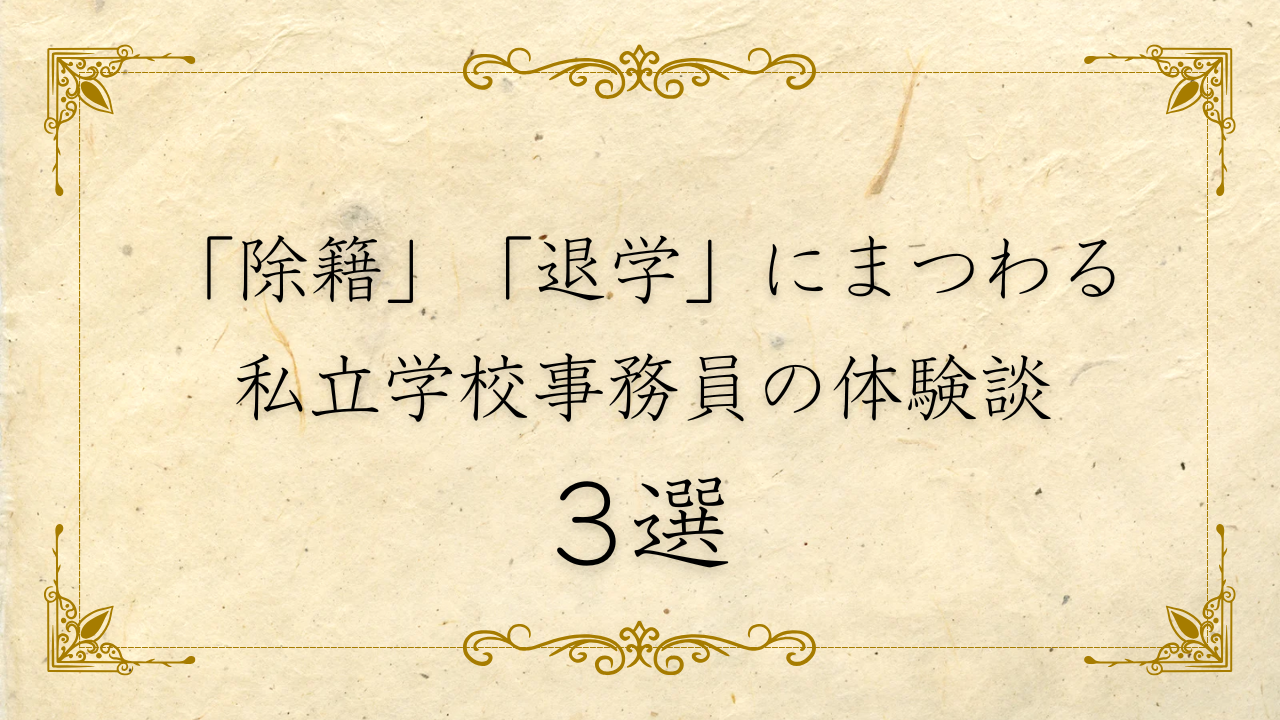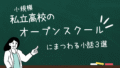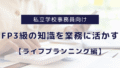この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・学生生徒の除籍や退学にまつわるエピソードを知りたいと思っている人。
「除籍なのに卒業証書は手元にある」
そんなことがあるのかなと思った人もいるのではないでしょうか。
「〇〇大学卒業」と公表しているにもかかわらず、大学側は「卒業していません」というコメント。
公職に就いている人が、こうした学歴詐称の疑いで世の中をにぎわすというケースがありましたね。
そこでこの記事では、「除籍」と「退学」の違いや、私が実際に体験した学生生徒の除籍・退学にまつわる話について紹介したいと思います。
「除籍」「退学」には学費の問題がつきものです。
こうしたケースを知っておくことが、学校現場の実態を知ることのきっかけになると思いますので、お読みいただければ幸いです。
【言葉の定義】退学と除籍の違い
まず「退学」と「除籍」がどう違うのかについて、理解しておきましょう。
私の経験上、大まかには以下のように理解しておけば問題ないと考えています。
- 退学:「学生生徒側」から「学校側」に届け出るもの≒依願退職
- 除籍:「学校側」から「学生生徒側」に行われるもの≒解雇(クビ)
退学は、「退学届」のような学校所定の書類に必要事項を記入して、その書類を学生生徒が学校に提出することで、当該学生の学籍がなくなるというものです。

サラリーマンの人が「退職届」を会社に提出して辞めるという状況をイメージしていただければと思います。
一方除籍は、例えば「〇〇の理由により、あなたをこの学校から除籍します」というように、何らかの理由が生じた際に、学校が学生生徒の学籍を抹消することになります。

サラリーマンの人が不正をはたらいて、それを理由に会社を解雇(クビ)される状況がこれに近いと思います。
どちらも学生生徒からすれば「学校からいなくなる」ということになりますが、具体的な内容が異なるわけです。
頭に入れておきましょう。
【いろんな事情がある】私の体験談3選
退学と除籍の違いを理解したところで、これらに関する私のエピソードを3つ紹介させていただきます。
その3つは、以下のとおりです。
- 学生の知らないところで除籍
- 両親の離婚の影響
- 奨学金制度の壁
正直なところ、どの話も学生生徒の立場からすると残念としか言いようがないものです。
暗い気持ちになるかもしれませんが、「そういうこともあるのか」という気持ちで読んでいただければと思います。
【①大学生もまだ子ども】学生の知らないところで除籍
これは以前の勤め先で、大学の事務員として働いていたときの話です。
いつも学費の支払いが期日間際の学生がいました。
実際に学費を支払っているのはその学生の父親で、納付期日が近づいてくるといつも大学に電話がかかってきます。
電話の内容も毎回「もう少し期日を延ばせないか」というもので、こちらも「困った人だなぁ」という印象でした。
それでもいつもなんとか期日当日には間に合わせており、なんとか除籍を免れていました。
しかし、ついにその時が来たのです。
期日になっても学費が振り込まれませんでした。
そのまま除籍の手続きが進み、その学生は除籍となってしまいました。

学生と少し面識があったので、除籍のことを知った際には残念な気持ちになったのを覚えています。
ところが、それからしばらくしたある日、別の事務員から妙な話を聞きました。
学生有志によるプロジェクトの集まりで、その学生の姿を見たとのこと。
その事務員も学生の顔を知っていたので、「あれっ?」と思ったそうです。
私の中でとても嫌な予感がしました。
案の定、そのあとの履修登録でトラブルが発生。
その学生が「履修登録をしようとしてもできない」と窓口に言いに来たのです。
窓口の担当者が状況を説明しますが、本人は納得がいかない様子。
とにかく、保護者に確認するよう説得してその場は一旦収まりました。

保護者が払ってくれているものと思っていたんでしょうね。
そして、学生から連絡を受けたからなのか、今度は父親から大学に電話が入りました。
対応した事務員に話を聞くと、とにかく「今からすぐに支払うから何とかしてくれ」の一点張りだったそうです。
さらに聞くところによると、高校時代も同じように納付期日を過ぎてから学費を納めるということがあったようで、「高校では何とかしてくれた」ということもしきりに言っていたとのことでした。

私の今までの経験に照らしてみても、確かにこのあたりの線引きは高校よりも大学の方が厳しい印象があります。
やはり、学生生徒数の規模が違うというのがその理由の一つではないかと思っています。
結局、大学側としてはどうすることもできないため、そのまま学生は大学を去っていきました。
ただこうした生徒自身が自分の除籍を知らないケース、実を言うとそんなに珍しいものではないのです。
偶然、その学生のことを私が知っていたので、事態を把握することができましたが、私の知らないところで同様のことは起こっているようでした。

保護者としては、子どもに学費のことで心配をかけたくないという思いがあるのでしょう。
大学側もそれに配慮してか、当時は除籍を通知する書類を「保護者と学生の連名」の宛名で送っていました。
そうすれば、保護者でも郵便物を開封することができるからだと思われます。
しかし、除籍になって一番被害を受けるのは学生本人だと思います。
保護者の気持ちも理解できますが、大事な内容の連絡は学生のことを優先して、本人にも届くようにする必要があると、私自身考えています。
皆さまも、勤め先等がどんな対応をしているか確認してみてはいかがでしょうか。
【②そのタイミングで?】両親の離婚の影響
これも、以前の勤め先での話です。
勤め先の設置する中学校に通う生徒が学費を滞納。
私が学納金担当でしたので、担任と連携して保護者や生徒への対応を続けていました。
いよいよ年度末が近づいてくる状況になり、こちらも焦ってきます。

その学校のルールとしては、年度を越えた滞納は認められないとされていました。
1学期分を2学期、3学期まで待つというところまでは何とか対応可能でしたが。
父親、母親両方と連絡をとり、粘り強く学費の納付をお願いし続けていましたが、あるとき父親から衝撃の一言を言われました。
それは、

離婚しましたので、これからは母親の方に連絡してください。
というものでした。
「はぁ?このタイミングで」と思いましたが、それから一切電話に応じません。
仕方がないので母親の方に電話をし、父親が電話に出ない旨を伝えると、「あぁ」と何かを察した様子でした。
その後、母親の頑張りによってなんとかその年度の学費は年度内に納めることができましたが、もうこれ以上学費を支払い続けることは無理と判断したのか、転学することに。

生徒には何も落ち度がないのに、と何とも寂しい気持ちになりました。
私立中学は私立高校のように就学支援金のような制度がありません。
義務教育なので、公立中学という選択があるからだと思います。
そのため、学費の負担は高校よりも重いという印象です。
何かしら諸般の事情があるにせよ、生徒にとってよりよい中学生活が送れるよう、家計のこともよく考慮して慎重に進学先を検討する必要があると思った一件でした。
【③制度設計は難しい】奨学金制度の壁
最後も以前の勤め先の話で、大学の奨学金業務を担当していた時のことです。
大学が独自に実施している奨学金の申し込みを受け付けていました。
提出された申込書類を確認していると、奨学金を申し込む理由を記載する欄に、驚くほど細かい字で書き込まれているものを発見。
目を近づけて読んでみると、「家計が苦しい」といった内容がびっしりと書いてありました。
その後、申込者一人ずつ面談を実施したのですが、面談でもその学生は家計の状況の厳しさを切実に訴えていたそうです。

残念ながら、私とは別の事務員が面談したので、あとから様子を聞いてみました。
申込者全ての面接が終了し、いよいよ選考を行います。
その奨学金は、家計状況だけでなく成績や面接の様子も考慮して判定するものだったので、それらを点数化して順位付けをします。
その結果、なんとその学生は不採用となりました。
家計状況や面接は悪くないのですが、成績状況が芳しくなかったため、採用枠には入らなかったのです。
申し訳ないという思いはありましたが、どうにもならないので不採用の旨を通知しました。
そして後日、別の部署からその学生が退学したという報告を受けました。
ショックと同時に何ともやりきれない気持ちになったのを覚えています。

経済的な事情が退学理由かわかりませんが、あの奨学金がもし採用になっていれば、という思いが頭をよぎりましたね。
財源の問題もあるため、採用枠を増やすことができませんし、採用の基準や判定方法なども変えようがありませんでした。
何より、その学生が採用されれば別の学生は代わりに不採用となるわけです。
「仕方がない」と考えて自分を納得させましたが、今でも何とかならなかったのかと思ってしまう出来事でした。
まとめ
私の経験談を3つ紹介しましたが、どれも共通しているのが「家計の苦しさ」だと思います。
このエピソードは今の「高等教育の修学支援新制度」が始まる前の話なので、大学については状況が変わっているかもしれません。
とにかく、学生生徒自身ではどうにもならない理由で学校を去ることがないように願うばかりです。
この記事が、私立学校事務員の仕事の理解につながればなによりです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。