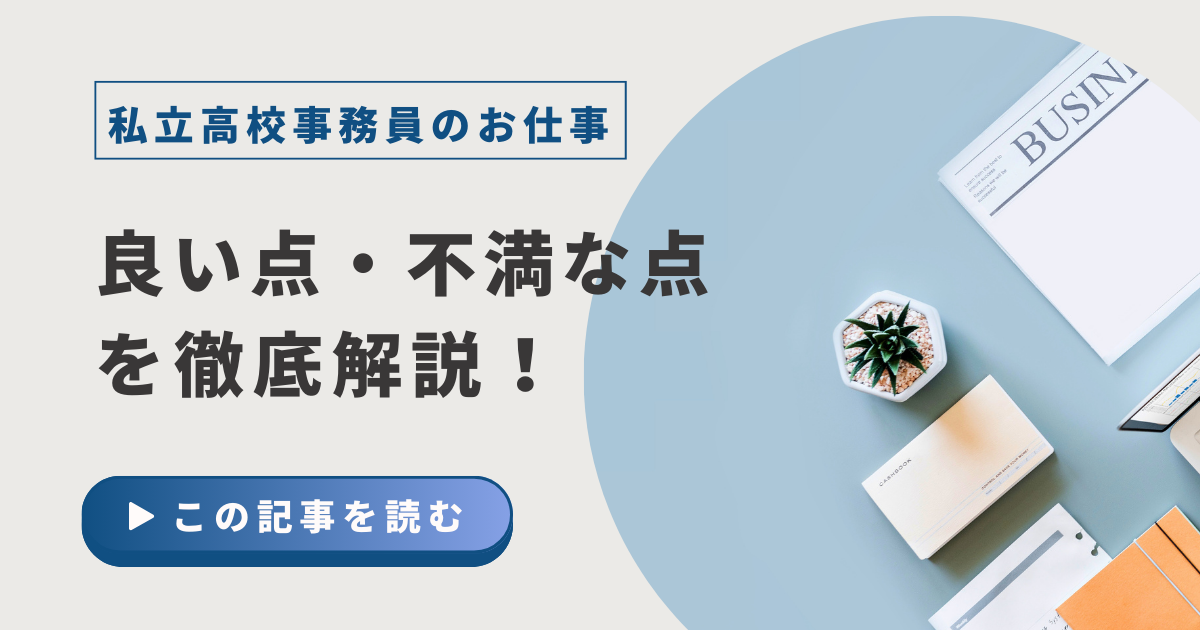この記事は、こんな人を対象としています。
・私立高校の事務員になる予定の方または目指している方
・私立高校の事務員の仕事に興味のある方
・私立高校に現在事務員としてお勤めで、他校のことが気になる方
一口に「私立高校事務員のお仕事」と言っても、各学校で違いがあります。
例えば「生徒数などの規模」や「運営主体となる学校法人」による違いが挙げられます。
私はこれまで20年以上、私立学校事務員として勤めてきましたが、その間2つの高校事務室で仕事をしてきました。
そこで、その2つの高校事務室での経験をもとに、前述の違いなどによる「働く上でここがよかった・不満だった」点を紹介させていただこうと思います。
これから私立高校事務員として働く方や目指している方の仕事選びでの参考になると考えていますので、どうぞお付き合いください。
【比較表】私の勤めてきた高校の状況
私が勤めてきた高校の状況をまとめたものが以下の表です。
| 項目 | A高校 | B高校 |
| 生徒数(全校生徒数) | 約1,000人 | 約300人 |
| 高校の種類 | 全日制 共学(男子の方が多い) | 全日制 共学(女子の方が多い) |
| 学校法人と高校の位置関係 | 同一都道府県 | 別都道府県 |
| 事務員数(正規・非正規合計) | 6名 | 3名 |
| 立地 | 最寄り駅から徒歩約5分 都市型 | 最寄り駅から徒歩約15分 郊外型 |
| 教育活動収入 | 約10億円 | 約3.5億円 |
今回の記事では、A高校で働いた際に感じた良かった点・不満に感じた点についてそれぞれ3つずつ紹介します。
【結論】A高校で働くうえで良かった点、不満に感じた点
先に結論として、よかった点と不満に感じた点をお伝えさせていただきます。
| 良かった点 | 不満に感じた点 |
| 学校のにぎわい | 多様な生徒の受入 |
| 立地のよさ | 電話・来客対応の多さ |
| 経営の安定性 | 仕事の自由度・裁量度の制限 |
以降、それぞれについて解説します。
【良かった点その1】学校のにぎわい
1,000人程度の生徒が在籍していると、学校自体に活気を感じました。
休み時間やクラブ活動の際に聞こえてくる生徒たちの活気のある声や、行事の際の盛り上った雰囲気は、学校現場で働く者に充実感を与えてくれます。
「自分は今、学校に勤めている」という意識が刺激され、私にとっては働くモチベーションへとつながりました。
校外で行事を行う際に、事務員も同行して保護者の受付業務などを担当しますが、その間学校を空にするわけにはいかないため、学校待機を命ぜられることがあります。

この時は、大変ショックです・・・。
こうした「学校のにぎわい」は学校で働く醍醐味の一つと言っても過言ではなく、生徒数の多さはその点に非常に大きくかかわっていると思います。
【よかった点その2】立地のよさ
実際に勤めてみて、電車を利用した通勤で重要なポイントは4点です。
- 最寄り駅から近い
- 最寄り駅がターミナル駅から近い
- 最寄り駅を発着する電車の本数が多い
- 学校からの最寄り駅が複数ある
当たり前のように思われますが、意外と抜けてしまうところです。
私はB高校に転職した際に、このポイントを軽視してしまいました。
その結果、最も悪影響を受けたのが自然災害発生時です。
詳しくは、B高校の不満に感じた点で紹介させていただく予定ですが、昨今の自然災害の状況から勘案して、今まで以上に重要視した方がよいと思われます。
その観点から見ると、A高校は4つのポイントすべてを満たしており、安心安全に通勤することができました。
【よかった点その3】経営の安定性
上述の表にも記載したとおり、年間約10億円の収入がありました。
収入が多いと、それだけ「選択肢」を増やすことができます。
例えば、私はA高校、B高校の両方で、生徒がパソコンの授業を受けるための教室の機器入替を担当しました。
その際、B高校では機器購入の代金を一括で支払うだけの資金的余裕がなかったため、リース契約という選択肢を取らざるを得ませんでした。
一方、A高校では一括購入という選択肢を選ぶことができました。
結果的にどちらがよいかという話は別にして、業務を担当する者としては、複数の選択肢があるということは、学校の財政状況にあった適切な方法を検討できるというメリットにつながると実感しています。
【不満に感じた点その1】多様な生徒の受入
生徒数が多い分、それに伴い様々な特徴を持った生徒を受け入れることになります。
よかった点として「にぎわい」を挙げましたが、にぎわいすぎてトラブルへ発展することもあります。
例えば、施設設備の破損。
様々な生徒が在籍するため、中には人一倍元気のいい生徒がいたりします。
そのような生徒が休み時間に活発に活動し、トイレの扉やガラスなどを破損することがあります。
進級によるクラス替えで、その生徒が以前とは別の校舎に移動すると、今度は移動先の校舎の施設設備が影響を受けます。
修理を担当する会社の方が「今度はこっちですか」とおっしゃるので「あの生徒が今年からこちらの校舎になりました」と伝えると「あぁ・・・。」と寂しそうにつぶやく様子は忘れられません。

これだけで他の業務がストップすることになりますので、繁忙期などはやりきれなくなります。
偶然、そのような生徒が在籍したからという見方もできますが、今のB高校ではそのような問題は起こっていません。
生徒の男女構成による違いもあると思います。
やはり受け入れる数が多いということは、その分多種多様な生徒が入学するということを認識しておく必要があります。
【不満に感じた点その2】電話・来客対応の多さ
不満その1とも関連しますが、生徒数が多いとそれだけ生徒以外の関係者との接触も増えます。
朝は保護者等からの生徒の欠席連絡から始まり、その後も会社や大学などからひっきりなしに電話がかかってきます。
加えて、直接窓口に来られるお客様の対応もあります。
そのため、朝に「今日はこれを終わらせよう」と思って開いたデータが、夕方になっても朝と同じ状態のままということを何度も経験しました。

「今日は何しに学校に来たのか」と暗い気持ちになる瞬間です。
生徒の欠席連絡については、最近は電話連絡からアプリによる連絡へと変わりつつある様子ですが、学校の規模が大きくなるほど学外とのやりとりも増えるということは理解しておきましょう。
【不満に感じた点その3】仕事の自由度・裁量度の制限
これは生徒数とは関係なく、学校法人本部との関係によるものです。
A高校は同じ都道府県に学校法人本部があり、距離も遠くない状況でした。
それも関係し、様々な手続きにおいて本部の決裁を取る必要がありました。
例えば、取引先への支払いは全て本部で行っていました。
預金口座を本部が管理しているため、高校は事務長といえども1円たりとも直接支払いすることはできませんでした。
事務長の承認を得た書類を本部に送り、本部の手続きを経て取引先に支払いが行われます。
支払関係だけでなく、行政へ提出する書類についても基本的に全て本部の決裁が必要でした。
遠くないとはいえ、本部とは離れているため、書類のやりとりをする日が定められており、時間的な制約がある点は個人的には不満でした。

高校内で完結できればもっとスムーズに進められるのにと思うことが多々ありました。
まとめ
私の経験をもとに生徒数、立地、仕事の裁量度など様々な面から見た良かった点、不満に感じた点を紹介しました。
あくまで一例ですが、皆さまが仕事を考える上での参考になれば幸いです。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。