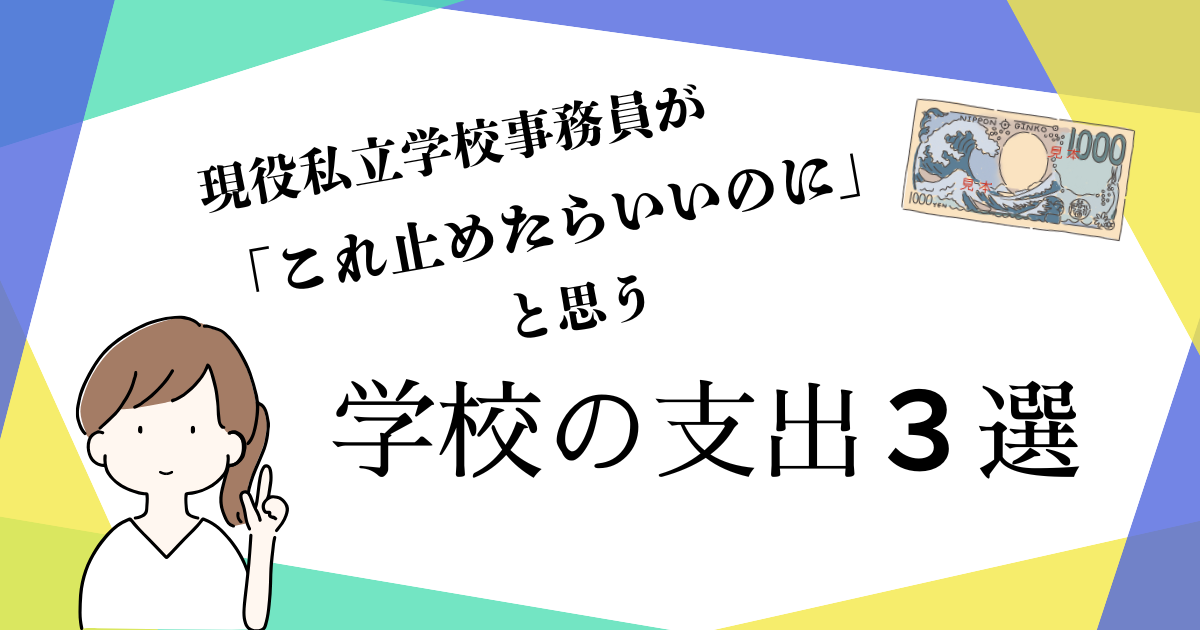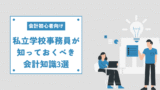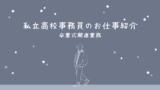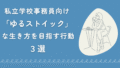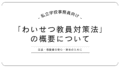この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・私立学校事務員から見て「これ無駄だな」と思う学校のお金の使い方について知りたいという人。
経理を担当していると、日々様々な学校の支出に関する書類が回ってきます。
例えば、授業や部活動など「教育全般」に使用するものや、学校全体の電気代や水道代など学校を維持するために必要なものなどが挙げられます。
こうした学校運営のために使われるお金の内容を把握できるという点が、経理業務の面白さの1つでもあるわけです。
しかし、そうしたお金の中には、「これって本当に必要なのか」と思うようなものが混じっていたりします。
そこでこの記事では、私立学校事務員歴20年以上、そのうちの多くの期間を経理担当として働いてきた私が、「これは無駄だ」と思った支出を3つ紹介します。
その3つは以下のとおりです。
- 教職員の飲食に関する支出
- 行事関連の来賓に関する支出
- 社交辞令的な支出
私の個人的な感情も入っていますが、私立学校事務員の方の中には共感していただけるものもあるのではと思っています。
「そんなことをしている学校があるのか」という参考にしていただき、「そういえばうちの学校も・・・」という気づきにつなげていただければ幸いです。
【①飯は自腹で食え】教職員の飲食に関する支出
人間、生活していればお腹がすくわけです。
そこに仕事は関係ありません。
だから学校のお金で飲食をすることに対して、私は理解できないというのが率直な意見です。
しかし、なぜかこれを請求する人が多い。
学校の規程上問題がないにしても、飲食を購入したレシート等が回ってくるたびに疑問を覚えます。
例えば、今の私の勤め先の旅費規程では、1日出張した場合に上限1,000円まで飲食代が支給されるように定められています。

細かいことを補足しますと、「4時間以上」の出張がこの場合「1日出張」に該当するというルールになっています。
この規程に則って、出張時に発生した飲食費を請求してくるわけです。
「学校以外のところへ行く必要があり、その途中で昼食を購入したので、そのお金をください」という意味になると思いますが、私からすれば「出張に行かなくても、昼飯は食べるだろ」と思ってしまいます。
コンビニなどで購入すると普段より割高になるのかもしれませんが、そうであれば弁当を用意するなど自分でなんとかできる部分はあるはず。
そういったことをせずに、ただ「規程で認められているから」という理由で学校のお金を使うことに、私は疑問を感じているのです。
そして、そういう請求をする人ほど上限額いっぱいまで飲食物を買おうとします。
レシートを見るとペットボトルの飲料を何本も購入しており、「これ、絶対帳尻合わせで買っているだけだろう」と思ってしまうわけです。
ただ、全ての飲食に関わる支出について否定しているわけではありません。
例を挙げると、以下のような場合ならやむを得ないと思っています。
- 研修会などに参加する際に、参加費に食事代が含まれている
- 宿泊を伴う出張で、朝食付きのプランの選択する
- 学生生徒等の進学先や就職先等などを開拓するために懇親会を開催する

私はそれでも②の場合、素泊まりを選択しますが。
先ほどの出張時の1,000円の例だと、「たかだか1,000円くらい」というご意見もあると思います。
しかし、「されど1,000円」
この1,000円を新たに学校が生み出すには、どれくらいの努力が必要かを考えてみましょう。
以前の記事でも紹介しましたが、収入にはそれに対応する支出が発生します。
以下の記事もご参照ください。
例えば、私の今の勤め先の入学検定料は20,000円です。
この金額だけで見れば、最大20回分の出張時の食事代が賄えます。
しかし、これを「収入と支出の差額」という観点から見てみると、また違った見え方をします。
日本私立学校振興・共済事業団が直近に発表した、私立高校の「事業活動収支差額比率」は1.9%でした。
事業活動収支差額比率については、以下の記事もご覧ください。

ここではざっくり、「私立高校は平均して収入の1.9%が手元に残る」とでもイメージしていただければと思います。
キリのいいところで2.0%と設定し、これを先ほどの入学検定料に当てはめると以下のように計算できると思います。
20,000円×2.0%=400円
つまり、受験生一人(20,000円)確保しても、そのために使うお金を差し引くと学校には400円しか残らないと考えられるわけです。
食事代1,000円との比較では、受験生を2.5人集めないと食事1回分を賄えない計算になります。
そう考えると、私の勤め先のような小規模な高校には決して「小さな支出」ではないように思えてくるのです。
今まで何度も「この規程を見直そう」と言ってきていますが、今あるものを無くすというのは難しいようで、なかなか進みません。
「何とかしたいなぁ」と思う今日この頃です。
【②生徒のため?】行事関連の来賓に関する支出
以前に、卒業式業務に関する記事を書いた際にもお伝えしましたが、私の今の勤め先では卒業式に、保護者や学校法人役員以外の「外部の方」へ参加のご案内を送ります。
私はこれも「無駄だなぁ」と感じています。
理由は「生徒は特に喜んでいないから」

私自身は、「卒業式によくわからないおじさんやおばさんが来られても・・・」という感覚です。
学校としては、卒業生に何らかの関係がある人たちに「おかげさまで、立派に卒業することができました」という報告の意味も兼ねてご案内していると思われます。
しかし、卒業式の主役はあくまで生徒。
喜ばない生徒が多いのであれば、お呼びしなくてもよいのではと思っています。
ちなみに、この案内に関連する支出は以下のとおりです。
- 案内状郵送料
- 来賓者への手土産代
- 当日対応に係る人件費
本校のケースでは、案内状発送数が約100通、実際に出席される来賓者数が30名程度になります。
これを教職員の飲食代のケースと同様に、金額ベースで見てみます。
・郵送料:@110円×100通=11,000円
・手土産代:@1,000円×30個=30,000円
人件費は計算がややこしいのでここでは一旦省きますが、以上の2点だけで41,000円になります。
先に算出した「400円」という数値で見ると、100人以上の受験生を集めなければこの41,000円という金額は賄えないという計算になります。

私としては「大きいなぁ」という印象です。
なお、入学式でも同じことを行っていますので、支出もこの倍になります。
私の以前の勤め先や他校の様子を見ていると、保護者やPTA、学校法人役員に限って案内しているので、今の勤め先もこれに倣ってはどうかと提案しています。
しかし飲食代のときと同じく、今までやってきたことを変えるのは難しく、まだまだこの業務は続きそうです。
粘り強く見直しを呼び掛けていこうと思っています。
【③時代の流れ】社交辞令的な支出
行事の来賓の件とも似ていますが、まだまだ昔ながらの風習が残っているところがあります。
例えば、お中元やお歳暮。
この記事を書いているまさに今がお中元のシーズンです。
このお中元・お歳暮の注文も私が担当していますが、いつも「もう止めたら」と思ってしまいます。
理由はこれも「生徒は特に喜ばないから」
近年の物価高や輸送コストの高騰により、これらの費用も上昇傾向にあります。

以前よりも「送料無料」とうたっている商品が少なくなっているように思いますね。
そうした流れも関係してか、民間企業の方でもこのような贈答品のやりとりを廃止するという話をニュースなどで耳にします。
私の勤め先も、ぜひこうした動きに便乗してほしいというのが本音です。
折角なのでこちらの支出についても、今までのケースと同様にお金の面から見てみたいと思います。
私の勤め先のお中元にかかる費用は、約150,000円です。
これをまた前述の「400円」を基準として、受験生数に換算すると約375人になります。
正直なところ、もはや入試数回分に匹敵する人数です。
だからこそ、見直してほしいと思っているので、これも引き続き廃止を呼びかけていきたいと思っています。
まとめ
全編を通じて、私の愚痴のように見えたかもしれませんが、そうではありません。
各項目で紹介した「収入と支出の差額で金額を見る」という視点を紹介したかったという思いがありました。
皆さまも、身の回りの支出をこの方法で見ていただき、「本当にこれだけの価値があるのか」ということを考えていただければと思います。
それが、皆さまの勤め先のムダ改善につながれば嬉しい限りです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。