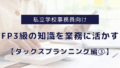この記事は以下のような人を対象としています。
・意見を求められた際に思いをうまく言葉にできないと悩む人
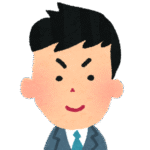
会議で「何か意見は」と言われたときに、言いたいことがうまく言葉にできないなぁ。
こんなことを思った経験、皆さまにもあるのではないでしょうか。
会議の場に限らず、
- 志願者やその保護者に学校のいいところを説明したいとき
- 上司や同僚に新しい仕事の方法について提案したいとき
- 家族や友人に自分の思いを伝えたいとき
といったケースでも、同じようなことを思ったことがある人が私の周りにも多くいます。

当然私もあります。
なんとなく言いたいことはあるのに、それが言葉にできない。
こうしたことが起こる原因の一つとして考えられるのが、「言語化力」を訓練する機会が与えられてこなかったから。
私たちは「大きな声でゆっくり話す」や「結論をまず伝える」など「伝え方」については、様々な場面で教えられてきましたが、そもそも「言いたいことを言葉にする」ことができないと、伝えようがありません。
そしてその方法を学ぶ機会は、今まで与えられてこなかったように思います。
そこでこの記事では、「”言う内容”を言葉にする力」を養うための訓練方法を、参考書籍の内容に基づき、紹介したいと思います。
A4用紙一枚と1日6分程度の時間があればできる簡単な方法です。
実際、私も実践してみて有用性を感じています。
- 意見を求められた際の「的確な回答」
- 話に具体性がある「説得力のある説明」
こうしたことができるようになることで、自分自身今より積極的に意見が言えるようになり、前向きに仕事に取り組めるようになります。
皆さまのお悩み解消の一助となれば幸いです。
書籍の紹介
書籍名:瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。
著者名:荒木 俊哉
出版社:SBクリエイティブ
発売日:2023年5月1日
【概要】言語化力の訓練方法
ここからは書籍に従い、「”言う内容”を言葉にする力」を「言語化力」という言葉で表現していきます。
まずは、この言語化力を訓練する方法の概要を紹介させていただきます。
ポイントは「やること」と「制限時間」です。
以下、書籍の言葉を引用します。
A4コピー用紙の一番上に自分への「問い」をひとつ立てます。その問いに対して、「頭に浮かぶこと」を次々に書いていきます。
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より引用
ただし、所要時間は「1枚につき2分」です。これを1日3枚、計6分書く。これを毎日の習慣にする。 P23
これが概要です。
至ってシンプルな内容になっています。
そして「頭に浮かぶこと」を次々書いていくにあたって大切なのが以下の点です。
「何でもいいから、まずは1つ書き出してみる」ということが大事です。その書き出した1つの言葉がトリガーとなり、そこから連想される別の「曖昧なイメージ」が、自然と言語化されるからです。 P22
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より引用
この概要を念頭に置いて、以下の詳しいやり方を見ていただければと思います。
【イメージが大切】言語化力が磨かれる過程
概要に加えてもう1点、皆さまと共有したいことがあります。
それが、言語化力が磨かれる過程についてです。
この言語化力が磨かれることで、私たちの状況がどのように変化していくか。
書籍ではそれを、6つの段階に分けて解説しています。
その6つの段階とは以下のとおりです。
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より加工して引用
- 「思い」のほとんどは頭の中で言語化されていない
- 頭の中にあるほんの一部の「言葉」を、まずは書き出してみる
- 書き出された「言葉」がトリガーとなり、「無意識の思い」が言語化される
- 言語化された「無意識の思い」をさらに書き出す
- 追加で書き出された「言葉」が再度トリガーとなる
- 「思い」が言葉の状態で大量にストックされる P83-85

実際にやってみる前に、この過程を頭の中でイメージしてみると、よりスムーズに取り組める実感があります。
言葉がどんどんつながっていく様子を想像しながら、チャレンジしてみましょう。
【6つのステップ】言語化力トレーニング
それでは、具体的なトレーニング方法を紹介していきます。
トレーニングは6つのステップに分かれていますので、以降は私が実際に取り組んでみたテーマを例に順に見ていきたいと思います。
【ステップ1】問いを決めて書き出す。
書籍の言葉を引用します。
ひとつの「問い」を決めたら、それをA4コピー用紙の一番上に書きましょう。そのときに、できるだけ大きく書くのが大切です。
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より引用
さらに、書いた「問い」を四角で囲んで目立つようにしてください。 P101
私が設定した問いは「なぜ学校法人会計を勉強するのか」です。
【ステップ2】用紙に線を引いて上下に2分割する
書籍の言葉を引用します。
用紙の真ん中に線を引いて、用紙を上下に分割してください。上には問いに対する「思考(思ったこと・感じたこと)を書き出してもらい、下には「理由(そう思った理由・そう感じた理由)を書き出していただくためです。 P104
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より引用
各自お手元の用紙に線を引いてみましょう。
【ステップ3】思考:「思い浮かんだこと」を一行書く
では、思い浮かんだことを一行書いてみましょう。
私が「思い浮かんだこと」は「会計は大切だ」というものです。
【ステップ4】言葉の解像度を上げる
書籍の言葉を引用します。
一行書き出した内容に対して「それはつまりどういうこと?」という意識を常に持ちながら、徐々に「言葉の解像度」を上げていくことです。P111
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より引用
「会計は大切だ」を掘り下げていきます。
- 会計が分かれば、学校の経営状況がわかる
- 保護者等の関係者に学校の正確な経営状況を伝えられる
- 関係者に安心を与えることができる
こんなところになります。
【ステップ5】理由:「そう思った理由」を一行書く
書籍の言葉を引用します。
「思考」ブロックで最後に書き出したメモを「丸」で囲みます。そこから、「そう思った・そう感じた理由」を、下の「理由」ブロックに書き出していきます。 P112
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より引用
先ほど書き出したものの最後は「関係者に安心を与えることができる」でした。
これの理由を考えてみます。
「赤字でないことなどを知れば、関係者も安心すると思ったから」 といった理由が思い浮かびましたので、A4用紙の真ん中に引いた線より下部にそれを書き込みます。
【ステップ6】言葉の解像度を上げる
書籍の言葉を引用します。
「思考」のときと同じように、「理由」についても、「それって、どういうこと?」と自分に問いながら書き出していきます。 P113
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より引用
「赤字でないことなどを知れば、関係者も安心すると思ったから」を掘り下げてみます。
- 最近、経営状況悪化で閉校する学校があり、不安に思っている人がいる
- 自分の子どもが通う学校の経営状況がどうなのか気になっている
- 不安を解消することで、関係者から信頼を得ることができる
【結論】このテーマでの私の思いを言語化した結果
以上、6つのステップを経て私の思いを言語化してみました。
まとめると以下のようになります。
- 問い:「なぜ学校法人会計を勉強するのか」
- 思い:「学校の経営状況を正しく伝えて、関係者からの信頼を獲得できるようになるため」

最初の「会計は大切だから」の状態からすれば、かなり「言語化」できたのではと個人的には思っています。
皆さまもやってみてはいかがでしょうか。
なお、実際にやってみるとわかると思いますが、2分間はかなり短いです。
これから練習を積んで、パッと言語化できる力を身につけたいと思います。
【おまけ】「経験」と「感じたこと」をセットにする
最後に、この言語化力を磨くにあたってもう1点役立つ内容を紹介したいと思います。
それは、問いに対する「経験」と「そのとき感じたこと」をセットで書き出すということです。
書籍では以下のように紹介しています。
「言語化力トレーニング」において、あなたが立てた「問い」に関する過去の経験を思い出す際に、できごとの中で「感じたこと」をメモに書き出す意識を忘れないこと。 P210
「瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。」より引用
経験とその際に感じたことは、その人自身のオリジナルの思いや意見になるということです。
先述の「なぜ学校法人会計を勉強するのか」の問いに対し、もし保護者等から実際に学校の経営状態を尋ねられた経験があれば、そのときに感じたことを一緒に書き出してみる。
今回は残念ながら時間オーバーのため、そこまで思い出すことができませんでしたが、意識していきたいと思いました。
まとめ
正直なところ、私はこの言語化というものが苦手です。
正確に言えば「その場ですぐに言語化すること」を不得意としています。
そのため会議などの場でも、気配を殺して意見を求められないようしていました。
しかし、生徒や保護者等から意見などを求められるケースは、私立学校事務員として働くうえで少なからず経験します。
いつまでも苦手意識を引きずらないように、改善に向けてこのトレーニングに取り組んでいきたいと思います。
私と同じように言語化がうまくできない方の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=20877633&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8926%2F9784815618926_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)