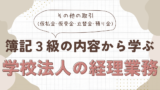この記事の目的は、以下のとおりです。
・就学支援金の会計処理を理解する
・就学支援金の監査対応について理解する
・就学支援金に関連するお金について把握する
前回に引き続き、「私立高校の無償化」について解説します。
今回は前回説明しました「お金の流れ」に基づき、
- どのような会計処理を行うのか
- 外部からの調査にどのように備えるか
をメインに解説します。 就学支援金の実務を行ううえでの参考になれば幸いです。
就学支援金の会計処理
それでは早速、どのような会計処理がなされるかを確認しましょう。
入金処理
まず、大前提としてこの就学支援金は「預り金」として処理するよう定められています。

本来、都道府県から生徒の世帯に直接支給されるべきものを便宜上、都道府県が高校を経由して支給しているだけなので、高校の収入にしてはいけないということです。
親(都道府県)が兄(高校)に、「このお金、弟(生徒の世帯)に渡しといて」とお金を預けたというケースをイメージしてもらえればと思います。
例を挙げて仕訳をしてみましょう。
例:就学支援金118,800円が高校の普通預金口座に入金された。
(分解)
「就学支援金118,800円」「普通預金118,800円」に分解します。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 就学支援金 | 負債 | 増加 | 右 |
| 普通預金 | 資産 | 増加 | 左 |
前述のとおり、就学支援金は「預り金」として取り扱います。預り金は「負債」グループに属します。 預り金の性質についてはこちらの記事もご参照ください。
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 118,800 | 預り金 | 118,800 |
入金時の会計処理は以上となります。
参考:入金された就学支援金の管理
なお、この就学支援金については、利息収入が生じないように当座預金口座等による管理が望ましいとされています。
学校設置者が預り金として就学支援金を受け入れている間は、他の資金と明確に区別し、
高等学校等就学支援金事務処理要領(第13版)より引用
透明性のある会計処理を行う必要がある。また、この間、就学支援金を預金することにより利息収入が生じないよう、就学支援金のみの当座預金口座等により管理を行うことが望ましい(なお、やむを得ない事情により当座預金口座等による管理が行えない場合は、当該利息収入を学校の教育活動に係る経費等に充当することは可能)。
学校事務員として、おさえておきましょう。
返金処理
前回の記事で紹介しましたが、就学支援金を授業料の徴収金額にどのように反映するかによって、「返金」や「充当」など処理方法が異なります。
まずは返金するケースの会計処理を確認しましょう。
例:授業料年額300,000万円をすでに納付済みの生徒が、就学支援金118,800円の支給対象の場合
まずは、授業料納付時の処理です。普通預金口座に入金があったとします。
(分解)
「授業料300,000円」「普通預金300,000円」に分解します。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 授業料 | 収入 | 増加 | 右 |
| 普通預金 | 資産 | 増加 | 左 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 300,000 | 授業料 | 300,000 |
続いて、就学支援金118,800円が入金されたとします。処理方法は説明済みですので省略します。
最後に返金時の処理です。118,800円を普通預金口座から生徒側に振り込むとします。
この時、「就学支援金を授業料に充てた」という処理事実を残す必要があります。
従って、まずは以下のような処理をします。
(分解)
「授業料118,800円」「普通預金118,800円」に分解します。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 授業料 | 収入 | 減少 | 左 |
| 普通預金 | 資産 | 減少 | 右 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 授業料 | 118,800 | 普通預金 | 118,800 |
これで300,000円入金された授業料から、一旦118,800円減らし、意図的に授業料が118,800円不足している状態を作ります。
そしてその不足分に対し、就学支援金を充てます。
(分解)
「授業料118,800円」「就学支援金118,800円」に分解します。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 授業料 | 収入 | 増加 | 右 |
| 就学支援金 | 負債 | 減少 | 左 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 預り金 | 118,800 | 授業料 | 118,800 |
これで、不足分の授業料に対し、就学支援金が充てられたことが会計上記録に残ります。
以上が返金時の処理になります。
充当処理
続いて充当するケースの会計処理を確認しましょう。
例:就学支援金118,800円の支給対象である生徒に対し、授業料年額300,000万円からその金額を差し引いた181,200円を徴収した場合
まずは、授業料納付時の処理です。こちらも普通預金口座に入金があったとします。
(分解)
「授業料181,200円」「普通預金181,200円」に分解します。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 授業料 | 収入 | 増加 | 右 |
| 普通預金 | 資産 | 増加 | 左 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 181,200 | 授業料 | 181,200 |
その後、就学支援金118,800円が入金されたとします。入金時の処理は省略します。
それを授業料に充当するわけですが、この処理は前述の返金時の最後に行った処理と同じになりますので、割愛します。

このように、充当の方が会計処理は少なくて済むわけですが、前回の記事で解説しましたとおり、生徒ごとに就学支援金と授業料徴収金額を把握し続ける手間が発生します。
規模の大きい高校ではかなりの負担になりますので、このあたりのバランスを考えて処理方法を検討した方がよいと思います。
外部からの調査への対応
この就学支援金ですが、前述のとおり「預り金」として処理するため、高校の収入にはなりません。
しかし、国の政策として重要なものであるため、都道府県からの「補助金」と同様に外部からの調査を受けることがあります。
具体的には、その高校を所轄する都道府県の職員が高校に訪問して、適切な会計処理がなされているかや関係書類が整備されているかなどを確認します。
これを「実地検査」というような言い方をします。
この実地検査に対応するために、以下の書類等を準備する必要があります。
- 就学支援金が入金された預貯金口座の通帳
- 会計帳簿
- 伝票
- 公文書
都道府県によって多少違いはあるかもしれませんが、私の経験上、この4つは共通して確認を受けます。
公文書とは、都道府県等が高校に対して送る文書のことで、就学支援金の金額を通知する際などに発行されます。
この公文書に記載された金額と、高校側が作成する会計帳簿等書類の金額との間に整合性があるかといった点などをチェックするわけです。

入金された就学支援金が正しく受け入れられ、適切に生徒側の授業料として処理されているか。制度を運用するうえで大事なポイントを確認するために検査が行われると理解しておきましょう。
就学支援金に関わるその他のお金
補足の知識として、この就学支援金に関わるお金を2つ紹介させていただきます。
奨学のための給付金
就学支援金が「授業料」に対するお金であるのに対し、教科書代や教材費などに充てるためのお金になります。
こちらは就学支援金よりも所得基準が厳しく、住民税非課税レベルの世帯が対象です。
ちなみにこのお金は、高校を経由せず直接生徒側へ入金される仕組みになっています。
高校側は、この給付金を申請するための書類を申し出があった生徒に配布します。
申請書類の提出方法については、高校によって異なるようです。
以前私が勤めていた高校では、直接生徒側から都道府県へ申請書類を提出していましたが、今の勤め先では、高校から提出しています。
就学支援金事務費交付金
就学支援金は本来、前述の「奨学のための給付金」のように都道府県等と生徒側が直接やりとりするものですが、対象者が多い等の理由により高校が間に入っているわけです。
そこで、その高校側の負担などを考慮して設けられたのがこの交付金です。
就学支援金の事務に携わる事務員の人件費や郵送料、紙代といった費用に対して交付されます。
こちらは就学支援金と異なり、高校の収入として取り扱われます。

しかし、この交付金がかなりの少額。実際の負担額に比べれば、まだまだ高校側の負担の方が大きいというのが正直なところです。
まとめ
就学支援金は高校の収入ではない。しかし、それと同じくらい大事なお金として適切な会計処理や証拠書類の整備に努めましょう。
国の教育政策として重要な「高等学校等就学支援金制度」について、私立学校事務員として業務にあたるうえで知っておくべきことを解説してきました。
これから事務員として働く方は、事前知識の習得にお役立ていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。