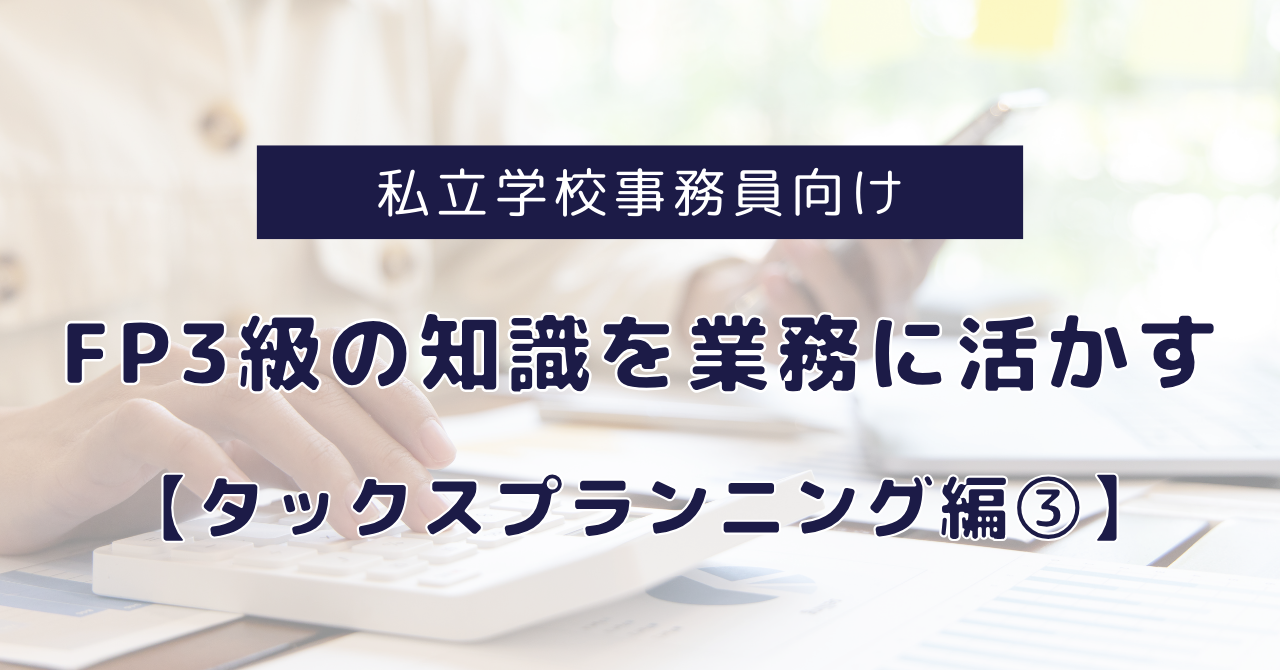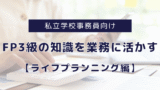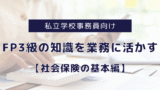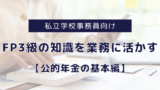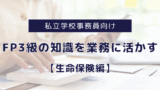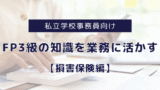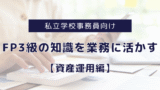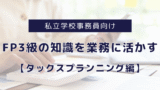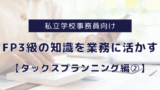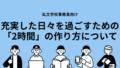この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・私立学校事務員の仕事にタックスプランニングの知識が必要なのかという疑問を持っている人。
以前の記事で、ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下、FP技能検定)3級の試験範囲の中から私立学校事務員の仕事に役立ちそうなものを紹介しました。
これまで「タックスプランニング」分野のうち「所得税」や「所得控除」について取り扱いましたが、この分野は私立学校事務員の業務に関連するものが他の分野よりも多いというのが私の印象です。
そこで今回はこれまでに扱えなかった内容で、私が「知っておくべき」と思ったものをピックアップしてみました。
これまでと同様に、FP技能検定3級の試験を参考にした問題を解きながら、必要な基礎知識を身につける形式にまとめています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとに今回の内容に関連した情報を紹介しています。
前回、前々回に引き続き「タックスプランニングの知識を事務員の仕事で使うことなんかないのでは?」と思っている方も、一読いただければと思います。
なお、この記事は掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
【第1問】住宅借入金等特別控除
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合に、注意すべき点として正しいものはどれか
正解:B
2年目以降は、要件を満たす給与所得者であれば年末調整によって控除できますが、最初の年分は確定申告をする必要があります。
なお、借入金の償還期間は20年以上ではなく「10年以上」であることが要件になっています。
また、住宅の場合、床面積が原則「50㎡以上」が要件になります。
【第2問】控除の種類
年末調整の対象となる給与所得者が、年末調整で適用を受けることができる控除は次のうちどれか。
正解:C
生命保険料控除や地震保険料控除は年末調整で控除できます。
年末調整で控除できないもの(控除を受けるためには確定申告する必要があるもの)の代表例としては以下のようなものがあります。
- 雑損控除(災害や盗難、横領などで損失が生じた場合に受けられる控除)
- 医療費控除
- 寄付金控除(ワンストップ特例制度を除く)
【第3問】税額計算
課税総所得金額300万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)はいくらになるか。
なお、計算には以下の速算表を使用することとする。
| 課税総所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 97,500円 |
正解:B
速算表を使った計算式は以下のようになります。
課税総所得金額×税率-控除額
この設問に当てはめると、
300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円
になります。
【第4問】年末調整
学校は、年末調整に係る資料をいつまでに税務署等に提出しなければならないか。
正解:A
学校や会社は年末調整の後、翌年1月31日までに関係書類を税務署などに提出しなければなりません。
なお、所得税の確定申告は所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出する必要があります。
【第5問】医療費控除
以下の医療費控除の計算式で、( )内に入る数値として正しいものはどれか。
実際に支払った医療費の金額の合計額-保険金等で補填される金額-( )
正解:C
医療費控除は、「(医療費-保険金等で補填される金額)-10万円」で計算されます。
ただし、納税者本人の当該年度の総所得金額等が200万円未満の場合、「総所得金額等×5%」で求められます。
また、医療費控除には上限額があり、その金額は200万円となります。
【理解度アップ】私立学校事務員の節税
5問紹介してみましたが、結局のところ「所得税」か「所得控除」のどちらかに関わってくる内容でした。

FP2級になると法人税なども出題範囲に含まれるのですが、FP3級はほぼほぼ所得税しか出題されないんですよね。
そんな状況を踏まえて、これ以降は「所得税」「所得控除」と関連がある「節税対策」について触れたいと思います。
私立学校事務員も含めて、収入が勤め先からの給与のみという人は、自営業者や個人事業主などと比べると節税として取り組めることが少ないというのが実情です。
そうした数少ない節税対策で、私が実際に行っているものは以下の2つになります。
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)
- 寄付金控除(ふるさと納税)
どれもすでにやっている方にとっては当たり前の内容かもしれませんが、まだやっていない人は参考にしていただければと思います。
小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)
この控除はiDeCoの掛金だけが対象というわけではありませんが、ここではiDeCoをメインに話を進めたいと思います。

なお、この記事ではiDeCoの加入をすすめているわけではありませんのでご注意ください。
小規模企業共済等掛金控除の特徴といえば、「その年に支払った掛金全額について所得控除を受けることができる」という点です。
生命保険料などは、所得控除を受けられる限度額が決まっていますので、そこが違いと言えます。
ちなみに、iDeCo公式サイトでどれだけの所得控除が受けられるかをシミュレーションすることができます。
参考までに、年収500万円の人であれば以下のような結果になりました。
- 12,000円/月の掛金であれば、年間14,400円の所得税軽減
- 20,000円/月の掛金であれば、年間24,000円の所得税軽減
iDeCoを検討するための材料にしていただければと思います。
あと、あくまで私の今の勤め先でのケースになりますが、このiDeCoによる所得控除を受けている人は少ないという印象があります。

教職員全体の1割程度といったところでしょうか。
政府があれだけ利用をすすめている割には、あまり普及していないように感じています。
そして、私学共済の積立貯金と併用している人も少ないという傾向も見られます。
積立貯金をしている人は積立貯金のみ、iDeCoをしている人はiDeCoのみといった具合で、積立貯金のみの人の方が圧倒的に多いです。
それぞれの利用者の様子をまとめると以下のようでした。
- 積立貯金のみの利用者:iDeCoは、「原則60歳まで積み立てたお金を引き出せない」「値下がりする可能性がある」というところに不安を感じている。
- iDeCoのみの利用者:同じ毎月積み立てるならより増やせそうな方にする。

積立貯金も引き出しにくいですが、iDeCoほどではないですからね。
結局、本人のリスク許容度や手元にどれだけ余裕資金が準備できているかといった観点から、自分にあったものを選択するのが一番だと思われます。
寄付金控除(ふるさと納税)
こちらについては「ふるさと納税」のかたちで取り組んでいる方が多いという前提で話を進めます。
設問2で取り上げたとおり、寄付金控除は基本的に年末調整ではなく確定申告を行わなければなりません。
ワンストップ特例制度を使えば確定申告する手間が省けるので、私の周りでも利用している人が多いように思います。
ただ、「ふるさと納税は節税ではない」という意見もあるようです。

ざっくり言えば、寄付した分だけ税金が減るというものなので、寄付でお金が出ていくか納税でお金が出ていくかの違いとも考えられるというわけです。
私自身は、日用必需品などをふるさと納税で手に入れるようにしているので、普通に買い物するよりかは得と思うようにしています。
あとは、特産品をふるさと納税で手に入れて、それを両親と食べたり飲んだりすることで楽しい時間を過ごすといったことにも活用しています。
ここ1年以内に災害などに見舞われた地域に寄付をして特産品を手に入れる。
その特産品を両親と一緒に味わう。
こうすることで、使った金額以上の心の満足が得られるように感じていますのでおすすめします。
まとめ
前述しましたとおり、FP3級のタックスプランニングの範囲はほぼ所得税関連です。
それだけ私たちの生活とかかわりの深い税金ということだと思います。
しかし、私たちはこの所得税を引かれた後の結果しか見る機会がありません。
そのことが、身近な税金であるにも関わらずいまいちその仕組みを理解できていない一因となっているように感じています。
ぜひ、FP3級を学んで「どのような仕組みなのか」や「どうすれば引かれる金額を減らすことができるか」といったことを考えてみましょう。
そうして得た知識が仕事をするうえでも役立つと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。