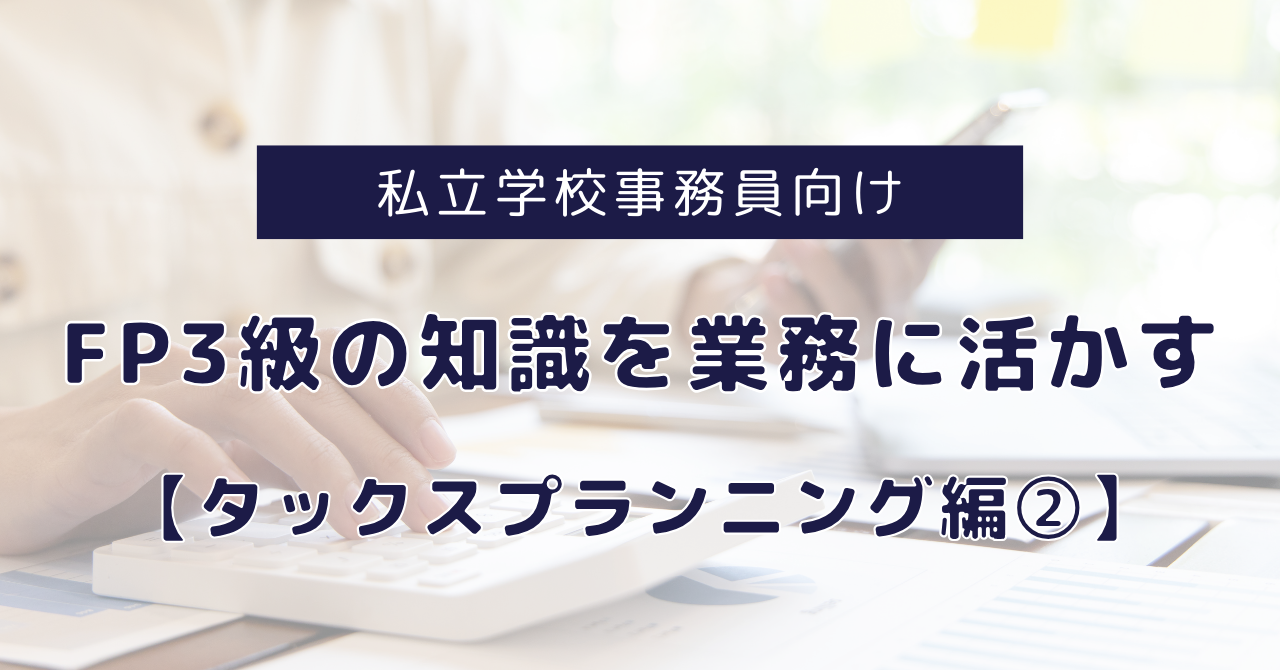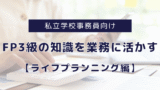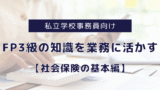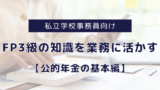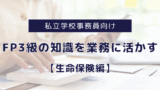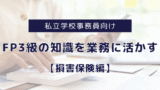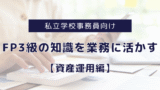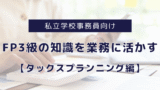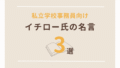この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・私立学校事務員の仕事にタックスプランニングの知識が必要なのかという疑問を持っている人。
以前の記事で、ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下、FP技能検定)3級の試験範囲の中から私立学校事務員の仕事に役立ちそうなものを紹介しました。
前回は「タックスプランニング」分野のうち「所得税」をメインに取り扱いましたが、この分野は他にも私が知っておくべきと考える内容があります。
そこで今回はその中から「所得控除」に関する内容をピックアップしてみました。
これまでと同様に、FP技能検定3級の試験を参考にした問題を解きながら、必要な基礎知識を身につける形式にまとめています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとにこの「タックスプランニング」に関連した情報を紹介しています。
前回に引き続き「タックスプランニングの知識を事務員の仕事で使うことなんかないのでは?」と思っている方も、一読いただければと思います。
なお、この記事は掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
【第1問】所得控除①
以下の条件における所得税の基礎控除の額として正しいものはどれか。
- 2024(令和6)年時点
- 合計所得金額が2,350万円以下
- 収入は給与のみ
正解:B
2024(令和6)年は、納税者の合計所得金額が2,350万円以下の場合、金額の多寡に関わらず一律48万円でした。
なお、令和7年度税制改正により、基礎控除の額などが見直しされています。
詳しくは、国税庁のホームページを確認しましょう。
令和7年度税制改正(国税庁ホームページへのリンク)
【第2問】所得控除②
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、適用を受けることができないものは次のうちどれか。
正解:A
配偶者控除や配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用できません。
控除の適用可否と納税者本人の合計所得金額との関係を整理すると、以下のようになります。
- 配偶者控除、配偶者特別控除:1,000万円を超えると適用不可
- 基礎控除:2,500万円を超えると適用不可
- 扶養控除:納税者本人の合計所得金額に関わらず適用可能
【第3問】所得控除③
所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「〇万円以下」の場合、配偶者控除の適用を受けることができる。
「〇」に入る数値として正しいものは次のうちどれか。 ※令和7年度税制改正後の場合
正解:B
いわゆる「扶養控除の年収の壁」に関係する部分になります。
こちらも令和7年度税制改正により変更が生じています。
- 従来:「給与所得控除55万円+所得要件48万円」=103万円
- 改正後:「給与所得控除65万円+所得要件58万円」=123万円
前述の国税庁ホームページを確認しておきましょう。
【第4問】所得控除④
所得税において、その年の12月31日時点で扶養控除の対象とならない扶養親族の年齢として正しいものはどれか。
正解:A
扶養控除についてまとめると以下のようになります。
- 16歳未満:ゼロ
- 16歳以上19歳未満:38万円
- 19歳以上23歳未満:63万円
- 23歳以上70歳未満:38万円
- 70歳以上の同居老親等:58万円
- その他の老人扶養親族:48万円
【第5問】所得控除⑤
納税者本人が、生計を一にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支払った場合の取り扱いとして正しいものはどれか。
正解:A
社会保険料控除は、社会保険料を支払った人の所得金額から控除することができます。
ここでいう社会保険料には国民年金や健康保険、介護保険などが含まれます。
なお、「年金」という言葉がついていても、確定拠出年金の個人型年金の掛金は、納税者本人に係る掛金のみが「社会保険料控除」ではなく「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
【理解度アップ】年末調整でのできごと
所得控除が直接関係する業務といえば、年末調整が一番に思い浮かぶ人も多いのではないでしょうか。
年末調整業務においては給与システム等を使用することがあり、その場合は設問で挙げた配偶者控除や扶養控除などはシステムが自動的に計算されるため、知識がなくても進めることができます。
しかし、以前の記事でもお伝えしてきましたが、担当者としては明確に「なぜその結果になるのか」や「なぜその書類の提出が必要なのか」といった仕組みの部分まで説明できるようになっておくべきと私は考えております。
今回、令和7年度税制改正により基礎控除の見直しなどがありました。
当然、システムを導入している学校ではシステムをアップデートするなどして対応しているでしょう。
そのため、年末調整の計算については問題なく処理することができると考えられます。
しかし、それは計算に必要な情報が正しくシステムに取り込まれている場合の話。
そもそも計算に含められるはずだったものが含められずに処理が進められるといったことが起こりえるわけです。
私の今の勤め先では、「寡婦控除」の対象であるにも関わらず、ずっとその申請が漏れていた教員がいました。
別の勤め先からの転職者だったのですが、年末調整の書類を見て「あれっ?」と気づいたのです。

その教員と雑談していた際に、「配偶者と死別した」旨のことをおっしゃっていたのをなぜか覚えていました。
本人に確認すると、

そんな欄に今までチェックしたことがない。
とのことでした。
こうしたことが起こりえるというわけです。
今回の改正の件で言えば、新たに設けられた「特定親族特別控除」
改正前の基準では「特定扶養親族」対象とならなかった人が控除対象となりました。
この控除を受けるためには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」という書類を学校に提出しなければなりません。
この書類の提出が漏れる可能性があります。
仮にこうした書類もシステム側で自動的に対応できる場合であっても、申請する側の理解が不足していた場合は同じく提出が漏れてしまいかねません。

先ほどの寡婦控除の件もそうですが、自己責任と言ってしまえばそれまでなんですけどね。
こうしたケースを防止するためにも、担当者は制度のことを理解しておき、関係者へ周知できるようにしておくべきだと思います。
そして計算結果についても、同様です。
同じく令和7年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の金額が見直されました。
これにより、私のような配偶者や扶養親族のいない者であっても、従来よりも基本的に控除額が増える結果になります。
こうしたことも、対象者に説明できるように準備しておくべきです。
システムの計算結果を見ながらでもよいと思いますので、一人ひとりの年末調整の金額について、担当者として説明できるようにしておきましょう。
【おまけ】事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
配偶者控除と似ていて混乱してしまうのが「社会保険における被扶養者認定」です。
- 配偶者控除:103万円の壁(123万円に見直し)
- 被扶養者認定:130万円の壁

数字も似ていてわかりにくいですよね。
この130万円の壁について、よく非常勤の教員から相談を受けます。
「配偶者の扶養から外れない範囲で働きたい」という内容がほとんどです。
一応、希望に沿えるように計画を立てるのですが、人手不足により業務量が増えたため、1度だけ収入オーバーになってしまったことがあります。
そんなときの救済措置として設けられているのが「事業主の証明による被扶養者認定」です。
「一時的な事情」で収入が増えた場合、厚生労働省が定める「事業主の証明書」を提出すれば「連続2回まで」被扶養者として認定してもらえるというものです。
所得控除のおまけ知識として、知っておくといざというときに役立つと思い紹介させていただきました。
なお、今後の制度見直し等によりこの措置はなくなるかもしれませんので、状況を確認していきましょう。
まとめ
所得控除については、令和7年度税制改正で様々な見直しが行われました。
こうした税金の知識は、直接年末調整業務に携わる事務員だけでなく、社会人として働く私立学校事務員全てに関係する内容ですので、知識を身につけておきましょう。
そのための第一歩として、FP3級の学習を始めてみることをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。