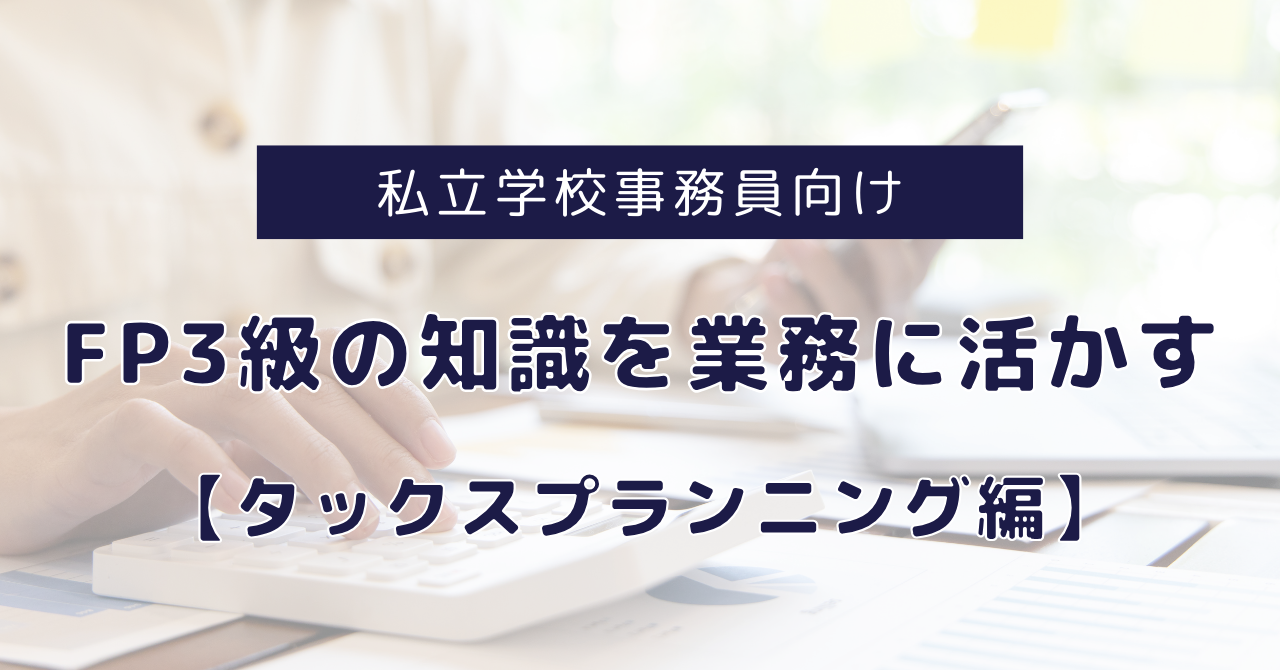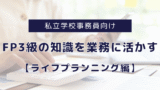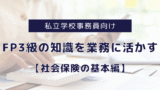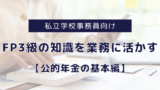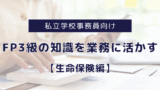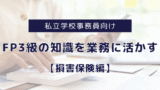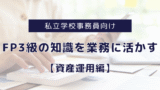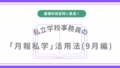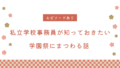この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・私立学校事務員の仕事にタックスプランニングの知識が必要なのかという疑問を持っている人。
以前の記事で、ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下、FP技能検定)3級の試験範囲の中から私立学校事務員の仕事に役立ちそうなものを紹介しました。
今回はその続きとして、「タックスプランニング」の部分で私立学校事務員として知っておくべきと私が感じたものをピックアップしてみました。
前回と同様に、FP技能検定3級の試験を参考にした問題を解きながら、必要な基礎知識を身につける形式にまとめています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとにこの「タックスプランニング」に関連した情報を紹介しています。
「タックスプランニングの知識を事務員の仕事で使うことなんかないのでは?」と思っている方も、一読いただければと思います。
なお、この記事は掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
【第1問】所得税①
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、次のうちうちどれか。
正解:A
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は雑所得となり、課税対象です。
なお、遺族年金や障害年金は非課税になります。
年金を受給しながら、私学にお勤めの人もおられますので、覚えておきましょう。
【第2問】所得税②
電車・バスなどの交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当で、所得税法上、非課税となる限度額は次のうちどれか。
正解:B
月額15万円を限度に非課税となります。
なお、自家用車等の場合は片道に通勤距離に応じた1か月あたりの限度額が別途定められていますので、国税庁のホームページなどで確認しておきましょう。
【第3問】所得税③
所得税における給与所得の金額を計算する際の算式として正しいものはどれか。
正解:A
給与所得の金額は「給与収入金額―給与所得控除額」により計算されます。
あわせて、給与所得控除額は、給与所得の源泉徴収票の支払金額によって計算式が異なる点もおさえておきましょう。
なお、退職所得は原則「(収入金額―退職所得控除額)×1/2」で計算されます。
【第4問】所得税④
退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合に適用される税率は次のうちどれか。
正解:A
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職所得ではなく「退職手当等の金額」に対して、20.42%の所得税が源泉徴収されます。
従って、多くの場合において本来の税額よりも多くの税金が徴収されることになります。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、課税退職所得額に応じた所得税率等を用いて源泉徴収等されます。
【第5問】所得税⑤
次の給与所得者のケースにおける退職所得控除額として正しいものはどれか。
- 勤続年数:22年
- 退職理由:定年退職
- 退職金額:2,000万円
正解:A
このケースにおける退職所得控除額の計算式は以下のとおりです。
800万円+70万円×(22年-20年)=940万円
なお、退職所得控除額の計算方法は、勤続年数が20年を超えるかどうかで変わります。
- 勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
【理解度アップ】学校法人にまつわる所得税マメ知識
学校法人は基本的に、公共性・公益性が考慮され、様々な税制上の優遇措置を受けています。
その関係もあってか、経理・会計担当でも通常の業務で取り扱うのは「所得税」「消費税」「印紙税」くらいというのが私の実感です。

細かいことを言えば、公用車を所有していたら「自動車税」を支払うこともありますね。
そして例で挙げた中で、最も関わる機会が多いと感じているのが「所得税」。
そのため、出題もすべて所得税に関するものを選んでみたわけです。
ただ、学校法人自体は所得税も非課税です。
例えば私たちの場合、預金利息には20.315%の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。
一方、学校法人は所得税法第11条により利息に対して所得税が課されません。
第十一条 別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配(貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
e-GOV法令検索より引用

「別表第一」に「学校法人」が掲げられています。
ですので、ここでいう「所得税」は我々個人にかかるものと理解していただければと思います。
- 講演の講師として来られた方への謝礼に係る所得税
- 給与や賞与で教職員ごとに計算する所得税(年末調整も含む)
- 退職時の退職金に係る所得税
こうした場面で所得税に関する知識は必要になってきます。
しかし、これらの多くは給与システム等で自動的に計算されるため、実務上は知識がなくても仕事を進めることができてしまいます。
ただ、以前から申しあげていますとおり、出てきた結果だけを見るのではなく、「なぜそうなっているのか」まで担当者は理解しておくべきというのが私の意見です。
そこで以降は、この所得税にまつわる「マメ知識」的なものを紹介していきたいと思います。
具体的には以下の2点です。
- 周辺会計と所得税
- 奨学金と所得税
【見落としていませんか?】周辺会計と所得税
PTAや同窓会、生徒会など、学校に関わる団体の会計を「周辺会計」と呼ぶことがあります。
これらの団体の会費等については、学校が「団体の代理」というかたちで学納金と一緒に徴収し、各団体へ渡す仕組みになっています。

少なくとも私が勤めてきた学校では以上のような徴収方法をとっていました。
この団体、基本的には「人格のない社団等」に該当するため、源泉徴収義務者となります。
つまり、これらの団体が謝金等を支払う場合、所得税等を差し引いて国に納める義務があるということです。
ところが、この源泉徴収が漏れることがあります。
理由は様々考えられますが、私としては学校の会計担当と周辺会計の担当とが別々であるケースでこのようなことが起きやすいという印象を持っています。

学校によっては、周辺会計を教員が担当しており、通帳などもその担当教員が管理している場合もあるようですね。
そのような状況だと、所得税に関する知識が十分でない者がお金の出し入れを行うことになり、徴収漏れが起こるわけです。
そしてそれが前例となり、「前からそうしていたからこれでいい」という発想に至ってしまいます。
こうした過ちを防ぐ方法としては、
- お金の出し入れは学校の会計担当に集約する
- 会計士による監査を定期的に受ける
といった方法が考えられます。
源泉徴収に限らず、ミス・不正の防止にもつながると思いますのでおすすめです。
【税務調査の思い出】給付奨学金と所得税
これは、以前の勤め先で税務調査が入った時の話です。
大まかなやりとりは以下のとおりです。

奨学金の担当者はどなたでしょうか?

はい、私ですが。

この給付奨学金は所得税の課税対象ではないのですか?

え?
奨学金が所得税の課税対象かどうかなど考えたことがなかったので、パニックです。
確かに、学生側からすると何10万円というお金をもらっているわけですから、所得と考えられなくもない。
そう思いつつとりあえず自席に戻り、税金に詳しそうな事務員やネットから情報を集めました。
そして行き着いたのが所得税法第九条の非課税所得の条文でした。
以下に引用します。
十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
e-GOV法令検索より引用
この「学資に充てるため給付される金品」に給付奨学金は該当するのではないかと思い、 その旨を調査官へ伝えに行きましたが、

あぁ、その件はもう大丈夫です。
と言われました。
担当者としての知識を試されただけだったのか、今となってはわかりませんが、1つ勉強になったことは確かでした。

「今までどおり」で仕事をしていて、見落としてしまっていることがまだまだあるんだろうなぁと思いました。
まとめ
「税金」と聞くと、どうしても難しそうなイメージがあると思います。
そのため、できる限りかかわりを避けたいと思ってしまいがちです。
ただ、そんな嫌がられる分野こそ、他の事務員との差別化につなげられるとも考えられます。
求人サイトなどを見ていても、「税金に詳しい人」は学校法人だけでなく民間企業でも重宝される人材のようです。
皆さんも、そんな周囲から求められる人材を目指して、まずはFP3級レベルの税金の知識を身につけてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。