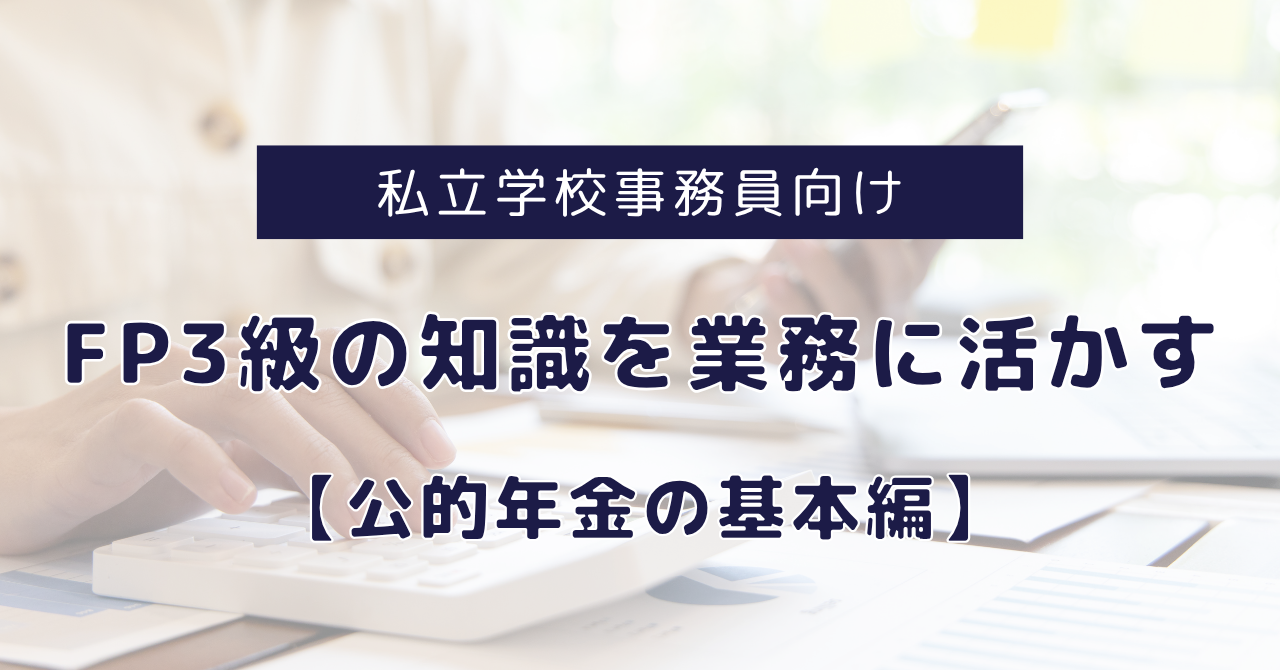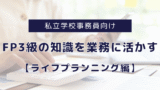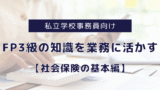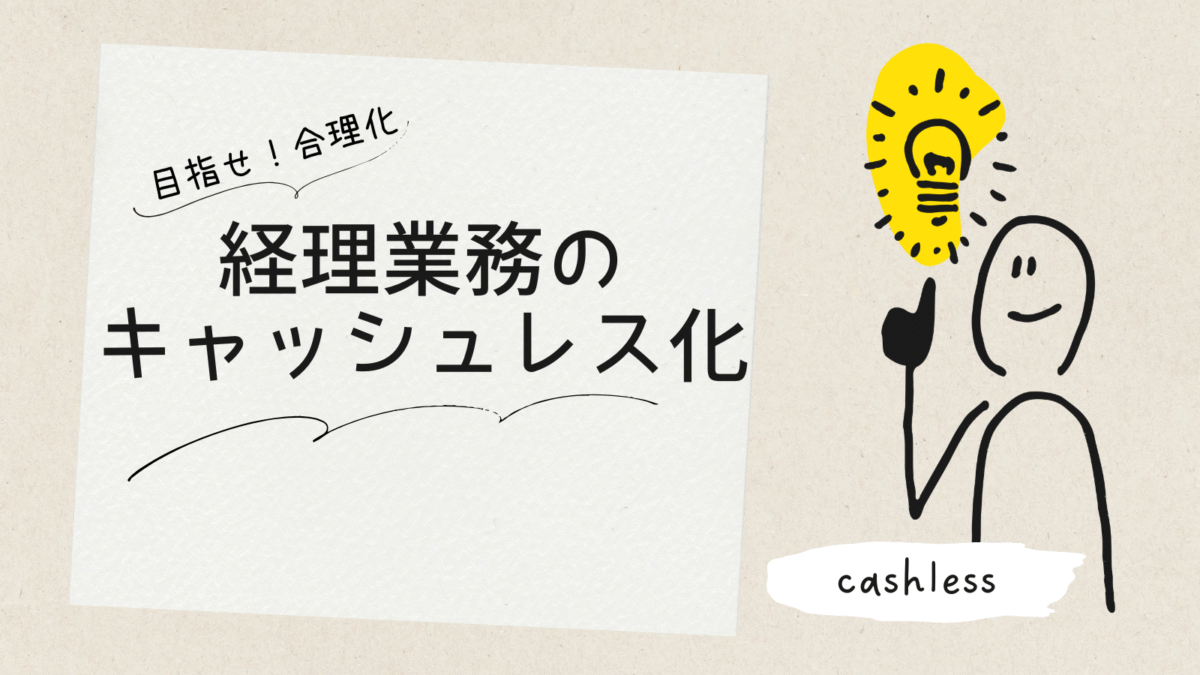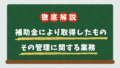この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・私立学校事務員の仕事に公的年金の知識が必要なのかという疑問を持っている人。
以前の記事で、ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下、FP技能検定)3級の試験範囲の中から私立学校事務員の仕事に役立ちそうなものを紹介しました。
今回はその続きとして、「公的年金の基本」の部分で私立学校事務員として知っておくべきと私が感じたものをピックアップしてみました。
前回と同様に、FP技能検定3級の試験を参考にした問題を解きながら、必要な基礎知識を身につける形式にまとめています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとに私が実際にこの「公的年金」のことで経験した事例などを紹介しています。
「年金の知識を事務員の仕事で使うことなんかないのでは?」と思っている方も、一読いただければと思います。
【第1問】学生納付特例制度①
学生納付特例制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生が対象であり、制度の適用を受けるための所得基準が設けられている。
その基準は、誰の前年所得が対象となっているか。
正解:A
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象になります。
ちなみに所得基準は以下の計算方法により算出されます。
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生本人の前年の所得額が、この計算方法で算出された金額以下の場合、制度の適用対象となるわけです。
【第2問】学生納付特例制度②
学生納付特例制度の適用を受けた期間の取り扱いについて正しいものはどれか。
正解:A
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。
日本年金機構ホームページより引用
なお、生活保護の生活扶助を受けているなどの理由による免除の場合、その免除期間は受給資格期間に算入され、さらに年金額にも少し反映されます。
【第3問】学生納付特例制度③
学生納付特例制度の受けた期間の保険料はさかのぼって納めること(追納)ができるが、期限が定められている。
その期限として正しいのは次のうちどれか
正解:C
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
日本年金機構ホームページより引用
なお、滞納や未加入期間の保険料は2年前の分までさかのぼって納付することができます。
【第4問】個人型確定拠出年金①
個人型確定拠出年金のメリットとして正しいものはどれか。
正解:A
個人型確定拠出年金に加入した本人が拠出した掛金の全額が、所得控除の対象です。
この場合は「小規模企業共済等掛金控除」として取り扱われることになります。
【第5問】個人型確定拠出年金②
個人型確定拠出年金の引き出しについて説明した以下の文の空欄に当てはまる組み合わせで正しいものはどれか。
個人型確定拠出年金は、通算加入者等期間が(①)年以上あれば、(②)歳以降引き出すことができる。
正解:B
個人型確定拠出年金の年金資産は、原則60歳になるまで引き出すことができません。
なお、老齢基礎年金も何らかの公的年金に「10年以上加入」している者に対して支給されます。
一緒に覚えておきましょう。
【理解度アップ】それぞれの制度について
公的年金の基礎というテーマでクイズ出題してきましたが、内容としては「学生納付特例制度」「個人型確定拠出年金」の2つの制度についてでした。
公的年金の分野は、基礎年金だけでも「老齢」「障害」「遺族」といった種類があり、もっと幅広い内容になっています。
しかし、実際のところ私立学校事務員の仕事で公的年金のことを扱う機会は滅多にないというのが私の感覚です。
そんな中で「FP3級の知識を仕事に活かす」という観点から、私の今までの経験を振り返ったところ、前述の2つの制度を紹介しようという思いに至りました。
そこでここからは、私の実体験も踏まえながらこれらの制度についてより詳しく見ていきたいと思います。
【わかりにくい?】学生納付特例制度
これがなぜ私立学校事務員の仕事に関係するか。
それは、大学生などこの制度の対象となる人からの問い合わせを受けるケースが毎年発生するからです。

「年金を猶予するやつ、申し込みたいんですけど」という感じで窓口に来られます。
制度そのものは難しくないので、前述の設問3つの内容だけおさえておけば問題ありません。
問題なのはその手続きについてです。
日本年金機構のホームページには、「国民年金保険料の学生納付特例制度」という専用ページがあります。
国民年金保険料の学生納付特例制度
(日本年金機構ホームページへのリンク)
ここに申請方法が記載された箇所があるわけですが、それを見て勘違いしてしまう学生生徒や保護者がおられます。
具体的には、申請先に「在学中の学校等」と記載されているため、「学校で申請手続きをすればいいのか」と勘違いしてしまうのです。
これは完全に間違いというわけではありません。
実際に学校で手続きができる場合もあります。
ただ、ホームページにも記載されていますが、「学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合」に限られるのです。
「学生納付特例対象校一覧」がホームページに掲載されており、その一覧表内の「学生納付特例事務法人の指定状況」という欄に「〇」が入っている学校であれば、学校で手続き可能となっています。
しかし、この一覧表だけを見てしまい、「一覧表に載っている学校だから、学校で手続きできる」と思ってしまう人が毎年少なからずいるわけです。

このように勘違いした保護者から「なぜ手続きできないのか」「ほかの学校ではできた」などといった電話がかかってきたりします。
そうした問い合わせへの対応として私は、上述の一覧表の中から自分の勤め先が記載されたページだけコピーしておき、勘違いして窓口に来た人にそれを渡すようにしています。
適切な対応ができるよう、覚えておくことをおすすめします。
【違いを理解】個人型確定拠出年金
いわゆる「iDeCo」というものです。
「公的年金」に対して「私的年金」と言われたりもします。
以前はこれに加入する際に、「事業主の証明書」が必要でしたが、法改正により不要となりました。

この証明書をもらうために職場に申し出なければならないので、二の足を踏む人もいました。
資産運用しているのをあまり人に知られたくないんでしょうね。
そのため、私立学校事務員の仕事でこの個人型確定拠出年金に関わるのは年末調整時くらいです。
前述のとおり、掛金全額が所得控除の対象となります。
ちなみに、掛金の上限は20,000円/月、年単位に直すと240,000円/年です。
これが「所得」から控除されるわけです。
ここが理解しておくべきポイントです。
所得税の金額を算出する流れを大まかにまとめると以下のようになります。
(収入-給与所得控除-所得控除)×税率=所得税額
この式の「所得控除」のところに、掛金の金額が入るわけです。
これと似ているのが「税額控除」。
先ほどの式でいうと、最後の「所得税額」から直接差し引かれるものになります。
年末調整をソフトなどで自動的に計算・集計していると、こうした違いをあまり意識せず機械的に処理してしまいがちです。

その状況は担当者としてよろしくないと私は考えています。
全く別物としてきちんと理解し、説明できるようにしておくことをおすすめします。
ちなみに学校法人への寄付について、所得控除か税額控除かを選べる場合があります。
控除額が同じであれば、一般的に税額控除の方が節税効果が高いと言われています。
保護者等から質問を受けることがありますので、適切に答えられるようおさえておきましょう。
まとめ
前述のとおり、私立学校事務員の仕事で直接年金に関する事務を取り扱うケースはあまりないと思います。
しかし、自分自身にも関わることなので、正しい知識を身につけておく必要があります。
そこでまずは、今回挙げたような仕事に直接関係しそうなところから知識を習得し、それをきっかけにさらに知識を広げてみてはいかがでしょうか。
この記事がそのお役に立てればなによりです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。