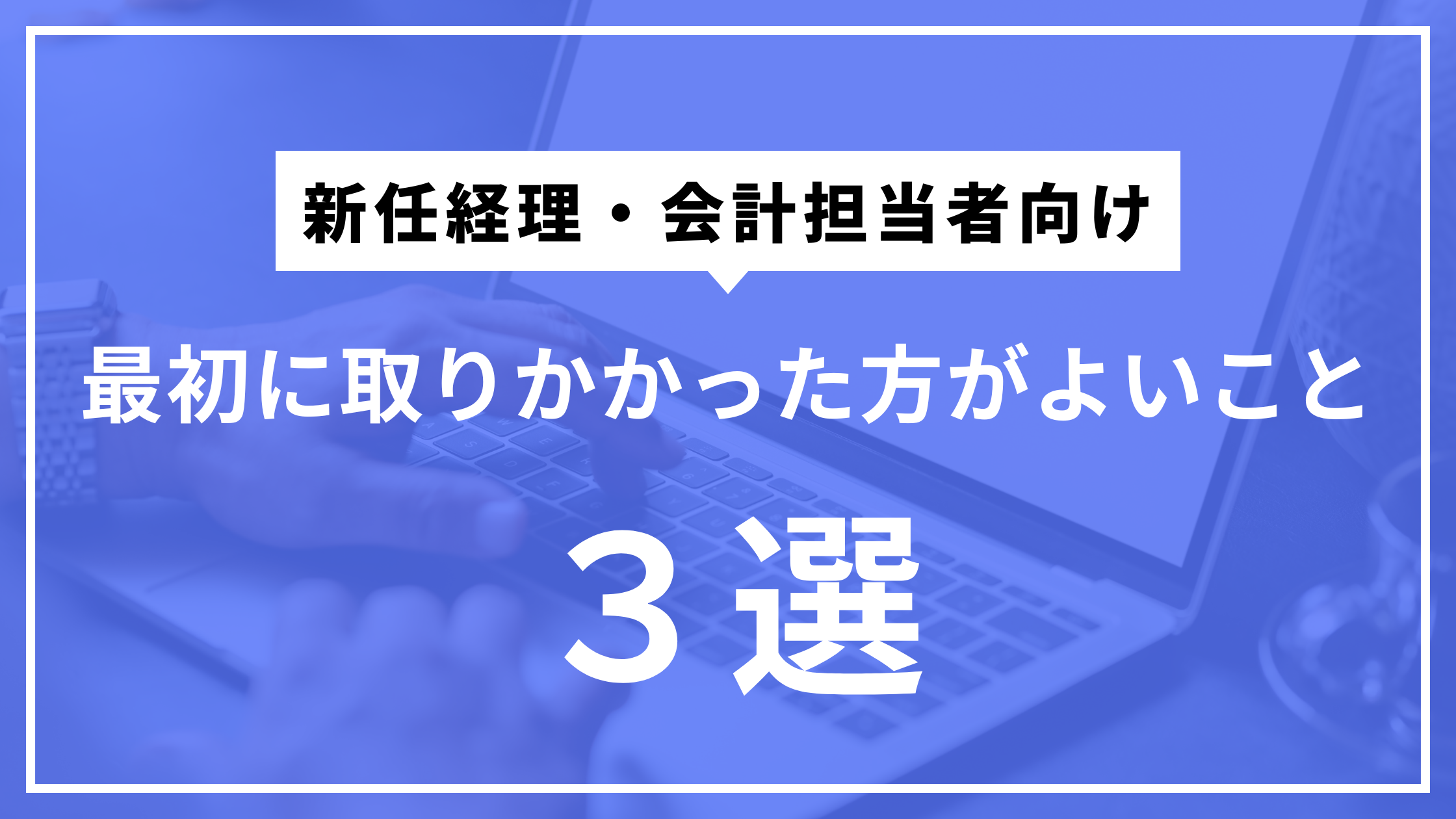この記事の内容は以下のとおりです。
・私立学校事務員で新たに経理・会計担当に就いた方が、業務を遂行するにあたり、始めに取りかかった方がよい行動を紹介
もうすぐ4月になります。
新入職員や転職して新たな学校等で働き始める方、人事異動で今までとは違う部署で働くことになった方など、4月から新しい環境での生活をむかえる方も多いのではないでしょうか。
その中には、新たに経理・会計担当に就く方もおられると思います。
私も20年以上前に、新卒で学校法人に入職し、私立学校事務員としてのキャリアをスタートしました。
その初日に「財務課勤務を命ず」という辞令を受け、「財務って何をするの?」と思った記憶があります。

最初に着任したのは高校事務室ではなく、本部事務局でした。
数字をほとんど扱わない文系学部を卒業した私にとっては、不安を覚える一言でした。
その時の経験をもとに、経理・会計担当に就いたばかりの方がまずやり始めた方がよいと思われる行動を3つご紹介させていただきます。
皆さまの不安払拭の一助になれば幸いです。
【結論】まずやってみるのはこの3つの行動
早速ですが、先に結論として3つの行動を紹介させていただきます。
以上の3つです。
先に言っておきますと、簿記や会計の勉強はすぐに始めなくてもよいと考えています。
1年間、経理・会計業務を経験してから始めても遅くはありません。

ちなみに私は担当着任後すぐに簿記3級の勉強を始めて、1か月経たないうちに挫折しました。
簿記の資格を取得したのはそれから約15年後です。
それでは、1つずつ紹介していきます。
【おすすめ行動①】やったことを毎日手帳へメモ
学校事務員の仕事全般に言えることですが、月単位、年単位で見るとルーティン化されているものが多いです。
そのため、「今日何をしたか」を手帳にメモするだけで、業務の流れをつかむことができます。

「何時に何をしたか」まで書く必要はありません。
時間術に関する書籍などでは、自分の時間の使い方を記録することを薦めていたりもしますが、今回紹介する内容はそこまで求めていません。
1か月間、とにかく箇条書きでよいので手帳に書き込み、翌月は前月同日の記録を読み返してみます。
これを繰り返していると、月単位の「やるべきこと」が見えてきます。
同じように前年同日の記録を確認することで、予算や決算など年に1回しか行わない業務も流れが把握できるようになります。
なお記録するにあたっては、3年手帳や5年手帳を使用することお薦めします。
以下のイメージのように、4月1日の記録が同じページを見るだけで、3年もしくは5年分確認できる様式になっています。
一目で見ることができて、大変便利と実感しています。
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||
| 2026年 | |||||||
| 2027年 |
余裕があれば、仕事内容だけでなく失敗したことなどもメモしておくと、後々役に立ちます。

仕事内容と失敗談をセットにしておくだけで、手帳が業務マニュアル的な役割を果たすようになり、業務ミスの防止や後任への引継ぎにも使えるようになりました。
これが習慣になり、業務を遂行できるようになれば、簿記や会計の知識不足は十分にカバーできます。
まずは、確実に仕事を進められるようになり、仲間との信頼関係を構築してから簿記や会計の勉強をすればよいというのが、私の実体験に基づく感想です。
以上が1つ目の行動です。
【おすすめ行動②】キャビネット、ファイルサーバー内資料の確認
①で紹介した「流れの確認」でスケジュール感覚をつかみながら、あわせて「どんな資料がどこにあるのか」を把握することが重要です。
経験や知識に乏しい新任担当者が一番頼れるのは「過去の資料」です。
自分が担当する業務の前任者などが、同じ部署に残っているのであれば、その人に直接尋ねることができますが、尋ねられる人がいないパターンの方が多いように思います。

前任者の人事異動等の理由で、自分が新たに着任したというケースがほとんどですので。
簿記や会計の知識を身につけて、わからないことを減らすというのも1つの対策ですが、時間がかかりすぎるためおすすめできません。
そこで、まずは自分の部署のキャビネットを実際に見て、資料の場所を確認しておくのです。
困ったときに「確かあのキャビネットに資料があった」と思い出すことができれば、それだけスムーズに仕事を進められるようになります。
また、学校現場、特に高校の事務室はまだまだ紙の資料が多いのでキャビネットの確認を例に挙げていますが、資料がデータ化されているケースも同様です。
その部署や事務室専用のデータ保存場所があると思いますので、そこを確認します。

私はデータを保存するフォルダが一覧になっている画面をスクリーンショットで撮るようにしています。
人が探し物を使う時間はかなり多いという調査結果もあるようです。
着任して間もないときは知識や経験が不足していて、なかなか仕事の中身で貢献することは難しいです。
そんな時に、資料探しをしている同僚などに「その資料はあのキャビネットあります」といったような対応をとることができますと、喜ばれます。
このように、資料の場所を把握することは、自分の仕事の効率化はもちろんのこと、職場の仲間との良い関係の構築にもお役立ちしますので、取りかかってみてはいかがでしょうか。
これが2つ目の行動です。
【おすすめ行動③】1年前の資料チェック
資料の場所を確認しましたら、せっかくなので中身もチェックしましょう。
まず、チェックすべきは担当業務の1年前の資料です。
経理担当であれば、1年前の同月の請求書などが綴じているファイルや会計伝票ファイルを確認します。

総勘定元帳や資金収支元帳は、もう少し経験を積んでから見るようにしても問題ありません。
毎年同じ時期に同じような請求があるケースが多いですので、これも①で紹介した「業務の流れの把握」という意味があります。
その「流れの把握」に加えて、会計伝票の入力内容と請求書等の書類を見比べてみて、「こういう内容を記載すればいいのか」といった「型」のようなものをつかむことを意識して確認してください。
そうすることで、簿記の知識がなくても会計伝票が作成できるようになります。
さらにそれを積み重ねることで、後々簿記の勉強をした際に勉強内容と実務経験とが結びつき、理解がしやすくなるという効果も期待できます。
経理業務以外に、学納金業務や補助金業務でも同様の行動をとることをおすすめしますが、注意点が1つあります。
それは「過去の資料を確認したらそうなっていました」という言葉は厳禁ということです。
私の失敗エピソードをご紹介させていただきます。
ある資料を作成する際に、昨年度の資料を見ると「資料図書」と「図書資料」という2つの文言を使っていることに気づきました。
内心「どう違うのだろう」と思いながら、同じようにこの2つの言葉を使用して資料を作成しました。
作成した資料を上司がチェックしたときに、「資料図書と図書資料はどう違うのか」と質問を受け、「昨年の資料がそういう記載でした」と答えてしまい、「ちゃんと意味を考えて資料を作れ」と厳しく指導を受けました。
その上司は昨年度も同じ部署に所属していたので、「去年この内容で承認したのでは」と思いましたが、何も考えずに資料を作成したのは事実なので何も言いませんでした。

昨年度のマネをするのは、あくまで効率よく「型」を覚えることが目的です。
決して「仮に間違えても、「昨年度もこうでした」と言えばいいか」といった言い訳に使うことが目的ではありません。
誤り等に気づいたら「これは「型」ではなかった」と考え、忘れてしまいましょう。
これが3つ目の行動です。
まとめ
私自身が経理・会計担当して新たに着任した際の経験をもとに、新任者におすすめしたい行動を3つ紹介しました。
これら3つの行動のポイントは「効率化」です
簿記や会計の勉強はとても大切ですが、時間がかかるという問題があります。
しかし、新任者は「早い段階」で「小さな成功体験」を積むことが大切です。それが周りからの信頼感につながるからです。
そのために、スケジュールや資料の場所の把握、「型」の活用に取り組み、効率よく行動できるようになりましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。