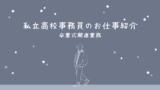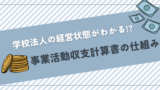この記事の目的は、以下のとおりです。
・学校が受け入れる寄付金について理解する
・寄付金の会計処理について理解する
・寄付金とその他の収入との違いを理解する
卒業式業務や新入生受入業務の紹介記事の中で「寄付金」について触れました。
今回はその「寄付金」について、
- 寄付金の種類
- 寄付金の会計処理
- 寄付金と補助金等他の収入との区別の仕方
を中心に、私が寄付金業務を担当するうえで留意していることを紹介します。
以前の記事で解説した「奨学金」と同様にこの「寄付金」も、民間企業をメインとした日商簿記の参考書などでは、取り扱われていません。
しかし、寄付金は学校法人にとって、学費や補助金の次に大きな収入源になりえるものです。
その重要な収入について、私立学校事務員として押さえておくべきポイントをこの記事では解説しますので、知識の習得にお役立ていただければ幸いです。
寄付金の種類
まずは、どのような寄付金の種類があるのか確認しましょう。
学校法人会計基準では寄付金を以下の3種類に分類しています。
- 一般寄付金
- 特別寄付金
- 現物寄付金
1つずつ見ていきましょう。
一般寄付金
一般寄付金とは、特に使途が指定されていない寄付金を指します。
ただし、現実的に全く使途の指定がない寄付金というものはあまりありません。
ではどんなものが一般寄付金として取り扱われるか例を挙げますと、「教育活動に対する寄付」といった程度の指定の場合が該当します。

「とりあえず、学校の教育に関することであれば、具体的な使途はお任せしますよ」というニュアンスで寄付されるパターンです。
ただ、使途の具体的な指定はなくとも、もし寄付者からその寄付金の使途を尋ねられた場合に明確にこたえられるよう、書類の整備等の準備はしておきましょう。
特別寄付金
前述の一般寄付金よりも具体的に使途が指定されている寄付金です。
例えば「〇〇建設資金としての寄付」といったものです。
校舎建設など大規模な工事を実施する場合、多額の費用が必要となります。
その費用を「自己資金」「借入金」「補助金」「寄付金」などどんな財源で賄うかを考える必要があります。
そうした具体的な目的をもって募集をし、集められた寄付金はこの特別寄付金に該当します。

なお、経理・会計担当の事務員の場合、この使途が「活動区分資金収支計算書」や「事業活動収支計算書」に影響があることもおさえておきましょう。
前述の「○○建設資金としての寄付」のように「施設整備」を目的とした寄付金は、活動区分資金収支計算書では「施設整備等活動」、事業活動収支計算書では「特別収支」として基本的に処理することになります。
活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書についての記事は以下の記事もご覧ください。
現物寄付金
前述の2つの寄付金は、学校側がお金で受領するものですが、この現物寄付金はお金以外のもので受け取ります。
例えば図書やパソコンなどが文字通り「現物」で寄付されます。

学校の図書館でたまに「○○文庫」のように、人の名前がついたコーナーがあったります。これは、その「○○さん」が図書を現物で寄付したことに対して設けられたものである可能性があります。
お金以外にもこうした寄付の受け取り方があるということも覚えておきましょう。
寄付金の会計処理
続いて、会計処理を確認しておきましょう。
一般寄付金と特別寄付金の会計処理
この寄付金は「収入」グループに属するものですので、これまでの記事でも紹介しました授業料などの他の「収入」グループの処理と同じです。
一応例を挙げて確認します。
例:保護者から「学校の教育活動への寄付」として100,000円を普通預金口座で受け入れた。
(分解)
「寄付金100,000円」「普通預金100,000円」
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 寄付金 | 収入 | 増加 | 右 |
| 普通預金 | 資産 | 増加 | 左 |
(仕訳)
前述の説明のとおり「教育活動への寄付」は一般寄付金で処理します。
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 100,000 | 一般寄付金 | 100,000 |
特別寄付金の場合は、「一般寄付金」を「特別寄付金」に変えるだけですので、ここでは解説は省略します。
現物寄付金の会計処理
現物寄付金も「収入」グループに属するため、基本的には一般寄付金等と同様の処理を行います。
ただし、大きな違いが1点あります。
それは、「現物寄付金は資金収支計算書には出てこない」という点です。

図書やパソコンを現物でもらうわけですから、お金(資金)が増えたり減ったりしないということです。
そのため、事業活動収支計算書にのみ「現物寄付金」として記載されることになります。
念のため例を見ながら確認しましょう。
例:保護者から100,000円分の図書が現物で寄付された。
(分解)
「寄付金100,000円」「図書100,000円」
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 寄付金 | 収入 | 増加 | 右 |
| 図書 | 資産 | 増加 | 左 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 図書 | 100,000 | 一般寄付金 | 100,000 |
前の例では「普通預金」という金融資産が増加した一方で、今回の現物寄付金では「図書」という現物資産が増加したという処理になります。

現物寄付金では「寄付された対象の資産が増える処理を行う」とここでは理解しておけば十分です。
寄付金と他の収入との区別の仕方
現物寄付金は例外として、寄付金は他の収入、特に学費や補助金と区別がつきにくい部分があります。
そのため、取扱いに関する基本的なルールが定められていますので、覚えておきましょう。
学費と寄付金の違い
学費のなかでも「施設協力金」のような名称で徴収されているものがあります。
名称だけ見れば「協力金」とついているので、「寄付金かな?」という印象を受けます。
そのため、両者を区別するルールが以下のとおり設けられています。
- 学費:学則等に金額や納付義務が記載されているもの
- 寄付金:学則には記載されていない納付が任意のもの
この「学則に記載の有無」「納付義務の有無」の2点で学費か寄付金かを判断するということになります。
補助金と寄付金の違い
どちらも「助成金」の意味合いがあり、似ている印象があります。
これも区別のための明確なルールが定められています。
- 補助金:国または地方公共団体の資金を原資としたもの
- 寄付金:国または地方公共団体以外の資金を原資としたもの
つまり「国または地方公共団体からもらったかどうか」で判断します。

私が以前勤めていた学校では、とある公益財団法人から「助成金」を受けていました。その財団は民間企業等に資金をもとに設立されていたため、上述のルールに基づき「寄付金」として処理していました。
【おまけ】自分で寄付を体験してみる
ちなみに、私は毎年自分の勤め先の学校に寄付しています。
理由は税金の勉強になると考えているからです。
寄付金をした場合、確定申告を行うことで「寄付金控除」により所得税等が還付されます。
この確定申告を行うという作業が、税金の仕組みを勉強するきっかけになると感じています。
提出した確定申告の書類を見て、どんな計算過程を経ているのかなどを調べてみると「なるほど」と思うことがあります。

税金に関する法律の改正などをニュースで見てもピンとこないですが、実際に自分の税金に反映されていることを確認すると「そういうことか」と思ったこともあります。
学校事務員は年末調整がありますし、ふるさと納税をした場合でも「ワンストップ特例制度」を利用すれば楽に控除を受けることができますが、勉強のために自分の手作業で確定申告を行ってみることをオススメします。
そうして実体験を積むことで、寄付者等に対し、より具体的で説得力のある説明ができるようになるという効果も実感しています。
まとめ
・寄付金はお金だけでなく、現物での受け入れも可能
・寄付金受入の際はルールを確認し、適切な処理が必要。特に「任意」であることは重要
今回の記事は、主に経理・会計担当の事務員向けの内容となりました。
しかし、実際に処理をしない事務員であってもその受け入れ方や他の収入との違い、寄付金控除については、保護者等関係者から問われることも想定されます。
その際に、ポイントを押さえて説明できるように知識を整理しておくことが大切です。
今回の記事が、その一助になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。