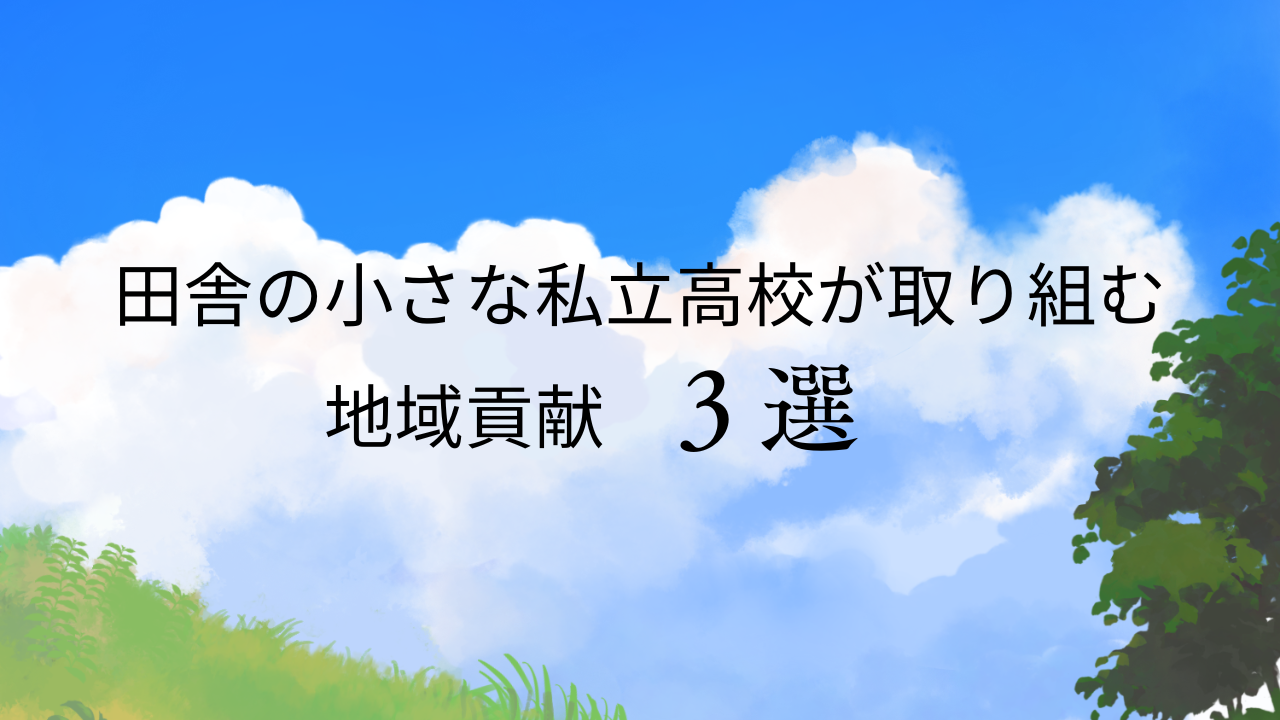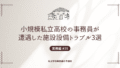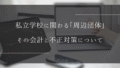この記事は以下のような人を対象としています。
・「田舎にある小さな私立高校は、地域のためにどんな取り組みをしているのだろう」と思っている人
学校は「公共性」が強く求められる存在です。
それは、単純に国や地方自治体から補助金の交付を受けているからというだけでなく、社会に役立つ人材の輩出など、学校の教育活動に対する世の中からの期待の表れでもあります。
そんな教育活動の一環として「地域貢献活動」に取り組む学校も少なくありません。
私の勤める学校も、小さいながらもそういった活動を行っています。
今回の記事では、そんな小規模私立高校が行っている地域貢献活動を3つ紹介させていただきます。
その3つとは以下のとおりです。
- 地域の事業者と協力したPR活動
- 地域の事業者との交流
- 授業で取り組む地域の魅力発信
私の勤め先のような田舎の小さな私立学校は、地域の人たちから愛されてこその存在です。
そんな学校を目指し、生徒や教職員が様々なかたちで取り組む地域貢献の様子が、皆さまの参考になれば幸いです。
【ボランティア活動にもなる】地域の事業者と協力したPR活動
地域の魅力を発信するイベントには様々な種類があります。
例えば学校の所在地である地域の自治体等が独自に催すものや、全く別の団体が開催するイベントにPRで参加するかたちのものなどです。
いずれのパターンにしても、その地域で活動する事業者と生徒や教職員が協力して、地域の良いところなどをPRします。
私の勤め先が実際に行ったものとして、「ホームタウンデー」というものがあります。
これは、サッカーのプロリーグである「Jリーグ」の試合にあわせて開催されるイベントです。
その地域に住んでいる小学生等が無料で試合を観戦できるなど、地域住民を対象としたサービスが提供されますが、それとは別に試合会場周辺で観戦に来られたお客様などに地域の魅力を発信するイベントも催されます。
そのイベントに生徒や教職員が参加するわけです。
純粋にボランティアとして、熱中症予防の呼びかけを行ったりもしますが、ゲームを企画して景品にその地域の事業者が生産している製品などをプレゼントするといった宣伝活動も実施します。

プレゼントを渡す際に、「これはこの地域に工場がある○○という会社が作っている製品なんですよ」などのPRをはさみます。
イベントの中でも子供向けの企画をすると、かなりの勢いで景品がなくなっていくイメージがありますね。
景品を受け取った人も、「この会社、このあたりにあるんですね」というリアクションをしてくださるケースも多く、PRの効果ありという印象です。
イベントを通じて、地域の事業者との関係が深まるという効果もありますが、生徒たちも「テレビCMで見たことがある会社が、自分の学校の近くにあったんだ」と関心を持ってくれます。
このイベントをきっかけに、授業の一環として生徒たちが事業者の工場を見学するなど、その後の交流にもつながることもあるので、お互いにとっていい機会になっているのではないでしょうか。
加えて前述のとおり、地域住民を対象としたサービスも提供されるため、観戦に来られた「学校の近くにお住いの方々」へのアピールにもなり、「あの学校、こういうイベントにも参加しているのか」と学校の存在をあらためて認識していただくチャンスとも捉えています。
地域の魅力発信と地域の事業者や住民との関係構築、さらに学校のPRも兼ねており、大変有意義な取り組みだと思いますので、ホームタウンデーに学校として参加してみてはいかがでしょうか。

なお、イベントが行われているタイミングでSNSにその様子をアップすると、サッカーチームのサポーターの方々など、普段は学校の投稿を見ないような人たちが反応してくれることもあるので、楽しいです。
【事業者も生徒も嬉しい】地域の事業者との交流
一つ目に紹介した取り組みは、「地域の魅力発信」をメインとした地域貢献活動の例でした。
そのため「その地域に住む方以外」が主な対象となるわけですが、「地域で活動する事業者」を対象として地域貢献活動を行うこともあります。
例えば、昼食の販売。
私の勤め先は食堂がないため、生徒は昼食を持参する必要があります。
しかしお弁当を準備することが難しいというご家庭も少なくないため、コンビニなどで食べ物を買って持ってくるケースもよく見受けられます。

一応、菓子パンを買える自動販売機を設置していますが、やたらと品切れになります。それだけ上述のようなご家庭が多く、需要があるということなのでしょうが、私の金銭感覚では絶対に買うことのない値段なので、いつも不思議に思っています。
そこで、お弁当などを販売してくれる地域の事業者に声をかけて、週に1回程度、お昼休みに昼食を販売していただくわけです。
声をかける際には、就労支援などを行っている事業者を選んでいます。
そうすることで、事業者・生徒・学校の3者でそれぞれに以下のようなメリットがあると考えています。
- 事業者:売上が確保でき、活動のPRにもなる
- 生徒:お昼休みの楽しみが増える
- 学校:地域の事業者の活動支援と生徒の喜びにつながる

昼休みの前の時間の授業が体育の場合、着替えなどの関係で授業が少し早く終わることがあるのですが、そんなとき着替えずに昼食販売の場所の前で列を作っていることもあります。
待ち遠しい気持ちが表れていて、見ていて嬉しい気分になります。
事業者側も「もっと生徒が喜んでくれるためには」という視点でアイデアを考えてくださり、それがさらに生徒たちを喜ばせてくれます。
正直、「物価高のこのご時世にこの値段でいいんですか」と思うケースもありますが、事業者としては少しでも収入源が増えた方がいいと考えておられるようです。
こちらとしてはありがたい限りです。
その地域全体が活性化するほどの効果は期待できませんが、地域貢献活動の小さな一歩としておすすめできる取り組みだと考えています。
【学びにもなり一石二鳥】授業で取り組む地域の魅力発信
前述の2つのケースが課外活動であるのに対し、授業の一環として地域貢献活動を行う場合もあります。
私の勤め先では、社会科や探求の授業で行われている様子です。
どんなに小さく、都市部から離れているような地域でも、何か一つは歴史的に重要なものや他の地域と比べて特徴的なものがあります。
そうしたものを見つけて、生徒と一緒に訪れたりするなどし、そこでの体験をアウトプットしてもらうわけです。
その際重要なのが、その地域の自治体関係者などを巻き込むこと。
市議会議員や役所の観光課の方、それ以外で地域の魅力や特色を発信しているような団体の方々は、こうした地域の魅力発信に関する取り組みの話をすると、喜んで協力してくださるというのが私の印象です。
そのような方々と一緒に取り組むと、生徒が発表する様子や生徒の制作物などを広報誌やSNSに取り上げてくださいます。
地域のPRにもなりますが、生徒たちも自分が作ったものが注目されることでやりがいを感じている様子です。
「学びはインプットよりアウトプット重視」と考えている私にとっては大変意義のある活動だと思っています。

前の勤め先での話ですが、自治体等も地域の魅力を伝えるために様々なツールなどを作成しているようなのですが、それをPRするところまで人や時間を費やす余裕がないという旨の話をされていました。
生徒たちがその役目を果たすという貢献方法も検討の余地があるのではないでしょうか。
まとめ
「地域の皆さまから愛される学校」というのは、田舎の小規模な学校にとって目指すべきかたちの一つではないかと思います。
その理想像に近づくために、小さなイベントでも学校として積極的に参加してみることをおすすめします。
「そんなイベントはない」と思っていても、よく調べれば身近にあるものです。
また前述のとおり、自治体など地域の魅力を発信したいと考えている人もいますので、そうした人たちとも連携してみるという方法もあります。
- 他人とのやりとりによるコミュニケーション能力の向上
- 自分たちが調べたことをまとめて、伝えるアウトプット力の育成
以上は一例ですが、地域貢献活動を通じて、こうした生徒たちの成長も期待できますので積極的に取り組んでみましょう。
もちろん事務員も、こうした企画を「計画」「実行」「継続」することにより、スキルアップを図ることができます。
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。