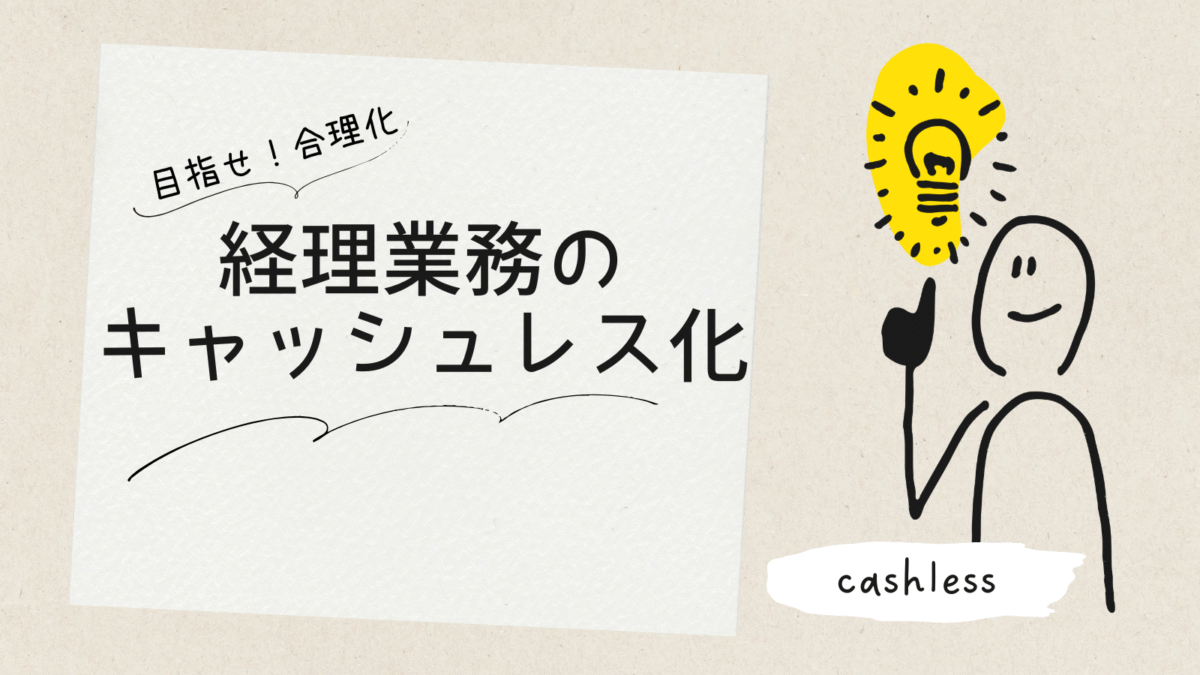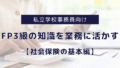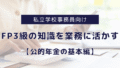この記事は以下のような人を対象としています。
・経理業務で現金を扱っていることにリスクや面倒さを感じている人
経理業務の一つに「現金管理」があります。
- 切手やレターパックの購入といった少額の支出
- 生徒のために講演に来られた講師の方への謝礼の支払い
こうしたケースで手提げ金庫から現金を出す。
学校によっては、教職員の立て替えたお金や出張旅費の精算にも、現金支払いで対応している場合があります。
そして、その日の終わりには現金の残高と帳簿が一致することを確認する。
これが「現金管理」業務の概要です。
一見すると「それのどこが問題なのか」と思ってしまうかもしれませんが、この業務にはリスクや無駄なコストが隠されています。
世の中のキャッシュレス化が進む中、学校の経理業務もこの流れに乗っていくべきだと私は考えております。
そこで今回は、「現金管理」のリスクやコストなどを理解したうえで、どのようにキャッシュレス化を図っていくかについて、私がこれまで取り組んできた実例なども含めながら紹介していきたいと思います。
具体的には以下のような構成です。
- 現金管理のリスクとコストについて
- キャッシュレス化の実例紹介
皆さまの業務の参考になれば幸いです。
【「少額」のワナ】現金管理のリスクとコストについて
学校の規模によると思いますが、多くの学校では手提げ金庫の中に10万円程度のお金を準備していると思います。
そして上述のようなケースで現金を出金する。
その後、残高が減ってきたら担当者が金融機関へ出向き補充、もしくは法人本部と定期的にやり取りをして補充してもらうといった流れになっているのではないでしょうか。
こうした現金管理業務には、以下のようなリスクやコストがあります。
- 現金盗難・紛失のリスク
- 担当者による横領のリスク
- 日々の出し入れや残高管理で発生する精神的・時間的コスト
1つずつ見ていきましょう。
現金盗難・紛失のリスク
これが一番発生する可能性が高いリスクだと思います。
特に高校事務室では、現金の取り扱いをしている間にも別の業務が遠慮なく降りかかってきます。
そうした際についうっかり金庫を開けっ放し、といったことが起こり、それが盗難のきっかけを与えることになるわけです。
また前述のように、自ら金融機関に出向き現金を引き出して補充する場合もあります。
そうなると、金融機関から学校までに道のりでひったくりに遭う可能性もゼロではありません。
「盗まれてもたかだか数万円」と思うかもしれませんが、ひったくられた際に大けがを負うというリスクもあるわけです。

以前は、取引先の金融機関の方にお願いして現金を持ってきてもらうという方法もありましたが、金融機関も業務の合理化を進めており、こうした対応をしなくなっている傾向があると感じています。
そして紛失のリスク。
バタバタしていて、お金をどこかに置いたままにしてしまうということがあります。
実際に私の今の勤め先では、ファイルの中から現金が出てきたことがありました。
おそらくすでに退職した担当者が、何かの拍子に挟んでしまったのだと思われますが、発見した方はたまったものではありません。
これが1つ目の問題点です。
担当者による横領のリスク
現金のやり取りは基本的に、現金管理担当者と相手方との間でしかその事実を確認することができません。
金融機関を通してお金のやり取りをすれば、金融機関という第三者が発行する伝票などで事実を確認することができますが、現金の場合それができないというわけです。
つまり客観的証拠が残らないということ。
これが「横領」というリスクにつながると考えられます。
実際、横領は起こりませんでしたが、私の以前の勤め先では大変危険なことを行っていました。
貸与型奨学金の返済を現金書留で受け付けていたのです。
現金書留で送られてきたお金は直接、奨学金担当者の手に渡ります。
そうなると、担当者がそのお金を自分のものにし、記録上は「返済済み」と処理してしまえば誰も事実を知ることができません。
監査法人も学納金や補助金などは入念に見ますが、貸付金の返済記録についてはそれほど厳しいチェックをしないのが現実です。

変な疑いをかけられるのも嫌だったので、この返済方法を廃止しました。
自分のことをいいように言うつもりはありませんが、色々な人がいるわけですので、誰が担当してもそうしたきっかけを与えない仕組みを作ることが大切だと思います。
これが2つ目の問題点です。
日々の出し入れや残高管理で発生する精神的・時間的コスト
いうまでもなく金額にかかわらず「お金」は大切な資産です。
そのため、管理にはひと際神経を使う必要があります。
出し入れのときには、金額に間違いがないかを入念に確認し、場合によっては別の事務員とダブルチェックを行う。
残高確認も、担当者がチェックしたものを上席者が確認するといったやり方をとっているところが多いのではないでしょうか。
このように何人もの事務員の時間を奪っているのが、現金管理という業務の現状です。
10万円そこそこのお金を管理するために、それほどの労力は必要なのかと思ってしまいます。
時間的にも精神的にも無駄なコストをかけている。
これが3つ目の問題点になります。
【合理化への道】キャッシュレス化の実例紹介
現金管理にまつわる3つの問題点を挙げましたが、実際に現金の取り扱いを減らすために私自身がどんな取り組みをしてきたかを紹介したいと思います。
代表例としては以下の2つになります。
- 教職員の立替・旅費精算の振込化
- 取引先等への支払いの振込化
教職員の立替・旅費精算の振込化
私が今の勤め先に入職した当時は、教職員が立て替えて支払った経費や出張時の旅費交通費の精算を現金で行っていました。
これらをすべて、教職員の給与口座への振込に変更したのです。
この際にネックとなったのが振込手数料。
これが発生するために、現金精算を続けていたという実情がありました。
そこで、学校がメインで取引をしている金融機関の担当者に振込手数料が無料になるよう交渉を開始。
当然最初は難色を示されました。
しかし、ネットバンキングの導入による相手側の業務負担の軽減などを提案し、お互いメリットが生まれるように交渉を継続。
最終的には、その金融機関の本支店間の振込に関しては手数料を無料にすることに成功しました。

無料化までの期間は2~3か月だったと記憶しています。
もともと教職員は入職の際に、その金融機関に給与口座を開設していたので、これにより教職員への振込は手数料無料という状況を作ることができたわけです。
「手数料を無料にする、なんて無理に決まっている」と最初から思い込んでいる人もいるかもしれませんが、相手へのメリットも提示しながら話を進めると、私の事例のようにうまくいく場合もあります。
今は、現金を準備するための両替でも手数料をとられる時代です。
まだ現金支給をしている場合は、いち早く止めることをおすすめします。
取引先等への支払いの振込化
次に取り組んだのが、取引先等への支払いを振込にすること。
都会から離れたところに位置する学校なので、取引先も地元の個人商店的なところが多く、昔から現金精算が続いている様子でした。
とりあえずまずは話をしてみようと思い、お花屋さんからお弁当屋さん、本屋さんなど手当たり次第に声をかけてみたところ、あっさりと「いいですよ」と受け入れてくれました。

結局、「今までそうしてきた」という理由で現状を変えようとしなかっただけなんですね。
また、そうした取引先は学校の近くに位置していることもあり、取引している金融機関も学校と同じであることも判明しました。
そうなると、前述の振込手数料無料化の効果がここでも発揮されます。
結果、コストもかからず支払いを振込化することに成功しました。
さらに、取引先だけでなく生徒対象の講演会を開催した際に支払う講師の方へ渡す謝礼金も振込にしました。
これも「謝礼を振込にさせてほしい」とお願いしてみたところ、皆さん快く承諾。
なんの苦も無く現金のやり取りを減らすことができました。

直接相手の顔を見て、お礼の言葉を述べながらお渡しするのが礼儀という考え方が染みついてしまっているから止められなかっただけなんだろうと思いました。
ちなみに郵便料金も「後納郵便」にすることで、切手を購入する際の現金のやり取りをなくせます。
取引先等のご協力があってこそですが、現金支払いを減らす方法は何かしらあるというのが実感ですので、思い切って見直してみてはいかがでしょうか。
まとめ
昔からの習慣で、現金を置いているというところが多いと思います。
しかしその現金、本当に必要なのでしょうか。
紹介したリスクやコストに見合うだけの意義があるように私は感じませんでした。
そのため、上述のようなキャッシュレス化への取り組みを進めたわけです。
紹介した方法は、何か最新の技術やシステムなどを使ったものではなく、泥臭い直接交渉という方法ばかりでしたので、「期待していた内容と違う」と思った方もおられると思います。
ご期待には沿えませんでしたが、特別な知識も必要なく誰でもできる方法だと考えていますので、紹介した次第です。
もちろん、相手方の事情も考慮せずに一方的に現金によるやり取りをなくそうと言っているわけではありません。
お互いが納得できる条件を探りながら、まずは一歩踏み出してみることが重要だと思いますので、身近なところから声をかけてみましょう。
それが経理業務の合理化につながるかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。