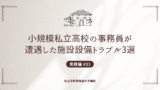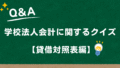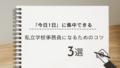この記事は以下のような人を対象としています。
・学校に防犯カメラを設置することの意義や効果を知りたいと思っている人。
この記事を執筆している時点では、連日のように学校内での教員による盗撮などの事件が報道されています。
それを受けて、「こども性暴力防止法」の運用ルールに関する国の検討会も開かれ、

学校を含めた教育施設などで子どもへの性暴力を防ぐために、防犯カメラの設置が有効である。
という見解が示されたといったニュースも耳にしました。
防犯カメラはこうした性暴力に関する事案以外にも、窃盗や不法侵入といった犯罪行為に対する抑止力も効果が期待できると思います。
そこで今回は、私の今の勤め先や以前の勤め先での防犯カメラに関するエピソードを交えながら、防犯カメラの有効性などについて触れていきたいと思います。
具体的な内容は以下のとおりです。
- こども性暴力防止法とは
- 防犯カメラの導入費用
- 防犯カメラの有無についてのエピソード
- 防犯カメラの設置と学校の責任
- 防犯カメラに関するエピソード
これから学校に防犯カメラを設置することを検討している人はもちろんのこと、すでに導入済みの方についても、参考になれば幸いです。
【予備知識】こども性暴力防止法とは
そもそも、冒頭に出てきました「こども性暴力防止法」を皆さまご存じでしょうか。
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といい、令和6年6月19日に成立しました。
この法律の所管は、文部科学省ではなくこども家庭庁です。
法律の概要については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、確認しておきましょう。
こども性暴力防止法について
(こども家庭庁ホームページへのリンク)
私立学校事務員としては、
「学校法人は雇っている教職員による児童等への性暴力が起こらないように適切に対応しなさい」
ということが法的に義務づけられると理解しておけばよいと思われます。

資料を見たところ大学や短期大学は含まれていないようです。
まあ、年齢的に「こども」ではないですからね。
この記事は性暴力防止がメインではありませんので、これ以上この法律については触れませんが、私立学校事務員として頭の片隅に入れておきましょう。
この法律に関する検討会で、防犯カメラ設置の有用性が述べられたわけです。
【結構なお値段】防犯カメラの導入費用
もう一つ参考までに、防犯カメラを設置するのにどの程度の費用がかかるかを紹介します。
今から6~7年前に20数台設置した際には、100万円を少し超える費用が発生しました。
1台あたり約4万5,000円といったところです。
その後、何台か入替をしましたが、その際には1台あたり約6万円かかっています。
この整備に対する補助金は当時見当たらなかったため、全額学校負担です。

うちみたいな小さな高校にはなかなか大きな出費でしたね。
なお、設置から約5年後に保守点検をしてもらったところ、みごとに数台が故障していました。
あまり長持ちは期待できないかもしれません。
点検費用は20数台で6万円程度といったところです。
あくまで私の今の勤め先での例ですが、おおまかな費用のイメージとして見ていただければと思います。
ちなみに教室内には1台も設置していません。
あわせてご参考までに。
【効果あり?】防犯カメラの有無についてのエピソード
では、実際に防犯カメラ設置の効果はあったのでしょうか。
ここでは「窃盗」についての事例を紹介したいと思います。
まず、私の以前の勤め先での出来事です。
ある日、校内の清掃アルバイトの人から、

女子トイレのゴミ箱にこんなものが捨てられていた。
との報告がありました。
見るとそれは2つの財布。
その場で中を確認しますが、お金は全く入っていませんでした。
陰鬱な気分でその財布を生徒指導部長の教員のところへ持っていきました。

生徒指導の教員あるあるだと思いますが、とにかく怖い人なんです。
常にピリピリしたオーラをまとっていて、声をかけるのも躊躇してしまうぐらいです。
すでに生徒から被害報告があったようで、教員からは「これだ」という反応が返ってきました。
そこから生徒指導部が中心となり犯人探しが開始。
しかし当時、学校には防犯カメラが設置されていなかったこともあり、犯人確保には至らなかったようでした。
一方、今の勤め先ではこんなことがありました。
前の勤め先と同じように財布の窃盗事件が発生したのです。
この時は防犯カメラが設置されていたので、すぐさま対象の教室付近を映すカメラの記録を確認しました。
すると、犯人と思わしき人物が映っていたのです。
この映像がもととなり、犯人確保に至ることができました。
サンプル数が少ないので、これだけで直ちに「防犯カメラは犯罪対策の効果がある」と言うのは早計かもしれませんが、参考にしていただければと思います。
また、今回紹介した事例は窃盗事件が発生した「後」の話であるため、「防止」という観点からの効果は検証できていませんので、その点についてもご承知おきください。

なお、以前の勤め先ではこの後にも校内でのトラブルが発生したため、防犯カメラを設置することになりました。
【損害賠償?】防犯カメラの設置と学校の責任
学校はどこまで防犯対策をする必要があるのでしょうか。
それについて少し触れている書籍がありましたので、少し長いですがその内容を引用します。
学校は、安全で適切な教育環境を提供すべく、必要な防犯対策を講じることが求められており、敷地境界、敷地内、建物内等における建築計画的な対応と、防犯監視システムや通報システム等の建築設備的な対応を、共に充実させることが必要とされています。学校がこれらの防犯対策を行わなかったために、外部侵入者の窃盗などによる被害が発生した場合、学校が、損害賠償に応じなければならない事態に陥る可能性もあります。 P59
「改訂新版 問題を解決する学校法務」より引用

「建築計画的な対応」は正門が職員室から見えるなど、「建築設備的な対応」はそのまま防犯カメラの設置などを指しているのかなと私は理解しています。
また、20年以上前の内容にはなりますが、文部科学省のホームページにも防犯対策に係る基本的な考え方が掲載されていますので、一読することをおすすめします。
防犯対策に係る基本的な考え方
(文部科学省ホームページへのリンク)
こうしてみると、防犯カメラの設置等について義務とまではいかないまでも、積極的な導入が求められているように感じます。
これらの内容を踏まえたうえで、校内の設備整備計画を検討することも私立学校事務員の仕事の1つだと思いますので、理解しておきましょう。
【不審者編?】防犯カメラに関するエピソード
最後にもう一つ、私のエピソードを紹介したいと思います。
以前の記事で、学校に不審者が侵入したエピソードを紹介しました。
今回紹介するエピソードもある意味で「不審者」に関するものです。
以前の勤め先で、担任の教員に執拗に面談を迫る保護者がいました。

様子を聞く限り、その保護者は担任にかなりの好意を寄せている印象でした。
相手をすると時間と労力がかなり消費されてしまうので、極力学年主任などが対応していましたが、生徒自身、不登校気味だったため、担任としては生徒と直接話がしたいという思いがありました。
そこで、保護者は管理職と学年主任が、生徒は担任が、というかたちで話をする機会を設けたのです。
管理職と学年主任は、とにかく保護者に面談の強要を止めるように説得する準備をしていました。
しかし約束の時間になった時、現れたのは保護者の一方のみでした。
生徒は、保護者と別行動になるように仕組んでいたので問題ないのですが、肝心な保護者の一人が見当たりません。
そこで守衛の方に確認をとると、二人で来校されたとの返事が。
ということは、学校の中にいるということです。
すぐさま、防犯カメラの記録を確認。
玄関からの映像を追いかけていきます。
すると、保護者の一方が待ち合わせ場所とは別の方向へ走っていく姿が映っていたのです。
その行き先には、生徒と担任との待ち合わせ場所があります。
ただ、その場所にたどり着くには鍵がかかった扉を開ける必要があるため、こちらとしては特に焦ることなく対応することができました。

案の定、保護者は扉に侵入を阻まれ、扉の前で座り込んでいました。
しかし、そこからが長い。
とにかく担任に会わせろの一点張りで、そこから動こうとしません。
警察にも連絡しましたが、解決には至らず時間だけが過ぎていきます。
そうして、ついに日付をまたいだあたりで、ようやく保護者の方が諦めてくれました。
結局、保護者との話し合いは行われないままで、何の進展もなくただただ疲れたという散々な一日となったわけです。
あの時の防犯カメラに映っていた保護者の姿は、私の私立学校事務員としての思い出として心に残っています。
まとめ
前述のとおり、学校は生徒等にとって安心安全な場所であるべきで、そのために学校は必要な対策を講じる必要があります。
その対策として防犯カメラを活用することは、一つの手段として意味があるというのが実感です。
ただ過剰な対応は、逆に生徒たちへ心理的にマイナスの効果を与えてしまうかもしれません。
いろいろな事例などを調べたうえで、自分の勤める学校に適した対応策を導入できるように日頃から情報を集めておきましょう。
この記事がそのための一助になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
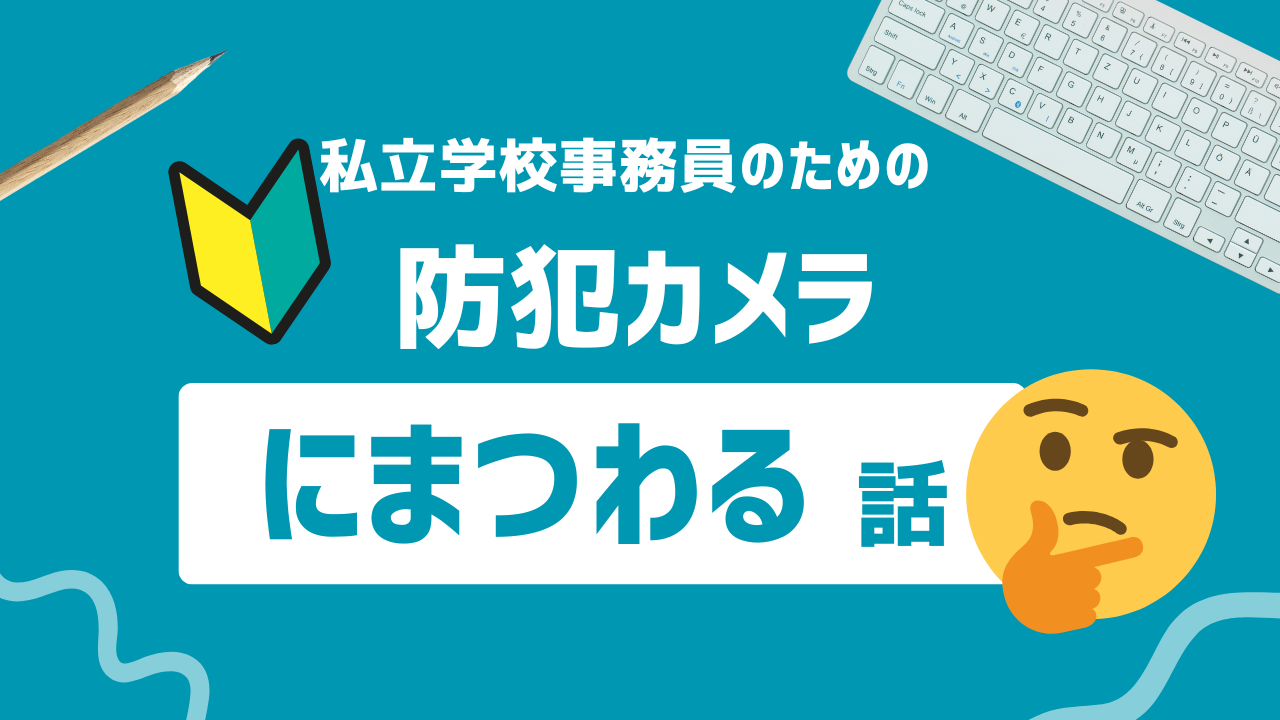
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=21136547&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8999%2F9784788718999.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)