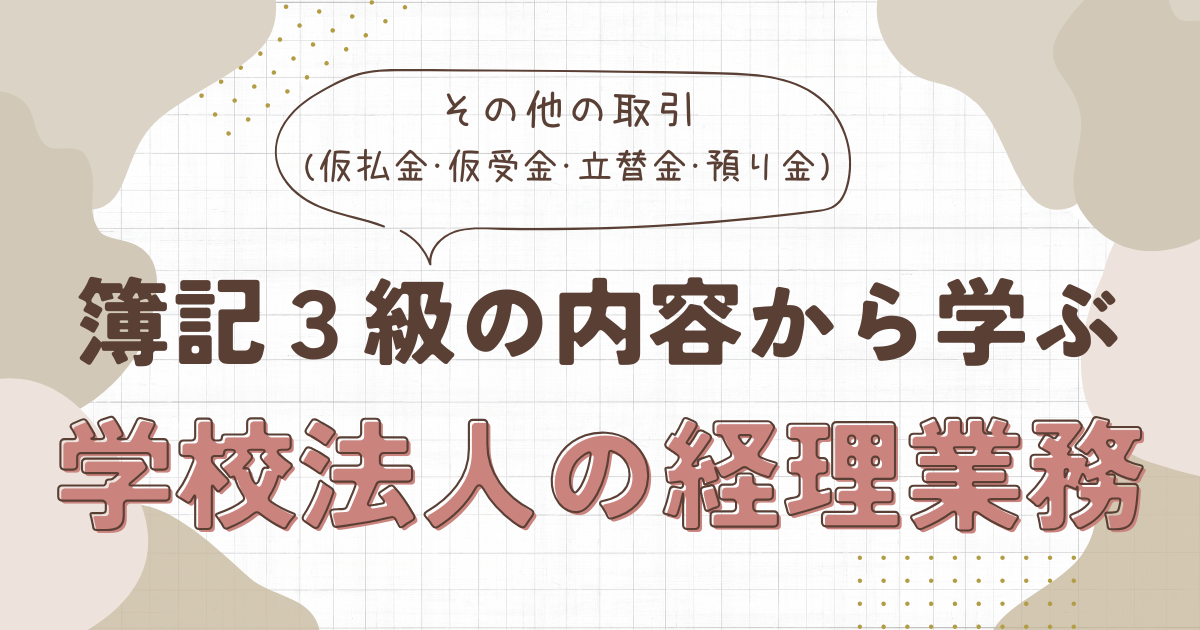この記事の目的は、以下のとおりです。
・預り金と仮受金の違いを理解する
・立替金と仮払金の違いを理解する
・経過的な勘定の仕訳ができるようになる
今回は、前回、前々回に引き続き簿記3級の範囲のうち「その他の取引」について、学校法人での業務に関するものに絞って解説します。
以前の記事はこちらからご覧ください。
| 〇 | 簿記の基礎 | 〇 | その他の取引 |
| × | 商品売買 | 〇 | 帳簿 |
| 〇 | 現金預金 | 〇 | 試算表 |
| × | 手形と電子記録債権(債務) | 〇 | 伝票と仕訳日計表 |
| 〇 | 有形固定資産 | 〇 | 決算手続 |
早速、解説させていただきます。
参考書籍
書籍名:みんなが欲しかった!簿記の教科書 日商3級 商業簿記 第12版
著者名:滝澤ななみ
発行所:TAC出版
発売日:2024年2月26日
【再確認:全体図】簿記3級における「その他の取引」の範囲
今回解説する範囲を確認するために、参考書籍で「その他の取引」として取り扱われている項目を整理した表を再度掲載します。
| 以前の記事で解説した項目 |
|---|
| 未収入金 |
| 未払金 |
| 前払金 |
| 前受金 |
| 貸付金 |
| 借入金 |
| 今回の記事で解説する項目 |
|---|
| 仮払金 |
| 仮受金 |
| 立替金 |
| 預り金 |
| 解説から省く項目 |
|---|
| 手形貸付金 |
| 手形借入金 |
| 受取商品券 |
| 差入保証金 |
| 消費税 |
| 株式の発行 |
この記事では、中央のブロックに記載の勘定科目について解説します。
なお、今回紹介する勘定科目も以前と同様に「資金収支計算書」に登場する科目です。「事業活動収支計算書」には登場しません。
仮払金
まずは、仮払金について解説します。
定義
参考書籍では以下のように説明しています。
従業員が出張に行く場合、あらかじめ出張にかかる金額を概算額で渡しておくことがあります。この場合、現金の支出があっても、支払内容や金額はまだ確定しないので、一時的に仮払金[資産]で処理しておきます。
参考書籍より引用

私の以前の勤め先では、学校から離れたところで入学試験を実施する際、その試験会場の担当者にあらかじめ一定額を渡しておくということをしていました。
この仮払金は「仮」に渡しているお金のため、必要があれば「返金」を求めることができます。そのため、「お金を返してもらえる権利」として「資産」グループに属します。
仕訳
(例)出張へ行く職員の仮払金10,000円を現金で渡した。
(分解)
「仮払金10,000円」と「現金10,000円」に分解することができます。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 仮払金 | 資産 | 増加 | 左 |
| 現金 | 資産 | 減少 | 右 |
(仕訳)
仮払金としてお金を出したときは「仮払金支払支出」という勘定科目を使います。
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仮払金支払支出 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
そして出張後、仮払金が精算された際の仕訳は以下のようになります。タクシー代として3,000円使用し、残金7,000円が現金で戻ったとします。
精算時には「仮払金回収収入」という勘定科目を使用します。タクシー代は「旅費交通費」という「支出」グループの勘定科目になります。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 仮払金回収 | 資産 | 減少 | 右 |
| タクシー代 | 支出 | 増加 | 左 |
| 現金 | 資産 | 増加 | 左 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 旅費交通費 | 3,000 | 仮払金回収収入 | 10,000 |
| 現金 | 7,000 |
このようにある勘定科目から別の勘定科目に金額を移すことを「振替」といいます。
仮受金
次は、仮受金について解説します。
定義
参考書籍では以下のように説明しています。
当座預金等に入金があったものの、その内容が不明な場合があります。内容不明の入金があったときには、とりあえず入金の処理をするとともに、一時的に仮受金[負債]で処理しておきます。
参考書籍より引用

これも私の以前の勤め先での経験ですが、生徒の祖父から学校の学費口座へ入金がありました。
生徒の親から頼まれて、代わりに学費を入金したとのことでしたが、こちらとしては全く名前が把握できていない人物からの入金だったため、ひとまず仮受金で処理ました。
そのあとの確認作業が大変難航することに・・・。
この仮受金は「仮」に受け取ったお金のため、「返金」を求められた場合は返金しなればなりません。そのため、「お金を返さなければならない義務」として「負債」グループに属します。
仕訳
(例)学校の学費用普通預金口座に100,000円の入金があったが、入金者が不明のため仮受金で処理をした。
(分解)
「仮受金100,000円」と「学費口座100,000円」に分解することができます。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 仮受金 | 負債 | 増加 | 右 |
| 学費口座 | 資産 | 増加 | 左 |
(仕訳)
仮受金としてお金を受け入れたときは「仮受金受入収入」という勘定科目を使います。
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 学費口座 | 100,000 | 仮受金受入収入 | 100,000 |
そして入金者等が判明した段階で「振替」をします。今回は、生徒の保護者からの授業料であることが判明したとします。
精算時には「仮受金支払支出」という勘定科目を使用します。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 仮受金支払 | 負債 | 減少 | 左 |
| 授業料 | 収入 | 増加 | 右 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 仮受金支払支出 | 100,000 | 授業料収入 | 100,000 |
立替金
続いて、立替金について解説します。
定義
参考書籍では以下のように説明しています。
取引先が負担すべき金額を代わりに支払ったり、従業員が支払うべき金額を代わり立て替えた場合、その立て替えた金額はあとで取引先や従業員から受け取ることができます。この場合の、あとで取引先や従業員から現金などを受け取る権利は立替金[資産]で処理します。
参考書籍より引用
立替金が発生するケースとしては、休職時の社会保険料が挙げられます。
社会保険料の自己負担分は通常、給料から直接差し引かれます。そしてこの社会保険料は、病気等で休職しているときも納める必要があります。
ところが、休職中は給料が支給されないため差し引くことができません。
そこで、学校がその人の社会保険料を一時的に立て替えて納めて、復職した際や傷病手当金から回収するという手段をとります。
この一時的に立て替える際に「立替金」を使用します。
この立替金は前述のとおり「あとで現金などを受け取る権利」として「資産」グループに属します。
仕訳
(例)職員が休職したため、当該職員の自己負担分の社会保険料50,000円を普通預金口座から立て替えて納めた。
(分解)
まずは「立替金50,000円」と「普通預金50,000円」に分解することができます。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 立替金 | 資産 | 増加 | 左 |
| 普通預金 | 資産 | 減少 | 右 |
(仕訳)
立替金としてお金を支出したときは「立替金支払収入」という勘定科目を使います。
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 立替金支払支出 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
そして、回収時には「立替金回収収入」という勘定科目を使用します。今回は仮に現金で回収したとします。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 立替金回収 | 資産 | 減少 | 右 |
| 現金 | 資産 | 増加 | 左 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 現金 | 50,000 | 立替金回収収入 | 50,000 |
立替金と仮払金の違い
立替金と仮払金の違いは、以下のように整理すれば問題ないです。
- 立替金:お金の使用内容が明らかなもの → 「社会保険料」という内容が明確
- 仮払金:お金の使用内容が不明のもの → 精算しなければわからない
預り金
最後は、預り金です。
定義
参考書籍では以下のように説明しています。
企業が従業員に給料を支払うさい、給料総額から源泉所得税と社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)を天引きした残額を支給します。
参考書籍より引用
天引きした金額は、従業員に代わって、あとで企業が税務署や年金事務所に支払わなければなりません。
この場合の、給料総額から天引きした源泉所得税や社会保険料は、あとで税務署などに支払わなければならない義務として預り金[負債]で処理します。
上述のようなケースの他に、学校特有の預り金としてPTA会費や修学旅行の積立金、就学支援金があります。
生徒の保護者から、学費と一緒にPTA会費を納めていただくかたちが一般的かと思います。
納めていただいたPTA会費は、学校からPTAにそのまま渡すことになりますので、一時的に学校がPTAに代わって「預かる」処理を行う必要があります。
この一時的に預かる際に「預り金」を使用します。
この預り金は前述のとおり「あとで支払わなければならない義務」として「負債」グループに属します。
仕訳
(例)授業料100,000円と一緒にPTA会費10,000円が学費用普通預金口座に入金された。
(分解)
まずは「授業料100,000円」と「PTA会費10,000円」、「普通預金110,000円」に分解することができます。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 授業料 | 収入 | 増加 | 右 |
| PTA会費 | 負債 | 増加 | 右 |
| 普通預金 | 資産 | 増加 | 左 |
(仕訳)
預り金としてお金を受け入れたときは「預り金受入収入」という勘定科目を使います。このケースではPTA会費をこの勘定科目で受け入れます。
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 普通預金 | 110,000 | 授業料 | 100,000 |
| 預り金受入収入 | 10,000 |
そして、PTAに会費を渡すときは「預り金支払支出」という勘定科目を使用します。今回は仮に現金で渡したとします。
(グループ分け、増減確認、左右判断)
| 項目 | グループ | 増減 | 配置 |
| 預り金支払 | 負債 | 減少 | 左 |
| 現金 | 資産 | 減少 | 右 |
(仕訳)
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 預り金支払支出 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
預り金と仮受金の違い
預り金と仮受金の違いは、以下のように整理すれば問題ないです。
- 預り金:お金の入金内容が明らかなもの → 「PTA会費」という内容が明確
- 仮受金:お金の入金内容が不明のもの → 内容を確認しなければならない
経過的な勘定とは
この記事で解説しました4つの勘定科目は「経過的な勘定」に係る収支になります。
学校法人会計基準では以下のように規定しています。
学校法人会計基準第五条
計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。
e-gov 法令検索より引用
4つの勘定科目の共通点は「一時的」です。
一時的に入金あるいは出金処理をするための勘定科目ということであり、これらをまとめて「経過的な勘定」と呼ぶことがあります。
そして上述の条文は、この経過的な勘定を「純額」で処理してもよいという内容です。
「純額」を預り金のケースで見てみましょう。
- PTA会費(預り金)を10,000円受け入れた。
- 受け入れた10,000円のうち、8,000円は年度内にPTAに渡したが、2,000円は翌年度に渡すことになった
このケースで決算書に「預り金受入収入10,000円」「預り金支払支出8,000円」と収入・支出それぞれに記載することを「総額表示」と言います。
一方、「預り金受入収入2,000円」と収入と支出の差額を多い方の勘定科目の方に記載することを「純額表示」と言います。

勤め先の学校がどちらの処理を採用しているか、よく確認して処理をしましょう。
まとめ
・立替金と預り金は、お金の「内容」がわかっている場合に使用。
・仮払金と仮受金は、お金の「内容」がわからないときに使用。
・一時的な処理で使う「経過的な勘定」は差し引きして「純額」で記載可能。
以上、また長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。