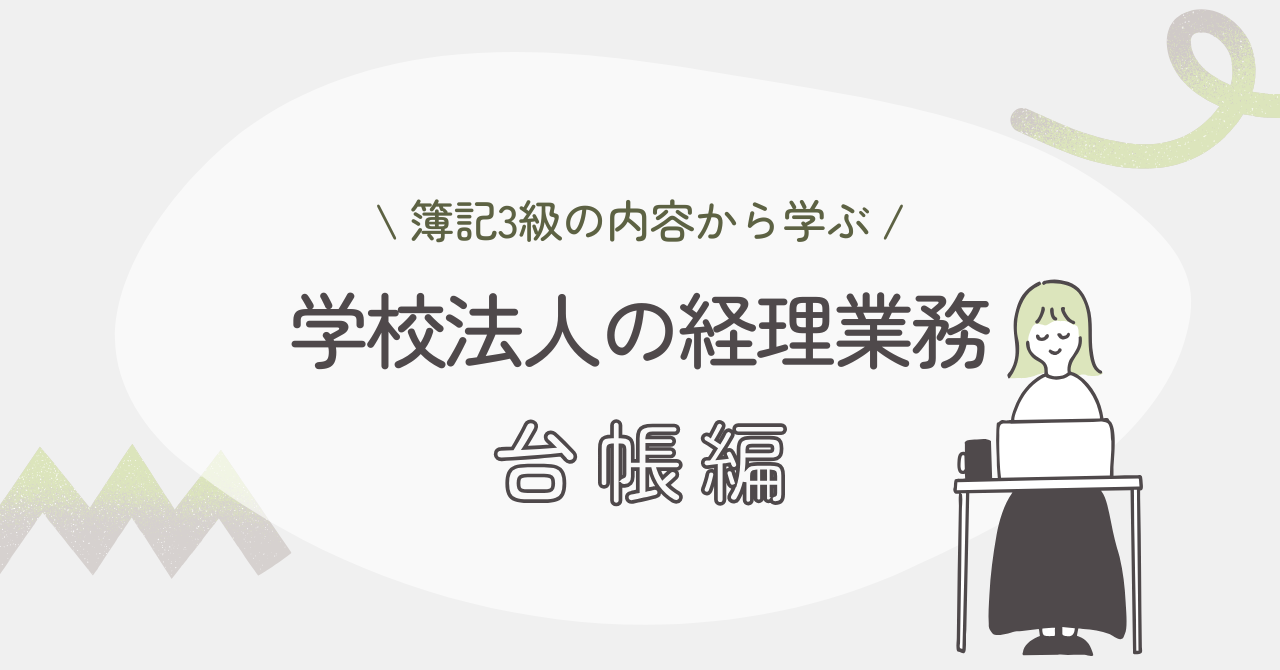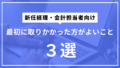この記事の目的は、以下のとおりです。
・学納金台帳について理解する
・固定資産台帳について理解する
・給与台帳について理解する
以前の記事で「会計帳簿」について解説しました。
その記事では、会計帳簿には「主要簿」と「補助簿」があり、「補助簿」は学校法人によって様々な種類があるという理由で説明を省略させていただきました。
しかしながら、決算に向けて会計帳簿を整備していたところ、以下の3つの「補助簿」については、どの学校法人も共通して作成していると思い、今回の記事にて紹介することとしました。
- 学納金台帳
- 固定資産台帳
- 給与台帳
「台帳」という言葉は聞きなれないかもしれませんが、この記事では「帳簿の別の言い方」くらいに捉えていただければ結構です。
これらの仕組みと役割を理解しておくことは、日々の業務の遂行や関係者への説明責任の履行のために役立つものと考えています。
この台帳には、日商簿記3級の内容にも関わるものがありますので、そのあたりを参考にしながら概要を解説していきます。 この記事を知識の習得にお役立ていただければと思います。
参考書籍
書籍名:みんなが欲しかった!簿記の教科書 日商3級 商業簿記 第12版
著者名:滝澤ななみ
発行所:TAC出版
発売日:2024年2月26日
【用語の確認】補助簿とは
参考書籍では以下のように解説しています。
補助簿は、特定の取引や勘定について明細を記録する帳簿で、必要に応じて作成されます。
参考書籍より引用

主要簿と違い、作成義務はありませんが、学校法人が主要簿よりもさらに詳細な情報を記録するために作成している帳簿という理解で問題ないと思います。
今回紹介する3つには共通点があります。
それは、「それぞれの所属するグループで最も金額が大きい科目の詳細を記録したもの」であることです。
- 学納金台帳:収入グループの「学生生徒等納付金」に関する台帳
- 固定資産台帳:資産グループの「固定資産」に関する台帳
- 給与台帳:支出グループの「人件費」に関する台帳
最も金額が大きいということは、それだけ学校法人の収支や財政状況に与える影響も大きいということになります。

それだけ重要度の高いものについては、より詳細な根拠資料を整備しなければならないと理解しておきましょう。
これらの整備が、学費を負担する生徒や保護者、補助金を交付する行政へ十分な説明責任を果たすことにつながるわけです。
それでは、それぞれについて解説していきます。
学納金台帳
学納金台帳は、生徒個人ごとに「いつ徴収するか」「いくら徴収するか」といったことを記録する帳簿になります。
名称は各学校で異なる場合がありますので、ご自身の勤め先の方でご確認ください。
あわせて様式例も確認しておきましょう。
| 氏名 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 未納分 |
|---|---|---|---|---|
| ○○ ○○ | ||||
| △△ △△ |
毎月徴収している場合は、月ごとの記載になるなど学校によって体裁は異なりますが、前述のとおり生徒個別に徴収状況が管理できるような仕組みになっています。
つまりポイントは「生徒個別の徴収状況を管理できる」というところです。 個別管理する目的は以下の2点です。
- 未納者の把握
- 関係者への適切な説明
目的①:未納者の把握
総勘定元帳では、入金された「金額」や「日にち」は確認できますが、「徴収状況」までは確認できません。

つまり「誰がいくら未納か」まではわからないということです。
民間企業で例えれば、自社の商品を販売した際の代金の入金状況を管理するためのものというイメージです。
当然、代金が回収できなければ会社は倒産してしまいます。
それと同じく、学納金を徴収できなければ学校も経営ができなくなってしまいます。
そういった意味でも、正確な徴収記録を管理することが重要であることがお分かりいただけると思います。
目的②:関係者への適切な説明
また、学納金を納める側の保護者等に対して、「正しい金額を徴収している」ということを証明する根拠資料としての役割もあります。
もし、保護者等から問い合わせがあった場合でも、学納金台帳を根拠にすることで説得力のある説明をすることができ、それが学校への信頼にもつながるわけです。
加えてこの台帳ですが、学校が受ける会計監査はもちろんのこと、行政からの調査でも提示を求められます。
その理由は2つ考えられます。
- 正確な収支状況を把握するため
- 補助金の交付金額の算定に用いている場合があるため
学生生徒等納付金はその学校の最も大きな収入であり、その金額の誤り等が与える収支状況への影響は大きいです。
そのため台帳をチェックし、数値の正確さを確認していると考えられます。
また、各学校に交付する補助金の金額を計算する際に、学納金の決算数値を計算根拠の1つとして用いているケースもあるようです。
当然、決算数値に誤り等があると補助金額にも影響が及ぶため、確認していると思われます。
このように、学納金担当の事務員にとってこの学納金台帳の整備は、学校法人会計基準が定める「真実性の原則」につながる重要な業務の1つに挙げられます。

なお、決算時にはこの学納金台帳と総勘定元帳の数字が一致することを確認します。
この確認作業を年度末にまとめて行うと、一致しない場合の原因探しに途方もない時間と労力を費やすことになりますので、高校であれば少なくとも学期ごとにあわせることをおすすめします。
固定資産台帳
固定資産台帳は、簿記3級にも登場する帳簿です。
参考資料では以下のように説明されています。
固定資産台帳は、所有する固定資産の状況を管理するために作成する補助簿です。
参考書籍より引用
こちらも様式例を確認しておきましょう。
| 固定資産番号 | 名称 | 取得年月日 | 取得金額 | 数量 | 設置場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ○○ | ||||
| 00002 | △△ |
「どんな固定資産」を「いつ」「いくら」「いくつ」取得し、「どこに」設置しているか。そして「現在いくらの価値があるか」といったことを記録したものになります。

スペースの都合で省略しましたが、台帳にはさらにその固定資産の現在の価値を算出するための情報も記録します。
固定資産台帳の作成目的は「教育の永続的な提供」になります。
もちろん正確な財政状況の把握という側面もありますが、私自身の学校事務員としての業務経験からすると、先に述べた作成目的の意味合いの方が強いように感じます。
総勘定元帳では「建物」や「機器備品」といった勘定科目ごとの増減は把握できますが、例えば「体育館」や「○○教室のパソコン」といった個別の資産の状況まで把握できません。
その資産状況の個別把握のために、固定資産台帳が作成されるわけです。
前述のとおり、学校の資産のうち最も大きな割合を占めるのが固定資産です。
これはつまり、教育活動を維持・提供するためには固定資産を整備することが重要ということを意味します。
継続的に整備するためには、個々の固定資産がどのくらい古くなっているかなどの情報を把握しておく必要があります。
そこで固定資産台帳を作成し活用することで、適切なタイミングで固定資産を更新することができ、さらにそのことが教育の永続的な提供につながるというわけです。
以上が固定資産台帳について理解しておくべき内容となります。
給与台帳
給与台帳は、その学校に勤めている教職員個人ごとに、給与の支払い状況等を記録する台帳です。
この台帳の作成目的は「関係者への適切な説明」になります。
そもそも、この給与台帳とは別に「賃金台帳」というものがあります。 似ていますが、両者の最も大きな違いは「賃金台帳は法律上作成・保管が義務付けられている」という点です。

詳しく知りたい方は労働基準法をご確認ください。
そして給与台帳の内容は、賃金台帳がほとんどカバーしているため、実務上は賃金台帳だけを作成するケースが多いです。
従いまして、様式例は賃金台帳の方を確認しておきましょう。
こちらは厚生労働省がテンプレートを公開していますので、それをご参照いただければと思います。
賃金台帳様式例(厚生労働省ホームページへのリンク)
様式例のように、従業員個人ごとに作成されるものになります。

以降で「賃金台帳」という言葉が出てきた際には、皆さんの頭の中で「給与台帳」に置き換えてお読みいただければと思います。
この賃金台帳の作成目的である「関係者への適切な説明」の「関係者」として特に意識しておくべきは以下の3者です。
- 生徒・保護者等学校関係者
- 補助金を交付する行政
- 税金や社会保険料の納付先である行政
①および②については、学納金台帳で述べた内容と同様であるため、そちらをご参照いただければと思います。
③が賃金台帳特有のものですが、給与の金額によって住民税や社会保険料の納付金額などが決まるためです。
金額に誤りがあると、未納など大きな問題に発展する可能性があるため、個別に資料を整備し、適切な管理をする必要があると理解しておきましょう。
まとめ
台帳も主要簿同様に、あらゆる関係者にとって大切な役割を担っています。
今は業務上、直接これらの台帳に携わらない方でも、いつ担当になるかはわかりません。
まずはこの記事の内容だけでも理解しておき、準備をしておくことが大切と思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。