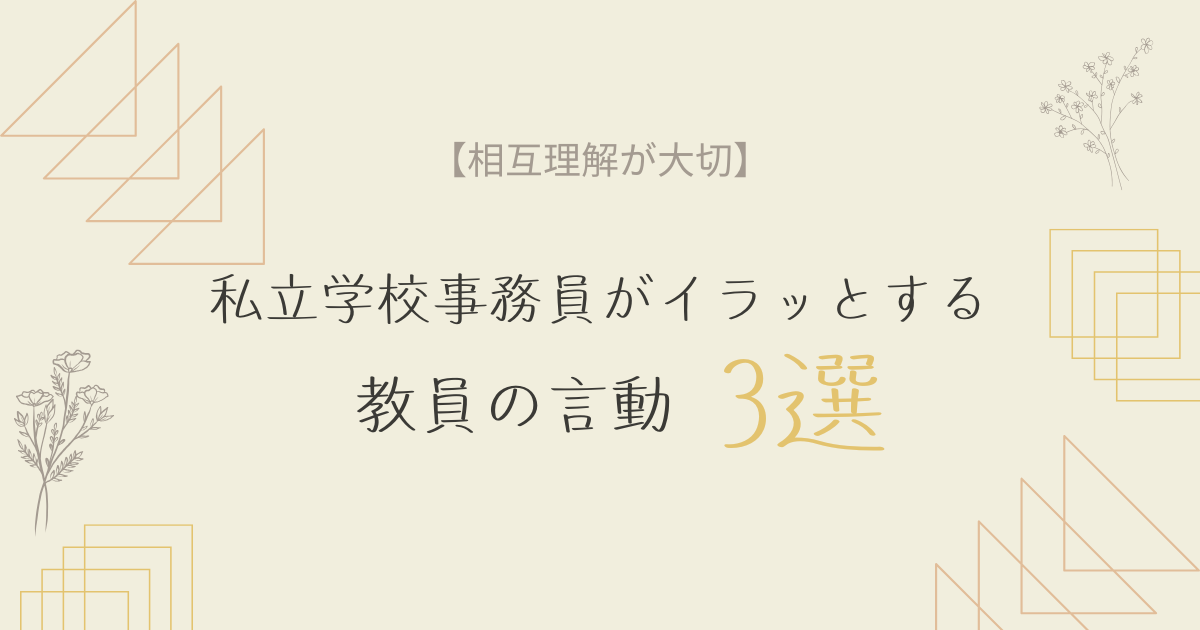この記事の内容は以下のとおりです。
・私立学校事務員として働く中で、つい「イラッと」してしまう教員の言動を3つ紹介
以前の記事で、教員との協働について解説しました。
教員と事務員が1つのチームとなることで、学校が直面する課題を解決することができ、それが生徒や保護者等の満足につながると思います。
しかし、どうしても考え方などに違いが生じてしまいます。
それは職種の違いなど様々な要因が関係していると考えられます。
そしてその違いが、時には相手の感情を逆立ててしまうこともあります。
そこでこの記事では、私が20年以上の学校事務員として働く中で、特にイラッとした教員の言動を3つピックアップして紹介します。
想定しているシーンは、主に高校です。
あらかじめ「こういう言動があるのか」ということが分かっていれば、心の準備ができ、ストレスが軽減されると考えています。
私立学校事務員として働くうえでの参考になれば幸いです。
【結論】私立学校事務員をイラッとさせる教員の言動3つ
先に結論として「3つの言動」を紹介させていただきます。
以上の3つです。
あくまで私の経験に基づく主観であることと、全ての教員に当てはまるわけではないということはご了承ください。
それでは、1つずつ紹介していきます。
【イラッとする言動①】「お金のことは事務」と言う
これを言われたことがある事務員の方は多いのではないでしょうか。
とにかく教員は「お金」を取り扱うことを嫌がる傾向があります。
現物としてのお金の取り扱いだけでなく、お金に関する保護者等とのやりとりも避けたがる人が多い印象です。

事務員でもこういう人はいるんですが、教員の方が圧倒的に多いように感じます。
確かに事務員の仕事は、学納金管理や取引先への支払いなど「学校に関わるお金」を扱うものが多いため、教員に比べてお金に対する「慣れ」があるのは事実だと思います。
しかし、この「学校に関わるお金」は事務員だけでなく教員も関係しているものです。
保護者等は「教員」や「事務員」ではなく「学校」に学納金を納めているわけです。
それを「お金のことはよくわからないので」という言葉で片づけてしまうのは、保護者等に対して失礼な態度だと私自身思っています。

このセリフを言う人は「わからない」のではなく「わかろうとする気持ちがない」という印象を受けます。
実際私が対応したケースをご紹介します。
ある教員が取引先から請求書を受け取りました。
その教員は、学校の手続きに則って処理をし、その請求書が私のもとに回ってきました。
具体的な話は省略しますが、請求書の内容が明らかにおかしいので、当然教員に確認をとります。
すると、その教員は「内容を見てない」と言うわけです。
「え、見てないんですか」と言うと、上述のように「お金のことはよくわからないので」と発言します。
この瞬間、イラッとしてしまいました。
もう、「お金」と聞いただけで拒否反応を起こしているわけです。
「内容を見ない」のは「わからない」ではなく「わかろうとする気がない」という気持ちの表れだと感じました。
しかし、この請求書への支払いは、保護者等が納めた学納金を原資に行われるわけです。
保護者等からすれば「自分たちの納めたお金が何に使われているか知ろうともしないのか」と考えてもおかしくない状況のように思います。

「お金のことはわからない」という言葉を直接保護者等に言わなければよいと考えているのかもしれませんが、口に出さなくても相手はなんとなく感じ取ります。
細かい財務比率などは理解しなくてもよいので、せめて学納金の金額や自分の担当する業務に関わるお金について「興味」は持つようにしていただきたいと思います。
それが「教員」ではなく「学校に勤める者」の責務だと私は考えています。
これが1つ目の言動です。
【イラッとする言動②】事務仕事になると思考停止する
①に似ていますが、事務仕事に苦手意識を持っている教員も少なくないと思います。
これについても、例えば「就学支援金の申請手続きを全て理解しろ」と言っているわけではありません。
教員と事務員それぞれ専門とする役割があり、そのお互いの得意分野を活かして、生徒や保護者に満足してもらえるように仕事に取り組めばよいわけです。
ところが、その得意分野を活かすということ以前の話があるわけです。
これも私が体験した話を紹介します。
ある教員が郵便物を出したいので、事務室に訪れました。
そして第一声が「郵便物出したいけどどうしたらいい?」でした。
一瞬「何を言っているんだろう」と思い、言葉に窮しましたが、なんとか気を持ち直して「どうしたらいいとは?」と聞き返すと「出し方がわからない」という返事が返ってきます。
とりあえず、「どれを出したいんですか」から始め、「相手に到着したということがわかる方がいいのか」や「到着は早い方がいいのか」など尋ねて対応しました。
しかし、話はこれで終わりません。
また後日、同じ教員が郵便物を出しに来ました。
そして前回と同じく「どうしたらいい?」と言います。
さすがにイラッとしました。

郵便は日常生活を送るうえでの基本知識の1つだと思っていたので、軽く衝撃を受けました。
この教員は①のお金の話と同様に「郵便のことがわからない」のではなく「郵便のことをわかろうという気持ちがない」のだろうと思います。
郵便だけに関わらず、自分の中で「事務仕事」と認識したものに対しては、それ以上関わろうとしないのでしょう。
このエピソードは極端な例かもしれませんが、同じように事務仕事に拒否反応を示す教員はいます。
ただ、私としては生徒に教える立場として郵便の出し方など、日常生活を送るうえで知っておくべきことは、自分である程度調べるなどして理解するよう努めなければならないと考えています。
学校の教員は「国語」や「数学」など教科だけを教えればいいものではないように思います。
もう少し生徒の見本となるように行動していただきたいと感じています。
これが2つ目の言動です。
【イラッとする言動③】職員室だけを守備範囲にする
おそらくほとんどの高校は、教員が滞在する職員室と、事務員が滞在する事務室とが分かれていると思います。

紙の資料だけでなく、データもお互い見られないように分かれているのではないでしょうか。
事務室には教職員の給与に関する資料なども保管しているので、あまり多くの人の目に触れないように分かれているなど、分けるメリットもあるわけですが、当然デメリットもあります。
その1つに、教員だけで情報共有が行われるということが挙げられます。
生徒の成績情報などは前述のとおり、誰でもアクセスできないように分けておくメリットはあるわけですが、配慮が必要な生徒の情報や授業の時間割、行事予定などは学校として共有が必要な情報です。
ところが、この情報を職員室だけ周知する場合があります。
事務室が知らないところで時間割変更が行われていたり、授業時間が通常の時間から短縮になっていたりします。

突然思いもよらない時間にチャイムが鳴るので確認すると、通常50分授業のところ、いつの間にか45分授業に変わっていたりします。
教員にそのことを問いただすと、「職員室の黒板に掲示していた。見てないんですか」と答えます。
その返答の様子にイラッとしてしまいます。
また、事務員は教員がデータを保存しているサーバーに入れないということを何度説明しても、「サーバーの〇〇フォルダに保存してますので、そこからコピーしてください」というような対応が返ってきます。
「そういえば事務室は別でしたね」くらいの存在としか認識されていない気がして、寂しい気持ちになってしまいます。
前述のとおり、事務室も「チーム学校」の一員であり、教職員が協働して学校運営に当たることが重要ですので、もう少し配慮をいただければと思う今日この頃です。
以上が3つ目の言動です。
まとめ
ネガティブな内容のように受け取られたかもしれませんが、私としては教員の悪口を言っているわけではありません。
大事なのは繰り返しになりますが「チームとしての学校」という意識を持つことです。
お互いチームメイトとして相手の「苦手なこと」や「言動のクセ」などを理解したうえで、「生徒や保護者の満足」の観点から、直すべきところは直すように指摘しあえるようになれたらよいと思っています。
この記事がその理解の一助になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。