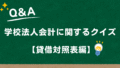この記事は以下のような人を対象としています。
・相手から本音を引き出して、相手の問題や疑問、現状の答えを導き出したいと思っている人
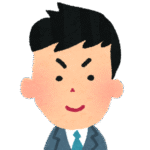
自分は人見知りだし、口下手だから人とのコミュニケーションがうまくいかないんだろうなぁ。
こんなお悩みを持っている私立学校事務員の方、おられるのではないでしょうか。
- 学費の支払いなどで相談に来られる保護者
- 進路に悩みを抱えている生徒
- 仕事上のやりとりが不可欠な同僚
そうした人たちとのコミュニケーションにおいて、相手の悩みや話したいことがうまく引き出せなかったというケースを、多くの人が経験していると思います。

もちろん、私も経験者の一人です。
そんな経験を今後、少しでも減らしていくためにはどうすればよいか。
それには、以下のステップを踏むことが有効だと考えられます。
- 自分の性格やコミュニケーション能力に問題があるという思い込みから抜け出す
- 「傾聴」のための簡単な技術と日々の意識の心がけを身につける
つまり、性格や口下手といった自分では変えることが難しいものに目を向けることを止めて、技術や心がけといった習慣化によって変えられやすいものに取り組むということです。
ただ、そうは言ってもどんな技術をどうやって身につければよいかわからないと思います。
そこで今回は、そうした傾聴の技術や心がけについて書かれた書籍を基に、そこから私が実際に取り組んでみて「これは効果があった」と実感したものを3つ紹介します。
その3つとは以下のとおりです。
- HHJの三大悪の排除
- ピックアップ・クエスチョン
- 行動理由と「見えるもの」への注目
傾聴のスキルをうまく活用することで、相手に対する理解が深まり、相手から信頼されるようになります。
その結果、知りたい情報を相手から引き出すことができるようになるというわけです。
簡単に取り組みやすいものばかりですので、皆さまも参考にしていただければと思います。
書籍の紹介
書籍名:悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る
著者名:中村 淳彦
出版社:飛鳥新社
発売日:2022年9月28日
【心構え】HHJの三大悪の排除
まず、この「悪魔の傾聴」において大前提となることを皆さんと共有したいと思います。
それは以下の4つの「しない」です。
書籍の言葉を引用します。
悪魔の傾聴は、相手に対して「~をしない」不作為の技術が中心です。
「悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る」より引用
自分の話をしない。
相手の話を否定しない。
自分の意見を言わない。
アドバイスをしない。 P10

どれもやった経験があるものばかりですね。正直、耳が痛いです。
何も考えずに人と接すると、どうしてもこの4つのいずれかをやってしまうと思います。
さらに書籍ではこの4つをまとめて、「HHJの三大悪」と表現しています。
HHJとは、
- H:否定する
- H:比較する
- J:自分の話をする
この頭文字3つを並べたものです。
この三大悪を絶対に行わなこと。
これが、「悪魔の傾聴」において最も重要なポイントとなっています。
ちなみにですが、最近私の同僚同士の会話で、以下のようなものがありました。
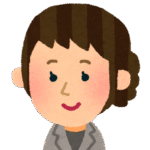
スマホを線路に落としてしまったから、帰りに駅の窓口に立ち寄って引き取りに行かないといけないんです。
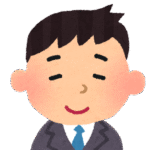
そうなんですね。首から下げられるスマホホルダーとか使えばもう落とすことはないんじゃないですかね。
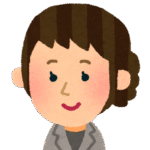
そうですね・・・。
この会話を聞いていて私は、これは三大悪のなかの「J:自分の意見」の典型例ではないかと感じました。
おそらくスマホを落とした方の人は、解決策を相手に尋ねたかったわけではないと思います。
とにかく「こんな残念なことがあった」ということを聞いてほしかっただけなのではないか、というのが私の予想です。
しかし、話を聞いた同僚はすぐさまアドバイスをしています。
案の定、会話はそこで途絶え、その後はしばらく沈黙が続きました。

一緒の部屋にいる身からすると、なんとなく微妙な空気を感じて、思わず席を立ってしまいました。
このように、ついやってしまいがちなHHJをいかに排除するかが、会話の成功率に大きくかかわってきます。
書籍でも著者がその実体験から以下のような意見を述べています。
これまで筆者はこれらの行為を「HHJの三大悪」と呼んでいます。三大悪を絶対にしないと心がけ、日々意識して実践するだけで会話の成功率は飛躍的にアップします。 P21
「悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る」より引用
皆さんも、普段から「HHJの三大悪」がなかったかを会話の後に振り返ってみてはいかがでしょうか。
【聞き逃し厳禁】ピックアップ・クエスチョン
「HHJの三大悪」を行わない。
それは理解したけれども、じゃあ具体的に何をすればよいのか。
書籍では基本スタンスとして以下の行動をすすめています。
まず、15~20分程度の初対面の相手との会話において、真っ先に聞き手のポジションをとって相手を主役にしてみます。
「悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る」より引用
やることは、相手の興味を聞きながら、相づちをうち、つなげていくだけです。 P18
言葉だけ見ると簡単そうですね。
しかし、私のようなコミュニケーション下手の人間からすると、

相手の興味を聞きだすのが難しいんだよ。
と思ってしまいます。
そんな人のために書籍で紹介されている技術が「ピックアップ・クエスチョン」です。
書籍の言葉を引用します。
ピックアップ・クエスチョンとは、すでに相手が発言した単語や主旨を拾い、即座に短い質問を投げかけるテクニックです。 P25
「悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る」より引用
書籍では、さらに具体的な方法も紹介していますので、その箇所を引用します。
ピックアップ・クエスチョンで相手の言葉を拾いながら、5W1Hを意識して質問することで、現状把握をしながら、相手から一歩踏み込んだ語りがでてくるのを待ちます。 P75
「悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る」より引用
この方法、実際やってみると簡単なうえに本当に効果があります。
先日、奨学金の業務として生徒と面談する機会があったので、この「ピックアップ・クエスチョン」を実行しました。

進学してどんなことを学びたいんですか。
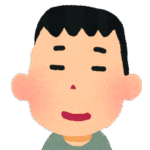
ゲームのことを勉強したいです。

ゲームですか。どんなゲームですか。
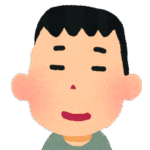
みんなでワイワイ楽しめるゲームです。

ワイワイ楽しむ、いいですね。いつからそんなワイワイ楽しむゲームに興味を持つようになったんですか。
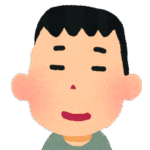
高校生になってから、ある時友だちで集まって〇〇というゲームをして盛り上がって・・・・。
といった感じで話が続き、面談の時間はあっという間に過ぎてしまいました。
その間、普段あまり話をしないという印象だった生徒が、ゲームに対する思いだけでなく、両親のために奨学金を希望していることなどまで自分から話をしてくれたのです。
私としてはこの生徒の新たな一面を知ることができ、大変有意義な時間になりました。
私のような者でも、こうした効果を実感できたので、皆さまも生徒や保護者、同僚とのやり取りで使ってみることをおすすめします。
【別の手段も】行動理由と「見えるもの」への注目
ピックアップ・クエスチョンを活用することで、ほとんどの会話のケースに対応できると思いますが、書籍ではこれ以外でも実用的な技術が紹介されています。
例えば、行動理由への注目。
書籍の解説を引用します。
「人の行動には必ず理由がある」として、会話を進行させてみます。 (中略)人の行動には理由があり、理由のなかには、必ずなにかしらの欲望や感情が存在します。 P31
「悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る」より引用
会話の中でピックアップできそうな単語や主旨以外に「行動」にも注目して、「どうしてそのような行動をとったのか」を尋ねるという方法です。

生徒がよく「親とケンカした」などと話しに来ることがあるので、そんなときはケンカの理由を尋ねたりしていますね。
会話がつながるので効果ありだと感じています。
さらに、何も話を切り出さないような人の場合は、その人が身につけているものなどに注目するという方法もおすすめしています。
書籍の言葉を引用します。
とにかく相手から見えた事象を拾って、会話が展開しそうなネタを質問に落とし込みます。 P50
「悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る」より引用
困ったときは、相手をよく観察してみましょう。
【結論】実際にやってみて実感したこと
前述の生徒とのやりとりのように、相手から聞きたいことを引き出す効果があるというのが実感です。
口下手な私でも、あれぐらいの短い質問であればなんとかなるので、実行のハードルは低いと感じています。
そう考えれば、最初にお伝えしたとおり、コミュニケーションがうまくいかない理由が、自分の性格やコミュニケーション能力に問題があることだけではないと、意識を少し変えることにつながりました。
他人とのコミュニケーションに苦手意識がある方は、ぜひどれか一つでも取り組んでみましょう。
まとめ
最後も書籍の言葉を引用したいと思います。
「いつも心に底辺を」という言葉を意識することによって、辛いことがあれば底辺だから仕方ない、一時的に成功しても「いつも心に底辺を」をもって舞い上がらない、調子に乗らない、常に冷静でいる。そういう効果が生まれています。 P163
「悪魔の傾聴 会話も人間関係も思いのままに操る」より引用
ちょっと卑屈すぎる印象を持つ方もおられるかもしれませんが、人の話を聞く際の心構えとしては、私はこのくらいがちょうどいいように感じています。
そう思い、私はこの「いつも心に底辺を」を手帳にメモしています。
そして「傾聴」を習慣化するために時々見返しています。
皆さまの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
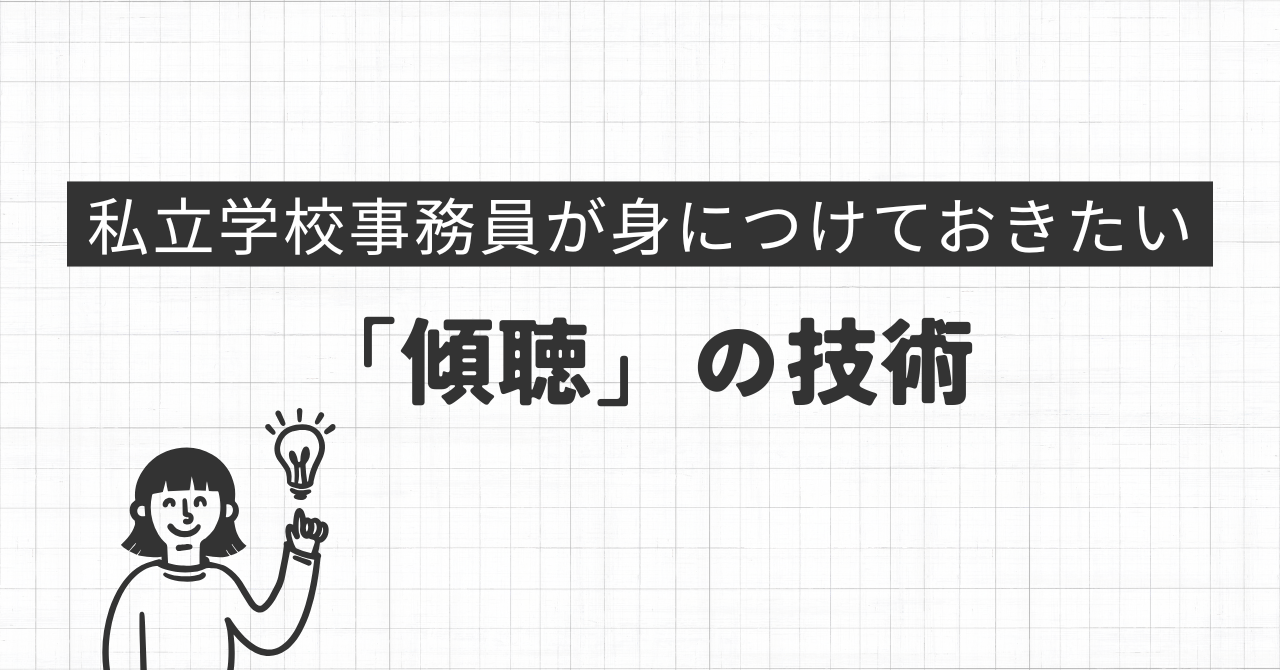
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=20723831&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9208%2F9784864109208_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)