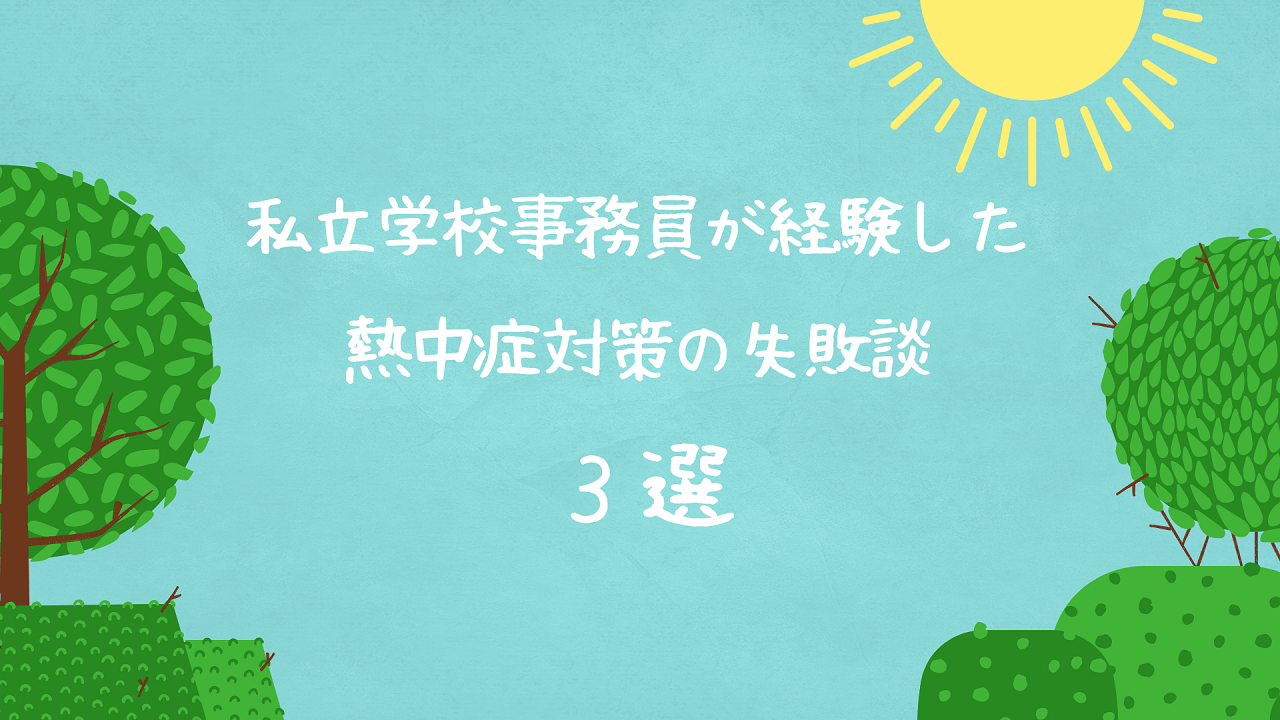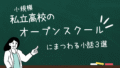この記事は以下のような人を対象としています。
・ADHDの生徒や教職員との接し方や活かし方を知りたいと考えている人
「ADHD」という単語、一度は耳にしたことがある人がほとんどではないでしょうか。
特に学校現場では、「学級崩壊」などネガティブな内容が報じられる際に使用されているような印象があります。
実際私の今の勤め先でも、その傾向の強い生徒の対応に多くの時間やエネルギーを費やしている様子です。
「授業中に不規則な発言をする」や「じっとしていられない」といった声が聞こえてくると、正直「大変だなぁ」と思ってしまいます。
しかし、学校としてはそういった特徴を持つ生徒も受け入れ、適切な教育サービス提供していく必要があるわけです。
そのためには、前述のようなADHDのネガティブな面だけでなくポジティブな面、言い換えれば「強み」となる点を理解しておかなければならないと私は考えています。
そこでこの記事では、ADHDの「強み」を紹介した書籍から、特に私立学校事務員として知っておくべきと感じたポイントを3つ紹介したいと思います。
その3つとは以下のとおりです。
- クリエイティブ
- エネルギッシュ
- ハイパーフォーカス
ADHDの傾向がある生徒との接し方をメインに想定していますが、多かれ少なかれこうした傾向が見受けられる大人もいますので、そうした方との接し方等の参考にもなればと考えています。
書籍の紹介
書籍名:多動脳 ADHDの真実
著者名:アンデシュ・ハンセン
出版社:新潮社
発売日:2025年4月17日
【言葉の確認】ADHDとは
まずは、「ADHD」という言葉の定義を確認したいと思います。
書籍では以下のように解説しています。
「多動脳 ADHDの真実」より引用
- まずはスタート地点、「どういう状態がADHDだと診断されるのか」から始めてみよう。
基本的には集中力、多動、衝動という3つの分野で問題が起きている。 P18
つまりは、
- 集中力:気が散る
- 多動:じっとしていられない
- 衝動:刺激を求めて突発的な行動する
などの問題が見られる状態と考えられます。
参考までに、私の勤め先での例を紹介します。
私の勤め先では以前、授業見学期間を設けて、教員が別の教員の授業を見に行くという取り組みをしていました。
その取り組みは事務員も参加可能だったため、事務員の一人があるクラスの授業を見学に行ったのですが、授業が終わる前に帰ってきたのです。
そして、帰ってきて発した第一声が以下のとおり。

とてもじゃないが見ていられない。
状況を尋ねると、まさに前述の3つの分野の問題が生じている様子でした。
- 集中力:教科書を見ていても、短時間で目を離して別のことをする。
- 多動:授業中でも離れた席の生徒のところへ歩いていく。
- 衝動:教員が話しているのを遮って話し出す。
「そんなにひどい状況なのか」と思った別の事務員が同じクラスを見学しましたが、やはり同じ感想。
事務室内が暗い雰囲気になりました。
しかしこれはこのクラスに限った話ではなく、程度の違いはあれども他のクラスも同様のケースが見受けられるようです。
まずはこうした様子を頭の中でイメージしていただき、以降の内容をお読みいただければと思います。
【①クリエイティブ】「気が散る、話が飛ぶ」→「枠にとらわれない」
書籍の言葉を引用します。
「多動脳 ADHDの真実」より引用
- ADHDの学生の方が平均的に散発的思考に優れていることがわかった。いくつもアイデアを思いついただけでなく、かなりの確率で他の人にはない独創的な答えを出したのだ。P70
先ほどの授業中の例にもあるとおり、ADHDの場合、集中力が続かず別のことに関心が移ってしまいます。
これは会話でも同様で、ADHDの傾向が強い生徒と話をしていると、さっきまで話していたことと全く違う内容の話を突然始めることがあります。

最初は全然ついていけず、思わず「何の話?」と尋ねてしまいました。
教員からも「あの生徒は話があっちこっちに飛ぶ」といった声を耳にします。
私たちのそうした経験が、「話が通じない」というネガティブなイメージにつながってしまっているように思えます。
しかし普通の会話ではそうかもしれませんが、「アイデア出し」というシチュエーションではまた別の面が見えてくるわけです。
前述のとおり、ADHDの学生は独創的なアイデアをいくつも思いつきます。
言い換えれば「クリエイティブ」という強みを持っているとこの書籍では紹介しています。

私の中では「枠にとらわれない発想ができる」という理解です。
こうした強みの部分が理解できていれば、普段の接し方にも余裕が生まれてきます。
話しが飛ぶことが分かっているので、「また枠を飛び越えた」と思いながら対応することができるようになりました。
もちろん、これはあくまで事務員目線での話。
授業を行っている教員からすれば、常に独創性のある発言を求めているわけではないので、対応が大変であることは承知しています。
ただそのうえで、事務員としてはADHDの強みに目を向けられるようになるために、そうした生徒との雑談の中で練習してみることをおすすめします。
私たち事務員とのやりとりが、その生徒にとっての「居場所」を作ることにつながるかもしれないからです。
機会があれば取り組んでみてはいかがでしょうか。
【②エネルギッシュ】「じっとしていられない」→「実行力がある」
書籍の言葉を引用します。
「多動脳 ADHDの真実」より引用
- ADHDにはじっとしていられない、実行力がある、リスクを恐れない、権威や伝統にひれ伏すことがないという特徴がある。既存のルーチンや仕事の作業手順がうまく機能しない時にも「でも今までずっとそうしてきたから」では納得せず、よりよい方法を探そうとする。P79
「既存のルーチン」「今までずっとそうしてきたから」
私立学校事務員的な言葉が出てきたという印象です。
前述のとおり、ADHDは生徒に限ったものではありません。
大人にもその傾向が見られることがあります。
そのため、一緒に働く教職員の中からこの強みを持った人を見つけることをおすすめしたいと思います。
そうすることで、事務員の仕事にありがちな「既存のルーチン」を打破することができ、またそれが仕事の効率化などにつなげることができると考えているからです。
書籍の中でも、はっきりとADHDの傾向がある子どもがいるグループと、一人もその傾向がないグループとでは、前者の方が与えられた課題を正しく解くことができたという実験結果が紹介されています。
ADHDの子どもに引っ張られるかたちで、グループ全体が課題解決に向けた行動をとるからのようです。
ぜひとも取り組んでみたいと思っていますが、残念なことに私の勤め先では、事務員の中でこの強みを持った人はいませんでした。

なんせ3人しかいませんので。
しかし、教員の中にはこの強みを持った人がいたのです。
その教員はとにかく既存のやり方を変えたがります。
AIなど新しい分野にも積極的に取り組んでおり、まさに「エネルギッシュ」。
残念ながら「事務室のことはノータッチ」という姿勢なので、事務室業務の見直しには携わってもらえていませんが、事務員でこのタイプの人がいればと思いました。
ただ、注意すべき点もあります。
それは①のところでも触れた「気が散る」ということです。
先ほどの教員も着手するところまではいいのですが、その取組みが長続きしません。
やりきる前にまた別のことを始めてしまいます。
この対処法として、逆にコツコツ積み上げることが得意な人を補助につけるということが考えられます。
実際この書籍でも、弱みをサポートする存在の重要性に触れています。
「多動脳 ADHDの真実」より引用
- とにかくアドバイスしたいのは「助けを求めること」だ。自分とは違うタイプの人を探し、自分の<弱み>を埋め合わせてくれる人と働くといい。 P102
一番エネルギーの必要なところは「エネルギッシュ」という強みを発揮してもらい、そのあとは、サポート役が引き受ける。
教職員でも生徒でもこうした活かし方ができれば、組織としての成長が期待できると考えています。
じっとしていられない人を見かけたら、「今までの常識を見直すチャンス」と考えてみましょう。

ちなみにこれも残念なことに、私の勤め先の教員はとにかく人の仕事に手を出したがらない。コツコツやってくれそうな人はいるのですが・・・。
【③ハイパーフォーカス】「他を忘れて突発的に行動」→「強い好奇心」
書籍の言葉を引用します。
「多動脳 ADHDの真実」より引用
- 「ハイパーフォーカス」といって何かに夢中になり、周りで何が起きているかも気付かないくらい集中力を傾けることができる能力だ。P87
- ADHDの人の多くは充分に興味深くて継続的にごほうびをもらえるならばハイパーフォーカスすることができる。P93
「気が散る」という弱みについて触れましたが、これは全てのことに対してではありません。
ADHDの人は、自分が興味を持っていることには高い集中力を発揮します。
これを「ハイパーフォーカス」と言うようです。
このハイパーフォーカスによって、本来やらなければならないことを放っておいてしまうというところが弱みと思われています。

ゲームばかりして、宿題をしないというケースをイメージしていただければと思います。
しかし別の見方をすれば、好奇心が刺激されることには何時間も集中できるという強みとして見ることができます。
この強みの方にフォーカスできるようになるためのキーワードが「継続的なごほうび」。
これを実践するために、私は「こまめに具体的にほめる」を心掛けています。
この書籍を読む前の話ですが、以前の勤め先の大学で「車」に強い興味を持った学生がいました。
この生徒、話が長いのと自慢話的な内容が多いということから、他の事務員が対応を避けていたため、私がよく話し相手になっていました。
「車」の中でも特に「レース」に非常に興味を持っていて、レーシング場の写真などをよく見せてくれたことを今でも覚えています。
その写真を見ながら、「特にここがお気に入りかな」というポイントが見つかれば「この写真の〇〇の部分がよく撮れている」などの感想を伝えていたのです。
それから月日が流れ、その学生はレースに関わることができる会社に就職。
そのことを私に伝えにわざわざ来てくれたうえに、
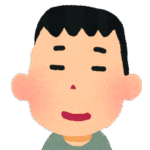
自分が関わったレースに招待しますから。
と言ってくれた時にはとても嬉しく感じました。
今思えばその学生の「強い好奇心」にフォーカスして「継続的にほめた」ことで、こうした関係が構築できたのかなと思っています。
皆さんも「〇〇の話ばっかり」とうんざりせずに、「あなたのハイパーフォーカスしていることはこれか」という意識で接してみてはいかがでしょうか。
まとめ
あらためてADHDの強みを以下にまとめます。
- クリエイティブ:独創的なアイデアを考えられる
- エネルギッシュ:既存の状況を打破できる
- ハイパーフォーカス:好奇心を刺激することには粘り強さを発揮できる
この書籍では、こうした強みを実験等に基づいて解説しています。
「大雑把→大胆」のように、単純に弱みを逆の意味でとらえているわけではなく、実験結果という根拠に基づいているわけです。
だから、より信憑性があると感じていますので、ご一読することをおすすめします。
ADHDに対する理解が深まり、皆さまの仕事や人間関係にプラスの効果をもたらすことにつながれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
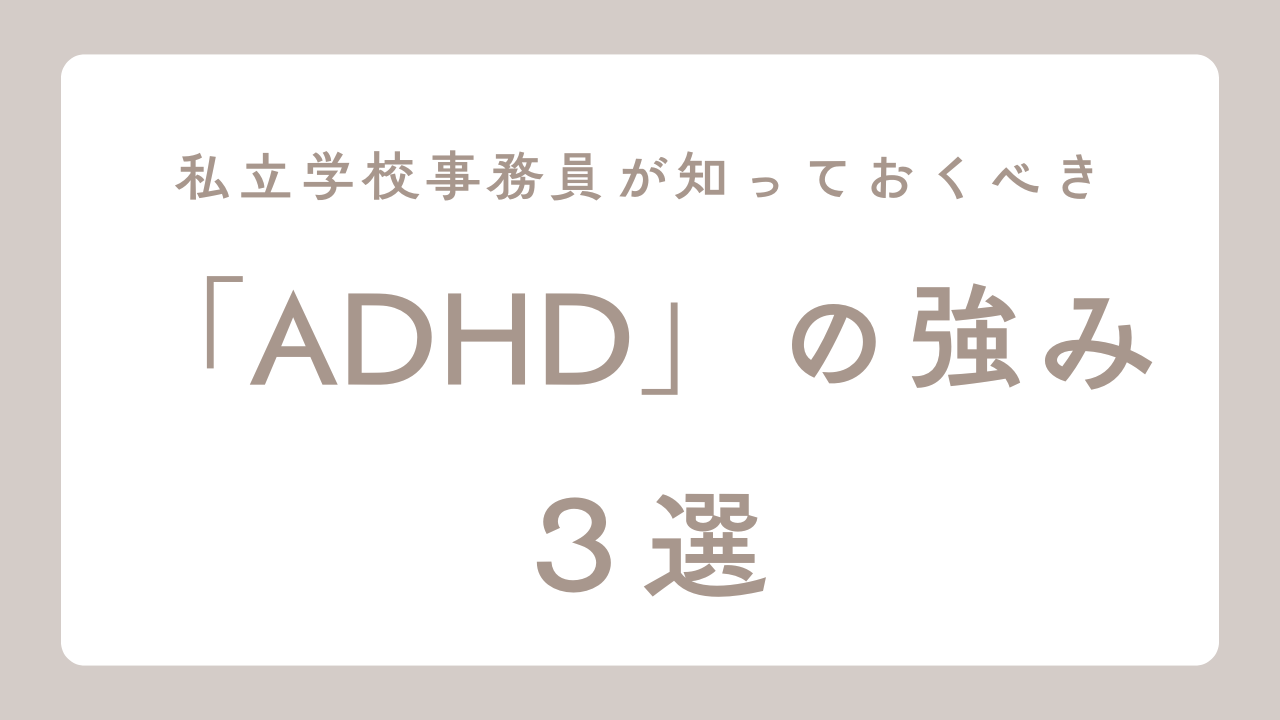
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=21558524&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0856%2F9784106110856_1_28.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)