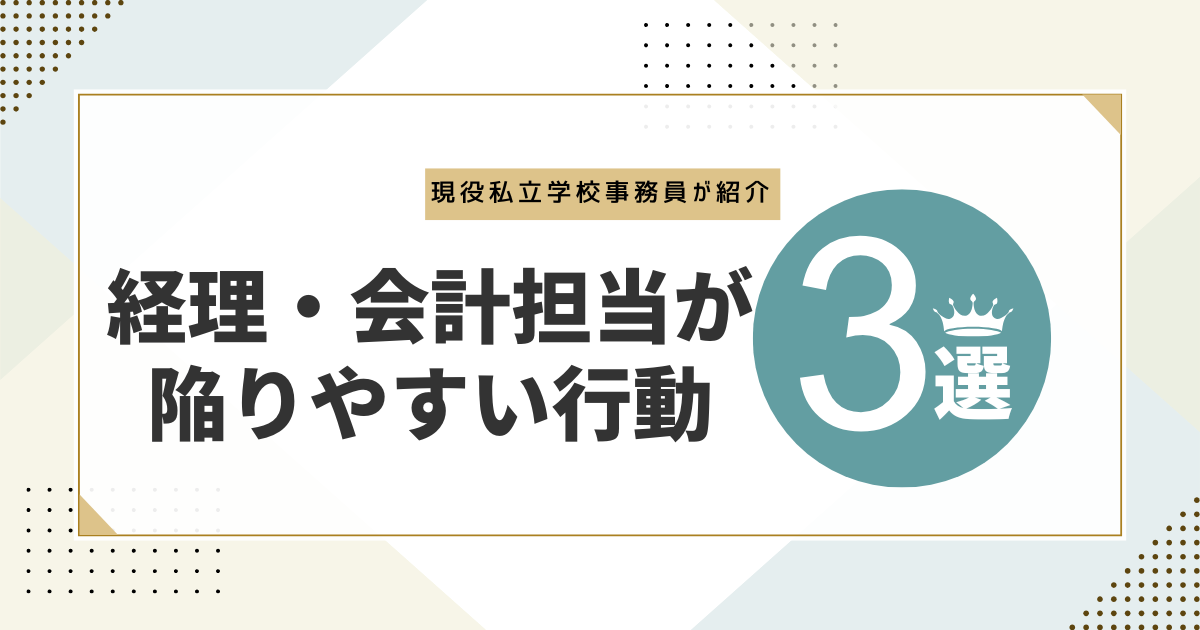この記事の内容は以下のとおりです。
・私立学校事務員で経理・会計担当者のうち、特に経験年数の浅い人がやりがちな「これは避けるべき」行動を紹介
経理・会計の担当者になると、他の事務員には見ることができない学校の「収支状況」や「経営状態」を見ることができるようになります。
またそれに伴い、経理・会計に関する専門用語も知識として身につけられます。
私が今までの学校事務員歴を振り返ると、そのような状況に慣れてきた際に、陥りがちな行動パターンがあるように感じます。
思い起こせば、私自身もそのような状態になっていました。
この行動パターンをとるようになると、周りの人たちからの印象が悪くなり、業務上必要な円滑なコミュニケーションに悪影響を及ぼす恐れがあります。
そこで、皆さまが今後経理・会計担当に就いた場合でも、私と同じ轍を踏まないように特に注意すべき3つの行動を紹介させていただきます。
この記事を読んで、皆さまがこれらの行動を回避することができれば幸いです。
【結論】注意すべき行動はこの3つ
早速ですが、先に結論として3つの行動を紹介させていただきます。
以上の3つです。
これらについて、私のこれまでの経験も交えながら紹介していきます。
【注意すべき行動①】比率・指標だけで判断
経理・会計担当になると、業務を遂行するなかで「財務分析」的なことも経験します。
例えば決算の業務では、自校の決算数値と他校や全国数値との比較を踏まえて、どのような状態であるかを関係者に示す資料を作成することがあります。
他にも、学校の将来計画を立てる業務に携わり、収支見通しの作成を担当する際にも、各種比率・指標を参考にします
このように、様々な経理・会計業務を任されるようになるにつれ、初めはゼロに近かった知識がどんどん増えていきます。
そうしたときにやりがちな行動が、この「比率・指標だけで判断」です。
決算数値を見て、「うちは○○比率がマイナスだからだめだ」や「△△比率が高いから、ヤバい」などの発言を周りの人たちにしてしまいます。

覚えたばかりの知識はすぐに使いたくなってしまうんですよね。
もちろん、「マイナス」や「高い」は事実なのですが、「だからだめ」と言われても、聞いた人からすると「何が原因なのか」まではわからず、不安だけを煽る結果となります。
「今年度だけマイナス又は高いのか」という時間的な側面も含めて、原因まで検討することが重要です。
また、その原因を考える際にも問題が生じることがあります。
具体例として「人件費比率」についてみてみましょう。
人件費比率は「人件費÷経常収入×100」で算出されます。
仮にある学校の人件費比率が70%、全国平均が60%だとします。
ここで「うちはずっと人件費比率が高いから、賞与カットなど人件費を抑える手を打たなければならない」と判断するのはまだ早いです。
算出式を確認すると、人件費比率が高くなるのは以下のどちらかになります。
- 人件費が高い場合
- 経常収入が低い場合
つまり前述の判断では「②経常収入が低い」のケースには触れられていません。
②の方で考えれば、生徒等から徴収する学納金の単価が低すぎる(学費が安い)ということも考えられます。

「人件費比率」という言葉に引っ張られて、人件費の方ばかり見てしまうわけです。
安易に人件費カットの方策に走ってしまいますと、教員や事務員の退職にもつながり、それがサービス低下を招くことで、生徒募集に悪影響を与えて、一層経常収入が減少することも考えられます。
覚えたばかりの比率・指標を使って、自分の意見を他の人に聞いてもらいたくなることはよくあります。
そのこと自体は悪いことではなく、アウトプットすることで知識を定着させる効果もあると考えられます。
しかし、比率・指標だけで判断することが不十分であると言えます。
この行動に陥らないために、以下の点を意識することをおすすめします。
・比率や指標を使って意見を言う時は、複数年比較して原因まで考える。
・比率や指標は「結論ありき」ではなく、あくまで「仮説」を立てるための材料である。
【注意すべき行動②】勘定科目の過度な使用
これは要するに「専門用語をむやみやたらに使う」ということです。
経理・会計で使用する言葉は、その他の業務に携わる人にとっては聞いたことのない外国語のような存在です。

皆さんも経験ありませんか。
よくわからないカタカナ言葉を言われて、「今のどういう意味だったんだろう」と思ったこと。
実際に私が聞いた言葉を1つ紹介します。
「基本金の未組入額が発生したら面倒だから、図書の未払いがないように注意してください」
経理・会計担当以外の方には知らなくても問題ない内容と思いますので、解説はあえて省略させていただきます。
ただ、何を言っているか理解できないと思った方は多いのではないでしょうか。
馴染みにない言葉を使って説明をしても、聞いている側は理解できません。
それにより、相手はあなたに「この人の言っていることはよく理解できない」という印象を持ってしまい、関係に距離ができてしまいます。

それでは、円滑なコミュニケーションをとることができず、業務に支障が生じる可能性があります。
また、やたらと正確な勘定科目にこだわってしまうというケースもあります。
例えば、相手が「立替で」という言葉を使ったときに、すかさず「それは仮払いになります」と言い返してしまうような状況です。
言われた方は「いや、そういう意味で言ったわけではない」と思ってしまいます。
経理・会計担当は「正確さ」が強く求められるポジションであるため、正確な表現を使うことはよいことではあります。
しかしこれもケースバイケースです。
上述の例のように、言葉のニュアンスさえ伝われば問題ない状況であれば、わざわざ正確な表現に直さなくてもよいと思います。
この行動に陥らないためのポイントは以下の2つです。
・とにかく、普段から会話で勘定科目を使わないようにする。
・勘定科目は「この場合の勘定科目は何が適切か」という直接的な質問を受けたときだけ使う。
【注意すべき行動③】「監査」「検査」の過度な使用
②と似ていますが、何か不都合なことが生じた時に、相手への説明で「それは監査で指摘されてしまう」などと言ってしまうケースです。

私が一番驚いたのは、どこかの会社から営業の電話がかかってきた際に「学校は行政から検査を受けているので、取引先を変更することは難しい」と対応しているのを聞いたときです。
「相手が学校のことを何もわかっていないのに、その断り方は・・・」と思いました。
事の重大さを伝えるために使っていると考えられますが、これだけ伝えられても相手は理解することが難しいと思います。
そもそも「監査」という言葉自体、多くの人にとって馴染みが薄いものです。
もちろん、会計士による監査や会計検査院や行政による検査で指摘を受けないように普段から気をつけることは、学校事務員として大切です。
ただ、「監査で指摘されないため」を理由としている言い方は注意が必要ということです。
経理・会計担当に就いて、経験年数が浅いととにかく「監査で指摘されないように」と意識してしまい、このような発言につながってしまうようです。
この行動に陥らないために、以下の点を意識するよう努めましょう。
・「監査」「検査」という言葉は同じ経理・会計担当者間でしか使わない。
・何が問題で指摘を受け、その結果どうなるのかまで自分の中で理解してから説明する。
まとめ
私自身も経験してきた3つの行動について紹介してきました。
3つの共通点としては「他人」の視点が欠けているということが挙げられると思います。
知識を身につけて学校事務員として成長することは、大変重要なことです。
そうした「自己の成長」という視点に、「他人への理解」という視点が加わることで知識だけでなくコミュニケーション力など他の能力も養うことができると感じています。
ぜひ、知識や経験を深めて、それをわかりやすく外に発信できるように日々の業務に取り組んではいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。