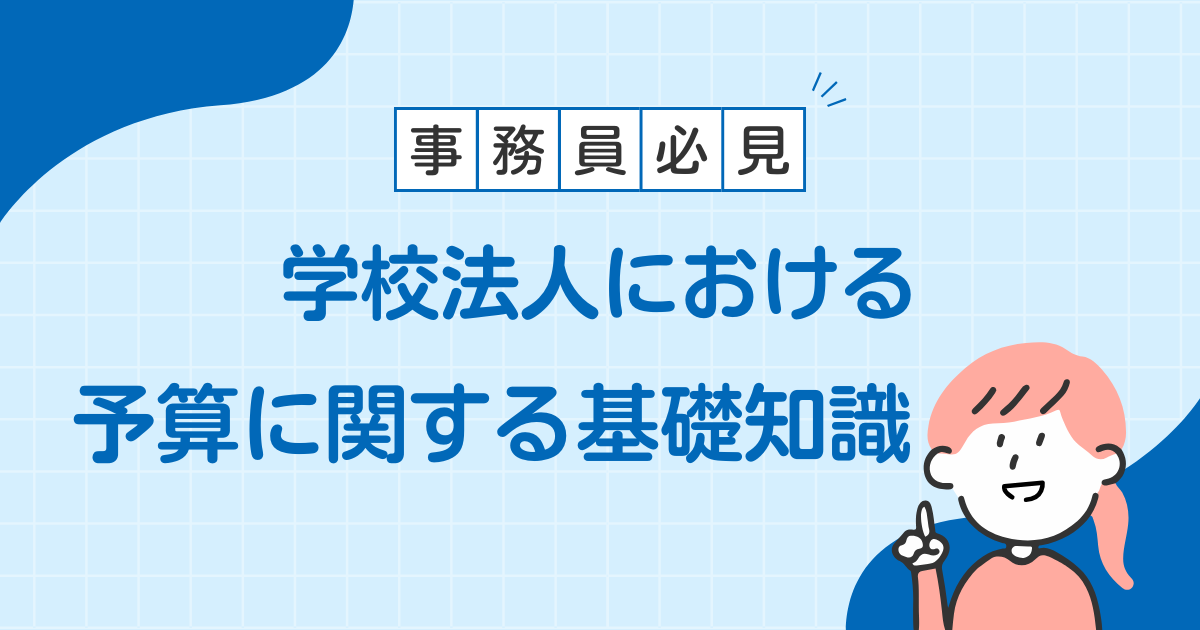この記事の内容は以下のとおりです。
・学校法人における予算制度の法的位置づけを理解する
・予算の目的と重要性について理解する
今回は学校法人における「予算」について解説します。
厳密に言うと、学校法人会計基準には「予算」に関する定めはありませんが、実務上は学校法人会計基準の内容を踏まえながら作成業務を行うため、学校法人会計基準の基礎知識として紹介させていただきます。
学校法人において「予算」の重要性は極めて高いです。
実際に、予算のとりまとめなど予算作成業務を直接行うのは経理・会計担当者ですが、担当者以外でも私立学校事務員として働くうえで、学校法人における予算の重要性や法的位置づけを理解しておくことは大切です。
私の私立学校事務員としての経験も踏まえて解説しています。
この記事の内容が、予算を意識しながら業務が遂行できるようになることの一助になれば幸いです。
予算の法的位置づけ
まずは、どのような法律を根拠に学校法人は予算を作成しなければならないかを理解しておきましょう。
関係する法律として、少なくとも以下の2つはおさえておく必要があります。
私立学校法
e-gov 法令検索より引用
第九十九条 学校法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。
私立学校振興助成法
e-gov 法令検索より引用
第十四条 第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人(以下この条において「助成対象学校法人」という。)は、収支予算書を作成しなければならない。
「私立学校法」は、学校法人や学校法人が設置する私立学校に対するルールのようなものです。
そして、「私立学校振興助成法」は学校法人が行政から助成を受けるために守るべきルールが定められたものです。
これらを踏まえて、それぞれの条文が定める内容をまとめると以下のようになります。
- 学校法人は(助成を受ける・受けないに関わらず)予算を作成しなければならない。
- 学校法人は、行政から助成を受けるためには作成した予算を「予算書」の形式で所轄庁に提出しなければならない。

所轄庁とは、大学や短期大学を設置している学校法人は文部科学省、それ以外の学校法人は都道府県と考えてください。
以上が、学校法人における予算の法的位置づけとなります。
予算作成の目的
ではなぜ、法律で定めるほど学校法人における「予算」が重要なのでしょうか。
それは以下の2つの目的が関係しているからです。
- 経営の健全性と永続性の確保
- 公的助成を受ける主体としての義務の履行
①は私立学校法、②は私立学校振興助成法の定めにそれぞれ関係しています。
目的①経営の健全性と永続性の確保
突然ですが、皆さんは以下の2人の人物のどちらの方が生活に「健全性」があると思いますか。
年収も同じですが、世帯構成など記載した内容以外は同じものとしてお考えください。
Aさん:年収500万円。自分の生活費などの支出額について1年間でどのくらい必要かをおおよそ把握しており、その支出額に基づいて計画を立てて日々の生活を送っている。
Bさん:年収500万円。自分の生活費などの支出額は把握しておらず、その時々の財布の状況を見ながら日々生活を送っている。
おそらく、ほとんどの方は「Aさん」の方が「健全性」があると思ったのではないでしょうか。
「学校は民間企業と違って、企業努力により年度途中に収入を大幅に増やすことはできない」という話をよく耳にします。
そのとおりではありますが、私は民間企業との違いよりも私たち一個人と学校法人との似ている部分に注目しています。
「年度途中にいきなり収入を増やすことはできない」という部分です。

宝くじで数千円当たったり、不用品を売却して数万円臨時収入があったりするかもしれませんが、生活に大きな影響を与えるほどの収入増が起こる確率は極めて低いです。
ということは、私たち自身に置き換えて学校法人の経営を考えた方が、腹落ちしやすいと考えています。
そこで上述のような例を挙げてみました。
「健全な経営=健全な生活」と考えれば、「計画=予算」の重要性が理解できるのではないでしょうか。
さらにこの「健全な経営=健全な生活」は1,2年だけ続ければよいわけではありません。
生きている限り、続けていかなければなりません。
加えて学校法人は「日本の学校教育の発展」という重要な役割を担っています。
日本の将来のために、私立学校法で予算作成を義務付け、健全で永続的な経営を行うことを求めているわけです。
これが予算作成の目的の1つ目です。
目的②公的助成を受ける主体としての義務の履行
これも、目的①の際に挙げたAさんとBさんの例に戻ってイメージしてみましょう。
Aさん、Bさんのどちらを支援したいと思いますか。
これもほとんどの人がAさんを選ぶのではないでしょうか。

Bさんのように「何に使うかわからない」状態の人にお金の支援などをすることは難しいです。
一方、Aさんのようにきちんとした計画がある人から頼まれれば、「じゃあ、この部分については支援しましょうか」と言いやすいように感じます。
さらに、学校法人が受ける助成金(補助金)は、税金が原資になっています。
その税金がBさんのような状態の学校法人に渡っている場合、税金を支払っている私たち国民はどういう印象を抱くでしょうか。
当然、いい印象を持つことはありません。
従って、学校法人は公的な助成を受ける義務として、教育・研究活動の計画を立てて、それを予算のかたちにして作成・提出しなければならないというわけです。

学校教育の発展に関わる計画に対して助成するのであれば、国民も自分たちのお金(税金)が使われていることに納得しますよね。
以上が予算作成の目的の2つ目です。
予算と実績の差異
以上のような法的位置づけや目的に基づき、学校法人は予算を作成するわけですが、100%予算どおりに計画を進めることはできません。
当然、実績(決算)との差異が生じます。
この「差異」については、経理・会計担当以外の方も意識していただきたい重要なポイントです。
経理・会計担当者は決算時に予算と決算の差異を分析します。
分析の結果、その差異が大きいものについては、担当者に理由を確認します。

例えば旅費について決算額が予算額と比べて大きく下回っている場合、さらに細かい実績を見て予算と比較し、「この部署が申請していた海外出張の予算が使われていない」などを洗い出すわけです。
この理由確認において、予算の重要性に対する意識が低い人の場合、「経費削減に努めた」や「計画を見直した」などテンプレートでも貼り付けたような回答が返ってくることが多いです。
本当にその理由で間違いなければ問題ありませんが、中には当初の計画段階から本当に必要だった疑わしいものもあります。
「とりあえず計画だけ立てておいて、実際にやらなかった場合でもその分お金が学校に残ったからいい」という意識は持つべきではありません。
前述のように、学校法人は「日本の学校教育の発展」を担っているわけであり、その発展のために1つ1つの事業を計画し、予算化しているわけです。
そして、その予算に対し行政が支援しているわけです。
そのことを強く意識して、経理・会計担当以外の方も計画の立案や予算の執行に携わることを心がけましょう。
まとめ
学校法人における「予算」は、法律で作成が義務付けられるほど重要なものです。
しかし会計の話になると、どうしても決算の方に内容が偏ってしまう傾向があるように思います。
そのため、予算に関する法律の定めがあることやその目的を理解する機会が少ないように感じています。
私立学校事務員としては、予算も決算も重要なものであることを意識する必要がありますので、この記事の内容を参考にしていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。