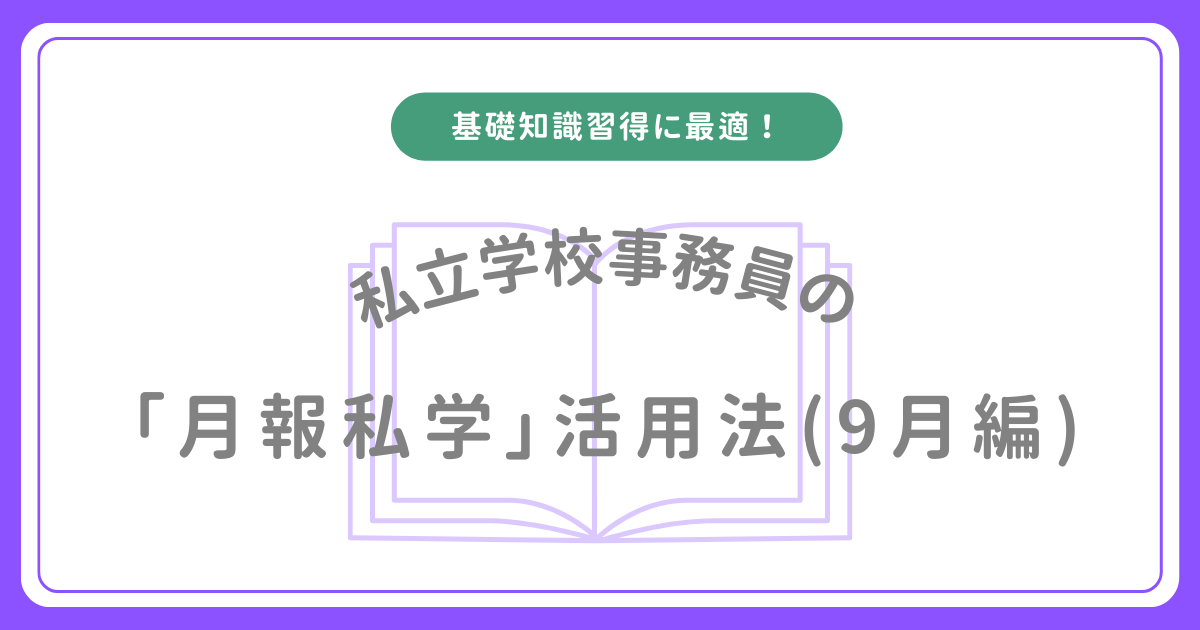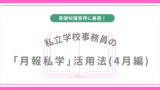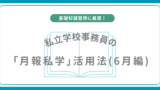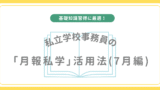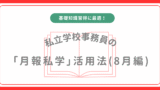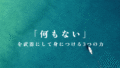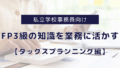この記事は以下のような人を対象としています。
・私立学校事務員として働くうえでの基礎知識を身につけるために、役立つツールを教えてほしい。
これまで、日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)が毎月発行する「月報私学」の各月ごとの活用法を紹介してきました。
今回は、その続きにあたる9月号の活用法の紹介になります。
9月号は9月1日に発行されるため、現時点では内容が不明ですが、例年9月号に掲載されている記事というものがあります。
そうした記事の中で、私が毎年参考にしているものを3つピックアップしたいと思います。
その3つは、以下のとおりです。
- 私学事業団の業務報告及び決算
- 被扶養者の再審査と加入者証等の検認を実施します
- 年金積立金の運用状況
あわせて、この時期には「私立大学・短期大学等入学志願動向」の最新データが私学事業団(私学振興事業本部)のホームページで公開されます。
このデータの説明が、今後発行される月報私学に掲載されるはずですので、もし9月号に掲載されていた場合はチェックしておきましょう。
前述のとおり本年度の9月号の内容は現時点でわかりませんので、掲載されていない場合もあります。その点はご容赦ください。
私学事業団の業務報告及び決算

私学事業団の決算が業務とどう関係するの?
と、思われた方もおられると思います。
確かに直接的に業務には関係ありません。
ただ、私たちの勤める私立学校とかかわりの深いパートナーが、「どんなことに取り組んでいるのか」といったことについて興味を持つことは意味があると考えています。

相互理解って大事ですよね。
私がこの私学事業団の業務報告及び決算に興味を持ったきっかけは、私学事業団職員の方との何気ない会話でした。
補助金のことや会計のことなどについて相談していた時のことです。
話が融資の内容になった際、事業団職員の方がこんな旨のことをおっしゃいました。
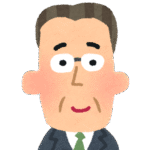
私たちは、私学の皆さんが受けた融資からの利息収入をもとに事業を運営しています。
どういうことかと尋ねてみると、経常費補助金などは国からのお金を原資にして私学に交付しているが、それはお金を右から左へ私学に渡しているだけとのこと。
刊行物の発行や私立学校への取材に係る費用などに加えて、職員の人件費も含めて融資から生じた利息で賄っているというお話でした。
通常、私学事業団のような組織は、その組織を所管する省庁等(私学事業団の場合は文部科学省)から運営費交付金というものが交付されています。
この運営費交付金は文字どおり、上述の職員の人件費など組織の運営に係る費用に充てられるお金です。
私学事業団はこの運営費交付金の交付を受けていないというのが、先ほど紹介した事業団職員の方の発言の趣旨になります。
そのような背景があるため、
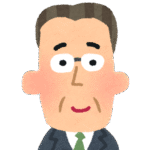
私たちは私立学校に生活を支えていただいているという意識を持っている。
といったこともお話しされていました。
融資を受けるということは、施設設備へ投資すること。
つまり将来の発展のためにお金を借りていると言えると思います。
そうした「私学の発展を支援することが、自分たちの生活につながっている」という気持ちを持って仕事に携わっている姿勢に、私は感銘を受けました。
その話が私の記憶のどこかに残っていたため、この月報私学の事業報告の記事を見かけた際に、「そういえば」と思い、読んでみたというのがきっかけでした。
実際にこの記事の「助成業務(助成勘定)の損益状況」というところを見てみると、前述したことが確認できると思います。
例えば、月報私学2024(令和6)年度9月号に掲載された内容からは以下のようなことが読み取れます。
「月報私学 令和6年度9月号」より加工して引用
- 貸付金利息(収益):41億円
- 人件費:11億円
- 業務経費:5億円
- 借入金利息(費用):22億円
つまり、融資から生じた利息を受け入れたことにより41億円の収入があり、そこから人件費と業務経費、私学事業団自身が支払う利息の合計38億円(11+5+22)を支払っているということです。

確かにそこには運営費交付金というものが現れてきませんね。
ただ、「助成業務(助成勘定)の損益状況」となっていますので、共済業務の方はまた別の状況になっているかもしれません。
その様子は、月報私学の記事からは確認できませんので、ここでのコメントは差し控えさせていただきます。
この記事では、他にも補助金や融資、寄付金といった個別の事業の様子も報告されているので、基礎知識を身につけておくという意味で目を通すことをおすすめします。
被扶養者の再審査と加入者証等の検認を実施します
これは、共済事務担当の方がメインですが、そうでない方も知っておくべき内容と考えています。
「被扶養者」として私学共済から認定を受けるためには、要件を満たす必要があります。
それは、例えば年収がいくら未満であるとか、加入者と同居しているといったものです。
こうした要件は認定を受ける際に一度だけ満たしていればよいわけではなく、「被扶養者」としての立場を継続するためには満たし続けなければなりません。
そこで私学事業団は、被扶養者がこの要件を満たしているかを確認するために定期的に「再審査」というものを実施します。
実際に確認するのは、各学校の共済事務担当者になりますが、再審査が必要となる被扶養者をもつ教職員から所得証明や住民票等を徴収するなどして、要件を満たしているかをチェックし、その結果を私学事業団に報告するわけです。
一方、特に再審査が必要ではない被扶養者もいます。

例えば生まれたばかりのお子様などは、再審査の対象にはなっていなかったと記憶しています。
そのような方には、氏名等の登録内容に誤りがないかを確認する「検認」という作業を実施することになります。
- 私学共済の被扶養者になるためには要件がある
- その要件は定期的に確認される
こうしたことは共済事務担当ではない人でも、私立学校に勤める者として理解しておくべきだと思います。
そして、この再審査・検認の際に起こりやすいと私が感じているのが、「被扶養者の外し忘れ」です。
お子様が就職した場合、被扶養者取り消しの手続きをする必要があるのですが、それが抜け落ちているというケースをこれまで何度も見てきました。
このあたりは私学共済というよりも、社会保険の基礎知識というべきものだと思います。
記事の中でもその点について紹介していますので、確認しておきましょう。
年金積立金の運用状況
私学共済に加入していると、月々の給料等から「退職等年金給付掛金」を徴収されています。
そして徴収された掛金は、「積立金」として扱われて管理されます。
この積立金の管理・運用を私学事業団が行っているわけです。
掛金を出している私たちとしては、その掛金がどのように運用されているか気にしておくべき。
私はそう考えているため、この記事をチェックすることをおすすめしています。
詳細は記事をご確認いただきたいのですが、年金積立金は3つに区分されて運用されています。

そもそも3つに区分されていること自体、知らなかった方が多いではないでしょうか。
この3つの年金積立金それぞれについての運用状況が解説されています。
難しい用語等がところどころ出てきますが、そうしたものについては興味があれば後ほど調べるとして読み飛ばし、とりあえずは運用がうまくいっているかどうかだけを確認するようにしています。
ちなみに昨年度の記事では、3つ全ての年金積立金においてプラスの運用状況でした。
掛金を拠出している者として、一読してみることをおすすめします。
まとめ
今回紹介した3つのトピックスについて、どれも直接的には業務に結びつかないという方が多いかもしれません。
しかし、「私立学校に勤める者」や「私学共済の加入者」という立場からすれば、知っておいた方がよい内容だと私は思っています。
ぜひ皆さまも、「自分の業務に直接関係あるか」という視点だけでなく、上述したように少し視野を広げて情報収集してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました