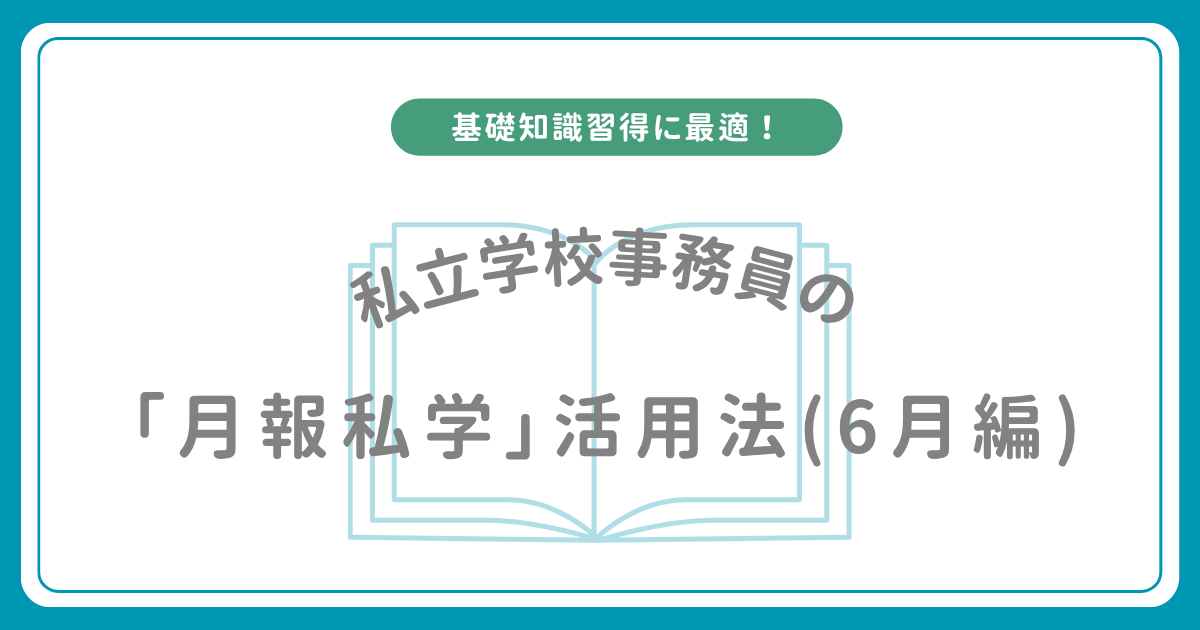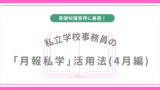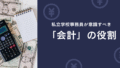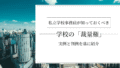この記事は以下のような人を対象としています。
・私立学校事務員として働くうえでの基礎知識を身につけるために、役立つツールを教えてほしい。
以前の記事で、日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)が毎月発行する「月報私学」の活用法について紹介しました。
今回は、その6月号の活用法の紹介になります。
6月号は6月1日に発行されるため、現時点では内容が不明ですが、例年6月号に掲載されている記事というものがあります。
そうした記事の中で、私が毎年参考にしているものを3つピックアップしたいと思います。
その3つは以下のとおりです。
- 標準報酬月額の定時決定
- 標準報酬月額の改定が必要なとき
- 新トピックス
今回は特に、共済事業に関するものが中心になっています。
担当業務として、直接私学事業団と共済事務関係でやり取りをしない事務員の方でも、自分の給料に関わる大事な情報となっていますので、ご参考にしていただければと思います。
標準報酬月額の定時決定
5月号の解説でも少し触れましたが、私立学校事務員は毎月の給料から「掛金」というものを私学事業団に納めています。

イメージとして、民間の保険に加入している方が保険会社に支払っている「保険料」と思っていただければここでは問題ありません。
保険料であれば、保険会社が定めたルール(保険加入者の年齢等)に基づいて算定されますが、掛金も一定のルールに従って決定されます。
そのルールが「学校法人がその人に支払った報酬の金額に基づいて決定される」というものです。
この「報酬」にどんなものが含まれるかについては、前述の5月号に掲載されていますので、一度ご覧いただければと思います。
「報酬」の金額に応じて掛金の金額が決まり、その金額を学校法人と本人が折半して私学事業団に支払うというのが、大まかな仕組みです。
では、「報酬」をいつ報告すればいいのかということになりますが、これはいくつかケースに分かれています。
その中でも、必ず年に1回は行われる報告のケースを「定時決定」といい、6月号にはこの定時決定についての解説が掲載されているわけです。
例えば、以下のような内容が載っています。
- 定時決定の概要
- 報酬の報告対象となる人の要件
- 報告の方法
- 報告にあたっての注意点

特に「定時決定の概要」を読んで、自分の掛金が「何を基に」「いつ決定し」「いつまでその掛金が適用されるのか」を理解しておきましょう。
自分が受け取る給与の金額に直結する超重要事項だと思っています。
定時決定の仕組みは私学共済に限らず、民間企業に勤めた際の「健康保険」にも当てはまります。
つまり、これら私学共済や健康保険などの「社会保険」についての知識は、社会人として働くうえでの基礎知識とも言えるわけです。
しかし、私立学校事務員にしても民間企業にお勤めの人にしても、この社会保険のことをあまり理解しておらず、毎月意識しないまま給与から天引きされているということが多いように思います。

私自身、ファイナンシャルプランナー2級の学習をしていた時に、自分がいかにこうしたことに無知だったのかを思い知りました。
社会保険や税金のように、自分の手元にお金が入ってくる前に引かれてしまうものの仕組みを学ぶことは、自分のお金について興味を持つことにつながり、業務に関する知識の習得に加えて自身の資産形成にも役立ちますので、この月報私学の記事を読んでみてはいかがでしょうか。
標準報酬月額の改定が必要なとき
前述の定時決定のところで、報酬を報告するケースがいくつかあるとお伝えしました。
パターンを列挙すると、以下のようになります。
- 定時決定
- 随時改定
- 産前産後休業・育児休業終了後の標準報酬月額改定
- 即時改定
このケースをまとめたフローチャートが、月報私学6月号には掲載されています。
定時決定は、毎年7月10日が報告期日に設定されているため、報告漏れ等は起こりにくいですが、それ以外のケースは、要件を満たすと随時報告が必要であるため、報告が必要となる要件を理解しておくことが求められます。
そういった要件をある程度理解しておくために、このフローチャートは役立つというのが私の実感です。

先ほど紹介しました定時決定の記事の続きで掲載されていることがほとんどですので、両面一枚に印刷して手元に持っておくことをおすすめします。
一応、実務上の話をしておくと、学校法人向けの給与システムを導入している場合、報告が必要な要件を満たすと自動的に「この人、報酬改定の報告が必要です」みたいなお知らせが出る機能がついていると思います。
それに従えば、報告漏れ等はまず起こりません。
しかし、単純に「よくわからないけど、お知らせが出ているから報告しておこう」というスタンスは事務員としてよくありませんので、きちんと理解したうえで、対応できるように知識を身につけておきましょう。

余談ではありますが、以前の勤め先の人事課の事務員からこんな話を聞きました。
残業代を目一杯請求して給与が一時的に爆上がりした人がいたのですが、当然報酬改定の対象となり、掛金もアップしたため、年間トータルの手取り額で見るとそれほど年収増にはならなかったそうです。
どこかでうまく調整されるシステムになっているようですね。
新トピックス
これは具体的な内容ではありませんが、6月号には共済事業に関するその年度の新たなトピックスが掲載されることが多いように感じています。
例えば令和6年度ですと、「健康保険証の廃止」や「子ども・子育て支援金制度の創設」、令和4年度には「短時間労働者加入要件の変更」といったことが掲載されていました。

年度末に国の予算等が承認され、色々な政策が決まってからその内容を記事にするので6月頃になるのかなと勝手に思っています。
「健康保険証の廃止」や「短時間労働者加入要件の変更」は、実務上に加えて自身の生活にも関わる内容でしたので、大変参考になりました。
年金や社会保険は毎年何かしらの変更があるように思います。
こうした情報は、知らないと損をするということもあるわけです。
しかし、インターネット等で調べてもどれが自分に関係する情報かを見分けることは容易ではありません。
そんなときにこの月報私学の記事を読んでおき、さわりだけでも理解しておくと、情報の取捨選択に役立つというのが私の意見です。
皆さんも、「6月号にはどんな新しいトピックスが載っているか」という興味を持って読んでみてはいかがでしょうか。
ただ、今年の6月号にそのような記事が載っていない可能性があることもご留意ください。
まとめ
前述のとおり、共済事業をメインに月報私学6月号の活用方法を紹介させていただきました。
もちろん、これら以外にも助成事業や私学事業団全体に関わる記事も掲載されているはずですが、まずは自分に身近なものから読んでみることをおすすめします。
そして読んだ後は、何かしらアウトプットするとより理解が深まります。
新入職員や部下へ説明する機会があれば、それを活用することもできますし、そうした機会がない場合でも、「もし、説明するとすれば」という仮定で読んだ内容をまとめてみるという方法も考えられます。
皆さまの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。