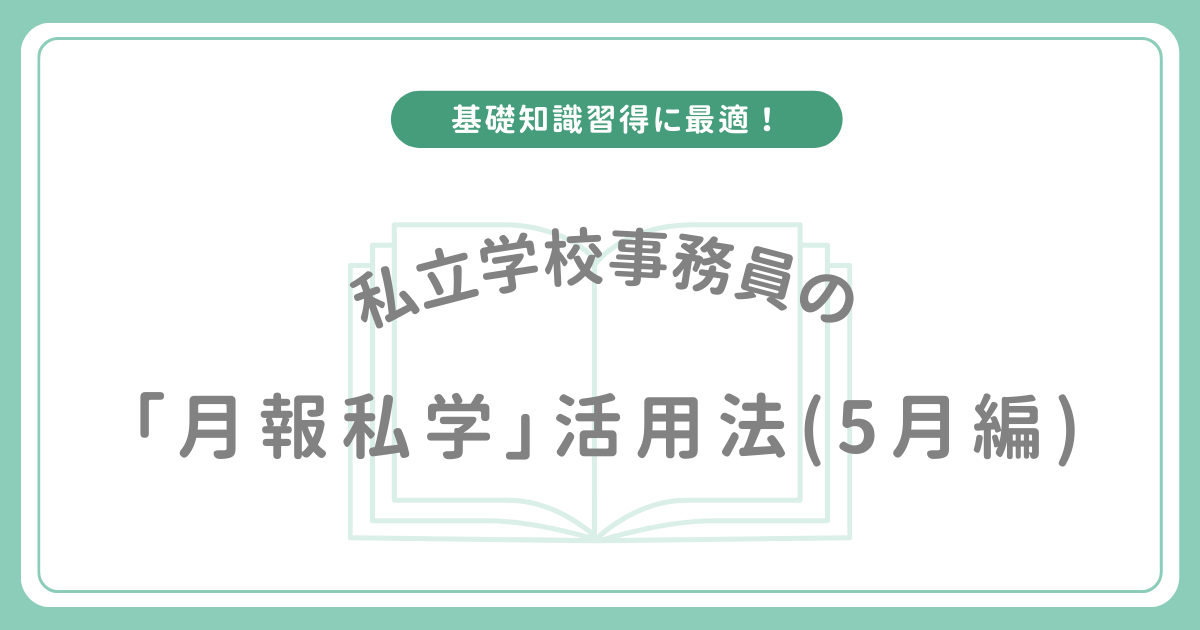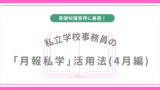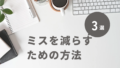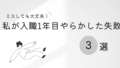この記事は以下のような人を対象としています。
・私立学校事務員として働くうえでの基礎知識を身につけるために、役立つツールを教えてほしい。
以前の記事で、日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)が毎月発行する「月報私学」の4月号の活用法について紹介しました。
今回は、その5月号の活用法の紹介になります。
5月号は5月1日に発行されるため、現時点では内容が不明ですが、例年5月号に掲載されている記事というものがあります。
そうした記事の中で、私が毎年参考にしているものを3つピックアップしたいと思います。
その3つは以下のとおりです。
- 私学事業団融資のご案内
- 報酬等の報告に関するQ&A
- 令和7年度の年金額
「自分の仕事には直接関係ない」と感じる内容もあるかもしれませんが、私立学校で働く立場として知っておくべき情報と考えていますので、ご参考にしていただければと思います。
私学事業団融資のご案内
私立学校において、永続的に教育活動等を行っていくためには、施設設備の新規取得または更新などを計画的に実施する必要があります。
それは以下のような理由があるからです。
- 内的理由:施設設備の老朽化など
- 外的要因:時代の変化への対応など

老朽化を放置していると、学生生徒等は安心安全な環境で教育を受けられませんし、これだけ通信技術等が発達するなかで、そういったことに対応できていない状況では十分な教育を提供できないですよね。
そのため、私立学校事務員として働いていれば、一度は建物の建設など大規模な工事を経験することになります。
その際に重要となるのが「資金の調達」です。
工事にかかる費用のうち、どれだけを自己資金で準備し、残りをどこから調達するかということは、将来の経営状況にも影響を与えます。

もしお金を借りた場合、借りたお金プラス利息を将来に渡って支払っていかなければならないからです。
マイホーム取得のための住宅ローンのようなイメージです。
その調達先の候補として、私学事業団が挙げられます。
月報私学5月号では、融資の対象となる事業や返済期間、金利が1ページにまとまった表が掲載されており、見やすく便利です。
また、今年度からの変更点もまとめられているため、上述に表と合わせて見開き1ページにしてプリントアウトして手元資料として保管しておけば、必要な時に確認することができます。
あわせて、知っておきたい制度が「利子助成制度」です。
この制度は、耐震化事業実施のための費用について、私学事業団融資を利用した場合、特定の要件を満たすことで、文部科学省からの利子助成を受けることができ、実質的な金利の負担が軽減される制度です。

昨今の地震災害の状況や今後の見通し等から、耐震化は急務であるという国の考え方がこうした制度に表れているわけですね。
前述の「永続的な教育活動」における「安心安全な環境での教育の提供」にもつながっています。
この制度についても概要が掲載されており、こういった制度があることも知っておくことで、資金調達に関する知識を広げることができます。
先に述べたとおり、担当業務によっては「融資なんて自分には関係ない」と考える人もいると思います。
しかし、私立学校事務員として「教育を永続的に提供するためには何が必要か」という観点は持っておく必要があることも忘れてはなりません。
その「教育の永続的な提供」のために、施設設備の計画的な更新等が必要であること。
そして、そうした更新等を実施するための財源の調達手段の一つとして私学事業団からの融資があること。
これらの基礎知識として、ぜひ私学事業団融資の概要をおさえておきましょう。

補足ですが、金利は毎月改定されます。
これは私学事業団の「助成事業」のホームページで確認できますので、最新の金利情報を知りたい場合はそちらを確認しましょう。
報酬等の報告に関するQ&A
次は私学共済に関する内容です。
私学共済に加入している私立学校事務員は、共済掛金というものを毎月の給与から天引きで支払うかたちになっています。

この掛金は学校と本人の折半になっています。
新卒で入職された方々は、自分の給与から差し引かれている金額は、実際の掛金額の半額程度ということも知っておきましょう。
この掛金を財源として、様々な共済事業が行われているわけです。
ではこの掛金、どのように金額が決まるのかというと、学校が自校で働く教職員の給与等の金額を私学事業団に報告することで決定します。
この報告業務について、知っておくべきことや私学事業団への問い合わせが多いものなどがここではまとめられています。
内容は主に事務手続きに関することですので、私学共済事務の担当者がメインの対象となります。
「報告すべき金額にはどんなものが含まれるか」や「報告するタイミングはいつか」といったことをわかりやすく端的にまとめているので、ポイントをおさえるために有用と感じています。
私学共済事務担当者以外の方も、毎月給与から引かれているものの仕組みくらいは理解しておくべきと思いますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。

これもいつでも見られるように、プリントアウトするなどして手元に持っておくことをおすすめします。
令和〇年度の年金額
最後も私学共済に関する内容です。
「年金」言われても、ピンとこない人の方が多いかもしれません。
私自身も40代ということで、正直まだ先の話という感覚です。
では、なぜこの記事をチェックしているのかというと、年金に関する知識は社会人としての基礎知識だと考えているからです。
皆さんも、ニュースなどで年金関連の話題をよく耳にしませんか。

例えば少し前には、「在職老齢年金」というキーワードに関するニュースに触れる機会が多かったように記憶しています。
在職老齢年金の詳しい内容は、月報私学の件と直接関係がありませんので説明は割愛しますが、このように年金に関する情報が報道されるケースは少なくないと思います。
しかし、ニュースを見ても、どんな影響があるのかいまいち理解できないということはよくある話です。
そこで、いざ年金について知ろうと思い立ったとしても、普段から意識していないと何から手をつけてよいかわかりません。
そうした際に備えるために活用したいのが、この月報私学5月号に掲載されている内容です。
当該年度の年金額の増減から年金額が変わったことの説明、制度の変更点などがまとめられています。
制度のより詳細な内容等については、私学事業団のホームページを確認する必要がありますが、「ひとまず年金について興味を持つ」という観点からすると、手ごろなボリュームであると感じています。
「年金をもらうのはまだ先の話」と考えずに、今のうちから少しずつ知識を習得する習慣を身につけてみてはいかがでしょうか。
まとめ
毎月定期的に発行される「月報私学」。
私立学校事務員に必要な知識が、インターネットから手軽に入手できる便利なものです。
当然、今回紹介した内容以外のことも掲載されています。
ご自身で実際に確認して、自分なりの読み方を見つけてみてはいかがでしょうか。
コツコツとこうした情報を集めて、知識として習得することが長期的には大きな力になると思いますのでぜひ、習慣化することをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。