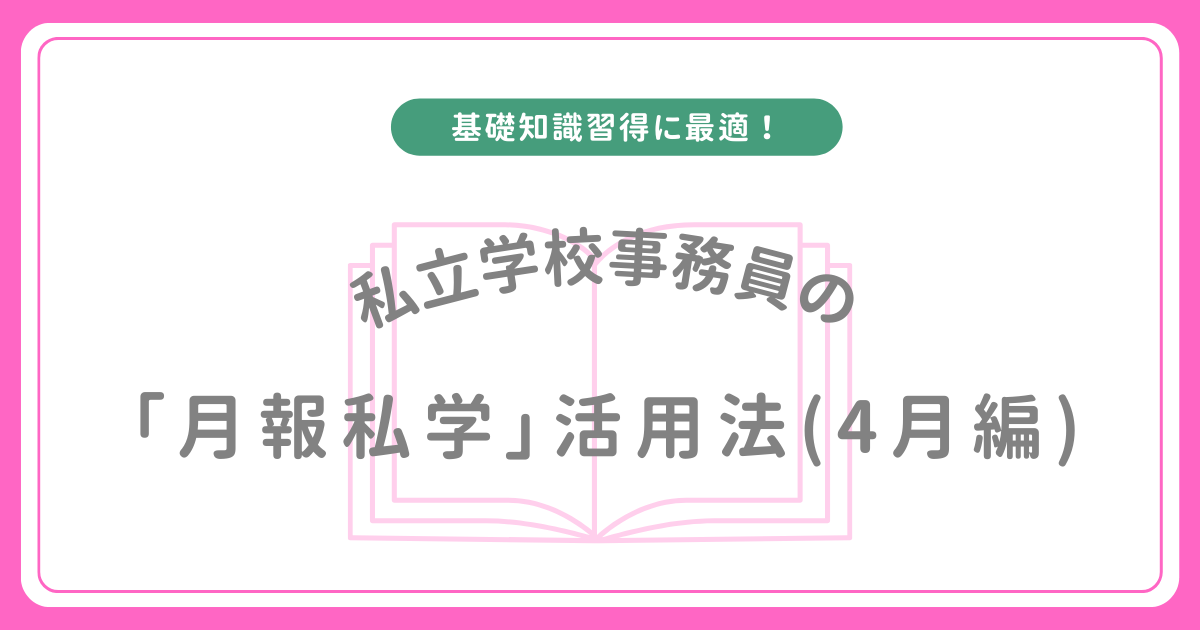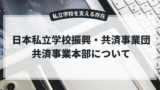この記事は、以下の人を対象としています。
・私立学校事務員に関する基礎知識を身につけたい方
・新入職員に私立学校で働くうえでの基礎知識を教える立場になった方
まもなく新年度をむかえようとしています。
新たに私立学校事務員として働くにあたり、自分がどんな知識を身につけておくべきか気になっている方もいるのではないでしょうか。
また逆に、そうした新入職員に対して、先輩としてどんな知識が必要か教える立場になった方もおられると思います。
そんなお悩みを解決するために役に立つツールがあります。
それが、日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)が毎月発行する「月報私学」です。
私学事業団のホームページにはたくさんのコンテンツがあり、なかなかほしい情報にたどり着けないということがあります。
一方で、この「月報私学」は発行される月にあわせた内容になっており、必要なタイミングで必要な情報を手に入れられる便利なものです。
この「月報私学」を活用すれば、私立学校事務員として働くために基本的な情報をおさえることができます。
私立学校事務員歴20年以上の私が、実際にどのように利用しているか紹介させていただきますので、参考にしていただければと思います。
月報私学とは
まずは、そもそも月報私学とはどういうものなのか紹介します。
これは、毎月1日に私学事業団が発行しているもので、助成事業と共済事業の両方に関わる内容を網羅した情報誌になります。
私学事業団の助成事業と共済事業については、こちらの記事をご参照ください。
事務員に関わらず、私立学校に勤める人に知っておいてほしい情報がまとめられています。
「情報誌」と言いましたが、学校法人の所在地に毎月紙媒体で送られてきます。
「学校法人の所在地」に送られてくるため、勤め先の学校が学校法人本部の場所から離れている場合は、学校には届きません。

例えば本部が東京で、勤め先の学校が大阪にある場合、月報私学は東京に届くということです。
では、そのような場合は読むことができないのかというと、そんなことはありません。
毎月1日になると、私学事業団ホームページに最新号が掲載される仕組みになっています。
参考までに、月報私学のリンクを掲載しておきます。
月報私学(私学事業団ホームページへのリンク)
過去のアーカイブも見ることができますので、後ほど紹介する財務データ等の収集にも役立ちます。
以上が月報私学の概要です。
そして、この月報私学は例えば「4月号には〇〇に関する情報が載っている」といった月ごとの傾向があります。
以降、まずは私が4月号でチェックしているポイントを紹介させていただきます。
4月号の記事のチェックポイント
月報私学4月号に掲載される頻度が高い記事で、私がチェックしているものは以下の3つです。
- 療養費・家族療養費の請求手続き
- 加入者貸付のご案内
- 私学共済制度のあらまし
これらの概要や活用のポイントを解説します。
療養費・家族療養費の請求手続き
「療養費」とは大まかに言うと、
- やむを得ない事情で保険証が使えなかった
- そのため、医療費を全額自己負担で支払った
こういったケースで、自己負担額を超える部分のことを指します。

保険証(私学共済に場合は加入者証と言います)を使用していれば、自己負担は3割で済むところ、10割負担したので差額7割を「療養費」として請求できるわけです。
全額自己負担したのが本人の場合を「療養費」、本人の被扶養者(妻や子など)の場合を「家族療養費」と言います。
この療養費の請求、4月に発生する確率が他の月に比べてかなり高いです。
どの私立学校も4月に新たな教員や事務員を受け入れることが多いため、全国の私立学校が私学共済に対し、同時期に集中して新たな加入者証等の発行を申請します。
そのため、他の月より加入者証等の発行に時間がかかり、届くまでの間、新入職者は手元に加入者証等がない状態が発生するわけです。

私が対応した中では、小さなお子様がおられる場合は医療機関にかかるケースが多いため、特に家族療養費が発生しやすいような印象があります。
この状況を想定して、月報私学の4月号には療養費等の請求手続きやよくある質問を1ページにまとめて掲載されています。
その当該ページをプリントアウトしておき、新入職者対象のオリエンテーション等のときに配布して説明しておくようにしています。

私はさらに手元にこのページをプリントアウトしたものを準備しておき、お尋ねに来られた際にはそれをスマホ等で撮ってもらって、医療機関窓口等で見せるようにお伝えしています。
加入者証等はマイナ保険証に変わるため、今後はこのような対応は必要ないかもしれませんが、こうした特定月特有の事象に対する有益な情報が掲載されていることがありますので、チェックしておきましょう。
加入者貸付のご案内
私学共済は加入者に対し、「教育」や「住宅」など目的の応じた貸付を実施しています。
もちろん入職していきなり、お金を借りようとする人はまずいませんが、このような制度があるという概要紹介のために利用しています。
これもプリントアウトしておき、説明資料として対象者に配布しています。

私の場合、概要は資料を見ていただくにとどめ、以下の3点を特に強調して説明するようにしています。
- 貸付を受けるためには、私学共済の加入者期間が引き続き1年以上(住宅貸付は5年以上)なければならない
- 貸付の要件等詳細は私学事業団のホームページで確認する必要がある
- 返済は給与天引きになる
加えて、自分自身の資料としても手元にキープしています。
- 貸付申込の流れがフローチャートでわかりやすく整理されている
- いつ申請すればいつお金が送金されるかなどスケジュールを確認できる
といったように事務手続き上も有用な情報が1枚にまとめられているからです。
特に「今申請したらいつ頃お金がもらえるか」は質問されやすいので、準備しておいた方がよいと思います。
私学共済制度のあらまし
この記事は、新入職員の方にこれから加入する「私学共済」というものがどういうものかを理解していただくために非常に有益な内容になっています。
例えば、
- ケガや病気等が対象の「短期給付事業」ではどんな給付の種類があるのか
- 加入者の健康で充実した日常をサポートする「福祉事業」はどんなものか
など、新入職者として知っておいた方がよい情報がプリント2枚程度にまとめられています。

私は2ページを1枚集約して、説明資料として活用しています。
そのうえで、以下の3点について説明しています。
- 負担額が一定額を越えた場合でも、基本的に加入者証を使って受診すれば手続きなしで自動的にお金が返ってくる
- 人間ドックの利用料補助がある
- 私学共済独自の積立貯金や保険などがあり、募集時期が来ればこちらから案内する
また、私学共済事務を担当する事務員の方は、共済業務に関する問い合わせ先一覧も掲載されているため、プリントアウトして手元に保管しておくことをおすすめします。
まとめ
私立学校の教職員として、新しい環境での生活が始まる際には不安に感じることが多いと思います。
その不安の解消に役立つ情報が、月報私学4月号には掲載されています。
まずは、来月発行の4月号を一読し、そのうえで各月について毎回発行のタイミングでチェックしてみてはいかがでしょうか。
ご自身の知識の習得にも大変役立つと思います。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。