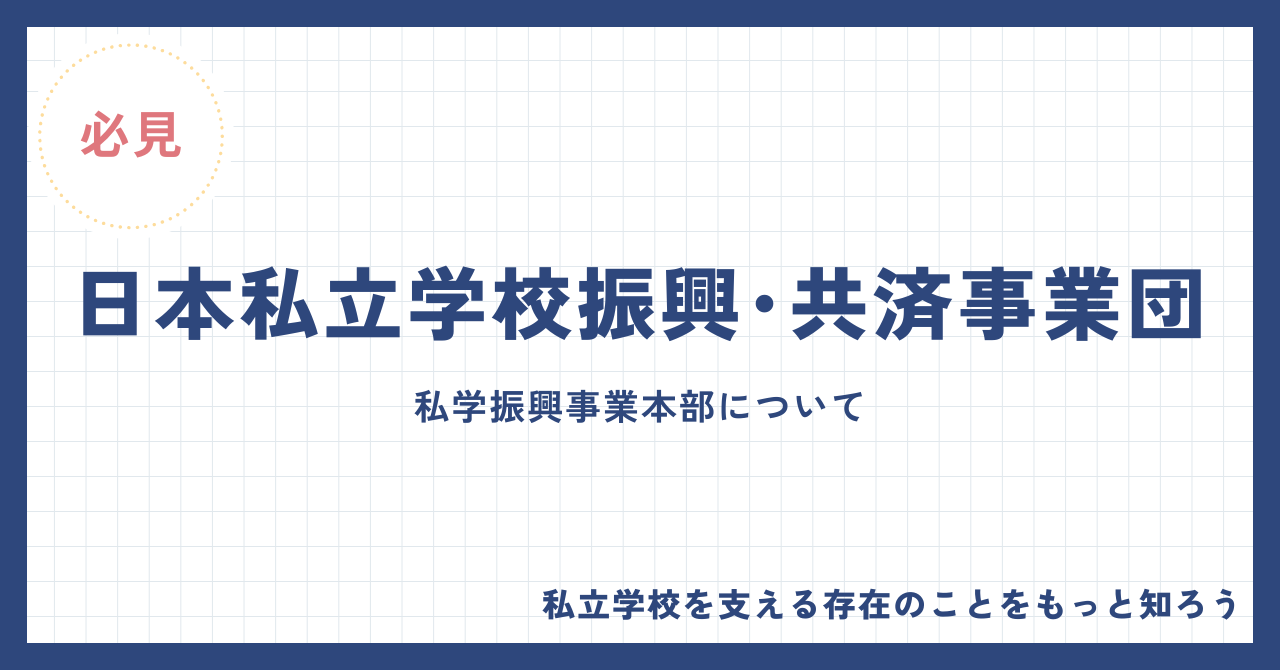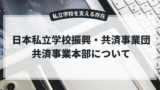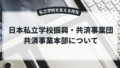この記事の目的は以下のとおりです。
・私学事業団の私学振興事業本部について理解する
・私学振興事業本部の助成業務の内容を理解する
前回の記事に引き続き、日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)の業務について解説します。
今回は私学事業団の業務のうち、補助金や融資、情報提供などを通じて、私立学校の経営を支援する「助成業務」についてです。
私立学校に勤める者として、どのような支援を受けることができるのか理解しておく必要がありますので、この記事を読んで知識を身につけておきましょう。
【再確認】私学事業団の組織構成
前回の記事にも掲載しましたが、以降の内容を理解しやすくするために、私学事業団の組織構成を再掲します。
| 共済事業本部 | 私学振興事業本部 |
|---|---|
| <共済業務>:私立学校教職員の福利厚生 | <助成業務>:私立学校の経営支援 |
| ・短期給付事業 ・福祉事業 ・年金等給付事業 | ・補助事業 ・貸付事業 ・助成事業 ・寄付金事業 ・減免資金交付事業 ・経営支援・情報提供事業 |
ご覧いただいたとおり、私学振興事業本部は様々な手段によって私立学校の経営をサポートしています。
以降、それぞれの事業の中から、特に関わりの深いものをピックアップして確認していきましょう。
【有益な情報で支援】経営支援・情報提供事業
私学振興事業本部は独自の調査や取材等により、私立学校経営に関する情報を数多く保有しています。
その保有する情報を全国の私立学校に提供することで、経営をサポートしています。
調査の中でも、私立学校事務員にとって特に馴染み深いものが「学校法人等基礎調査」です。
毎年4月に調査依頼があり、生徒数や教職員数、財務状況などを回答する内容となっています。
この調査で集めた情報を加工・分析して、提供しています。
その提供の方法としては、大きく分けて「経営相談」と「情報発信」の2つがあります。
経営相談は文字どおり、私学事業団の職員が経営上の問題点について、私立学校へアドバイス等を行うものです。
私学事業団では、この経営相談のための専門部署を設けており、経営相談は原則無料となっています。

私の以前の勤め先は経営困難な状況ではありませんでしたが、経営相談を受けていました。経営上の悩みがあれば、とりあえず相談してみるという考え方でよいと思います。
もう1つの方法である「情報発信」は、冊子の刊行やホームページへの掲載、セミナーの開催によって行われています。 私が仕事上で特に活用しているものを以下に列挙します。
- 今日の私学財政
- 自己診断チェックリスト
- 経営判断指標
- 入学志願動向
「今日の私学財政」以外は私学振興事業本部のホームページから誰でも見ることができます。
自校の財政状況の説明などの際に、自分の説明内容をより説得力のあるものにするために大変有益であると思っています。
毎年、ニュース等で「定員割れの学校」や「経営困難な学校」といった情報を耳にする機会があると思いますが、その根拠データは上述の「今日の私学財政」や「入学志願動向」がもとになっていることがほとんどです。
その他にも、特色のある教育や経営の取組みをしている私立学校の事例集など、お役立ち情報がたくさんホームページで公開されていますので、一読することをおすすめします。
【お金で支援】貸付(融資)、補助金事業
施設の新築・増改築や大型の設備の整備など、多額の費用が必要な事業を私立学校が実施する際に、融資をすることで経営を支援しています。
学校の種別(大学や高校など)に関係なく、学校法人であれば利用できます。

以前に私学事業団の職員の方とお話した際に、「私たちは国から補助を受けずに、融資の利息で人件費や事務費と賄っている。
だから「私学あっての事業団」という気持ちで対応しています」という旨のことをおっしゃっていました。
私学事業団職員の私学に対する思いを感じた瞬間でした。
一方、私立の大学、短期大学、高等専門学校が対象ですが、人件費等を補助する「私立大学等経常費補助金」の交付業務も行っています。
また、近年では「高等教育の修学支援制度」が始まり、それに伴う授業料等減免費交付金に関する業務も担っています。
補助金は多くの私立大学等において、学費に続き2番目に大きな収入源であるため、申請手続きにミスや漏れがないように、担当者は私学事業団に確認をとりながら良好な関係を構築することが重要となります。

なお、私立高校は直接私学事業団から補助金の交付を受けることはありませんので、この補助金業務においては関わる機会がありません。
【間接的に支援】寄付金事業
今まで紹介してきた業務は、お金や情報によって直接的に私立学校を支援していましたが、私立学校を取り巻く関係者(企業等)を通じて支援するものもあります。
それが寄付金事業です。
事業名だけ聞くと、私立学校へ私学事業団が寄付することをイメージしますが、そうではありません。
私立学校(学校法人)への寄付を希望する企業等法人に対して、税制上の優遇が受けられる事業を行っており、これを「受配者指定寄付金制度」といいます。
詳しい説明は割愛しますが、寄付者と私立学校、私学事業団の三者間でやりとりをすることにより、寄付者は法人税法上、支出した寄付金全額を損金の額に算入することが認められます。

「損金って何?」と思うかもしれませんが、ここではその言葉の意味は置いておき、「企業が私立学校に寄付をすると、税金の負担を少なくできる」とだけ理解すれば問題ありません。
企業等法人が寄付をしやすい状況を整備することで、私立学校は寄付金を集めやすくなり、学費や補助金以外の新たな財源を確保することに結びつく効果が期待できるわけです。
なお、私学事業団の業務ではありませんが、個人が私立学校に寄付をした場合に税制上の優遇措置が受けられる「特定公益増進法人に対する寄付金」という制度がありますので、あわせて覚えておきましょう。
私立学校に勤めていると「創立〇周年」といった記念事業を実施することがあり、その際には広く寄付金を募るケースが多いです。
寄付をすることに対する心理的なハードルを少しでも下げて、より多くの寄付金が集められるよう、私立学校事務員は上述の制度について認識しておく必要があります。
まとめ
前回の記事とあわせて、私立学校やそこに勤める個人のことまでサポートする存在であることがお分かりいただけたかと思います。
私学教育の振興を、私たちと一緒に担うパートナーである私学事業団のことを理解する一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。