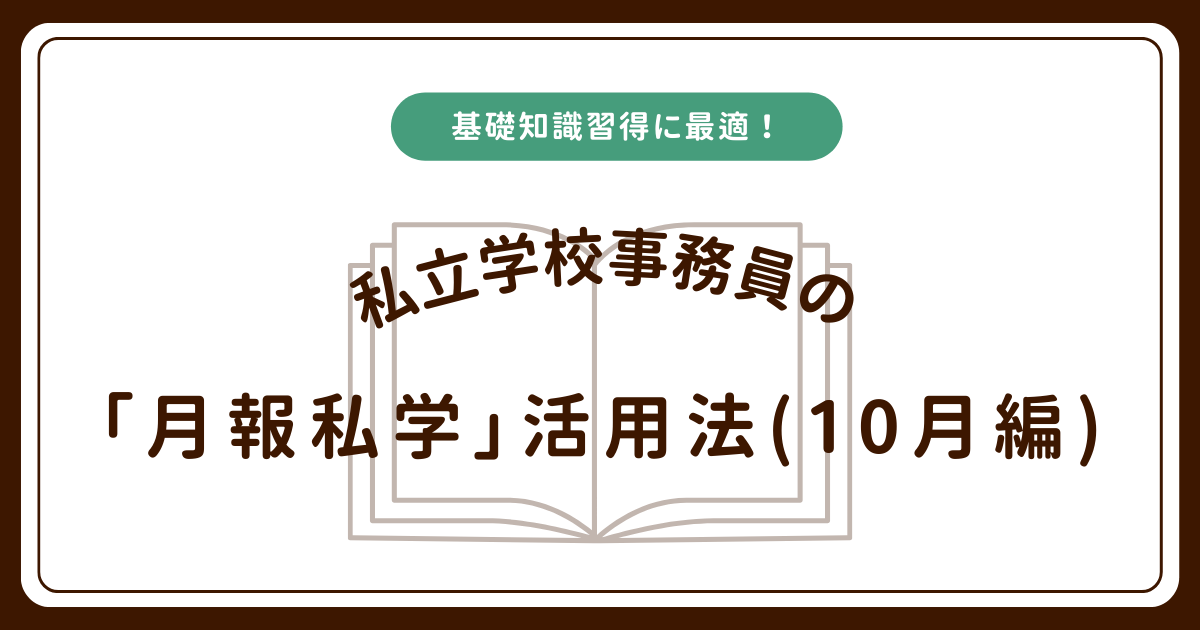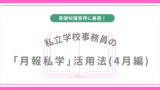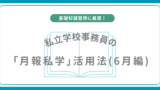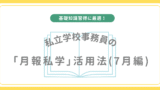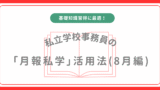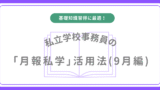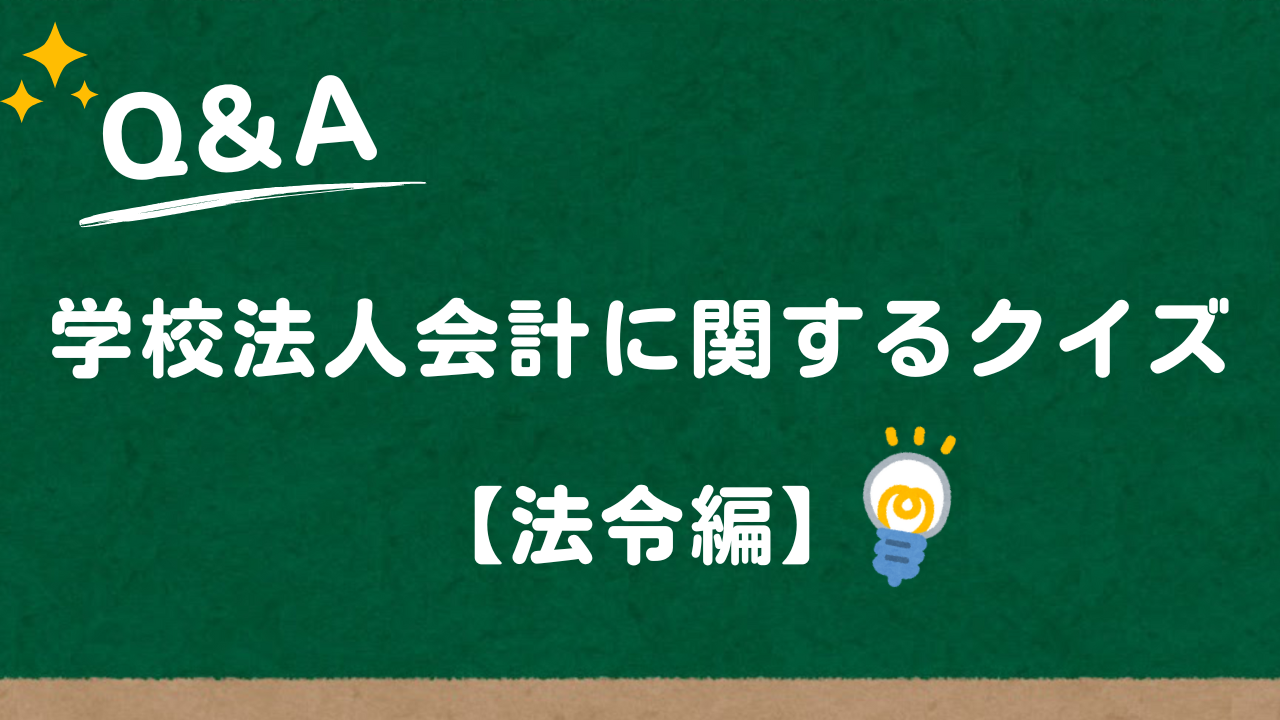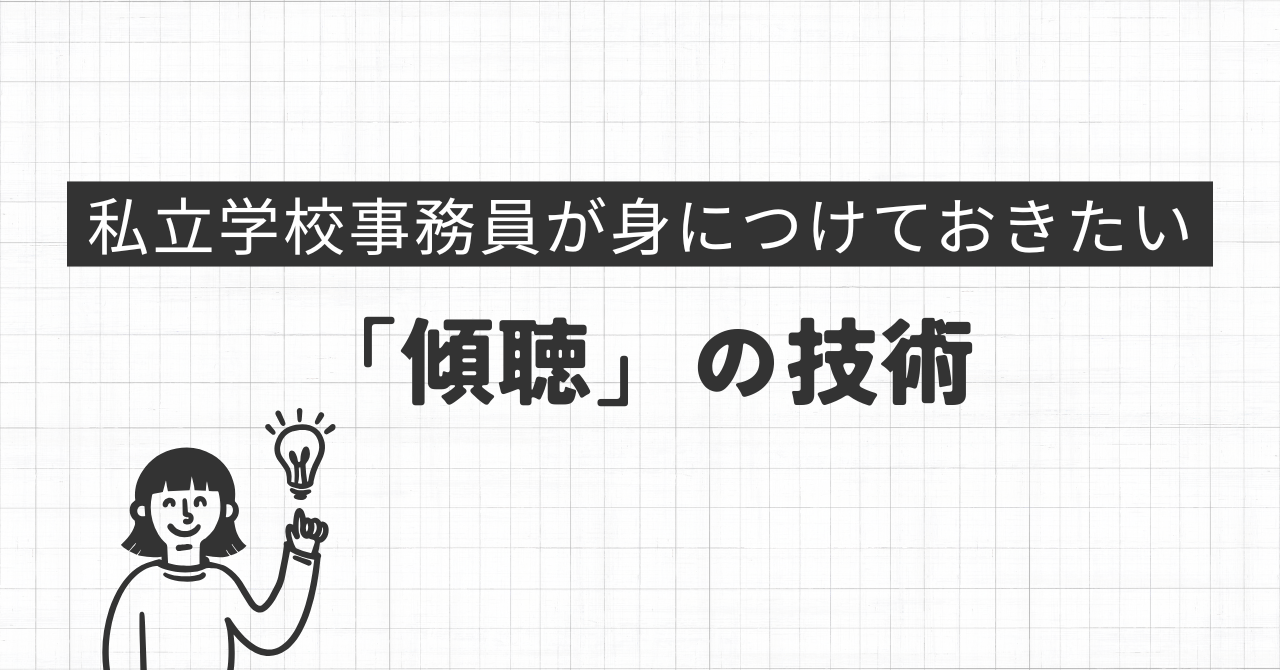この記事は以下のような人を対象としています。
・私立学校事務員として働くうえでの基礎知識を身につけるために、役立つツールを教えてほしい。
これまで、日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)が毎月発行する「月報私学」の各月ごとの活用法を紹介してきました。
今回は、その続きにあたる10月号の活用法の紹介になります。
10月号は10月1日に発行されるため、現時点では内容が不明ですが、例年10月号に掲載されている記事というものがあります。
そうした記事の中で、私が毎年参考にしているものを2つピックアップしたいと思います。
その2つは、以下のとおりです。
- 令和〇年度 私学助成関係予算の概算要求
- 令和△年度 私立大学等経常費補助金 配分方法の主な変更点等について
どちらも学校法人にとって貴重な収入源となる「補助金」に関する情報ですので、しっかりと内容をおさえておきましょう。
ご参考になれば幸いです。
なお、前述のとおり本年度の10月号の内容は現時点でわかりませんので、掲載されていない場合もあります。その点はご容赦ください。
令和〇年度 私学助成関係予算の概算要求
令和8年度の概算要求については、文部科学省のホームページにも情報が掲載されていますので、参考までにリンクを貼っておきます。
令和8年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧
(文部科学省のホームページへのリンク)
私はこの記事を見る際に2つの視点を意識しています。
その2つとは以下のとおりです。
- 当該年度のポイント
- 過年度と比較してのポイント
試しに、令和6(2024)年度概算要求(以下、R6概算要求)と令和7(2025)年度概算要求(以下、R7概算要求)の月報私学の記事を参考にしてみましょう。
視点① 当該年度のポイント
この視点では、単純に当該年度の記事だけを読み込みます。
まず、見るべきは「新規」という文字がないかどうか。
ここが当該年度の一番のポイントとなっている場合が多いからです。
例えばR6概算要求の記事では、私立大学等経常費補助のなかで「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」という項目に「新規」の文字が付されていました。
記事を読んでみると、この項目のポイントとして以下の2つが挙げられています。
- 戦略的な経営改革
- 複数大学等の連携による機能の共同化・高度化
この記事が掲載された段階では、正直なところ具体的な内容まで予測することは難しいと思います。
ですので、ここではひとまず、
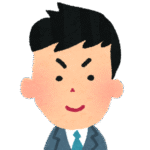
こんな新規項目ができたのか。
ぐらいで留めておいて問題ありません。
そのあとのフォローを忘れないようにしましょう。
具体的には、その項目について補助金の募集があった際に、その内容を確認するわけです。
これも先ほどの「少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援」を例にして見てみます。
大学等には、詳細な要件等が記載された募集要項が送られてくると思いますので、それを確認してみましょう。

残念ながら高校事務室勤務の私の手元にはそのような資料はありませんので、ここでは詳細については触れません。
直接、補助金申請を担当していない人でも、申請担当者に言えば見せてくれると思いますので、あらかじめ声をかけておくことをおすすめします。
なお、文部科学省のホームページに当該補助の概要等が掲載されていましたので、参考までにリンクを貼っておきます。
少子化時代を支える新たな私立大学等の経営改革支援
(文部科学省ホームページへのリンク)
これを見る限りでは、
- 戦略的な経営改革:地域社会等との連携&専門人材の育成
- 複数大学等の連携による機能の共同化・高度化:文字どおり
といった内容のように推察されます。

選定結果の資料を見ると、「原則5年間、継続的に支援」と書いていますね。
単年度交付しておしまい、というわけではないようです。
このような感じで、
- 新規項目のチェック
- その答え合わせ
といった見方をおすすめします。
補助金申請担当でなくても、行政の方針や動向といったことを意識して業務にあたることが大切です。
そのきっかけとして、月報私学の記事を活用してみましょう。
ちなみに、余談ですが令和8年度の概算要求資料のなかには「イノベーション創出に向けた教育研究環境整備支援」という新規項目が入っていました。
興味がある方は、10月号の記事(掲載されていた場合)を確認してみてください。
視点② 過年度と比較してのポイント
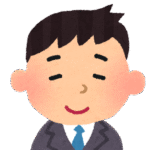
とは言っても、今回の概算要求には新規項目がないよ。
というパターンもあります。
実際、R7概算要求の記事には「新規」の文字はありませんでした。
こんな時に役立つのが「過年度との比較」です。
実際にR6概算要求とR7概算要求を比べてみましょう。
見るべきところとしては、やはり要求額や前年度予算額の増減の部分になります。

細かな項目については、資料を作る人によって記載されたりされなかったりするので、参考程度に見ています。
校事務室勤務の私としては、昨年度記事を見た時に、私立高等学校等経常費助成費等補助の減額が気になりました。
特に一般補助が、R6概算要求では875億円であるのに対し、R7概算要求では868億円と7億円の減額となっています。
ただ、資料をよく見ると「幼児児童生徒1人当たり単価の増額」と記載されていたので、

単価は増額されたけど、それ以上に幼児児童生徒の数が減ったから全体として予算額が減少したのかな。
と、思ったりもしました。
このように、色々と仮説を立てながら比較してくと、私立学校を取り巻く環境について理解が深まると思いますので、取り組んでみてはいかがでしょうか。
あとは、先に少しだけ触れました項目について。
一応ここも確認しています。
これも一例ですが、R6概算要求とR7概算要求の資料を比較すると、
- R6概算要求:私立高等学校等ICT教育設備整備費
- R7概算要求:私立高等学校等の教育DXの推進
という項目の違いに目がいきました。
そこでR7概算要求の方の記事をよく見ると、R6概算要求の方には記載のない「校内LAN」という文言を発見。
ちょうど、校内LANの整備を計画していたので、担当教員と連携して補助金申請の準備を進め、実際令和7年度に補助金の採択を受けることができました。
校内LANの補助自体は令和6年度から継続されていたのかもしれませんが、こうした記事をきっかけに気づくこともありますので、よく見てみるようにしてみましょう。
令和△年度 私立大学等経常費補助金 配分方法の主な変更点等について
具体的な変更点等については、おそらく大学等の補助金申請担当者はすでに私学事業団が開催している説明会などで知っているものと推察されます。
したがって、そうした人たちにとってはあまり目新しい内容ではないでしょう。
そうした状況からすると、大学等の事務員で直接補助金申請に関わらない人や高校事務室勤務の人にとっての情報と言えると思います。
では、そのような人たちはどのようにしてこの記事を読めばいいのでしょうか。
私の実体験として以下の2パターンを紹介します。
- 大学に勤めている場合:補助金申請担当者に自校への影響を確認する
- 高校に勤めている場合:国の教育行政に対する基本姿勢を理解する
前者は、とりあえず記事を片手に担当者をつかまえて、

これってうちにどんな影響があった?
と尋ねてみるというものです。
「うちは関係なかった」とか「〇〇といった対応が必要」などの返事があると思うので、そうした情報を基に、自校の様子を把握してみましょう。
そもそもの変更点の意味が分からない場合は、そのことを尋ねてみてもいいと思います。
大学は人事異動により様々な部署で働く可能性があります。
こうしたヒアリングを通じて大学のことや補助金のことを理解しておくと、突然の異動があった際に役立つかもしれません。
私はこの方法を実践し、ある補助項目について事前に担当者から情報を収集していたおかげで、実際にこの補助項目の担当部署に異動になった際、

これは補助金対象の事業だ。
と、理解したうえで業務にあたることができました。
補助金に直接関係する業務は、他の業務よりも根拠資料の整備などに一層注意を払う必要があるので、事前に把握しておくことが大切だと私は思っています。
そのために月報私学を活用しましょう。
一方後者の方は、おおまかな傾向をつかむといったイメージになります。
大学や短期大学は国(文部科学省)が管轄ですので、国の教育行政に対する考え方が色濃く表れるというのが私の考えです。
だから、変更点等を確認することにより、

次はこんなことに力を入れようとしているのか。
といった気づきが得られると思っています。
記事の内容だけでは詳細をつかむことはできませんが、項目だけでも見ておいて損はないというのが実感です。
まとめ
10月号は例年「補助金」がメインの内容となっています。
冒頭にも述べましたとおり、補助金は私立学校にとって大切な収入源の1つです。
国の動向などを適切に把握することが、補助金獲得に結び付くこともあります。
またお金の面以外に、そうした補助金獲得を目指すことが、勤め先の教育改善につながる可能性もあるわけです。
ぜひ10月号の記事を確認してみましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました