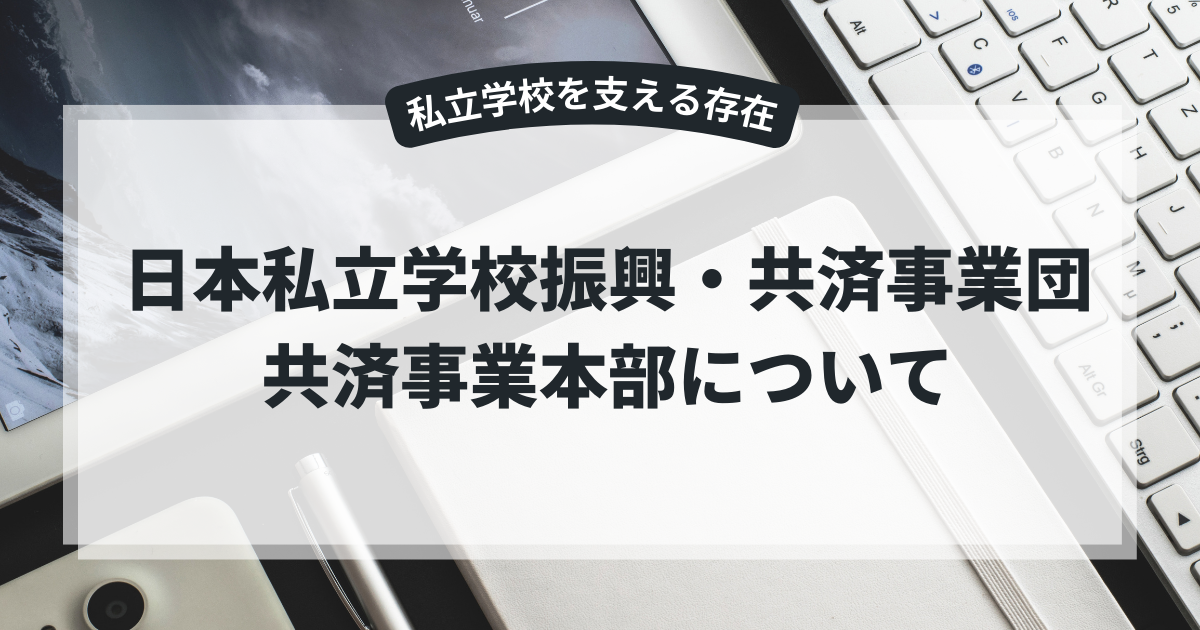この記事の目的は以下のとおりです。
・日本私立学校振興・共済事業団について理解する
・私学共済加入の基本事項を確認する
・共済業務の概要を理解する
私立学校事務員として働く上で、つながりの深い関係にある外部団体の1つが「日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)」です。
私立学校の経営のサポートやそこで働く教職員の福利厚生など、大切な役割を任なっている存在です。
担当業務によっては私学事業団と直接やりとりをすることもありますので、どのような団体か概要だけでもこの記事を読んで理解しておきましょう。
【基本】私学事業団の組織構成
私学事業団の組織は大きく分けて「共済事業本部」と「私学振興事業本部」の2つに分けられます。
そして「共済事業本部」が担当する業務を「共済業務」、「私学振興事業本部」が担当する業務を「助成業務」と呼びます。
| 共済事業本部 | 私学振興事業本部 |
|---|---|
| <共済業務>:私立学校教職員の福利厚生 | <助成業務>:私立学校の経営支援 |
| ・短期給付事業 ・福祉事業 ・年金等給付事業 | ・補助事業 ・貸付事業 ・助成事業 ・寄付金事業 ・減免資金交付事業 ・経営支援・情報提供事業 |

私立高校に勤める人は前者の「共済業務」のイメージが強いと思います。
もともとは「共済事業本部」と「私学振興事業本部」は別々の団体であるため、窓口も分かれています。
問い合わせをする際には注意が必要です。
ちなみに、共済事業本部の方への電話はかなりつながりにくいです。
問い合わせた経験がある私立学校事務員の方は、共感していただけると思います。
この2つの組織の活動により、私立学校の振興を支えています。
以降は「共済業務」の概要について紹介し、次回の記事で「助成業務」の概要を紹介します。
【前提】私学共済への加入
共済業務の対象となるためには、私学共済へ加入する必要があります。
しかし、私立学校の教職員全員が自動的に私学共済に加入できるというわけではありません。
加入には条件がありますが、基本的に「専任」として採用されると私学共済に加入できます。
私学共済に加入する私学教職員を「加入者」、加入者に養われている人(配偶者や子など)で私学共済に加入する人を「被扶養者」と言います。
加入すると「加入者証」「加入者被扶養者証」が交付されます。民間企業等でいう「保険証」にあたります。
ただし、現在はマイナンバーカードへの移行の関係で、新規交付されなくなりました。
逆に退職する場合は、加入者証と加入者被扶養者証は私学事業団に返さなければなりませんが、この加入者証等の返却が個人的には面倒な業務の1つと思っています。
退職する日までは加入者証等は使用できますので、返却せずにそのまま退職を迎えるケースが多いです。
そのため、退職後に返却することを失念してしまいがちです。

ただ、これもマイナンバーカードへの移行の関係で、令和7年12月2日以降、加入者証等は回収して私学事業団に返納する必要がなくなります。
悩みごとが1つ減って、ほっとしています。
【病気やケガのサポート】短期給付事業
民間企業でいうところの「健康保険」にあたるものです。
短期給付事業の主な内容は以下のとおりです。
- 加入者が病気やケガ、出産等をした際の補助
- 加入者が病気やケガ、出産等をしたことで、仕事を休み、給料が減額となった場合の補助
- 被扶養者が病気やケガ、出産等をした際の補助
教職員本人やその配偶者、子が病気やケガをした際には、私学事業団がサポートしてくれるという理解で問題ありません。
これら補助の多くは、医療機関で加入者証を使用することで、その情報が自動的に私学事業団に連絡されるため、特段の手続きなしに受けることができます。
一方、結婚時に給付される「結婚手当金」や病気等で仕事を休職した際に給付される「傷病手当金」のように、私学事業団に情報が入らないようなものは、学校からの申請が必要となります。
私個人の主観ですが、短期給付事業に関わる業務のうち、以下の3つは申請が必要と覚えておくとスムーズに処理できます。
- 限度額適用認定証の申請
- 傷病手当金の申請
- 結婚手当金、出産手当金の申請

それぞれ頻度はそれほど高くありませんので、前回に申請した際の書類を時系列にファイルしておき、手元に管理しておくことをおすすめします。
【日々の生活をサポート】福祉事業
病気やケガ以外で日常生活をサポートする事業です。
福祉事業の主な内容は以下のとおりです。
- 共済積立貯金事業
- 貸付事業
- 人間ドック利用料補助
他にも「ガーデンパレス」というホテルの運営や、定期保険や拠出型企業年金保険事業なども行っていますが、とりわけ上述の3つが処理する機会が多いというのが私個人の印象です。
特に共済積立貯金は利用者が多いように思います。
特徴としては「給料から天引きされる」「引き出しに時間がかかる」という点が挙げられます。

自動的に給与から差し引かれて貯金でき、なおかつ引き出したいと思っても、お金が私学共済側で管理されているため、すぐに引き出せないというところが、意志の弱い私にも向いていると感じています。
人間ドック利用料補助も毎年申請できるため、活用している人が多いように思います。
以前は2年に1回しか申請できませんでしたが、最近改正されました。
上限額20,000円で、税抜金額の半額が補助されます。
あと、業務とは関係ありませんが、私立学校に入職した際に「私学共済ブック」という冊子が配布されます。
この冊子に「厚生施設利用補助券」というものがついており、それを使って様々な施設の利用料等の割引を受けることができます。
施設によってはかなりお得な割引を受けられるので、活用しています。
【老後の生活をサポート】年金等給付事業
老後の年金に関わる事業です。
この事業については、退職後に支給される年金に関わるものであるため、在職中に特段何かを申請するといったことは発生しないと思います。
少なくとも私は今まで一度もこの事業に関わる手続きを処理したことはありません。
私学事業団から送られてくる「ねんきん定期便」を対象者に配布する程度です。
私学事業団は年金の運用・管理も担当しているということだけ理解しておけば問題ないと思います。
まとめ
私たち私立学校教職員の健康やその他日常生活をサポートしている「共済事業本部」のことを理解する一助になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。