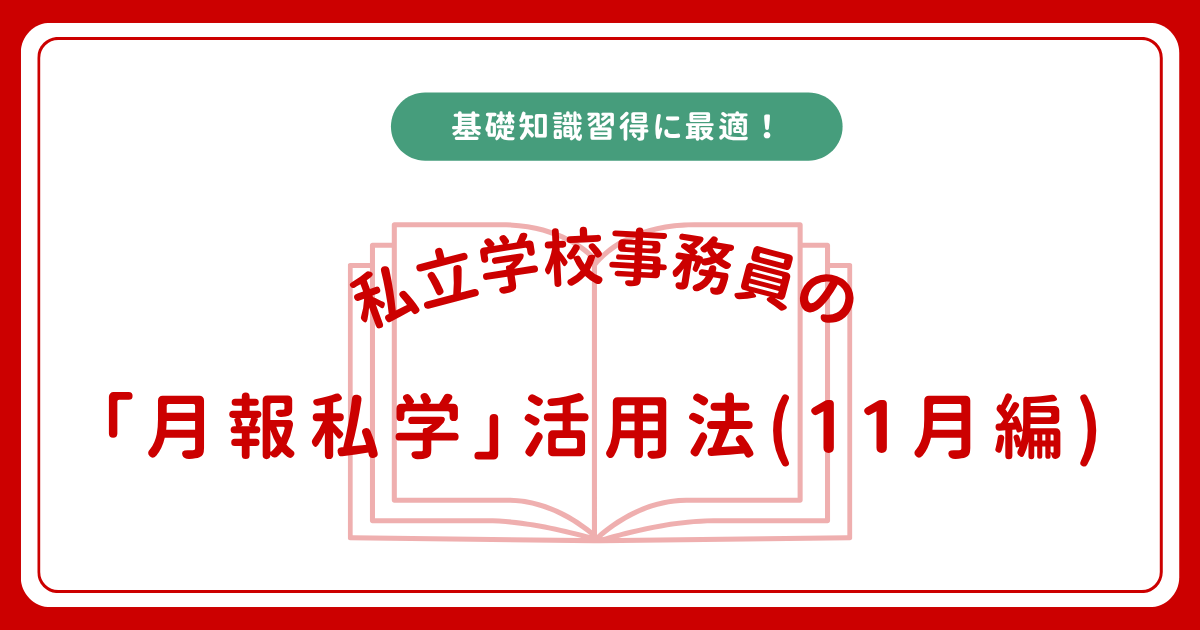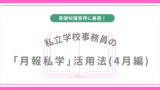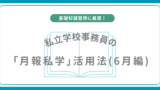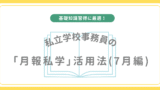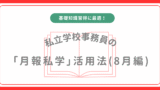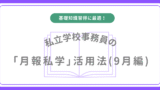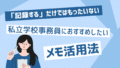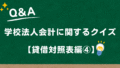この記事は以下のような人を対象としています。
・私立学校事務員として働くうえでの基礎知識を身につけるために、役立つツールを教えてほしい。
これまで、日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)が毎月発行する「月報私学」の各月ごとの活用法を紹介してきました。
今回は、その続きにあたる11月号の活用法の紹介になります。
11月号は11月1日に発行されるため、現時点では内容が不明ですが、例年11月号に掲載されている記事というものがあります。
そうした記事の中で、私が毎年参考にしているものを3つピックアップしたいと思います。
その3つは、以下のとおりです。
- 私立幼稚園の財務状況
- 職務上、通勤途上の傷病や交通事故等で受診するには
- シリーズ学校訪問記
学校の経営上のことから教職員の健康に関することまで、幅広い内容となっています。
ご参考になれば幸いです。
なお、前述のとおり本年度の11月号の内容は現時点でわかりませんので、掲載されていない場合もあります。その点はご容赦ください。
【私立幼稚園の財務状況】
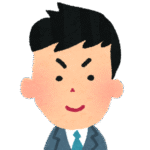
幼稚園の財務状況。注目したことがなかった。
こういう人、おられるのではないでしょうか。
ニュース等で取り上げられるのは主に大学や短期大学、場合によっては高等学校が扱われることもあるといった感じというのが私の印象です。
所管の違い(国と地方公共団体等)や規模の違いなど、理由は様々考えられますが、何にせよ幼稚園の財政状況に関する情報に触れる機会は少ないように思います。
加えて、私立幼稚園に勤めている人または幼稚園を設置する学校法人に勤めている人以外の人からすれば、そもそも興味を持ちにくいといったことも推察されます。

私は以前の勤め先と今の勤め先、どちらも幼稚園を設置する学校法人に勤めているので、幼稚園の財政状況についてはそれなりの興味を持っています。
- 情報量が少ない
- 興味を持ちにくい
こうした要因により、幼稚園の財政状況とは縁がない私立学校事務員の方は多いと私自身考えているわけです。
そう考えると、この月報私学11月号で提供される情報は、「情報量が少ない」という要因を解消する貴重な存在であると言えます。
そんなせっかくの機会ですので、チェックしておきましょう。
見るポイントとしては、
- 過年度との比較
- 他の学校種別(大学や高校など)との比較
が挙げられます。
視点① 過年度との比較
こちらについては、基本的に記事の内容が5年前の財政状況との比較になっているので確認しやすいと思われます。
私がチェックするのは、
- 事業活動収支差額比率(基本金組入前当年度収支差額/事業活動収入)
- 流動比率(流動資産/流動負債)
- 基本金組入前当年度収支差額がマイナスの法人数
の3点です。
とりあえず、この3点を見てトレンドを確認します。
昨年度の11月号掲載分を例に見てみましょう。
- 事業活動収支差額比率:下降
- 流動比率:上昇
- 基本金組入前当年度収支差額がマイナスの法人数:上昇

全体として私立幼稚園も厳しい財政状況にあることが見て取れますね。
このトレンドを、自分の勤める学校法人が設置する幼稚園の状況と比べてみるわけです。
視点② 他の学校種別との比較
今度は、大学や高校などの財政状況と比較してみます。
比較するポイントは、先ほどの「過年度との比較」で挙げた項目のうち、「事業活動収支差額比率」と「基本金組入前当年度収支差額がマイナスの法人数」の2つです。
これも、直近の月報私学を例に見てみましょう。
大学や短期大学の令和4年度決算集計データは、2024年2月号の月報私学に掲載されていますので、そちらの数値と見比べます。
- 事業活動収支差額比率
比率は幼稚園が一番高いが、5年前との比較では短期大学に次いで幼稚園の落ち込み方が大きいように見える。 - 基本金組入前当年度収支差額がマイナスの法人数
こちらも短期大学の次に増加割合が高いように見える。
短期大学の経営が厳しいことは、ニュース等でよく報じられていると思います。

募集停止などの情報をよく耳にする印象がありますね。
しかし実は、幼稚園もかなり厳しい状況にあるということがうかがえます。
頭の中で「何となくそうかな」と思っていることでも、こうして過年度や他との比較といった数値で確認することが大切です。
この記事は月報私学11月号の内容チェックがメインですので、これ以上の内容には触れませんが、これをきっかけに内容を分析するところまで進めるとさらに理解が深まるかもしれません。
まずは、情報のアップデートを目的に記事を見てみましょう。
【職務上、通勤途上の傷病や交通事故等で受診するには】
次は私学共済に関わる内容になります。
いわゆる「労災」とも関係する話です。
- 職務上、通勤途上の災害(労災)
- 職務上、通勤途上以外で第三者からケガをさせられた場合
こんなケースについて、知っておくべきことが紹介されていますので、私学共済業務担当者というより、私学共済加入者として一読しておくことをおすすめします。

いつ何時、どんな目に遭うかわかりませんからね。
少し横道にそれますが、以前の勤め先でこんなことがありました。
あるとき、教員が足を引きずりながら出勤してきたのです。
慌てて事務長に、

〇〇先生が足引きずって歩いてます。
と報告しました。
そうすると事務長から、

あの先生、痛風だから放っておいていいよ。
と言われたのです。
どうやらよくお酒を飲まれる方で、もともと痛風を患っていたようなのですが、私は高校事務室に着任して間もない頃だったのでそのことを知りませんでした。

そうか、痛風だったのか。
と思い、それ以上触れなかったのですが、しばらくして別の教員から、

〇〇先生が通勤途中にバイクでこけたみたいです。
という報告が事務室に入りました。

え、事務長、痛風じゃないみたいですけど?
という言葉がのどから出かけていましたが、事務長を見ると「余計なことを言うな」という雰囲気で私を睨んでいます。
その迫力に負けて、結局口に出さずに粛々と労災の手続きについて、当該教員に説明しに行きました。
皆さまも、様子がおかしい方には思い込みで対応せずに、まずはお声かけしてみることをおすすめします。
また、今の勤め先では学校に報告なく、勝手に「労災です」と言って医療機関を受診したケースがありました。
クラブ活動中のケガなので、労災に該当するとは思われますが、労災は学校の管理監督責任に関わることでもあるわけです。
授業中、クラブ中、通勤途中などでケガ等した場合はとにかく学校へ連絡ということを普段から周知徹底しておくことも大切だと思います。
【シリーズ学校訪問記】
最後はコラム的なものになります。
これとは別に「連載 魅力あふれる学校づくりを目指して」という記事が掲載されることがあるのですが、それとはまた別の内容になります。
- 連載 魅力あふれる学校づくりを目指して:校長などその学校側からの目線の記事
- シリーズ学校訪問記:学校を取材した私学事業団職員からの目線の記事
といった違いがあるように感じています。
別の号にも掲載されることがありますが、11月号に載ることが多いです。
学校の特色や取り組みなどが「連載・・・」の方より客観的な視点でまとめられている印象を持っています。

もちろん「連載・・・」の方も読んでいますよ。
法人本部系の部署に所属する私立学校事務員は、あまり他の学校と接する機会ないというのが私の実感です。
加えて、日々の仕事もルーティン業務がメインであまり変わり映えしない。
そうなると、どうしても心身ともに閉鎖的になりがちです。
そうした状況を少しでも改善するために、こうした他私学の取り組みなどを目にして刺激を与えるというのも一つの方法だと思っています。
例えば昨年の11月号は「外国人留学生」に対する取り組みを取材して、紹介していました。
単純に記事を読んで、他私学の状況を学んでもいいですし、大学にお勤めの方であれば自分の勤め先の国際交流担当部署に記事で紹介されている取り組みについて尋ねてみるのもいいと思います。
アンテナを広げるために活かしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
平均して20ページ前後の「月報私学」
ボリューム的には少ないですが、中身はこれまでお伝えしてきましたとおり、私立学校事務員として身につけておきたいことが詰まっています。
そうした情報を1回読むだけで理解することは難しいと思います。
理解を深めるためにまずは、読んだ内容の中から何かしらのアクションにつなげることを見つけてみる。
他人に説明するという行動でもいいと思います。
ぜひ11月号の記事もそうしたことを意識して活用しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。