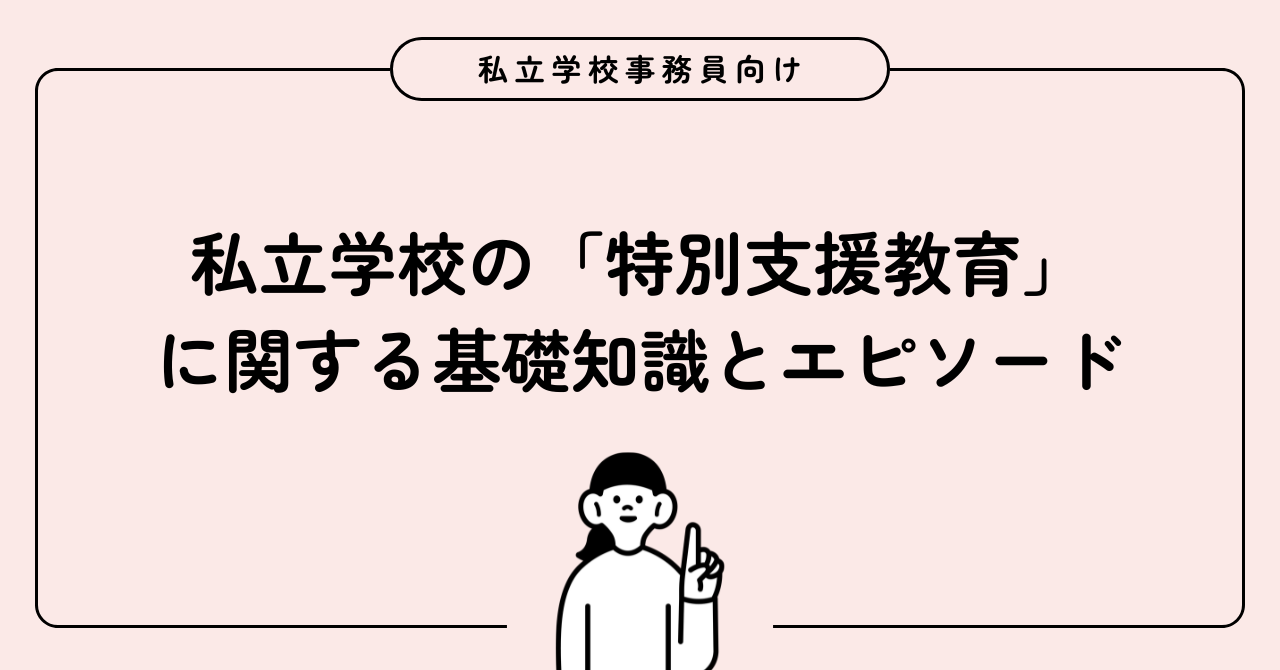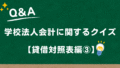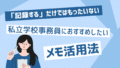この記事は以下のような人を対象としています。
・「特別支援教育」について関連する法令やエピソードなどを知りたいと思っている人。

うちの子は中学の時は、特別支援学級に在籍していました。
私立学校事務員として働いて20年以上。
以前より、こういった言葉を保護者から耳にする機会が増えたように感じています。
入学前の入試相談会などでも、教員が同様の話を受け、相談対応をしているケースが見受けられます。
自分の昔を思い出すと、学年に一人二人、今で言うこの「特別支援」に該当していたように思われる同級生がいたような記憶があります。

それでも、一人二人の話です。
そんな様子から勘案すると、私立学校事務員として勤めるにあたり、「特別支援教育」について知識を増やしておく必要があると思っています。
スクールカウンセラーなどの専門家レベルの知識までは不要だと思いますが、頭に入れておくと業務の参考になりそうと私が個人的に思っている関連法令や事例などを記事にまとめてみました。
具体的な内容は以下のとおりです。
- 特別支援教育とは
- 障害者差別解消法について
- 障害を持つ生徒に関する補助金のエピソード
- 私の体験談紹介
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
【言葉の定義を確認】特別支援教育とは
まずは共通認識として、「特別支援教育」という言葉について内容を確認しておきましょう。
文部科学省のホームページに説明が掲載されていましたのでそちらを引用します。
「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
文部科学省ホームページより引用より引用
特別支援教育
(文部科学省ホームページへのリンク)
また、特別支援教育について調べると「通級」という言葉をよく目にするので、そちらも参考までに文部科学省の説明文を引用します。
「通級による指導」とは、大部分の授業を小・中・高等学校の通常の学級で受けながら、一部、障害に応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態で、障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服するため、特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導を行います。
文部科学省ホームページより引用より引用
「障害に応じた通級による指導の手引 解説とQ&A(改訂第3版)」(文部科学省 編著)より抜粋
(文部科学省ホームページへのリンク)
特別支援教育という大きな枠組みの中に、通級という仕組みがあるというのが私の理解です。
「特別支援教育」と聞くとただ何となく、
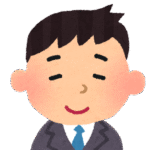
障害を持つ子どもだけが集められて受ける教育ですよね。
と思っている人も多いのではないでしょうか。
そこには生徒等への「配慮」という面が強く押し出されているように私は感じています。
しかし、文部科学省の説明にあるとおり「生活や学習上の困難を改善又は克服するため」という重要な目的があるわけです。
この目的の部分こそが、私立学校事務員として特に意識しておくべきではないかと私は考えておりますので、ここで紹介させていただきました。
覚えておきましょう。
【法令はとりあえずこれ】障害者差別解消法について
特別支援教育に関する法令のなかで、私が特に押さえておくべきと考えているのが「障害者差別解消法」です。
さらに、この法律でポイントとなるのは以下の2点だと思っています。
- 「障害者」≒障害者手帳を持つ人
- 合理的配慮の提供義務
「政府広報オンライン」というサイトでは、以上の2点も含め、わかりやすくこの法律について解説していますので、そちらもご覧いただくことをおすすめします。
事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化
(政府広報オンラインホームページへのリンク)
障害者手帳の有無に関わらず、心身の障害等で生活に制限を受けている人に対して、その人の求めに応じ、合理的配慮を行うこと。
ざっくり言えばこのようなことになると私は理解しています。
この合理的配慮を学校法人は行わなければならないとされています。
この法律が施行された当初、学校法人はこの合理的配慮について「努力義務」とされていました。

できるだけ合理的配慮するよう努力してね、というニュアンスです。
しかし法律の改正により、令和6(2024)年4月1日から努力義務ではなく法的義務へと格上げとなったのです。
ただし、何でも障害者側の言うことを聞けというわけではありません。
「過重な負担」を伴わないものとされています。
どの程度が「過重な負担」となり、どんなものが「合理的配慮」になるのかは個別のケースによると思われますが、日本学生支援機構のホームページに事例等が紹介されていますので、こちらもご一読することをおすすめします。
合理的配慮とは
(日本学生支援機構ホームページへのリンク)

ちなみに私の今の勤め先では、配慮依頼の文書配布やテストのルビふりなどを実施しています。
適切な対応ができるように、基本的な部分は理解しておきましょう。
【お金のためではないけど】障害を持つ生徒に関する補助金
言葉の定義のところで触れましたが、特別支援教育の目的は「生活や学習上の困難を改善又は克服するため」です。
文章で見ても伝わりづらいところですが、この目的達成には人的・物的両方において学校に様々な負担が発生します。
国や地方公共団体もその点については理解している様子で、こうした障害を持つ生徒等の受け入れに対して補助金を交付しているケースがあります。
例えば私の勤め先を所管する地方公共団体では、
- 障害を持つ生徒の受け入れ
- 障害を持つ生徒のための設備等の改善・改修等
といった取り組みに対し、通常の学校運営に対する補助とは別枠で補助金を交付しています。
前者については、身体障害者手帳等を有している生徒が主な対象となっているようです。
ただし、手帳の写しまでは地方公共団体に提出しなくてもよいかたちになっています。

正直なところ、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の写しまで学校に提出させることはハードルが高いです。
そのため私の勤め先では毎年、学校所定の用紙に手帳の種類や取得年月日、更新年月日を記入して提出してもらうことで、把握に努めています。
地方公共団体には、手帳の写しを学校で保管していない旨を伝えたうえで、補助金を申請しています。

あとはそちらの判断にお任せします、といったスタンスです。
この件で補助金が交付されているので、事情を考慮していただいているものと思っています。
一方後者の方は、エレベーターの設置などあまり大掛かりなものは対象外となっています。
会計的な話をすると、勘定科目でいう「建物」や「構築物」に該当するようなものは対象となりません。
以前、新たにスロープを設置した際に担当の会計士から、
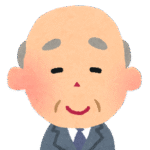
これは構築物ですね。
と言われて、泣く泣く補助金申請を断念したことがあります。
大規模なものについては別途、文部科学省が補助金を交付している場合もありますので、私立学校事務員としては情報をつかんでおきたいところです。
補助金を有効活用して、目的達成に向けた環境整備を進めましょう。
【事例紹介】一人受け入れると・・・。
タイトルから察していただけると思いますが、特別支援教育が必要な生徒を受け入れると、その生徒と同様の支援が必要な生徒が連続して入学してくるケースがあります。
例えば今の勤め先には、「漢字が読めない」という特性を持った生徒が在籍しています。
この生徒が入学するまでは、こういった特性を持った生徒を受け入れたことがありませんでした。
ところが、この生徒を受け入れた後、数年間続いて同じように「漢字が読めない」という特性を持った生徒が入学したのです。
この時に、私はふと以前の勤め先での出来事を思い出しました。
それは視力に障害を持つ生徒を受け入れた時のことです。
初めてのケースでしたので、点字プリンターを購入するなど様々な環境整備を行いました。
すると、その翌年度も翌々年度も同じように点字プリンター等が必要な生徒が入学してきたのです。
単なる偶然かもしれませんが、別々の学校で同様のことが起こったので私の中では、一つの法則のようなものがあるように感じています。
つまり、最初の受け入れでしっかりした対応をしておく必要があるとも言えます。

どうせ、今年だけだろう。
などと思わずに、特別支援の目的に沿って、できる限りの体制整備を行うようにしましょう。
まとめ
前述しましたとおり、昔と比べて学校は多様な生徒が学ぶ場になってきています。
ということは、そこで働く事務員は様々な特性を持った生徒と日々関わることになるということです。
専門的な対応までは必要とされないまでも、そういった生徒たちが「生活や学習上の困難を改善又は克服するため」の教育環境を整備するという役割を私立学校事務員は担っていると私は思っています。
その役割を果たすために一歩ずつ知識を身につけていきましょう。
今回の記事がそのきっかけにつながれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。