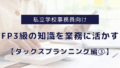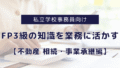この記事は以下のような人を対象としています。
・毎日がただなんとなく過ぎていくなぁと感じている人
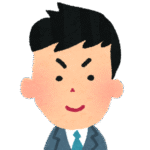
自分はなんて地味な生活をしているんだろう。
こんなことを思った経験、皆さまにもあるのではないでしょうか。
- 平日はいつも家と学校の往復の繰り返し
- 仕事は代わり映えのしないルーティン業務
- 休みの日は家でごろごろし、気づいたらもう夜
といった以前の私のような生活を送られている私立学校事務員の方もおられると思います。

「以前は」ですよ。
これはこれで特に大きな問題があるわけではないので、
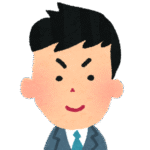
まぁ、いいか。
とそのままにしてしまいがちです。
ただ、頭の片隅にぼんやりと冒頭のような言葉が浮かんできてしまいます。
どうして、そのような思いが生じてしまうのか。
それは、日々の生活のなかに「小さな幸せ」を作り出すための方法を学んでいないからだと私は思っています。

実際、私はそうでした。
そこで今回は、参考書籍の内容をもとに、私が実際に取り組んでみた「時間との向き合い方」について紹介したいと思います。
24時間のうちたった2時間でも、意識的に「最高のひととき」を味わうための時間を確保する。
そのための「時間との向き合い方」を理解して実行することで、悩みが軽減されます。

それは私自身も実感しています。
さらにそれがきっかけで、「自分を幸せにしてくれる時間」を意識して持つようになり、今よりもっと充実した日々を過ごせることにつながるわけです。
皆さまのお悩み解消の一助となれば幸いです。
書籍の紹介
書籍名:いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才 本当に大事なことだけをして、毎日を充実させるシンプルな考え方
著者名:今井 孝
出版社:すばる舎
発売日:2024年6月30日
【前提】「最高のひととき」に必要なもの
まずは、「最高のひととき」を味わうために「必要な時間」についてです。
書籍のなかで著者は、幸せな人たちとそうでない人たちとの違いを、自身が調査した結果として以下のように紹介しています。
1日のなかに「最高のひととき」をつくり出している、ということです。その「最高のひととき」を平均すると、2時間程度でした。
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より引用
普通の人との明確な違いは、1日のなかで2時間だけ。つまり、人はたった2時間だけでも充実すれば、十分幸せなのだということです。 P9
1日24時間のうち、「最高のひととき」に充てる時間は2時間あればよいということ。
率で言えば、1日の約8%でよいというわけです。

しかも「平均2時間」ですから、もっと短くてもいいというわけですね。
これくらいならつくり出せそうな気がしませんか?
幸せな人たちは丸一日、充実した時間を過ごしていると思っていましたが、この箇所を見て「これならできそう」と感じたことが私にとっての転機になりました。
そして、その「平均2時間」の間に何をすればよいか。
書籍ではこのように述べています。
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より加工して引用
- 自分がどんな感情を得たいのかを知り
- その感情を得られることを日々おこなう P30

目的を明確にするということですね。
手段が目的化してしまわないように著者は忠告しています。
「幸せな日々を過ごすこと」が目的で、そのために「毎日、〇〇をする」といった手段を決めるわけですが、時間がたつと「毎日、○○しないと」という手段が目的になってしまいがちです。
そういったことにならないように、まずは「どんな感情を得たいのか」をはっきりさせるわけです。
後ほど触れますが、得たい感情を1つに絞る必要はありません。
自分が幸せを感じるケースは様々ですので、いろんな感情を想定してみましょう。
まとめると、
- 1日に2時間程度を「最高のひととき」のために意識的にあてる。
- 「最高のひととき」で得たい感情を明確にする。
ということになります。
それでは以降、詳しく見ていきます。
【小さなことでOK】「自分を幸せにしてくれるものリスト」の作成
最初に「得たい感情」と「それを得るためのもの」をリスト化します。
書籍の言葉を引用すると以下のとおりです。
「自分を幸せにしてくれるものリスト」をつくると、それだけで幸せに一歩近づきます。何が自分の幸せなのかがわかってくるからです。 P82
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より引用

頭で思っている内容を「見える化」することが大切なわけです。
リストを作成するときのポイントは「小さなことでいい」ということです。
これも書籍の箇所を引用します。
小さなことに気づくと、自分を幸せにしやすくなります。
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より引用
意識的に、自分を幸せにする時間を増やすことができるからです。 P82
小さなことでよければ、心理的なハードルが下がり、「幸せ」を感じやすくなるという効果が期待できます。

実際私は、「生徒があいさつしてくれた」といった日常のよくある一コマでも「幸せ」を感じられるようになりました。
そんな小さなことすら思いつかないという人のために、著者はこんなやり方をおすすめしています。
小さな幸せも思いつかないという場合は、「好きな食べ物」から思い出すのがいいでしょう。 P84
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より引用
さらに、リストを作成するにあたって意識したい「カテゴリー」について、書籍では以下のように紹介しています。
- 簡単にできること
- ちょっと無理すればできること
- とんでもないこと
この3つのカテゴリーで考えると、日常の小さな幸せも再確認できるし、制約を外した大きな夢を気兼ねなく書くこともできます。 P83
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より加工して引用
私のリストの一部を参考までに紹介します。
- 簡単にできること ジムで運動 サウナに行く ゲームをする
- ちょっと無理すればできること 温泉旅行に行く 某アウトドアブランドの商品を買う
- とんでもないこと 両親と世界一周する 学校法人を設立する

書き出すと、いろいろ思いつくことがあって案外楽しいですよ。
そして、書き出した項目をさらに以下のように分類します。
- 達成感
- ふれあい
- リラックス
「自分を幸せにしてくれるものリスト」をこの3種類に入れて見てみると、自分が感じる幸せの傾向がわかります。 P90
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より加工して引用

私は「リラックス」に幸せを感じる傾向があるようです。
小さなことでも思いつくままに挙げていくわけですが、その際の注意点があります。
それは「一時的な快楽」を目的にするものはNGということです。
なぜならその行動を行ったあとに、一種の「むなしさ」だけが残ってしまうからです。
そうなってしまっては幸せどころの話ではなくなってしまいます。
そうならないための方法として、書籍では以下のような方法をすすめています。
「幸せ」なのか「一時的な快楽」なのかを見分けるための簡単な方法があります。それは、自分にこう問いかけることです。
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より引用
「それをしている自分自身を好きだろうか?」 P95
その行為をしているときの自分を、もう一人の自分が客観的に見ている状況を想像してみてください。
例えば、私はお酒を飲むのが好きですが、飲んでいる自分はあまり好きではありません。
一時的に気持ちよくなりたいだけのために飲んでいるように思えてしまうからです。
ですので「お酒を飲む」はリストには入れていません。
こんな感じでリストを作っていきます。
この作業だけでも、「何しようかな」とワクワクしてくるので、おすすめします。
【まずは1つずつ】スケジュールの作成
リストの作成ができたら、次はスケジュールを作成します。
スケジュール作成にあたって大切なことを書籍で解説していますので、それを確認しておきましょう。
最高の1日は簡単に手に入ります。
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より引用
そのために必要なのはたった2つだけです。
それは「ご褒美」と「達成する仕事」です。
これがセットになっているのがキモです。 P106
そして、「達成する仕事」を決めるポイントは以下のとおりです。
達成したら嬉しいことを具体的に1つ選びましょう。
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より引用
そして、その仕事を中心にして1日や1週間のスケジュールを組むわけです。 P113

ご褒美を得るためにたくさん仕事をやり遂げなくてもよい、と思えば心理的な負担が少なくてすみますね。
「ご褒美」と「達成する仕事」が決まったらあとはスケジュールを組むだけ。
その時、大まかな1日の流れを決めておくとスケジュールを組みやすくなります。
書籍では一例として以下のようなテーマを設定することをすすめています。
朝は達成感、昼はふれあい、夜はリラックス P124
「いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才」より引用

私はこれに倣って、朝には伝票チェックや月次決算資料の作成など、「できた!」と実感しやすい仕事をセットし、夜のリラックスとしてご褒美を用意しています。
【結論】実際にやってみて実感したこと
以前までは、

なんとなく疲れたからサウナに行こう。
といった感じで好きなことをしていましたが、この方法を試してみて日々の生活にメリハリがついたように感じます。
意識的に「やること」と「楽しむこと」をセットすることで、なんとなく時間が過ぎていくという感覚が薄れてきたという感覚です。
やることは1日1つでよく、ご褒美もちょっとしたものでOKという取り組みやすさがこの「時間との向き合い方」の魅力だと思いますので、皆さんもぜひ実践してみてはいかがでしょうか。
より詳しいやり方は書籍に書いていますので、読んでみることもおすすめします。
まとめ
私の周りの事務員にも「毎日同じようなことの繰り返し」といったことを言う人がいます。
特に私と同じく経理業務などのバックヤード部門の人にそういった傾向が見られるように感じています。
しかし、人生100年時代と言われるなかで、なんとなく日々を過ごしているのは大変もったいない。
今回の記事が、そうした日々から抜け出して、少しでも日々の充実度をアップさせることにつながれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
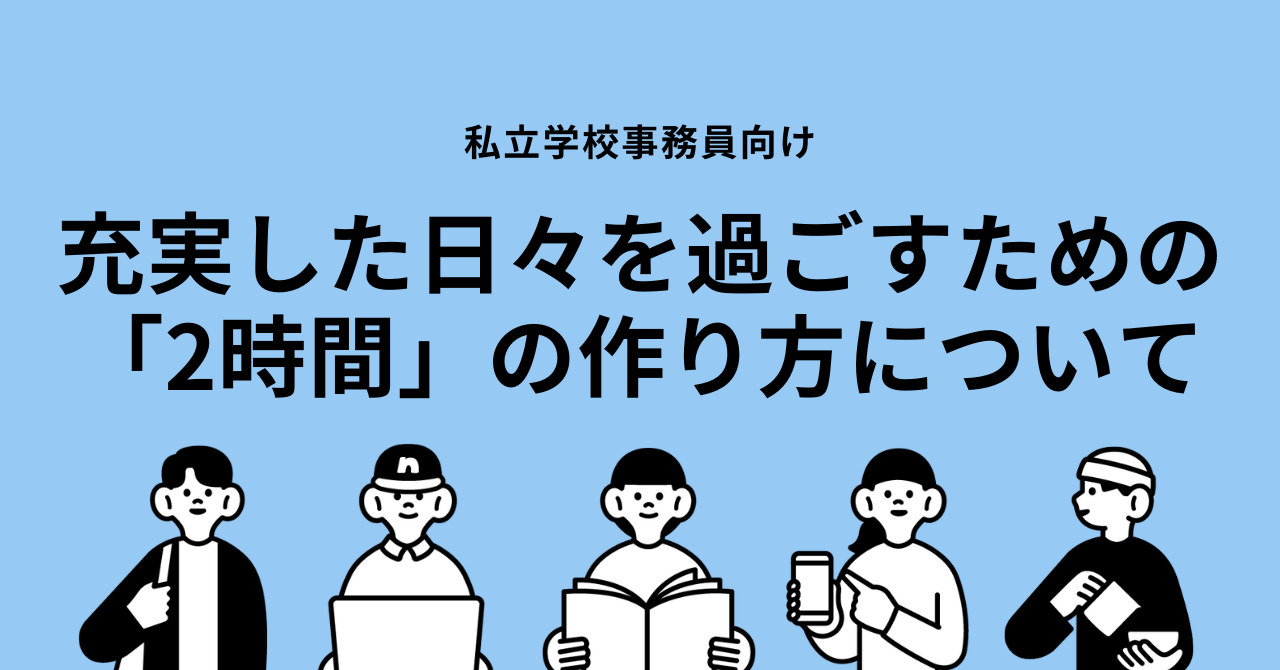
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=21257783&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2335%2F9784799112335_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)