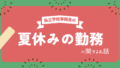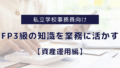この記事は以下のような人を対象としています。
・規模の小さな学校でも取り組めるデジタル化の実例を知りたいと思っている人
様々なメディア等を通じて耳にする「DX」という言葉。
皆さんも、一度はどこかで聞いた覚えがあるのではないでしょうか。
そんな世の中の風潮もあり、
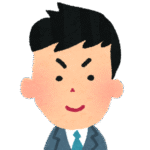
自分の勤め先でもDXを推進しなければ。
とお考えの方もおられると思います。
しかし、「やらなければ」という意識はあっても何から手をつければいいかわからない。
そんな人も多いように感じています。

私もその一人でした。
そんな私に、ある一冊の書籍が気づきを与えてくれました。
その書籍で書かれていたのは、
「デジタル化とDXは違う」
ということでした。
どうやらDXを進めるためにはステップがあり、そのステップの1つとして「デジタル化」がある。
そう理解した私は、

じゃあ、まずデジタル化から始めてみよう。
と思い、取組みを開始しました。
今回この記事で紹介するのは、そんなデジタル化に取り組んだ私のエピソードです。
エピソードは以下の3つになります。
- 給与明細書
- 年末調整
- 振込
書籍の紹介
書籍名:総務部 DX課 岬ましろ
著者名:須藤 憲司
出版社:日経BP 日本経済新聞出版
発売日:2021年9月21日
【意味を確認】言葉の定義
まずは「デジタル化」と「DX」の定義を確認しておきましょう。
それぞれ、書籍の解説を以下に引用します。
デジタル化とはデジタイゼーション/デジタライゼーションとも呼ばれ、「業務プロセスを最新の技術を用いてより便利に進化させること」を意味します。 P67
「総務部 DX課 岬ましろ」より引用
DXとはデジタルトランスフォーメーション、つまり「デジタルによる顧客体験の変革によって儲ける」という提供価値のDXであり、顧客体験がデジタルで変わらないといけません。 P67
「総務部 DX課 岬ましろ」より引用
もう少し厳密に言うと、
「総務部 DX課 岬ましろ」より加工して引用
のように、書籍ではDXを2種類に分類しています。

書籍でも例を挙げていますが、紙でのやりとりをオンラインにするといった取り組みは「デジタル化」に該当します。
当然、「社会にインパクトを与える変革」にいきなり挑戦するのは無理な話です。
そのため、DXはステップを踏んで進めることを書籍では進めています。
そのステップと各ステップにおける目的は以下のとおりです。
「総務部 DX課 岬ましろ」より加工して引用
- アナログのデータ化→属人化の解消
- プロセス/システムのデジタル化」→自動化&効率化
- 社会にインパクトを与える変革→差別化&競争力向上
これを見て私は、

まず、①と②から手をつけてみよう。
と考えたわけです。
DXという言葉に多少興味はあるけれど、何をしたらいいかわからないという人は、この言葉の定義とステップだけでもまずは頭にいれていただき、日々の業務を見直してみてはいかがでしょうか。
【さようなら専用用紙】給与明細書
最初に取りかかったのが、給与明細書のデジタル化です。

前述の例で言うと「システムのデジタル化」になりますね。
給与明細書のデータそのものは、すでに給与システムを導入していたため、前述のステップでいう①はクリアしていました。
そこで、これをステップ②に進めようと考えたわけです。
それともう一つ、この給与明細書のデジタル化を進めようと思った理由があります。
それは「追加の費用が発生しない」というメリットがあったからです。
既存の給与システムに給与明細書をデジタル化する機能が備わっていました。
私の今の勤め先のような規模が小さな学校がデジタル化やDXを進めようとすると、ネックになるのが「資金力」。
最新の技術やシステムなどを導入しようとしても、そのための資金がありません。

もっと言うと、それだけのお金をかけても生徒数や教職員数が少ないため、「わざわざそんなにお金をかけてまで」という考えに至ってしまいます。
その点、お金をかけずに取り組めるこの「給与明細書のデジタル化」は、上席者等の承認が取りやすく、仮にうまくいかない場合でも簡単にもとに戻すことができるので進めやすかったわけです。
では、これによって何が自動化/効率化されるのでしょうか。
デジタル化する前は、給与明細専用用紙にプリントアウトし、これまた専用の窓あき封筒に封入していました。
大した人数ではありませんが、それでも印刷・封入作業といった手間が毎月発生します。
加えて、用紙や封筒が不足したら発注しなければならないわけです。
デジタル化することでこうした作業から解放され、業務を効率化することができます。
実際導入後は、上述のような作業は発生しなくなりました。
給与明細を確認するための専用サイトに、教職員が各自でログインして自分で明細の内容を見るかたちなので、印刷・封入は不要です。
給与振込のためのデータを作成すれば、その内容が専用サイトの方に反映されますので、給与明細の準備のためだけに行わなければならない作業というものもありません。

強いて言えば、「専用サイトで今月の給与明細が見られるようになりました」という旨のメールを教職員あてに送る作業が必要ですが、これもシステムの方でメールを送るタイミングをあらかじめ設定しておけば自動的に配信されます。
こうして、特に大きなトラブルなく「給与明細書のデジタル化」を進めることができ、自動化&効率化という目的を達成することができました。
【いつでもどこでも】年末調整
次に取りかかったのが、「年末調整のシステム化」です。
年末調整といえば、
- 「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」といった資料をプリントアウトして、対象者に配布
- 各自が記入したものを添付資料とセットにして回収
- 担当者が給与システムにデータを入力して12月の給与に反映
というのが毎年の恒例作業でした。
これも給与システムでデータ化はできており、①のステップは完了しているため、②のステップを進めることに。
そのための仕組みも、既存の給与システムに備わっているので、追加費用なしで取り組むことができました。

既存のシステムにはまだまだ使いこなせていない機能が潜んでいる可能性があります。
皆さんも一度じっくり確認してみることをおすすめします。
この年末調整システムも給与明細と同じように、専用サイトへ各自がログインして必要な情報を入力するものでした。
そのため、こちらはサイトの利用準備ができた旨をメール配信すればよいだけです。
こうして、この年末調整も特にトラブルなどは起こることなく、自動化&効率化することができました。
参考までに自動化&効率化できたポイントを以下に挙げます。
- 紙で配布していた資料をペーパレス化することができた
- 教職員個人のスマホ等を利用して、年末調整に必要なデータの提出が可能となった
- 紙で提出された情報を、再度システムに入力するという二度手間を解消できた

ちなみにこのシステムを利用することで、源泉徴収票もデジタル化されました。
【リスクも回避】振込
最後に紹介するのは振込作業のデジタル化です。
私は以下の2つの業務についてデジタル化を進めました。
- 紙の振込用紙からネットバンキングへの変更
- 現金対応していたものをネットバンキングによる振り込みに変更
まずは、紙の振込用紙による振り込みについて。
こちらは、前述の給与明細書や年末調整のデジタル化よりも前から、取り組んできました。
そこには、金融機関へ支払う手数料の問題が関係しています。
紙の振込用紙による振込の方が、ネットバンキングによる振込よりも手数料が高かったのです。
金融機関側も、窓口業務の効率化を進めたいという意向があり、ネットバンキングの導入はスムーズに進みました。
導入には月々の使用料が5,000円程度必要でしたが、このタイミングで振込手数料の見直しも交渉し、一部の振込手数料を無料にすることができたため、トータルとしては今までと同程度の費用負担でおさめることができました。

やはりコストはおさえたいので、譲れないポイントでした。
こうして金融機関側の協力もあり、ネットバンキングの導入はスムーズに完了。
振込用紙への手書き作業などアナログだった部分がデジタルに置き換わりました。
続いて、取り組んだのが現金業務のデジタル化。
現金を準備して支払っていたものを、ネットバンキングで行うようにしました。
例えば、PTAの方々の交通費。
それまでは現金を準備し、当日渡して領収書を徴収するというやり方でしたが、両替の手間など無駄が多い状況でした。
これをネットバンキングによる振込に変更。
PTAの方々は、すでに子ども(生徒)の学納金を口座引落で支払うために、学校へ口座を届け出ています。
その口座へ交通費を振り込むように話を進めました。
幸い、PTAの皆さまから協力を得られたので、これも無事デジタル化することができました。
これにより自動化&効率化できたポイントは以下のとおりです。
- 振込用紙の記入、銀行届出印の押印作業
- 現金の準備、両替対応
- 領収証の作成
まとめ
「DX」という単語だけ聞くと、とても大掛かりで専門的な人材が必要なイメージを思い浮かべてしまいがちです。
しかし、参考書籍で紹介しているように、ステップに分解して取り組めば決して高度な専門知識が必要なものではありません。
ただ、最後のステップ「社会にインパクトを与える変革」はなかなか着手が難しいのも事実です。
参考書籍でもここでストップしてしまうケースが多いと指摘されています。
この部分については、私もこれから取り組むことになりますが、まずはそのための準備としてこの記事で紹介した私の事例を参考にしていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
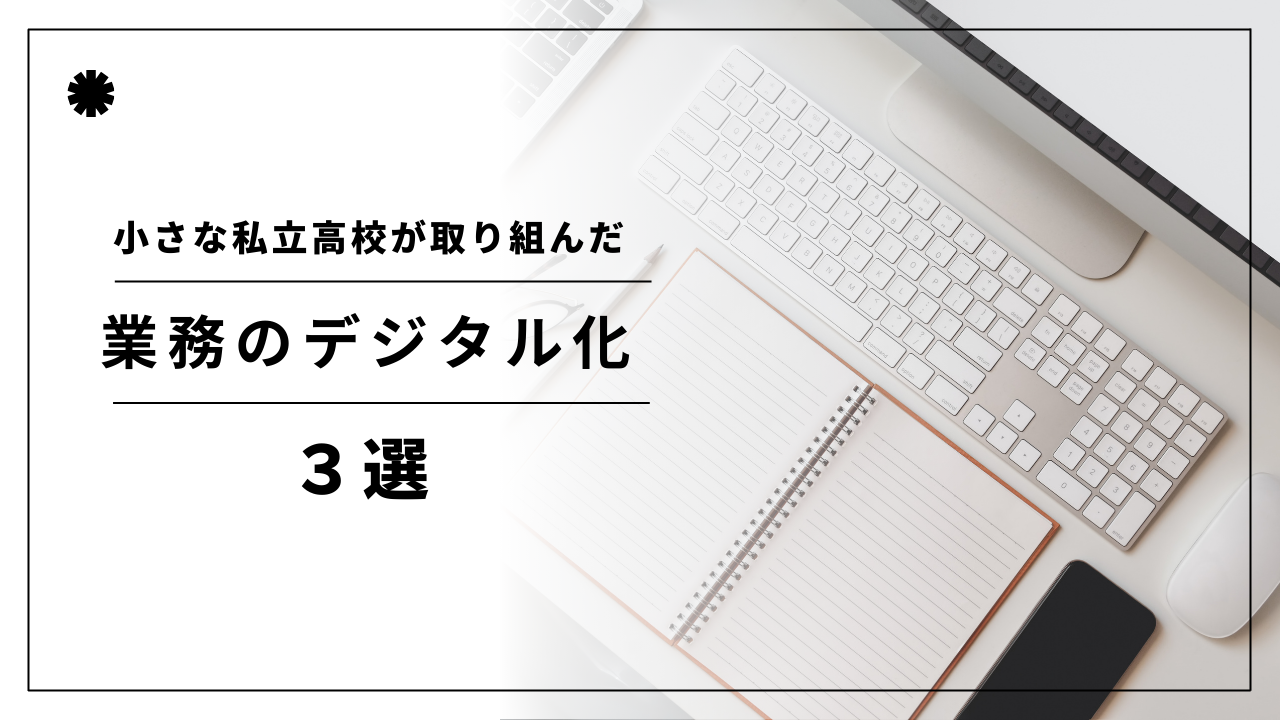
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=20444926&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4322%2F9784532324322_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)