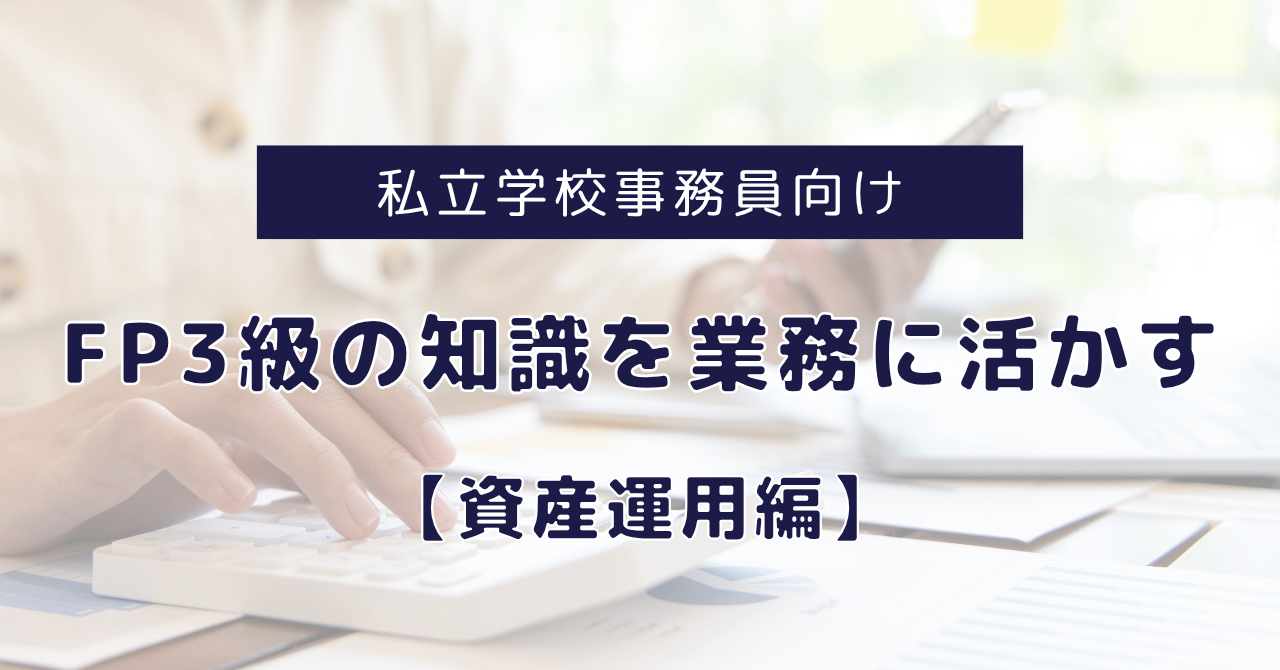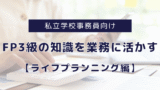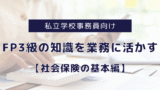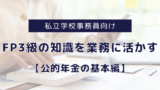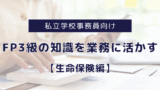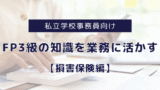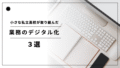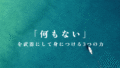この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・私立学校事務員の仕事に資産運用の知識が必要なのかという疑問を持っている人。
以前の記事で、ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下、FP技能検定)3級の試験範囲の中から私立学校事務員の仕事に役立ちそうなものを紹介しました。
今回はその続きとして、「資産運用」の部分で私立学校事務員として知っておくべきと私が感じたものをピックアップしてみました。
前回と同様に、FP技能検定3級の試験を参考にした問題を解きながら、必要な基礎知識を身につける形式にまとめています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとにこの「資産運用」に関連した情報を紹介しています。
「資産運用の知識を事務員の仕事で使うことなんかないのでは?」と思っている方も、一読いただければと思います。
【第1問】預金保険制度
預金保険制度により、定期預金や利息の付く普通預金などの一般預金等において、1金融機関ごとに預金者1人当たり保護されるのは次のうちどれか。
正解:B
元本1,000万円までとその利息等が預金保険制度の保護対象となります。
なお、決済用預金(利息が付かない普通預金など)は全額保護、外貨預金は国内銀行に預け入れられていても保護対象外です。
【第2問】債券①
債券の性質で一般的に正しいものはどれか。
正解:B
市場金利が上昇すると、新たに市場金利で発行される債券の方が金利が高いため、それまでに発行された債券の人気がなくなり、価格が下落します。
【第3問】債券②
債券の発行体の信用度が低下し、格付けが引き下げられた場合の債券価格と利回りの動きについて、一般的に正しいものはどれか。
正解:B
信用度が下がると債券価格は下落しますが、その分安く購入できるようになるため、利回りは上昇します。
【第4問】投資信託
日経平均株価や東証株価指数などの市場インデックスに連動した運用成果を目指す運用手法は次のうちどれか。
正解:A
「インデックスに連動≒平均」の運用成果を目指すのがパッシブ運用、インデックスを上回る運用成果を目指すのをアクティブ運用といいます。
基本的に、パッシブ運用の方がアクティブ運用よりも信託報酬などが安いという特徴があります。
【第5問】利息
利率や期間など他の条件が同じの場合、満期時の元利合計が最も多くなるのは次のうちどれか。
正解:A
他の条件が同じであれば、利息の再投資期間が短い(複利計算の回数が多い)ほど増え方が大きくなります。
1カ月複利は1年間で12回複利計算を行うので、半年や1年複利よりも元利合計が多くなるわけです。
【理解度アップ】収入の多角化と資産運用
学校法人の収入源と言えば「学納金」と「補助金」。
この2つが収入の9割を占めていると言っても過言ではありません。
さらに言えば、どちらも「生徒数」の影響を受けるという性質があります。
つまり、
- 「生徒数の減少」が「学納金収入と補助金収入の減少」につながる。
- 学校の収入の約9割は学納金と補助金なので、両者の減少は学校の経営状況の悪化に直結する。
ということになります。
しかし、生徒数が減少したからといってすぐに教育サービスの提供に支障をきたしているようでは、生徒は安心して学校に通うことができません。
そのため、こうした現状に対して、学校としては何らかの対策を打っておく必要があります。
その対策の1つとして考えられるのが「収入の多角化」。
生徒数の影響を直接的に受けない収入の柱を育てておき、不測の事態にも備えておくわけです。
そのような考え方に基づき、多くの学校が取り組んでいるのが「資産運用」です。
ただ、大規模の学校法人であれば、金融機関出身者を雇い、資産運用の業務に充てることもできるわけですが、小規模なところではそうはいかないのが正直なところ。

実際、私の以前の勤め先は銀行出身者を担当に充てたうえで、資産運用自体は外部の会社に一任していました。
担当者は運用そのものではなく、その外部の会社とのやりとりをメインに行っていたと記憶しています。
実際、今の勤め先は基本的に学校法人本部から独立して、高校単体で資金管理等を行っているコンパクトな組織のため、そんな専門人材を置く余裕はありません。
それでも健全な財務状況を目指すために「収入の多角化」は考えておく必要があります。
そこで必要となってくるのが、最低限の資産運用の知識というわけです。
学校が不利益を被らないように、取引先の金融機関とやりとりができる程度の知識は身につけておく必要があります。
その知識の習得に、FP3級の学習が役立つというのが私の実感です。
以降は、私が実際に経験した学校法人の資産運用にまつわるエピソードを紹介していきたいと思います。
具体的には以下の2点です。
- 定期預金と決済用普通預金
- 資産運用規程とFP3級の知識
【預金が基本】定期預金と決済用普通預金
私学事業団のホームページに「学校法人の資産運用状況」というものが公表されています。
「学校法人の資産運用状況」(日本私立学校振興・共済事業団ホームページへリンク)
そこには少し前のデータになりますが、令和5(2023)年度決算数値に基づく、全国の大学・短期大学・高等専門学校法人の資産運用状況が掲載されています。
その資料を見てみると、運用対象資産のほとんどを現金預金や債券が占めていることがわかります。

やはりこの辺りは、「私立学校の公共性」が関係しているのでしょうね。
利益よりも安全性重視といったところですね。
そうした状況も勘案して、前述の設問も5問中4問は預金や債券、そしてその利息に関するものを選んだわけです。
特に私の今の勤め先のような、規模の小さい高校だと資産運用というと定期預金がメインというところが多いと思われます。
そこでこの定期預金による利息収入をいかにして増やすかが、ポイントになるわけです。
私の場合、設問5のように、1年複利ではなくもっと利息の再投資期間が短いものにできないかといった交渉をしたこともあります。
そうして色々取り組んでみた結論としては、シンプルに「他の金融機関との比較」が一番効果的でした。
私が今所属している学校法人は、異なる地域に学校を設置しています。
そのため、

「A県のB銀行さんから、定期預金で〇%つけると提案を受けているのですが」
という話を出すと、大抵同じ利率を付けてくれます。
もし、お勤めの学校の所在地から離れた都道府県の状況がわかるのであればおすすめの方法です。
そして逆に「安全性重視」という意味では、決済用普通預金口座の存在も理解しておくべきです。
利息が付かない代わりに、全額が保護されるという預金になります。
資産運用の観点からは何の魅力もありませんが、一昔前の超低金利の時代であれば、安全性確保のために活用するというのも1つの手だと思っています。
世の中の情勢を見ながら、柔軟に定期預金と普通預金のバランスを調整すること。
金額としては微々たるものですが、資産運用初心者はこうしたところから始めてみればいいと思います。
【説明責任の履行】資産運用規程とFP3級の知識
前述の私学事業団の調査結果に話が戻りますが、多くの学校法人が運用対象資産を現金預金または債券で保有している状況です。
こうした「どのような金融商品で資産運用を行うか」については、基本的に各学校法人において資産運用規程等を整備して明文化していると思われます。
私立学校事務員としては、資産運用の担当者かどうかに関わらず、自分の勤める学校法人について以下の点は把握しておくべきだと私は考えています。
- 資産運用に関する規程の有無
- 購入可能としている金融商品の種類
- 購入の意思決定を行う機関
学校法人の資産運用は生徒・保護者等からの学納金や国・地方自治体等からの補助金が原資となっています。
そうしたステークホルダーから、資産運用に対するスタンスを尋ねられた際に「わからない」と答えていては、説明責任は果たせないと思っているからです。

最低でも「規程があって、こういう金融商品が購入可能になっていて、実際に購入するにはこんな手続きを経る必要があるんです」くらいのことは説明できないと、保護者等は不安を感じてしまいますよね。
さらに、金融商品に関する基礎知識があれば、安全性の高いものを購入対象にしているなどといった説明も可能となります。
そうした意味でも、FP3級程度の資産運用に関する知識は身につけておいた方がよいと思うわけです。
古い話になりますが、リーマンショックの頃に保護者からこうした話を受けたことがあります。
当時は大学の学納金業務を担当していましたが、保護者からの学納金に関する問い合わせの対応をしていたところ、

この学校は、危ない資産運用とかしていませんか。
という旨のお話をされました。
そのころは、どこかの学校法人が資産運用で大きな評価損を出していることがマスコミに取りざたされていた時期でしたので、保護者の方も不安に思ったのでしょう。
幸いこの時は、それほど強く説明を求められなかったので、上述のような基本的なことをお話しして対応を終えましたが、こうした質問をいつ誰が受けるかわからないと感じました。
そのような経験もあり、前述のような規程の把握と基本的知識の習得を進めているわけです。
早速、規程の確認から始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 教育活動を継続するためには「収入の多角化」を考える必要があり、その方法の1つとして資産運用があるということ。
- その資産運用の原資となる学納金や補助金に関わるステークホルダーに対し、説明責任をはたすこと。
こうしたところで、FP3級の資産運用に関する知識が活用できると私自身、実体験から感じています。
もちろん仕事以外のプライベートな資産形成で役立つ知識でもありますので、学んでみて損はないと思います。
皆さんも早速勉強を始めてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。