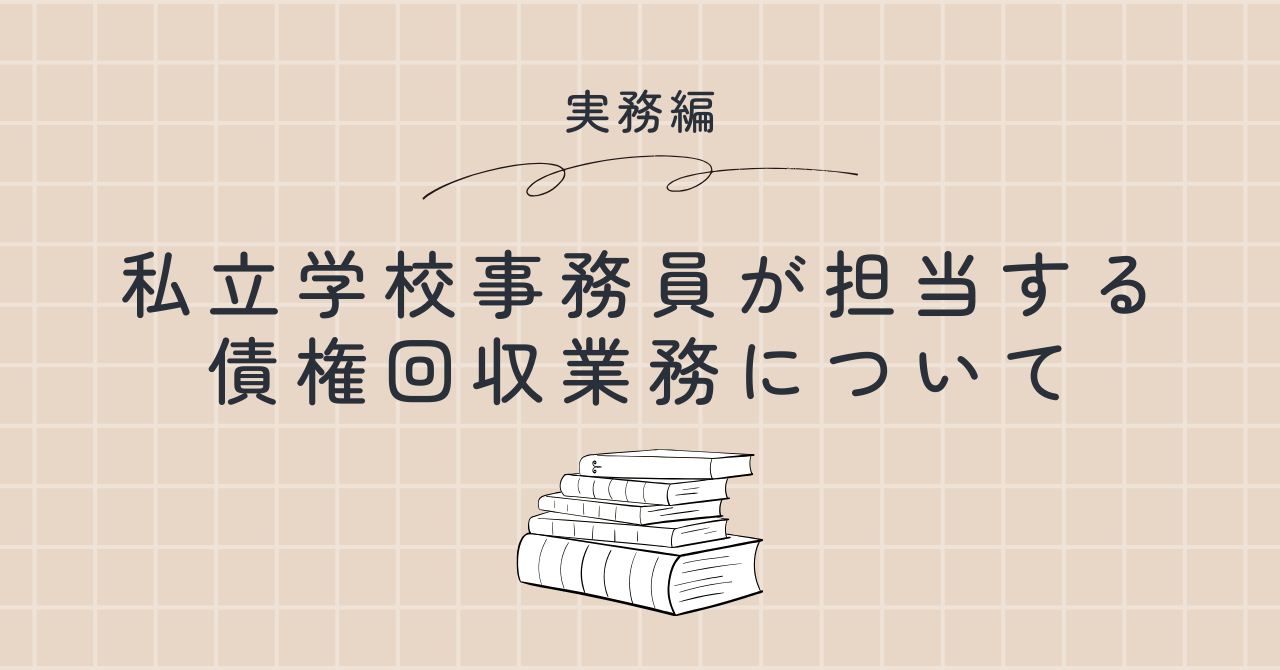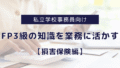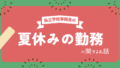この記事は以下のような人を対象としています。
・学納金や貸与奨学金などを督促する業務について知りたいと思っている人。
本来、納めるべきだった学納金を納めないまま退学した者。
在学中に学校から奨学金の貸与を受け、卒業後に返済する予定だったが、返済が滞っている者
皆さんの勤め先にも、このような人が1人くらいいるのではないでしょうか。
実際、私の以前の勤め先でも数十人おり、その内容は主に貸与奨学金の滞納でした。
私は、そんな滞納者も含めた奨学金貸与者への返還請求業務を入職1年目に担当。
前任者も異動しており、尋ねる相手もいないなか、過去の資料を確認しながら業務を進めていました。

今振り返れば、「去年もこのタイミングでこれを送っているから今年も送ろう」とか「前からこれで問題ないのだから、このままでいいか」といった、何とも言えない仕事の仕方をしていたなぁと反省しています。
そこで今回は、こうした督促業務を担当することとなった人をメインの対象として、実務上知っておくべき点などについて紹介したいと思います。
具体的には以下の3つです。
- 督促業務の流れ
- 「時効」についての注意点
- 私の体験談
実務の参考にしていただければ幸いです。
なお、この記事は掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
【割と煩雑】督促業務の流れ
督促業務の大まかな流れは以下のとおりです。
- 請求
- 消し込み
- 再請求(督促)
ステップ1:請求
退学等の理由により、すでに学校に在籍していない者に対する未納学納金請求は、随時行います。
一方、貸与奨学金の請求についてはあらかじめ学内規程等により、毎年の返還期日が定められていると思います。

例えば総額100万円借りた人であれば、「毎年〇月△日に10万円ずつ10年間で返還」といったことを定めているはずです。
この期日の約1ヶ月前には、本人の手元に請求書が届くように準備をします。
件数がそれほど多くなければ、wordとexcelの差し込み印刷で十分対応可能です。
ちなみに、私が以前の勤め先でこの業務を担当していたときには、奨学金返還用の振込用紙を作っていました。
そして請求書を作成し、いざ送ろうとした際に振込用紙の在庫が足りないことに気づいて大慌て。
急いで印刷会社に注文して、何とか返還期日までには送ることができましたが、その年だけ請求書到着から返還期日までの期間がかなり短いという事態になってしまいました。

今は、電子決済など様々な振込方法があると思いますので、返還する側と請求する側とが両方の負担が少ない方法を選択すればよいと思います。
ステップ2:消し込み
この作業が地味でありながら、一番労力を費やすというのが私の実感です。
奨学金返還受入用の口座の入金明細をチェックし、入金が確認できたものを以下のような「奨学金台帳」というものに記録していきます。
| 〇年度 | △年度 | □年度 | ×年度 | |
| Aさん | 10/31 100,000 | |||
| Bさん | 10/31 50,000 |
これに抜け漏れや記載間違いがあると、
- 入金しているにも関わらず誤って督促してしまう
- 未入金なのに督促から漏れてしまう
といったことが起こるため、細心の注意を払いながら正確に行う必要があります。
私は確認のために以下のようなことを行っていました。
- 「〇月〇日、Aさん △円」といったように声に出しながら記録
- 日にちごとに、会計ソフト上の金額と奨学金台帳に記録した金額が一致しているか確認

上の例で言うと、会計ソフト上「10月31日 150,000」となっていれば、当然奨学金台帳の記録も、10月31日に入金があった人を合計すると「10月31日 150,000」になるはずですよね。
後者の方法で記載ミスは防げませんが、少なくとも記載漏れは防ぐことができます。
返還期日が迫ってくると、こうした地道な作業に追われることになるのです。
ステップ3:再請求
期日になっても入金がなかった人に対しては、再度請求します。
これもおそらく規程で「期日から1ヶ月以内に督促状を送る」といったルールを定めていると思いますので、それに従って進めましょう。
また、奨学金を借りる際に連帯保証人や保証人を決めているはずですので、そういった人たちにもこのタイミングで請求を行います。

ちなみに、私の以前の勤め先では延滞利息をとっていました。
なお、決算のタイミングで監査法人などから、こうした貸与奨学金の返還状況を確認されます。
返還が滞っているものについては、適切な会計処理が行う必要があるからです。

徴収不能引当金というものを計上するのですが、ここでは説明を割愛させていただきます。
正しい財政状況を外部に公表するという観点からも、大変重要な意味のある業務であるという意識を持って取り組むようにしましょう。
【勘違いが多い】「時効」についての注意点
こうした「学納金を請求する権利」や「奨学金の返還を請求する権利」などのことを「債権」といいます。
この債権を扱うにあたり、知っておくべきことの1つが「時効」です。
中でも特におさえておくべきポイントは以下の3点です。
- 消滅時効
- 時効の援用
- 時効の「完成猶予」と「更新」
【放っておくと危ない】消滅時効
債権は「権利」なわけですが、ある条件を満たすことにより権利を失うことになります。
これを「消滅時効」といい、民法には以下のように定められています。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
e-GOV法令検索より引用
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

未納学納金の督促や奨学金の返還請求の場合、二のケースは考えにくいのでここではとりあえず「5年間請求しなかったら権利を失う」と覚えておきましょう。
なお、以前は債権の種類によって消滅時効の期間が異なっていましたが、2020(令和2)年4月施行の民法改正によって、上述の期間に統一されました。
「民法改正なんて関係ないだろう」と思っていると見落としてしまいますので、日ごろからの注意が必要です。
【自動的ではない】時効の援用
前述のとおり、5年請求しなかったら債権は消滅するわけですが、5年経過したら自動的に消滅するわけではありません。
奨学金のケースで言うと、借りていた人が「援用」というアクションを起こす必要があります。
これについても民法の条文を確認しておきましょう。
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
e-GOV法令検索より引用

私は、奨学金督促業務を担当していた当時、このルールを知りませんでした。
時効は「時効による利益を受けます」という意思表示が必要という点もおさえておきましょう。
【逃がさない】時効の「完成猶予」と「更新」
では、この時効、期間を延ばしたりすることができないのかというと、そういうわけではありません。
これも民法に定めがありますので確認しておきましょう。
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
e-GOV法令検索より引用

難しい言葉が並んでいますが、ひとまず「裁判所を通じて何か手続きしたら、時効が成立するのを先延ばしにできたり、今まで経過した期間がリセットされて、再度イチからカウントされることがある」と覚えておきましょう。
そして、私の中で一番勘違いが多いという印象なのが、この「完成猶予」。
「督促を送り続けている限り、時効は完成しない」と思っている方が多いように思います。

前述の条文でも「支払督促」と書いてあるので勘違いしてしまうのでしょう。
私も実際、そのように別の職員から言われました。
前述のとおり、裁判所等での手続きを経なければ時効の成立を妨げることはできません。
ただ単に督促を続けているだけでは、「時効」の観点からは不十分というわけです
では、裁判所等を通じずに督促をすることに意味はないのでしょうか。
結論としては意味はありますので、それに関する民法の条文を見てみましょう。
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
e-GOV法令検索より引用

条文でいう「催告」は「督促」とでも読み替えてもらえればと思います。
一応、督促すると6ヶ月時効の成立を延ばせるのですが、それはどうやら1回限り。
延々と督促し続けても、あまり意味はないということです。
当時の私のように勘違いしていた人はよく覚えてきましょう。
【取立屋?】私の体験談
こうした督促業務を行っていると、思わぬ体験をすることがあります。
私の中で特に思い出深いのが、直接自宅まで訪ねたケースです。
当時の上席者と一緒に、学納金を未納のまま卒業した生徒の家まで取り立てに行きました。

「退学」ではなく「卒業」です。私が入職する前の話なので経緯はわかりませんが、なぜ未納者を卒業させたのか、いまだに理解ができません。
記録が残る郵便等で督促し続けていたようですが、一向に音沙汰なし。
督促していた担当者が女性であったため、何かあってはいけないということで私が上席者と行くことになりました。
チャイムを鳴らしたり、郵便受けに直接督促状を入れるなど、学校事務員の仕事としてイメージしていたものとは全く異なる経験でしたので、今でもよく覚えています。
最終的に完済まで至ったので、こうした努力が報われてよかったというのが率直な感想です。
20年以上の私立学校事務員生活の中で、直接自宅に請求に行ったのは後にも先にもこの1回だけなので、大変レアな体験ができたと思っています。
皆さんも、もしかするとこのようなケースに遭遇するかもしれませんので「貴重な体験」と思って臨んでみてはいかがでしょうか。
まとめ
今までの記事でも何度か触れてきましたが、私立学校事務員の仕事は法令や規程等に則って、適切に対応することが求められます。
今回紹介した督促業務もその例外ではありません。
しかし、当時の私のように法令等の知識がないまま、前例踏襲で業務を進めている人も少なくないと思います。
私立学校法など直接学校に関係するもの以外の法令についても、改正情報はないかアンテナを張っておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。