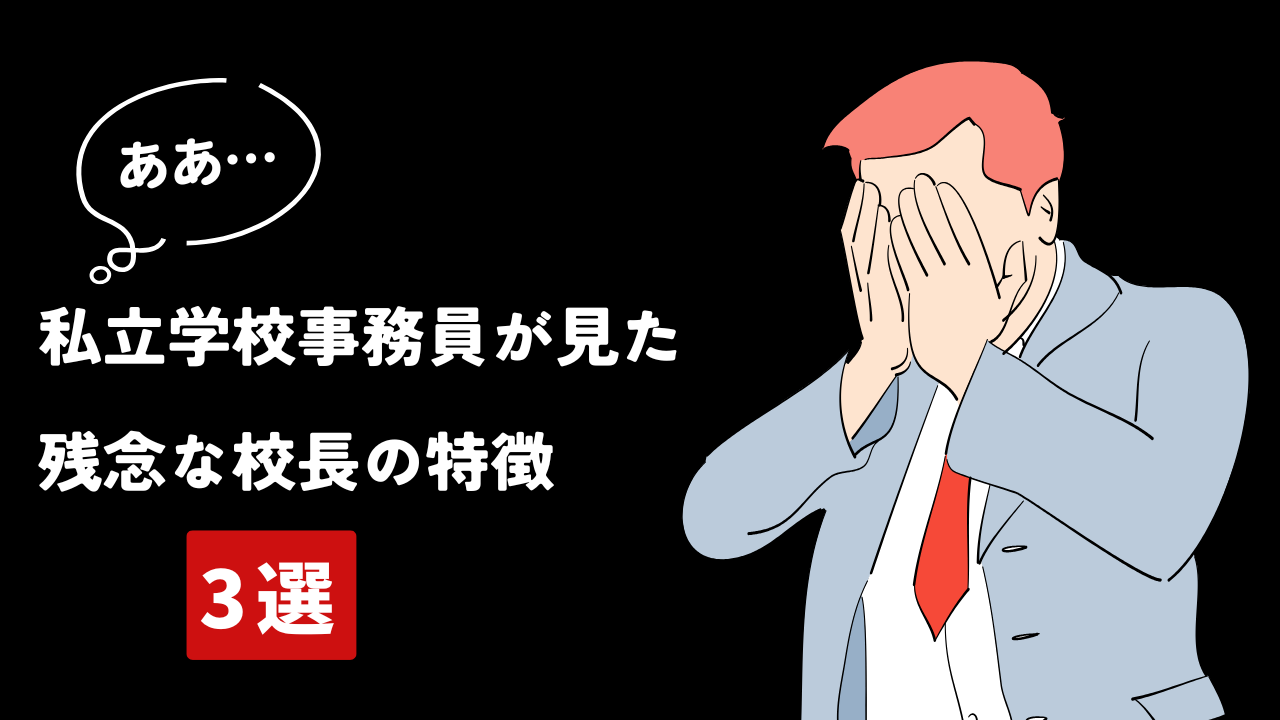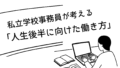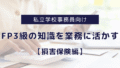この記事は以下のような人を対象としています。
・「校長ってやっぱり立派な人ばかりなのかなぁ」思っている人。
学校の「代表」とも言うべき存在、それが校長。
そんな印象を持っている人も多いのではないでしょうか。
私自身の子どものころを思い出してみても、行事等の際に生徒の前に出てお話をされるなど、「何か、他の先生とは違う雰囲気をまとった人」という記憶が残っています。
また、経営状態が芳しくない学校が立ち直ったりすると、その学校の校長がメディアの取材を受けるといったケースもあります。
そうしたときの校長は、正にその学校の「顔」そのものです。
しかしそうしたイメージは、保護者や生徒、メディアなど外部から見た場合の話。
学校に勤めて、一緒に働くとその印象はまた違ったものになることがあるわけです。
実際、私が今まで勤めてきた学校における校長は、上述のような世間のイメージとは異なる部分が多かったと感じています。
そこで今回は、私が見てきて「残念だな」と感じた校長の特徴を3つ紹介したいと思います。
その3つとは以下のとおりです。
- 教員の労務管理ができない
- 仕事を任せられない
- 自分のお金にだけ興味を持つ
皆さんの勤め先と比べて、「共感できる」とか「そんな人いるの?」といったことを考えながらお読みいただければと思います。
【そもそも】校長の法的位置づけ
前述した「校長は学校の代表」と関係しますが、多くの人は「学校には当然校長がいるもの」と思っています。
もちろんその通りなのですが、そこには一応法律上の定めがあることをご存じでしょうか。
学校教育法には以下のように定められています。
第七条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
e-gov 法令検索より引用

まぁ、当たり前といえばそうなんですけどね。
逆に、教頭は要件を満たせば置かないことができるようです。
さらに、校長は置くだけではなく、届け出が必要ということも学校教育法に定められています。
第十条 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
e-gov 法令検索より引用

校長交代があったら、届け出が必要ということも覚えておきましょう。
「これは法律上どうなっているのか」を確認することは、私立学校事務員として働くうえで大事なことの1つだと考えていますので、皆さんも意識してみてはいかがでしょうか。
【①いくら話上手でも】教員の労務管理ができない
これも1つ、学校教育法の定めを確認しておきましょう。
三十七条
e-gov 法令検索より引用
④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
「監督」という言葉を聞くと、私はまず「労務管理」をイメージします。
勤務実態の管理や職場の安全性確保などがその例です。
特に「勤務実態の把握」は、昨今における「教員の長時間労働問題」にも関わってきますので、校長は大きな責任を負っていることを意識しながら、把握に努める必要があると思っています。
ところが、こうしたことへの意識が薄い校長がいるわけです。
例えば勤怠管理。
私の勤め先では、勤怠管理システムを導入しており、校長などあらかじめ権限を付与された人は全教職員の出勤時間や退勤時間を見ることができます。
数十人しかいない教職員の勤怠データを確認するのにそれほどの時間はかかりません。
にもかかわらず、まずこれを見ようともしない。
そして、勤怠状況を報告しても関心を示さない様子。
以前にこんなやりとりがありました。
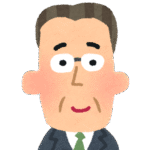
〇〇先生がこのところ朝早くに出勤して、夜遅くに退勤していますね。
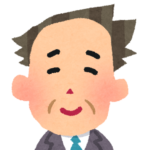
あぁ、そう。今、△△の仕事があるからね。
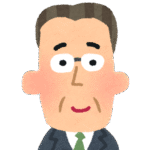
この状態が続いているようですけど、大丈夫なんですか。
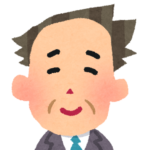
ちょっと、本人と話をしてみるわ。
で、結局本当に話をしただけ。
その後も、この教員の出退勤時間に変化はありませんでした。
このような事態が起こらないようにする、若しくは起こっていたら改善するというのが校長の役目だと思っている私にとっては、

この校長、何を考えているんだろう。
という気持ちになりました。
教員側も、
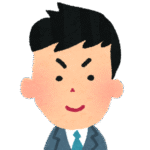
校長は勤務のことに口を出さないぞ。
と思うようになり、就業時間中に何も言わず平気で外出する者も現れました。

ちなみにその外出の事実を伝えても、当該教員に対して特段の対応をとった様子は確認できませんでした。
保護者や入学希望者などに、学校のことなどを話したりする際には上手にお話しをされるのですが、やるべきことがきちんとできていない姿を見ているので、正直「口先だけ」という印象を抱いてしまいます。
地味なうえに、それをしたところで入学志願者数が増えるわけでもない「労務管理」という仕事。
校長も含めて、こうした地道なことに手を抜かない人が、周りからの信頼を得られるように思っています。
【②他にやることが】仕事を任せられない
先ほどの労務管理の例で、「数十人しかいない教職員の勤怠データを確認するのに、それほどの時間はかからない」という話をしました。
この件で言うと、勤怠データの確認作業そのものは、校長ではなく別のしかるべき立場の人(事務長や副校長など)に任せてもいいと思っています。
きちんと別の者に指示したうえで自らはデータを確認しないのであれば、それは関心がないわけではないというのが私の考えです。
こうしたルーティン業務的なものは任せて、自分は判断・決定に集中する。
これが校長の仕事における1つのかたちだと思います。
ところがこうした業務を任せられない校長もいます。
これも私の勤め先の例ですが、校内の清掃の仕方に口を出す校長がいました。
オープンスクールなど、外部の人を招くイベントの際に必ず校内を回って確認。
机の脚の裏についているホコリまでチェックします。

もちろんキレイであることに越したことはないのですが、それは「チェックすべき点」としてまとめておき、イベント担当者などに任せればよい話です。
重要なのはイベントの内容なので、こちらとしてはそこに注力してほしいのですが、そのことを言うと、
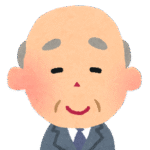
それは各教科やコースの担当者の方が詳しいから。
と言って、関わろうとしません。
見方によっては「自分が率先して掃除をする姿を見せることで、教員たちの行動を促そうとしている」とも解釈できます。
しかしこの言動からは、イベント内容が不評だった場合の責任から逃れようとしているように私は感じてしまいます。
他にも、エピソードがあります。
あるクラブが大会で優勝した際の出来事です。
その内容を記載した横断幕を作ることになったのですが、何故か校長がそれをデザインして制作会社に注文しているのです。
そして、生徒が登下校時に通る入口に優勝旗を飾るのですが、その旗の出し入れを行うのも校長。

クラブを管轄する生徒指導の先生に任せられないのでしょうか。
このケースでは、教員に変な気遣いをしているようで、個人的に残念な印象を受けました。
【③本当に苦手?】自分のお金にだけ興味を持つ
「お金のことはよくわからない」という校長もいました。
学校の財政状況などを説明しても、最初から理解しようとする様子が感じられないのです。
人間、得手不得手があるので、数字やお金のことが苦手という人がいること自体は否定しません。
しかし、それが本当に「苦手」なのであればという話。
こんな校長がいました。
予算や決算の際に、資料を持参して説明に伺います。
一通り説明しますが、そのたびに返ってくる言葉は、

お金のことはよくわからないから、これでお任せします。
皆さんを信用していますので。
というもの。
まぁ、仕方がないと思いつつ仕事を先に進めます。
ところがそれとは別に、出張旅費や立替金の振込の件で報告に行くと、

まだあの時の出張の分、振り込まれていませんよね。
などと確認してきます。
これを聞いて私は、

お金のことがよくわからないのではなく、「自分以外の」お金のことをわかろうと思っていないのでは。
と感じました。
お金のことをわかろうと思えばわかるのではないか。
自分のお金ではないから関心が持てず、理解できないだけではないか。
そんな思いが頭によぎります。
前述のとおり、得手不得手があるのは仕方がないとしても、校長として「学校のお金」に興味を持つ必要はあると思います。
そこを抜きにして、自分のお金のことは気にしているという姿勢に、残念さを覚えました。
まとめ
3つの残念ポイントを、私の経験も交えながらお伝えさせていただきました。
まとめると「人とお金」に関心が薄いということになると思います。
もちろん、全ての校長がこのような人だというわけではありません。
ただ、私が関わってきた校長の中にはこうした傾向の人がいたということです。
こうした残念な部分をサポートしながら、学校全体として社会に役立つ存在であり続けたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。