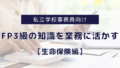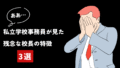この記事は以下のような人を対象としています。
・人生後半も、収入と働きがいを両立し、充実した職業人生にしたいと考えている人
以前の記事で、40代の私立学校事務員が意識すべきことを紹介しました。
その記事では、書籍の内容を参考にしながら、40代の人が仕事で意識すべき「変化」について私なりの意見をお伝えさせていただきましたが、今回はその続編的な内容です。
私自身、40代中盤に差し掛かり、「人生後半」という言葉に敏感になってきているという実感があります。
今回参考にした書籍も、まさにタイトルに「人生後半」という文言が入っていたので手に取りました。
そして、その書籍に書いてあった「収入と働きがいを両立できる充実した職業人生」という言葉に大変興味を引かれて購入。
実際読んでみて、私自身参考になる部分が多いと感じたので、今回記事にして紹介しよう思いました。
私と同じように人生後半を「収入と働きがいを両立できる充実した職業人生」にしたいと思っている方の参考になれば幸いです。
書籍の紹介
書籍名:人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために
著者名:都築 辰弥
出版社:日経BP 日本経済新聞出版
発売日:2025年4月8日
【大前提】どんな人生後半を送りたいか
この参考書籍ですすめているのが、
「幸福収入700万円を80歳まで稼ぎ続けられるようになってほしい」
ということです。
そのため、そもそも「定年退職後は働きたくない」と考えている方には、参考になりません。
その前提を踏まえて、以下読み進めていただければと思います。
まず、ポイントとして挙げられるのが「700万円」という点。
書籍では以下のように説明しています。
なぜ700万円か、というと、それには理由があります。ズバリ、人間が幸福感を覚える収入のピークは年収700万円あたりといわれているからです。 P17
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用
さらにもう1つポイントとして挙げられるのが「稼ぎ続けられる」という点。
退職金などで1年だけ年収700万円を達成すればよいというわけではないということです。
その点について、書籍では以下のように理由を説明しています。
キャリアに対して主体性を持って取り組む意識と行動をキャリアオーナーシップといいます。キャリアオーナーシップを高め、年収700万円が続くように能動的に行動することで、1カ所の勤め先に依存せず、自分の望むキャリアを自分で選ぶことができるようになります。 その選択の自由こそが、収入や幸福感、さらには働きがいをも実現する可能性を高めてくれます。 P20
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用

つまり、自由にキャリアを選べる状況を維持しながら、年収700万円を稼ぎ続けましょう、ということだと私は理解しています。
まずはこれが大前提になるわけです。
ただ、「年収700万円もいらない」など人それぞれ思うところがあるのもわかります。
実際私もそう思っています。
そこで以降は、「700万円」という「収入」の部分は一旦頭の片隅に置いて、「稼ぎ続けられる」という「働きがい」の方にスポットを当てていきたいと思います。
【「コンテンツ」を見つけよう】65歳までの仕事で意識すべきこと
参考書籍では、
- Ⅰ期:現在から再雇用終了までの期間
- Ⅱ期:再雇用終了後の期間
に分けてやるべきことを整理しています。
そして、
- Ⅰ期:本業+複業で年収700万円
- Ⅱ期:複業を起業・個人事業主として年収700万円
を目指すことを薦めています。
なお、「複業」と書いていますが「副業」の変換間違いではありません。
参考書籍ではそのように表現されています。
書籍の中では「複業」とネーミングした理由を解説していますが、ここでは割愛させていただきます。
この「複業」の探し方がポイントです。

読んでいて、このポイントを意識して上述の「Ⅰ期」の仕事に取り組むことが「キャリアオーナーシップ」の向上につながると私は感じました。
稼ぎ続けるにはこのキャリアオーナーシップが重要ということでしたね。
その複業探しのキーワードが「コンテンツ」。
この言葉の解説を以下に引用します。
会社や他社が、あなたにお金を払ってでも教えてもらいたい何かのことです。コンテンツはたいてい「〇〇する方法」という語尾で表現できます。 P77
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用
そしてこの「コンテンツ」を武器に、以下のような人材を目指すわけです。
なくても会社が回らないほどではないけれど、あったほうが便利な今はまだない拡張機能。複業人材に期待されているのは、そのような便利機能を提供することなのです。 P78
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用
さらにこの複業、ターゲットが会社だけとは限りません。
これも書籍の言葉を引用します。
企業に雇用されるという前提を捨てれば、年収700万円が続くために活かせるスキルはビジネススキルだけではありません。ココナラでもたくさん出品されているように、趣味やプライベートの経験、ちょっとした特技を活かし、個人のお客さんからお金をもらう「BtoC」タイプの働き方もキャリアのひとつのあり方です。 P58
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用
まとめると、
- 「○○する方法」=コンテンツ=拡張機能(便利機能)を見つける
- 拡張機能がまだついていない会社等にその機能を提供する
という流れで複業を始めることになります。
この流れの中で特に重要と私が感じたのが、提供できる拡張機能を見つけること。
正直なところ、複業まで始めるとなると心理的にハードルが高いという印象を受けたからです。
まずは「コンテンツの決定」をスモールゴールとして設定する。
後述しますが、これだけでも今の仕事における「働きがい」につながると実感していますので、皆さんもそこから始めてみてはいかがでしょうか。
【実践】自分の「コンテンツ」を見つける4つのステップ
以降はこの「コンテンツの決定」のための4つのステップについて、私が実際に取り組んだことも交えながら紹介したいと思います。
その4つのステップとは以下のとおりです。
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より加工して引用
- 職務経験・人生経験の棚卸し
- 経験タグ付けワーク
- 市場調査
- タイトルを考えよう
1つずつ見ていきましょう。
【ステップ1】職務経験・人生経験の棚卸し
書籍の言葉を引用します。
社会人になったときから現在に至るまでに経験した仕事を、思いつくままに書き出してみてください。 P87
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用
フォーマットも紹介されているので、私が作成したものの一部を例にして見てみましょう。
| 年/月 | 会社名 | 部署名 | 担当業務の詳細 | 取り組んだ課題 | 達成したこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 20XX年Y月~ | 学校法人△△△△ | 財務課 | 予算・決算担当。部下に予算・決算策定のポイント等を指導しながら、自身も学校法人全体の決算数値をまとめ上げ、理事会提出資料を作成。 | 新入職員等に学校法人会計を教える機会がなく、私立学校で働くうえでの基礎知識を身につけることができていない。 | 学校法人会計の基礎知識やそれを普段の業務でどう意識すべきかなどをまとめた研修内容を作成し、新入職員等の育成に寄与。 |
【ステップ2】経験タグ付けワーク
書籍の言葉を引用します。
職務経験棚卸し・人生経験棚卸しをもとに、あなたのこれまでの経験を象徴する軸キーワードを可能な限り縦にリストアップしてください。 P92
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用

コツはインスタグラムのタグ付け感覚で行うことのようです。 インスタをしていない私にはピンときませんが。
そして次は関連タグの洗い出しです。
次に、それぞれの軸キーワードを細分化した関連タグを最大10個ずつ書き出してください。関連タグを絞り出すコツは、5W1Hです。 P92
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用
これもフォーマットが紹介されていますので、私が作成したものの一部を例にしながら見てみましょう。
| 軸キーワード | 関連タグ | 関連タグ | 関連タグ | 関連タグ | 関連タグ |
|---|---|---|---|---|---|
| 経理会計業務 | 学校法人会計基準 | 決算書の見方 | 研修講師 | 新人育成 | プレゼンテーション |
そしてそれらの軸キーワード・関連タグの選別を行います。
選別のポイントは以下のとおりです。
書き出した軸キーワード・関連タグの中から、そのテーマについて1時間語り続けることができるほどの情報量を持っているテーマを可能な限りたくさん選び、丸をつけてください。 P92
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用
とりあえず一旦「学校法人会計基準」と「決算書の見方」であれば、何とか1時間くらい語れそうと感じたので、これらを選びました。

実際、研修講師をしたときも30分はしゃべっていたので、まだ膨らませる余地はあるかなと思っています。
【ステップ3】市場調査
これもやり方が紹介されています。
〇をつけた軸キーワード・関連タグで、「アマゾン(Amazon)」などで検索してみてください。過去に関連本が出版されていれば、ニーズありと判断できます。 P93
「人生後半の働き方戦略 幸福年収700万円を続けるために」より引用
実際にamazonで検索したところ、関連本がヒット。
他にもネット検索をすると、この内容に関連したセミナーも催されている様子でしたので、「ニーズあり」と判断することにしました。
【ステップ4】タイトルを考えよう
最後はタイトルの設定です。
「〇〇する方法」でタイトルを考えてみました。
- 経営状態のいい学校法人、悪い学校法人を見分ける方法
- 数字が苦手でも大丈夫!学校法人会計基準のキホンを身につける方法
- 経理会計業務以外の人も対象!学校法人会計基準を業務に活かす方法
こんな感じですね。
【所感】ステップ1~4をやってみて
「コンテンツの決定」を目標にやってみて率直に感じたのは、

「拡張機能」の提供先が学校法人に偏ってしまう。
ということでした。
これはおそらく、私が今まで自分の勤め先の学校のことばかり考えて仕事をしてきたから。
個人的な感覚ですが、私立学校事務員として働いている人の多くは、この傾向を持っていると感じています。
内向きで、ルーティン業務が多く、外部の環境のことを意識する機会が少ないということの影響ではないかと思われます。
だからこのワークを通じて、「自分の望むキャリアを自分で選ぶこと」ができるようになるためには、もっと視野を広くして仕事に取り組む必要性があると感じました。
例えば、ルーティンで行っている月次決算業務。
これを、

「月次決算を自動化するための方法」という拡張機能を身につけるためにはどうすればよいか。
と考えながら取り組むことで、民間会社にもアピールできる「コンテンツ」につなげられるのではと思うわけです。
今までやみくもに「とりあえず将来のために資格をとっておこう」と考えて、資格取得に励んでいたこともありましたが、上述の意識を持っていれば身につけるべき知識やとるべき資格がより明確になると感じました。
それが短期的には「今の仕事へのやりがい」となり、中長期的には「キャリアオーナーシップ」の向上に結びつく。
これが、このステップを通じて私が今後の仕事に活かしたいと思った点です。
まとめ
前述のとおり、私と同じように、自分が学校法人で働く姿だけをイメージして仕事をしている人も多いのではないでしょうか。
しかし、「自分の望むキャリアを自分で選ぶ」という選択の自由を持って定年退職後の人生を送るためには、学校法人以外にも提供できる「コンテンツ」が必要です。
収入と働きがいの両方を満たした人生後半をむかえるために、ぜひ皆さんもこの記事で紹介したことを実践して、「コンテンツ」見つけてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
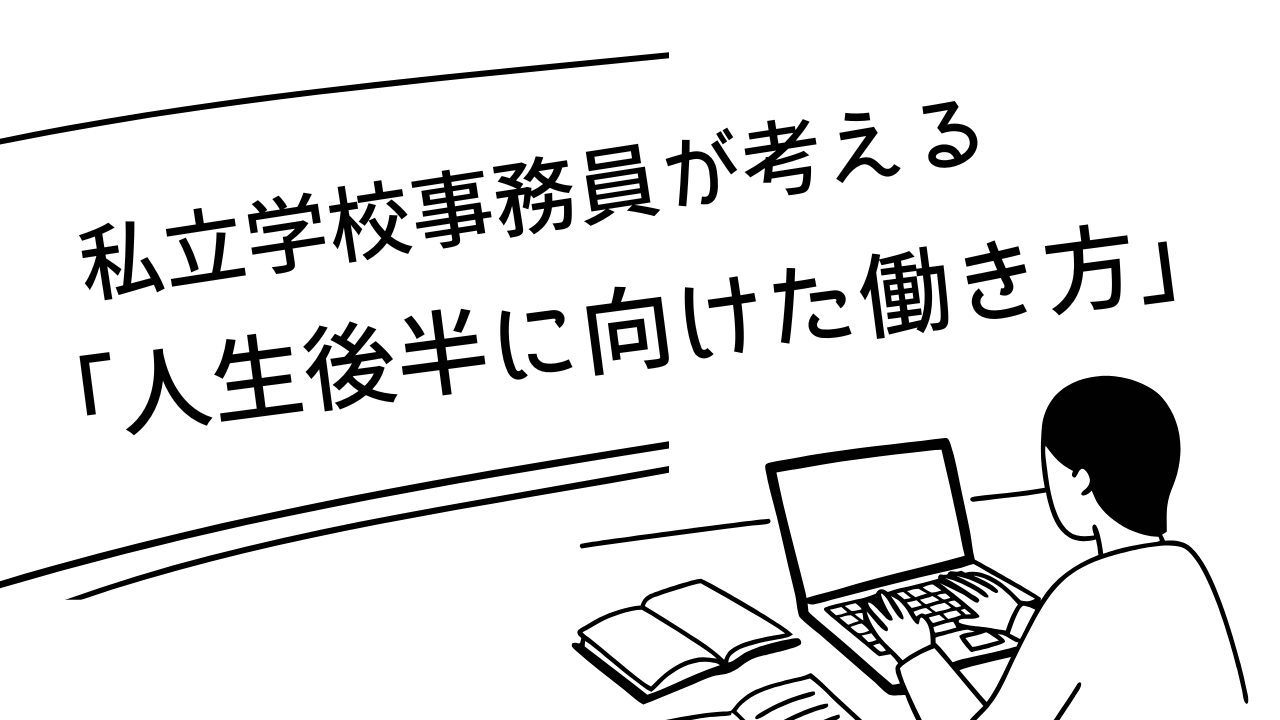
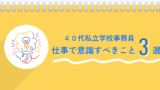
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=21545688&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1908%2F9784296121908_1_25.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)