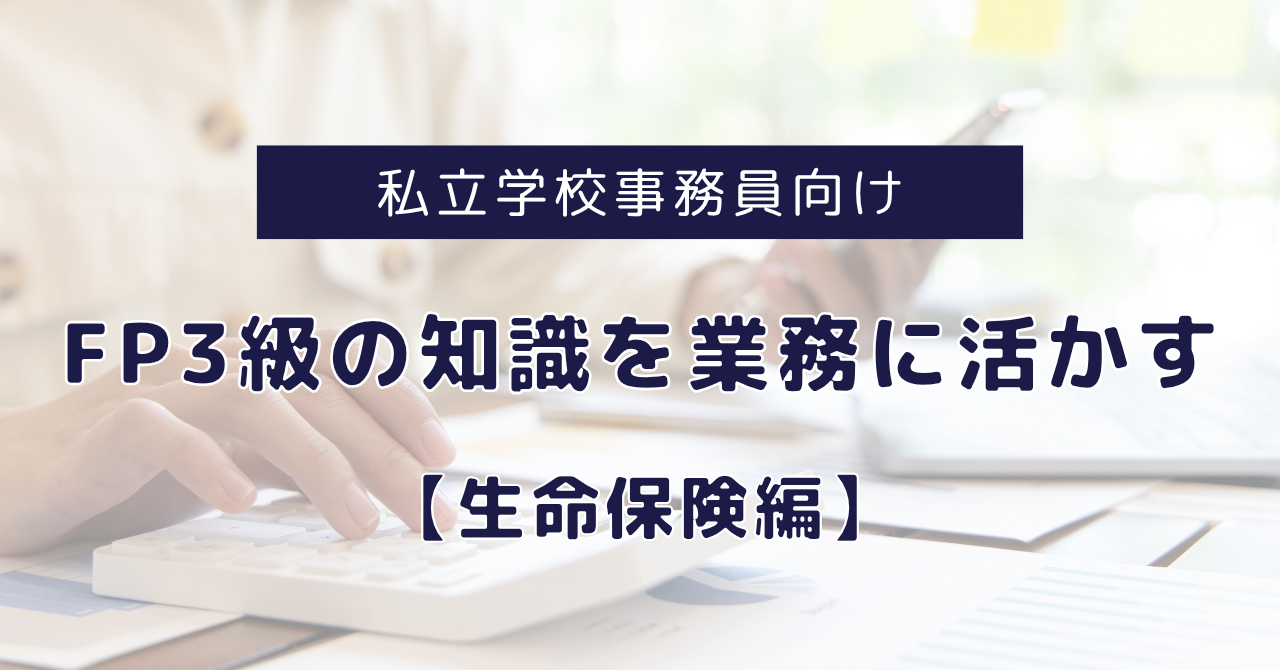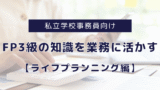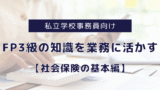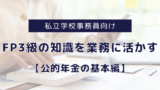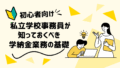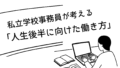この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・私立学校事務員の仕事に生命保険の知識が必要なのかという疑問を持っている人。
以前の記事で、ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下、FP技能検定)3級の試験範囲の中から私立学校事務員の仕事に役立ちそうなものを紹介しました。
今回はその続きとして、「生命保険」の部分で私立学校事務員として知っておくべきと私が感じたものをピックアップしてみました。
前回と同様に、FP技能検定3級の試験を参考にした問題を解きながら、必要な基礎知識を身につける形式にまとめています。
問題を全部で3問用意し、全ての問題のあとにこの「生命保険」に関連した情報を紹介しています。。
「生命保険の知識を事務員の仕事で使うことなんかないのでは?」と思っている方も、一読いただければと思います。
【第1問】所得控除①
次のケースの場合、所得税における生命保険料控除の額はいくらになるか。
本年中の保険料支払額が、一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料それぞれ10万円。 (すべて2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等に該当)
正解:C
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約は、年間8万円以上保険料を支払った場合、「一般」「個人年金」「介護医療」それぞれ4万円が所得税の生命保険料控除の限度額になります。
従って設問の場合、それぞれ10万円支払っているので、
限度額4万円×3(一般・個人年金・介護医療の3つ)=12万円 となります。
【第2問】所得控除②
設問1のケースにおいて、住民税の控除額はいくらになるか。
正解:A
生命保険料は所得税と住民税それぞれにおいて控除を受けることができます。
- 所得税の限度額:12万円
- 住民税の限度額:7万円
なお、住民税の限度額は「一般」「個人年金」「介護保険」を個別にみると、各2.8万円が限度額になっています。
ただし、全体としては2.8万円×3=8.4万円とはならず、7万円が限度額となっている点は注意しましょう。
【第3問】所得控除③
社会保険料と小規模企業共済等掛金の所得控除について正しいものはどれか。
正解:C
社会保険料も小規模企業共済等掛金も、その年に実際に支払った金額全額を所得から控除することができます。
なお、5万円というのは地震保険料の所得控除の上限額です。
【理解度アップ】生命保険と年末調整
私の私立学校事務員としての経験を思い返しても、生命保険そのものについての質問を受けた記憶はありません。
唯一思い出されるのが以下のやりとりです。
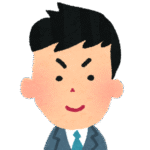
生命保険に入ることを検討しているので教えてほしいことがあります。

なんでしょうか。
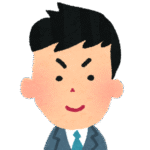
私学共済でカバーしていない部分について保険に入ろうと思っているので、どういったことがカバーされていないかを教えてください。

(いや、ざっくりしすぎだろう・・・)
結局どんな保険に入ろうとか、相手のイメージが漠然としているので答えようがなかったため、「私学共済ハンドブック」を渡して、「これを持って保険会社の方と直接相談するのがいいと思います」とお伝えしました。
こんな感じですので、生命保険の中身についてよりも「生命保険料控除」の方が私立学校事務員の仕事に直接関わりがあると思い、上述のような設問をセレクトしました。
以降では、この生命保険と年末調整について少し掘り下げて見ていきたいと思います。
【毎年恒例】年末調整のときに聞かれること
高校事務室で勤務していると、毎年年末調整のときに発生する恒例の問い合わせがあります。
それは、

保険料の紙(保険会社から送られてくる年末調整用の資料)は持ってるんだけど、どの数字を年末調整の書類のどこに書いたらいいのかわからない。
というものです。

ちなみに、新しく入職した人とは限らず、以前から勤めている人が毎年尋ねてくるというパターンが多いですね。
今は紙ベースではなく、パソコンやスマホから入力するかたちに変わりましたが、このやり取りは引き続き行われています。
そうした問い合わせに対応するには、生命保険料控除の正しい知識が必要です。
私が年末調整の業務を始めて担当したときには、こんなやり取りもありました。

この「新」とか「旧」とかあるけど、何が「新」で何が「旧」なの?

・・・。まぁ、とりあえず保険会社の都合で「新」とか「旧」に分けてるんじゃないですかね。

どっちでも、お金が返ってくるんならいいんだけど。
このやり取りでは相手がそれほど気にしていなかったからよかったのですが、やはりきちんとした回答をしないと、相手が「この人に聞いて大丈夫なのか」と不安に思ってしまいます。
ちなみ設問1で「2012年1月1日以後に締結した」という文言があったと思いますが、これが要するに「新」ですよという意味です。
- 旧制度:2011年12月31日以前に締結した保険契約
「一般」と「個人年金」の2つであわせて10万円が控除の限度額 - 新制度:2012年1月1日以後に締結した保険契約
「一般」「介護医療」「個人年金」の3つであわせて12万円が控除の限度額
細かい計算方法は気にせず、とりあえずこれだけおさえておけば問題ないと思います。
他にたまに言われるのが、

これで〇万円(生命保険料控除の合計額)税金が安くなるんですね。
ということ。
普通に考えて「そんなに安くなるわけないだろう」と思うのですが、何故か言われることがあるのです。
スルーするわけにはいかないので、「所得控除」と「税額控除」の違いを説明し、「そんなには税金減りませんよ」ということをやんわりお伝えしています。
なお、所得控除と税額控除の違いは以前の記事でも少し触れていますので、そちらもご覧いただければと思います。
実際に尋ねられた際に、適切に対応できるようにしておきましょう。
【全く別物】積立共済年金制度とiDeCoや企業型DC
私学共済のホームページで注意喚起を呼び掛けているのが、「iDeCoや企業型DC等と積立共済年金制度は全く別のものです」ということ。
私学共済への問い合わせが増えているようです。
これらの制度も年末調整に関わってくる場合がありますので、少し触れたいと思います。
「積立共済年金」「iDeCo」「企業型DC」と3つの制度が出てきますが、この3つは「積立共済年金」と「iDeCo」「企業型DC」とに分類できます。
前者が「保険」であるのに対し、後者2つは保険ではありません。

積立共済年金は「拠出型企業年金保険(Ⅱ)」というものになります。
詳しくは説明しませんが、一旦「保険なんだ」とだけ理解しておきましょう。
また、積立共済年金は私学共済、iDeCoは国民年金基金連合会が実施しているものです。
こうした点が私学共済のホームページにある「全く別のもの」という意味だと考えられます。
そのため、年末調整でもそれぞれ取り扱いが異なるわけです。
積立共済年金は2つのコースを選ぶことができ、選んだコースによって「個人年金保険料控除」か「一般の生命保険料控除」のどちらかを受けることができます。
一方、iDeCoは「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。
企業型DCはおそらく年末調整で関わることがほとんどないと思われますが、一応、2つの違いを載せておきます。
- iDeCo:「自分で」掛金を拠出し、「自分で」運用する年金制度
- 企業型DC:「企業が」掛金を拠出し、「自分で」運用する年金制度

企業型DCの掛金は企業が拠出していて、自分が負担しているわけではないのでそもそも個人の所得控除の対象にならないというわけですね。
金額でみると、積立共済年金は両方のコースに加入した場合、
個人年金保険料控除:上限4万円
一般の生命保険料控除:上限4万円
で、あわせて最大8万円の控除が受けられると思われます。
一方、iDeCoは私立学校事務員の場合、最大24万円(2025年度時点)の控除が受けられます。
それぞれの制度の控除の種類や金額の違いを頭に入れておきましょう。
まとめ
FP技能検定3級で学ぶ「生命保険」の内容から、特に年末調整の業務に関わる「控除」にスポットをあてて紹介しました。
毎年発生する業務であり、教職員からも質問を受けるケースが多いように感じていますので、参考にしていただければと思います。
なお、今回は私立学校事務員の仕事には直接関係しないため、生命保険の内容については触れていません。
しかし、個人が生命保険に加入する際には必要な知識だと思いますので、これを機会に学習してみることをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。