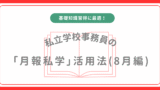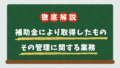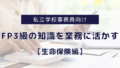この記事は以下のような人を対象としています。
・私立学校事務員の「学納金業務」について理解を深めたいと思っている人。
私立学校事務員の仕事の一つに「学納金業務」があります。
この業務、割と新人が担当する傾向が高い。
実際私も新卒で学校法人に入職して、最初に担当したのが大学生の学納金業務でした。
その後も事務室で勤務しているときは、これまた新卒で採用された事務員がこの業務の担当に。
そうした経験から、この業務には「様々なことの基本」となる要素が含まれていると感じています。
そこで今回の記事では、学納金業務で身につけられる力やおさえておくべき法的知識について紹介したいと思います。
これからこの業務の担当になる人や部下に担当させようと考えて人などの参考になれば幸いです。
書籍の紹介
書籍名:改訂新版 問題を解決する学校法務
著者名:弁護士法人 名川・岡村法律事務所
出版社:時事通信出版局
発売日:2024年2月15日
【基本が大事】学納金業務で身につけられる3つの力
まずは、学納金業務を通じてどのような力が養われるかについてです。
私個人の経験から、次の3つが挙げられると考えています。
- 簿記の基礎力
- 他者との交渉力
- スケジュール管理力
以下、1つずつ見ていきます。
【簿記の基礎力】
簿記の知識がない人がいきなり経理・会計担当の部署に配属されても、正直なところ「何をすればわからない」という状況に陥ってしまうでしょう。
そして仕訳や勘定科目といったルールは、簿記初心者にとって馴染みが浅く、理解するのに時間がかかるというのが私の印象です。
それを乗り越えるには、とにかく数をこなすこと。
「型」として覚えてしまうというやり方が、基礎を身につけるために最も効率的だと私は思っています。
そうした「簿記の基礎を身につける」という観点から学納金業務をみると、
- 入金が頻繁に発生するので、入金仕訳の「型」を覚えられる
- 「授業料」や「入学金」といった勘定科目を覚えられる
こうした意義があると考えられます。

簿記の参考書を買って取り組んでも、なかなか頭には入りにくいです。
「学納金に関係すること」に範囲を絞ることで、小さくても一歩前進することができます。 あとはそこから知識を広げていけばいいのです。
補助金業務では簿記の知識を使う機会が少なすぎ、預貯金管理業務だと逆に簿記初心者にはボリュームが多すぎると私自身は感じています。
その点では、学納金業務に必要な簿記の知識はちょうどいいレベルだと思います。
お金の入金処理は仕訳の基礎、「授業料」や「入学金」は収入の勘定科目の基礎。
そう考えて、この業務にあたってみることをおすすめします。
【他者との交渉力】
学校には様々なルールがあり、そうしたルールに基づいた行動を生徒や保護者に求めるケースも発生します。
しかし、時にはルールに従わない人も出てくるわけです。
そのような人たちと交渉して、こちらが希望する行動をとってもらう。
こうした力も私立学校事務員としては必要になります。
その点で、学納金業務はまさに実践を積む絶好の場だと思います。
- ルール:学則や学納金規程
- とってほしい行動:期日までの納付
学納金未納者に対し、このルールに基づき、いかにして納付してもらうかを交渉する。
学納金業務を担当すれば必ず経験するシチュエーションと言えます。
この経験を積むことで、交渉力を身につけることができるわけです。

まずは規程に基づいた論理的な交渉を身につけ、さらに経験を重ねることで相手の感情も考慮した対応ができるようになります。
私も最初のころは、「規程でそう決まっていますので」という杓子定規な対応しかできず、よく相手を怒らせていました。
そうした失敗の経験を経て、次第に「こう言った方がいいかな」と相手の様子を見ながら話を進められるようになったと実感していますので、怒られてもくじけずに場数を踏むようにしましょう。
【スケジュール管理力】
私立学校事務員の仕事といえばルーティン業務です。
仕事の多くが年単位、月単位でほとんど決まっています。
そんなルーティン業務を遅滞なく、正確にかつ確実に処理していくことが求められています。
そして学納金業務はまさにルーティン業務の代表例。
- 納付期限はいつか
- 督促はどのタイミング行うのか
こういったことが規程で決まっており、そのタイミングにあわせて請求書を準備・発送するなど業務を進めていきます。
そして、1年間「いつ」「何をしたか」を手帳やパソコンのスケジュールソフトなどに記録しておき、次年度以降はそれを確認しながら仕事をする。
これで、まず仕事の漏れや遅れといったものはなくせると思います。
このやり方は当然、他の業務でも応用できます。

実際、経理業務は毎月の締日や支払日が決まっていますし、補助金業務も申請や実績報告の時期が決まっているので、スケジュール化しやすいです。
このスケジュール管理力を養うことで、私立学校事務員の仕事の8割方は対応できるようになると思いますので、新卒者などには特に身につけていただきたいと思います。
【今までどおりでいいのか?】学納金業務に関わる法的知識
私立学校事務員の基礎力というべき3つの力を身につけてもらうために、新人の方などには学納金業務をまず経験してもらっている。
これが私の実体験に基づく考えです。
そんな私の実体験を振り返ってみて、そういえば教わっていないと思い当たることがあります。
それは「学納金を請求することの法的根拠」です。
当たり前のように学生生徒や保護者に学費を請求しているわけですが、そもそもそこにはどんな法的な根拠があるのか、ということを教わる機会はありませんでした。
そこで以降は、その点について参考書籍に基づいて触れていきたいと思います。
①学生生徒等、保護者と学校の関係
まず、学生生徒等と学校の間には「在学契約」があるというのが最高裁の考え方です。
つまり、この契約関係により「学生生徒等」が「学校」に学納金を納める義務があるということになります。
逆に「保護者」にはその義務はないということになるわけです。
書籍でもその点について以下のとおり紹介しています。
「改訂新版 問題を解決する学校法務」より引用
- 在学契約の当事者が生徒であるとする最高裁の考え方を敷衍すると、理論的には、学費の支払義務も生徒自身が負い、法的には、保護者は在学契約に基づく学費の支払義務を負わないことになると考えられます。 P61

単純に「生徒が学納金を払わないのなら、保護者が払うのが当然」と思っていた人が多いのではないでしょうか。
ちゃんと法的根拠があったのです。
ただし、この記事では高校生以上のケースを想定してることをご留意ください。
だから、「今まで保護者に請求していたから」という理由だけで、保護者宛に請求書を送ることはないように理解しておくべきです。
では、どうすれば保護者に請求できるのか。
それが次に説明する「連帯保証契約の締結」になります。
②連帯保証契約
連帯保証については別の記事で紹介しましたので、そちらを参照いただければと思います。
簡単に言えば「本人と同等の義務を負っているのが連帯保証人」ということになります。
ほとんどの学校では、生徒が入学する際に「誓約書」をとっているというのが私の認識です。
この誓約書に保護者が署名等することで、保護者と学校との間に保証契約が結ばれる仕組みになっているはずです。

保証契約とは、この場合「生徒が学費を支払わない場合は、保護者が支払います」ということを約束しているものだと理解していただければ結構です。
この契約があるから、保護者へ学納金を請求することができることになります。
しかし、注意点が1つ。
それは「保証人」ではなく「連帯保証人」でなければならないということです。
連帯保証人は前述のとおり、本人と同等の義務を負っていますが、保証人はそうではありません。
詳しくは先に紹介しました関連記事をご覧いただければと思いますが、連帯保証人には認められていない権利でも保証人には認められている場合が多いです。
請求しても理由を付けて支払いを断られたりしないよう、連帯保証人として保証契約を締結するようにしなくてはなりません。
その際の注意点が3点あり、これらは全て民法によって定められています。
その3つとは以下のとおりです。
「改訂新版 問題を解決する学校法務」より引用
- 必ず書面を作成
- 「連帯保証」の文言を明記
- 極度額の設定
3つ目の「極度額の設定」について、参考書籍の解説を引用します。
「改訂新版 問題を解決する学校法務」より引用
- 令和2年4月1日施行の民法改正により、個人が保証人となる根保証契約は、予測可能性を担保するため、極度額(根保証により担保することができる債権の合計額の限度)を定めなければ無効とされます。P61

「根保証」という聞きなれない単語が出てきましたが、ここでは一旦「次々と保証する対象が増える可能性があるもの」と思ってください。
例えば学納金。
1年次の学費100万円が未納の場合、連帯保証人が保証するのは100万円になります。
その後、2年次の学費100万円も未納になった場合、保証の対象が200万円に増えるわけです。
こんな感じで増えていくのが根保証の性質です。
こうした根保証契約の連帯保証人になる場合は、あらかじめ保証する最大の金額を決めておき、それを連帯保証人になろうとしている人に示さなければなりません。
この「最大の金額」を「極度額」といいます。
これらの注意点を踏まえて、連帯保証契約を締結するようにしましょう。
まずは、勤め先の誓約書が上述の3つの注意点を満たしているかをチェックすることをおすすめします。
まとめ
前述のとおり、学納金業務は新入職員が担当するケースが多いです。
しかしだからといって、重要度が低いというわけではありません。
むしろ、学校の収入のほとんどは学納金という実態を考えれば、学校の経営を支える極めて大切な業務と言えると思います。
そんな学納金業務を担当するにあたり、意識しておくべきことや知っておくべき知識を紹介しました。
この記事の内容が、仕事の理解を深めることにつながれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
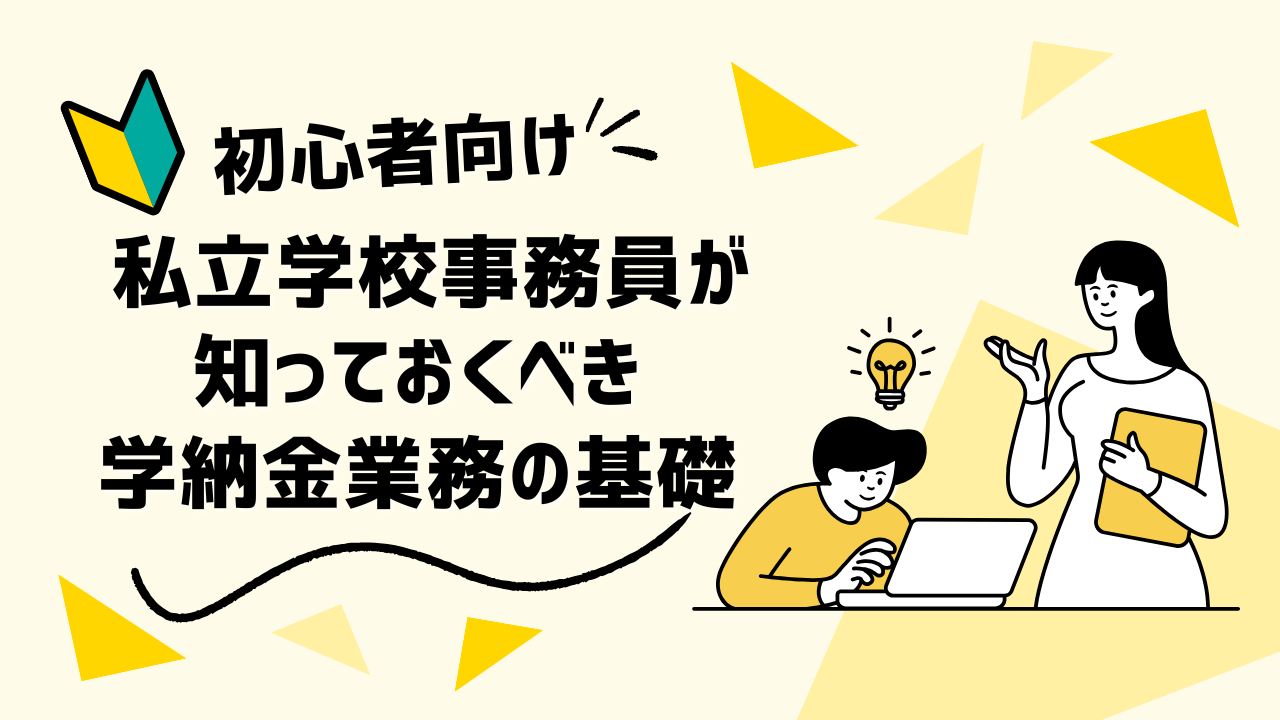
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/429b8c70.55b8a264.429b8c71.7834a660/?me_id=1213310&item_id=21136547&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8999%2F9784788718999.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)