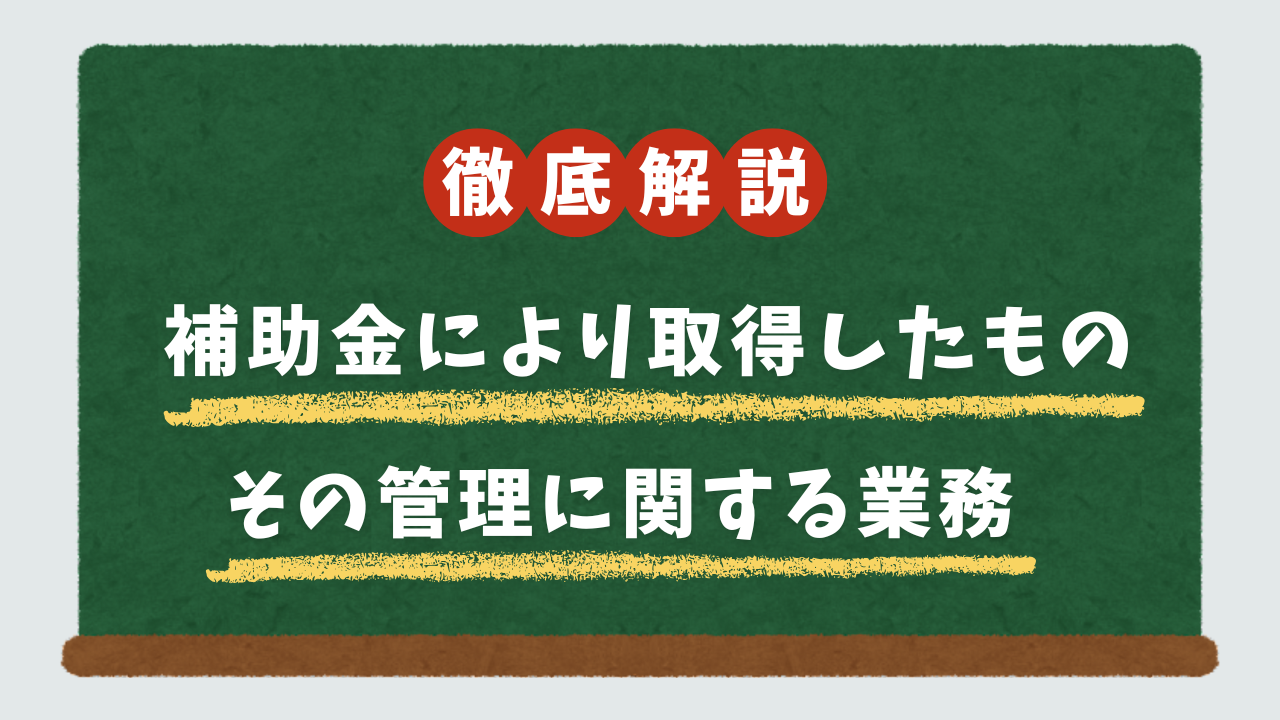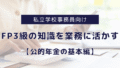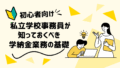この記事は以下のような人を対象としています。
・補助金を使って購入したものの扱いについて知りたいと思った人
学生生徒等の教育環境を維持・向上するためには、何かとお金がかかります。
これが学校事務員が抱える悩みの種の一つ。
「いつ」「何を」「いくらで」といった計画を立て、その計画を実現するための財源を確保する。
言葉にすると簡単なのですが、実際は難しい。
その一つの要因として、学校の収入に占める学納金の割合の高さがあると思います。
学納金は企業の売上のように突然伸びたりすることがまずありません。
そういった意味で、学校は限られた収入源でお金のやりくりを考えなくてはならないのです。
その学納金以外の収入源として頼りにしたいのが補助金。
これをうまく活用して、教育環境を整備することが基本だと私は考えています。
しかし、補助金は原資が税金であることから、適正に使用されるための様々なルールが設けられています。
そこで今回は、その様々なルールのうちの1つである「処分制限」について紹介したいと思います。
補助金の交付を受けて購入したものの管理に関する法令や私の実体験などをまとめましたので、皆さんの実務に役立てていただければ幸いです。
【基本ルール】関係する法令の確認
補助金に関する業務を行うにあたっては、その法的根拠をしっかり確認しておくことが大切です。
そこでまず確認しておきたい法律が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」。
この法律には以下のように定められています。
(財産の処分の制限)
e-gov 法令検索より引用
第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

要するに、承認を受けずに勝手に処分するなということですね。
これが基本ルールになります。
この基本ルールをさらに具体的にしたものが「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」です。
当該施行令では、以下のとおり定められています。
(処分を制限する財産)
e-gov 法令検索より引用
第十三条 法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 不動産
二 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
三 前二号に掲げるものの従物
四 機械及び重要な器具で、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定めるもの
五 その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

法律の方では「財産」としか書かれていませんでしたが、施行令の方でその「財産」とは何かを施行令の方で具体的に定めているわけですね。
この施行令第十三条でポイントとなるのが「四」と「五」です。
「各省各庁の長又は補助実施法人の代表者」が定めたものが「財産」になる。
学校法人の場合、多くは「文部科学大臣が定めたもの」になると考えられます。
実際、文部科学省が取り扱う「私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱」では以下のように定められています。
第28条 取得財産等のうち施行令第13条第4号及び第5号に規定する財産は,1個又は1組の取得価額が50万円以上の設備とする。
e-gov 法令検索より引用
2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は,補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して,文部科学大臣が別に定める期間とする。

第1項の方で「財産となるものの基準金額」、第2項の方で「処分制限期間」を定めているわけですね。
つまりまとめると、
- 補助金で整備した財産は勝手に処分してはいけない。
- 処分するにはしかるべき人の承認が必要。
- どんなものが「財産」になるかは、その補助金ごとに決められている。
といった感じになります。
「こうしたポイントが法令で定められています」と説明できるようにしておきましょう。
なお、補足ですがこの処分に関する例外も「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」で定められていますので、以下をご参考ください。
(財産の処分の制限を適用しない場合)
e-gov 法令検索より引用
第十四条 法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合
二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合
【困った人たち】補助金担当者を焦らせた実例紹介
上述のとおり、補助金の交付を受けて整備したものは法令に基づき、適切に取り扱わなければなりません。
しかし、こんな法令をしっかり理解している人はあまり多くいないというのが実感です。
特に教員はその傾向が高いと思います。

補助金の要綱まで読み込んでいる教員は今まで見たことがありません。
授業と特に関係ないので、当然と言えば当然なんですが。
そうした教員の行動により、担当者(私)が困った状況に追い込まれたエピソードを2つ紹介します。
その2つは以下のとおりです。
- 無断持ち出し
- 無断処分
購入したものを無断で持ち出した事例
補助金の一連の流れを簡単に表すと以下のようになります。
募集→申請→決定→事業実施・完了→報告→検査→補助金交付
この「申請」の際に、見積書を提出するなどして具体的に何を購入するかを明らかにします。
そして「検査」のときに、検査官の人はその見積書等に記載されたものが納入されているかを一つ一つ確認するのです。

大学だと検査が行われないことがありますが、高校の場合は所管の都道府県の職員の人がほぼ必ず検査に来られます。
事件はこの検査の時に起こりました。
購入した物品をチェックするため、検査員の人と設置場所を回っていたところ、あるべきところに物品が見当たらないのです。
事前に確認した際には、確かにそこにあったので「どうしてないのか?」と大慌て。
すぐさま、全教職員に「知りませんか」と呼びかけました。
するとある教員から、別の教室で使用するために持ち出したという連絡があり、すぐに確認。
なんとか見つけることができました。
先に紹介した法律にも定められていますが、「補助金等の交付の目的に反して使用」してはいけません。

本来あるべきところ以外のところで使用していると、その目的外利用が疑われてしまいます。
本件については無事検査を乗り切ることができ、問題はありませんでしたが、何とも言えない緊張感を味わった一日でした。
購入予定のものを無断で処分しようとした事例
あるとき、学校の敷地内を歩いていると、ゴミ置き場に何か捨てられているのを発見。
妙に見覚えのあるものだったので、近づいてよく確認してみると、やはり前年度に補助金の交付を受けて購入した物品でした。

見つけた瞬間は「なぜここに?」という思いで頭がいっぱいになりました。
急いでゴミ捨て場から移動させ、上席者に報告。
すぐに、教員を集めて確認が行われました。
ほどなくして捨てた人が明らかになり、事情を尋ねたところ、
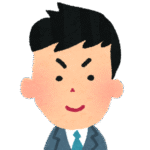
破損したので処分した。
とのことでした。
補助金の要綱上、「財産」は「1個又は1組の取得価額が50万円以上」と定められており、この物品は50万円未満でしたので、管理の対象外ではありました。
しかし、そんなルールを理解したうえでとった行動ではないことは明らかです。
後日、教員が一同に集まる職員会議の場で、補助金で購入したものは壊れたりしたからといってすぐに捨てず、上席者の判断を仰ぐことが周知されました。

補助金で購入した物品には、「これはいつの補助金で購入したものです」ということを記載したシールを貼っています。
処分する際には、そのシールが貼っていないかを確認するよう呼びかけています。
皆さまも、くれぐれもご注意ください。
まとめ
補助金はお金をもらって終わりというものではありません。
交付を受けたあとも、守るべきルールが存在しています。
私立学校に勤める者として、そうしたルールを理解しておくこと。
それが税金を原資とする補助金を使って事業を行う者の義務だと考えています。
私の事例も参考にしていただき、学校として適切な管理体制を構築し、実務に反映させていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。