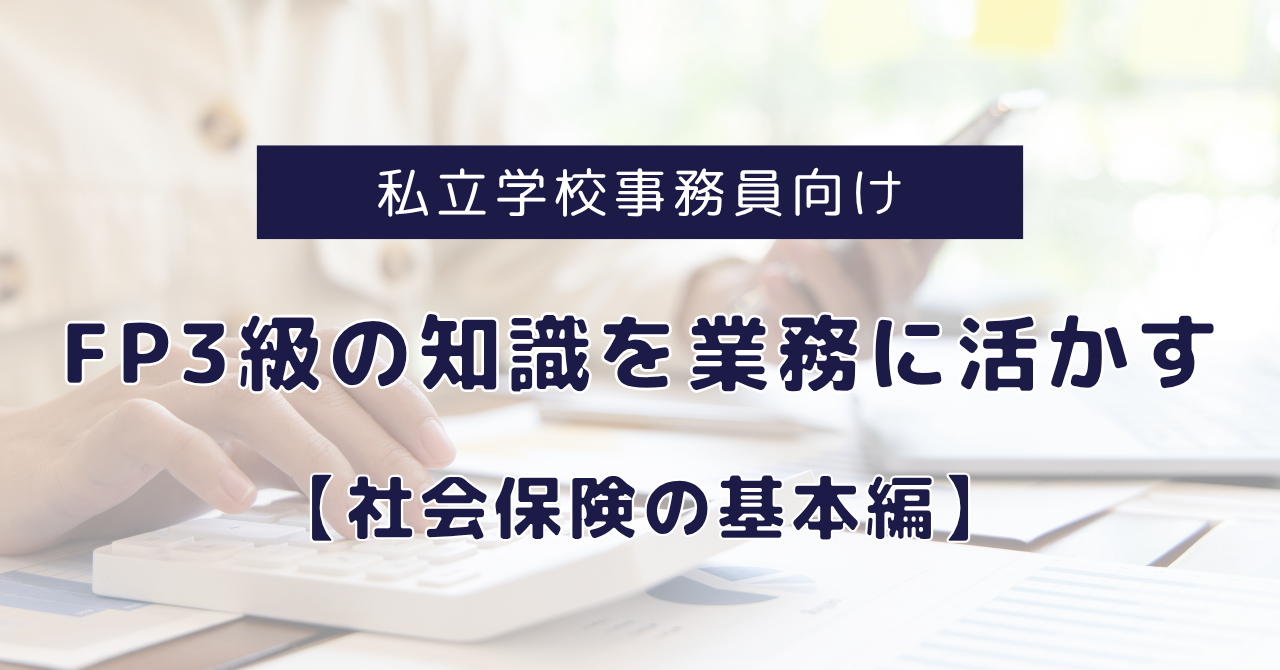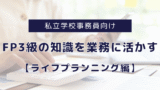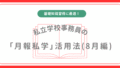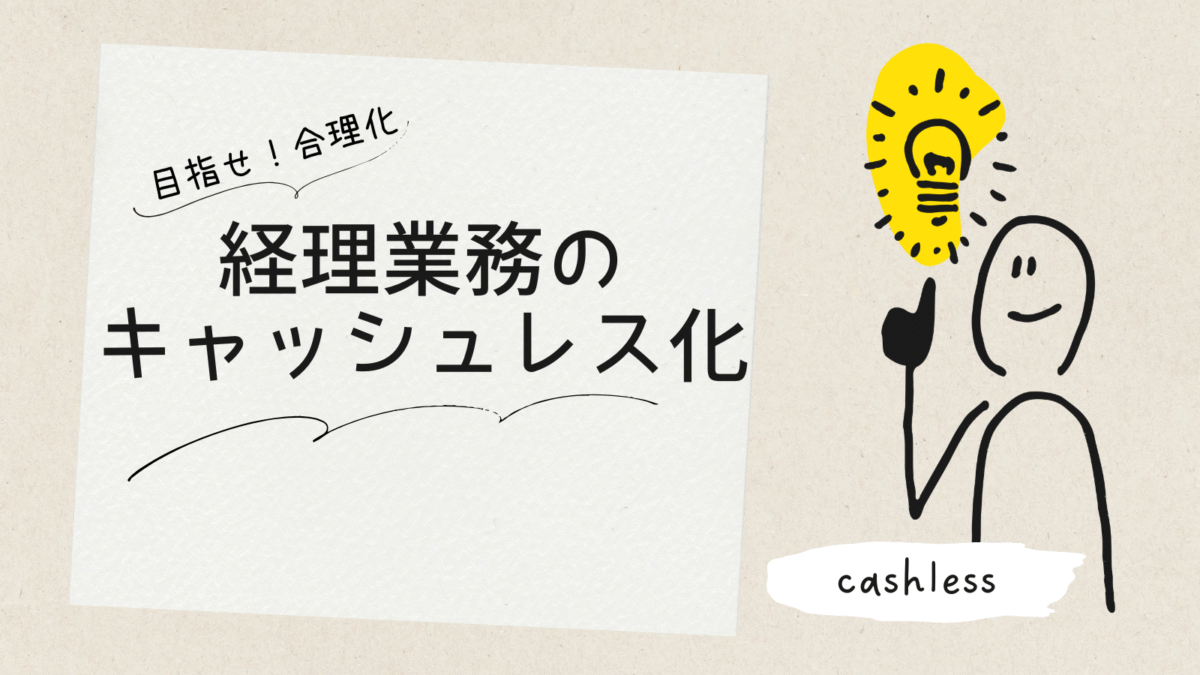この記事の内容は、以下のような人を対象にしています。
・教職員から社会保険に関する問い合わせを受けたときに必要な知識と対応方法を知りたいと思っている人。
以前の記事で、ファイナンシャル・プランニング技能検定(以下、FP技能検定)3級の試験範囲のうち、「ライフプランニング」の分野で私立学校事務員の仕事に役立ちそうなものを紹介しました。
今回はその続きとして、「社会保険の基本」の部分で私立学校事務員として知っておくべきと私が感じたものをピックアップしてみました。
前回と同様に、FP技能検定3級の試験を参考にした問題を解きながら、必要な基礎知識を身につける形式にまとめています。
問題を全部で5問用意し、全ての問題のあとに理解がより深められるような情報を紹介しています。
傷病手当金や任意継続制度、雇用保険など、事務員の仕事をしていると一度は扱うことのあるものを選んでみました。
ご自身にも関係する内容でもありますので、この機会にぜひ知識を増やしておきましょう。
【第1問】傷病手当金
日本私立学校振興・共済事業団の加入者に支給される傷病手当金の額の計算方法は以下のとおりである。空欄に入る組み合わせのうち正しいものはどれか。
1日につき、支給開始日の属する月以前の、直近の継続した( ① )の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の( ② )から、学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額
正解:C
直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する額の80%から、学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額になります。
日本私立学校振興・共済事業団 私学共済事業ホームページより引用
【第2問】任意継続加入者
私学共済制度の任意継続加入者となるためには以下の要件をすべて満たす必要がある。
空欄に入る組み合わせのうち正しいものはどれか。
- 退職の日まで引き続き( ① )加入者であった人
- 退職の日から( ② )以内に、任意継続加入者となることを所定の用紙で私学事業団に申し出た人
- 払込期日(納期限)までに、任意継続掛金を私学事業団に納付した人
正解:B
私学共済制度の任意継続加入者制度とは、退職の日まで引き続き1年と1日以上、学校等に勤務し、加入者であった75歳未満の人が、最長2年間、在職中と同じように短期給付を受けたり、福祉事業を利用したりすることができる制度です。
日本私立学校振興・共済事業団 私学共済事業ホームページより引用
なお、「1年と1日以上」には、過去の任意継続加入者であった期間は含みません。
【第3問】雇用保険①
雇用保険の基本手当を受給するための要件は原則以下のとおりである。空欄に入る組み合わせのうち正しいものはどれか。
ただし、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除くものとする。
離職日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
正解:B
原則、離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があることが要件になります(自己都合、定年退職の場合)。
【第4問】雇用保険②
勤務期間10年未満で自己都合により退職し、雇用保険の基本手当の受給資格者となった教職員が受給することができる基本手当の日数は最大何日か。
正解:A
定年退職や自己都合退職の場合、算定基礎期間が10年未満であれば、基本手当を受給できるのは最長90日になります。
なお、算定基礎期間が10年以上20年未満であれば最長120日、20年以上であれば最長150日になります。
【第5問】介護保険
私学共済の「掛金」は「短期(福祉)掛金」「介護掛金」「加入者保険料」「退職等年金給付掛金」で構成されているが、「介護掛金」を負担する必要がある加入者の年齢要件のうち、正しい組み合わせはどれか。
正解:B
原則として40歳以上65歳未満の加入者が介護保険料として掛金を納付します。
特に届け出等は必要なく、40歳到達時に自動的に対象者となります。
なお、公的介護保険の被保険者は65歳以上を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満を「第2号被保険者」と呼びます。
【理解度アップ】「傷病手当金」と「任意継続」のポイント
「傷病手当金」「任意継続」「雇用保険」「介護保険」と問題を解いてきました。
ここからは、これらの制度のうち、私が実務上で取り扱うことが多かった「傷病手当金」と「任意継続」について、より詳しい内容に触れていきたいと思います。
【近年増加傾向?】傷病手当金
まずは、傷病手当金です。
私の感覚では、傷病手当金を受給するケースが近年増えているように感じています。
つまり休職して報酬が減額されるということになりますが、その休職理由は主に「メンタル不調」。
精神的に疲弊してしまうケースが多いという印象です。
こうした場合に備えて適切に対応できるよう、この傷病手当金の手続きは理解しておくべきと思います。
それでは要件を整理しておきましょう。
おさえておくべきは以下の3点です。
- 職務外の原因で病気やケガをしたために休業(欠勤)
- 報酬が減額された又は無給
- 連続して4日以上休業
特に注意すべきは1点目の「職務外」の部分。
職務による場合は「労働災害」にあたり、「労災保険」の対象となると考えられます。
傷病手当金の手続きは私学共済あてに行いますが、労災保険の手続きは労働基準監督署が窓口となり、全く別物です。
状況をよく確認する必要があります。
ただ、前述のような「メンタル不調」の場合、職務上か職務外かの判断が難しいように感じています。
正直なところ、対象者側から「これは労災だ」という申し出がない限りは、傷病手当金の方で手続きを進めています。
職務「外」は傷病手当金、職務「上」は労災保険。
覚えておくべきところです。
また、私学共済への「加入期間」が要件に入っていない点もポイントです。
前述した雇用保険の「基本手当」のように、被保険者期間が要件になっているものもありますので、違いを整理しておきましょう。

私の勤め先では、今年の4月に入職したばかりの教員が早くも休職に入りそうな様子なので、傷病手当金の請求準備を進めています。
請求自体は実際に休んだ後でなければできませんが、休んでしまうと直接本人とやり取りすることが難しくなります。
そのため「休みが続きそう」と感じた時点で、必要書類や今後の流れなどをまとめておき、本人の状態を考慮しながら、休む前にある程度説明しておくことをおすすめします。
もう1点、見落としがちなのが「支給期間」です。
私学共済のホームページや「加入者のための私学共済ブック」には、普通の病気やケガの場合の支給期間は1年6ヶ月間になると記載されています。
しかし実際は、「同一の傷病については」通算して1年6か月間が支給期間になるが正しいのです。
つまり、一度復職して再度同じ傷病で休職した場合、1年6ヶ月から前回休職した際に支給を受けた期間を差し引いた残りの期間までしか傷病手当金を受給できないことになります。
この「同一の傷病については」の記載は、主に共済事務担当者が利用する「事務の手引き」で確認することができます。

厳密には、私学共済のホームページの「短期給付・限度額適用認定証にかかるQ&A」にも載っていますが、なぜ普通に傷病手当金の紹介ページに載せないのかは疑問です。
こうした状況のため、知らない人も多いというのが私の印象です。
ちなみに、私の前の勤め先でこの「同一の傷病」についてしつこく確認してくる事務員がいたという話を聞いたことがあります。
共済事務担当部署の事務員に「この場合はどうか」ということを何パターンも尋ねてきたそうです。
一度休職していたことがある事務員でしたので、「どんな診断書を出せば、もう一度1年6ヶ月丸々傷病手当金をもらえるか」を確認していたのかもしれません。
そう思うと、その事務員に対し、正直あまりいい印象を受けませんでした。

心意はわかりませんので、私が悪いように考え過ぎなのかもしれませんが。
【民間企業と異なる?】任意継続制度
次は任意継続制度です。
概要は設問のところで紹介しましたので、省略します。
この概要の中でも特に意識しておきたいのは「加入期間」です。
民間企業等にお勤めの場合に加入する「健康保険」でも同様に任意継続制度がありますが、私学共済とはこの加入期間にかかる要件が異なっています。
- 健康保険:資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上
- 私学共済:退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者
つまり、4月1日に入職して翌年3月31日に退職した人は、私学共済の場合、任意継続制度の対象外となるわけです。

このような契約期間のケースが多いと思いますので、うっかり任意継続を案内しないように注意が必要となります。
あと多い質問が、「任意継続と国民健康保険のどちらの方が掛金が安いか」というものです。
これは答えづらいので、私の場合はあらかじめ私学共済のホームページから「任意継続掛金早見表」をプリントアウトして、その人が該当する部分にマークして渡すようにしています。
そして、「それを持って役所に行って相談してください」とお伝えしています。
この方法だと誤りが起こりにくいと思っていますので、試してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回取り上げたのは「社会保険の基本」の中でもほんの一部分にすぎません。
これら以外にも様々な手当や制度等があります。
すべてを理解しておくことは不可能に近いと思いますが、主なものを知っておくだけでも自分や一緒に働く人にとって役立つ知識になると思っています。
逆にこうした知識がない場合、入らなくてもいい保険に入ってしまうなど、損するケースにつながることも考えられるわけです。
そんなことがないようにこれをきっかけに、少しでも知識を広げることをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。